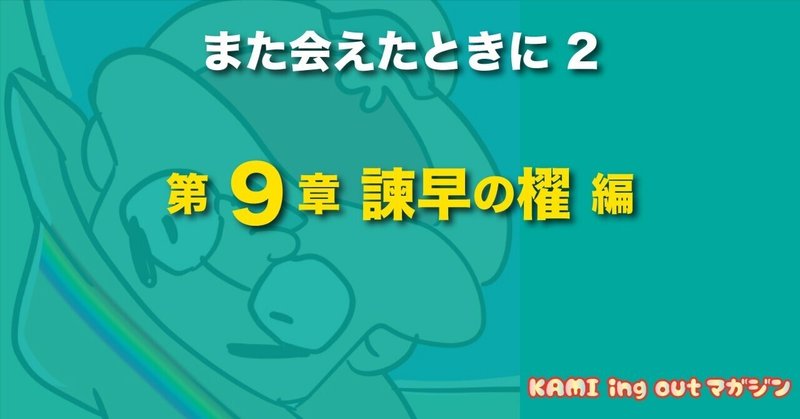
ロードムービー原作 「また会えたときに 2」 第9章 (諫早の櫂 編)
皆様。お休みをいただき、ありがとうございました。
おかげさまで、リフレッシュできました。
そういえばこの1年、ゆっくりと映画を観る時間もなかった僕でした。
小説も読まず、YouTubeも見ず、オンデマンドのドラマも観ず、テレビもまったく観ていません。
外界のことは何も知らず、ニュースなんかは友人から聞いて驚くほど。
昔は情報を仕入れることを楽しみにしていたのに、今はそれよりも仕事ばかり。
そこにnoteの執筆が重なっていき、気がつくと寝ることを惜しんでおりました。
執筆自体はとても楽しくて、時間を忘れて進められるのですが、自分の姿が全く見えていませんでした。
そして友人にこう言われました。
「くまさん、クマが出来てるよ。気晴らしに映画でも行ってきたら?」
そこで勧められた映画を久しぶりに観に行って、驚きました。
八幡様:「泣きまくってましたね。」
僕:「いや、もう。本当にびっくりしました。自分でもこんなに涙が出るとは思わず、周りにいたお客様が引くくらい、止まりませんでした。
めっちゃ泣いたら、しゃっくりが出るんですね。恥ずかしかったです。」
八幡様:「ティッシュがないのでハンカチで鼻をかみながら、しゃっくりを飲み込みつつも映画に没入できるのは、アニキくらいですよ。」
僕:「おかげさまで、感動をいただきました。それにしても映画って、あれもひとつの『旅体験』ですよね。」
八幡様:「その通りです。世界中を旅することはもちろん、制作者の脳内の旅もできます。
しかも、それらは音楽、セリフ、映像で迫ってくる。つまり、映画は最大級の情報空間なのです。」
僕:「たしかに。。。。」
八幡様:「人は、情報を多く仕入れることで、現状を俯瞰できるようになっていきます。
目の前のことも大切ですが、広い視野を持つことも時には重要です。」
僕:「おっしゃる通りです。
鹿児島から長崎に向かった行程はとても複雑でした。
でも、一生懸命走っていると必ず強い味方が現れて、大事な情報をくれるものですね。あ、熱ッ!」
八幡様:「どうしました?」
僕:「いや、頭がもうアッチッチで!」
八幡様:「この陽射しです。青年もヘルメットを脱いだらパンチパーマになっているかもしれませんね。」
僕:「想像すると・・・完全に大仏さんじゃないですかっ!」
八幡様:「長崎は遥か先です。御仏にならい、安らかな心で歩んでいきましょう。」
「また会えたときに 2 」 第9章
繋いで、流して、平らかに。
鹿児島から長崎を目指し、海沿いを一路北上する青年。
まあ、同じ九州だからそんなに遠くはないだろうし、半日ほどで着くかな、とタカを括っていたが、九州大陸の大きさを甘く見すぎていた。
出発してからはじめて給油したガソリンスタンドのお父さんに、あんたのバイクで下道を走ったらまあ、ここから10時間くらいはかかるじゃろうと言われ、出発してはや2時間後に軽く意気消沈する青年。
しかし、進むしかない。
問題は、どうやって進んでいくかだ。必要なのは、最適な道順。まず、その作戦を綿密に立てなければならない。
いやしかし、ちょっと待った。髪の毛がうざい。
炎天下のせいで、オレンジ色のヘルメットの中もオレンジ色に燃え盛っている感覚だ。
この、剛毛の髪めえ!
数十年後には毛根という毛根から総スカンを食らわされるとも知らず、青年は己の豊富すぎる毛量を恨んだ。
あ、散髪するところがあれば、入って短くしよう。あ、いやまずは腹ごしらえか。
違う。まずは道順だ。
長崎へのルート設定を早く確立させること。それが最大優先なのだ。
そうと決まれば、次はどこで情報収集をするか、だ。
青年の大好きなガソンリンスタンド、昔からそこにある店構えのご飯やさん、笑顔で道ゆく人などなど。
青年の目に入ってくる中で、今回ピカリと光ったのは、交番だった。
青年は躊躇なく、とある小さな交番に入り、ヘルメットを脱ぐ。
髪の毛がパンチパーマになっていないことを確認して、こんにちは〜! と三日月の目でご挨拶。
奥から「は〜い!」
と出てきたのは、チェック柄のエプロンをして、2歳くらいの赤ちゃんを抱っこした、若いお母さんだった。
お母さん:「はい、いらっしゃい!」
と屈託のない笑顔。
ここ、飲食店? 間違った? とあたふたする青年だが、お母さんは赤ちゃんをあやしながら言う。
お母さん:「どぎゃんしたと? 迷った? なんか拾った?」
青年は気づいた。そうか。お巡りさんの奥さんだ。ここに住んでるんだ。
若奥様は、青年の心の動きを察したように、
奥さん:「あ、すみまっせん。うちのおまわりさんは、今パトロール中たい。ごめんね。あたしがなったけ対応するけんね〜。」
そう笑顔で言ってくれたので、安心した青年は正直に言った。
青年:「ここから長崎まで行きたいんですが、どうやって行けばあの50c cバイクで行けるでしょう。」
奥さん:「うわあ〜〜! そぎゃん小さかバイクで長崎まで! 急ぎなんね? よーし。わかったぞ。探してみよう!」
そう言って、机の上に大きな地図帳を開いた。
奥さん:「まずねえ、今はここね。で、目指すのがここ。ほれ。津奈木町(つなぎまち)ね。」
青年:「つなぎまち? いい名前ですねえ!」
奥さん:「昔ん天皇しゃんがこっちきた時な、船ば『おつなぎになった』ちゅう伝説があるらしいばい〜。
そんで、ここから、、、ここまでいく。まずは。
はい、ここまでメモしてー!」
青年:「あ、はい! 津奈木町から・・・。」
奥さん:「長洲町(ながすまち)へ。」
青年:「つなぎ、から、ながす。ですね。はい書きました。」
奥さん:「そこからフェリーがあるけん、乗っていきよ。そしたら、雲仙ん多比良(たいら)に着くけんね。そこが島原ばい。よかとこばい〜!」
青年:「ふむ! 長洲町から、フェリーで一気に島原ですか!」
奥さん:「うん。そっから諫早ば抜けて、長崎まで行く、と。まあ、こんな感じばい!」
青年:「繋ぎ、流す、平ら。覚えました! つないで、流せば、平らになる。つないで、流せば・・・。」
呪文のように土地の名前を覚えた青年は、これで行けると確信した。
青年:「ありがとうございました! では!」
奥さん:「あ、ちょっと! 待ちっちっちっち。」
と呼び止めて、机の後ろの棚から取り出したのは、年賀状の束だ。
それをどさっと机に出した。
奥さん:「お兄さん、諫早ん行くよねえ?」
年賀状をまるでトランプのように、横にずらっとスライドして並べる。
青年:「あ、はい。言われたとおり行こうかと思っていますが・・・。」
奥さん:「じゃあ、せっかくやけん、諫早ん・・・あのねえ。ちょっとまちよおー。」
たくさんの年賀状から、なにかを探しているようだ。
奥さん:「あった!」
一枚の年賀状を掲げる。
その裏面には、ボートのパドルらしきイラストが大きく描いてあった。
奥さん:「諫早といえば、こんお店に行ってご覧!
名前はねえ、『櫂(かい)』!
まあ、なにを食べてもうまかお店でねえ。
ここの奥さんがうちん友達でね。今年赤ちゃんが産まれたとよ〜。」
青年:「へえ〜それは! 嬉しいですねえ。」
奥さん:「でも、なかなか会えんたい。
やけん、まだお祝いばしとらんのや。
お兄しゃん、できればプレゼント、持っていって渡しちゃってくれん?」
青年:「ぼ、僕がですか?」
奥さん:「ごめんやでえ〜。旅のついででごめん。えーか?
なあ、ほら、タカ坊もお願い! って言いよるたい。
(高い声で)お・に・い・しゃん! オネガイッ!」
タカ坊はどう見ても寝ているが。。。
またしてもな急展開に青年は戸惑う。
奥さんの怒涛のトークに頷きつつも、
青年:「で、できるかなあ?」
と、少し悩ましい。
青年はとみちゃんのことを思い出していた。違うケースとはいえ、青年はなんだかこの旅、配達人になる機会がやたら多い。
いいのだろうか、こんなことばっかりで。ていうか、そもそも何を手渡すのだろう?
奥さんはそんな青年の不安を気にすることもなく、後ろの部屋から小さな紙袋を持ってきた。
奥さん:「これ。ディディモスのベビーラップたい。
あんまり売っとらんけん、あげよう思うて。思いつきなんやばってん、頼まれてくれん?」
青年:「モスバーガーのベビーナッツ?」
奥さん:「違う! ディディモスってブランドの、赤ちゃんばくるんで抱っこする、布んこと!」
青年:「ああ、わかった! ベビーラップですね!」
奥さん:「そう言うてたけどな、あたし!(笑)」
そう言って、ピンクのリボンが付いた紙袋を渡された。
なんで道を尋ねた僕にこんな大事なものを預けるのかなどと考えるヒマもなく、渡された以上、よし、もうやるしかないと思う。
それが長崎への行き方を詳しく教えていただいたお礼にもなる。
青年:「お安い御用です! お茶漬けサラサラです! 僕も目的があると嬉しいですから!!」
奥さん:「嬉しか〜!! ありがとう! あたし、『せっちゃん』って言うと。
友達は『白崎さん』ね。住所もメモに書くけん、くれぐれもよろしゅうお伝えしなっせ!
あ、あと、お茶の子さいさい、ばい!」
多比良から諫早へ
熊本県の長洲町から長崎に向かうフェリーはちょっと小ぶりで、船体は白を基調にカラフルな色使いをしていた。ダックス号によく似合う可愛さだ。
フェリー乗り場に着いた時間もちょうどよく、待たずにすぐ乗れた。
紳士的に波静かな有明海を粛々と渡り、青年が持つかっぱえびせんをつけ狙うカモメさん達と賑やかに過ごしながら、多比良港に到着した。
長崎県は高校の修学旅行以来、2度目となる。
さんさんと照りつける太陽に負けないほどのマグマ熱を感じさせる雲仙の噴煙を左に見ながら、諫早へすんなりと到着。
交番から5時間以上はかかったが、ガソリンを入れるのは1回で済んだ。最初に想定していたよりも相当ショートカットできたようだ。
有り難う、せっちゃん。
さあ、ここから、このところライフワークと化している配達仕事にとりかかるのだ!
お店の名前は、櫂!
えーっと、どんなお店だろうか?
もらったメモの住所の付近を看板を探しながらトロトロと走っていると、肌が真っ黒で、角刈りの男性とすれ違い、目が合った。
あれ? 睨まれた?
いや、青年のバイクをじーっと眺めていたので、バイク好きなのかも?
すれ違ったあと、バックミラーを見ると、まだ青年の方を見ている。
あ、ひょっとして?
ブレーキをかけて、後ろを振り返ると同時に、
青年:「白崎さん?」
角刈りの男:「鈴木さん?」
おおっ! やはり!!!
青年は、嬉々として男性に向けてバイクを切り返す。
白崎さん:「熊本のせっちゃんから連絡をもらいました。白崎と申します。」
一見、怖いヒトかと思ったが、標準語と、洗練された礼儀正しさが心地いい。
青年よりは年上だが、若い。青年は27歳と踏んだ。
しかし、いつ着くのかわからないだろうに、ここでずっと待っていてくれたのだろうか。青年は申し訳ない気持ちになった。
白崎さん:「どうぞこちらへ。お店まで、少し歩きます。」
青年は、ダックス号を降りて押しながら、一緒に歩く。しかし、白崎さんは何も喋らない。あまり感情を外に出さない、無口な人のようだ。
青年は、そんな白崎さんの性格を想像する。
クールだけど、丁寧な物腰で、僕をずっと待ち続けてくれていた白崎さん。
きっと、とっても真面目で、これぞ自分の生きる道だ! と決めたら、1歩たりともブレずに進むことができる、強い意志を持っているすごい人だ。
うん、尊敬!
櫂
お店の場所は本当に分かりにくく、細い路地を一度入っただけでは辿りつかない場所にあった。
まるで隠れ家のようなロケーションが青年をまた興奮させる。
白崎さん:「ここです。小さい店ですが。」
そこは、民家の一軒家を改装した建物だった。自己主張を控えた、なんとも清廉な佇まいだ。
相当な旧家屋に見えるにも関わらず、1階に「出窓」が付いているのが目を引く。
その出窓の中には大きな茶トラの猫が、この熱さにもめげず寝ていた。
猫はうっすら目を開けて青年を見ると、ぐるんとひっくり返り、お腹を見せてグググっと伸びをする。
いまは午後2時。暖簾はかかっていない。
玄関の横に掲げられている木彫りの看板がある。
料創
理作
櫂
青年:「なるほど。料創、理作、櫂。いやあ、なんか哲学的な重みを感じますなあ。」
白崎さん:「ぷっ。いや、上から読みます。創作料理、櫂。」
青年:「あっ、はずかしいっ!」
賢明な読者はもうお分かりのとおり、青年は、文字の読解が得意ではない。
言葉の空間認知が苦手で、時折おかしな読み方をしたり、思い切り間違った聞き取りをしてしまうのだ。
それで昔からあまたの苦労を重ねてはいるが、生まれつきで治しようもないし、だいたい周囲には笑って許してもらえているので、それでヨシとしている。
お店の入り口近くには、大きなカヌーが置いてあった。長いボディーだ。2人乗り用だという。
お店は奥に細長い造りで、左側のキッチンに面したカウンター席。その奥に、テーブル席がある部屋が続いている。
お店の右側、カウンターの後ろには、2階へあがる階段がある。
1階だけで、20人くらいは入れそうな感じだ。
キッチンは磨き抜かれてどこも輝いている。こういうところにも、白崎さんの几帳面な性格がうかがえる。
白崎さん:「どうぞ、おかけください。」
白崎さんはそう言って、自分はキッチンの中に入り、青年に冷たいお茶を出してくれた。
早速いただこうとカウンターに座りかけた青年は、後ろを振り向き、また立ち上がる。
階段の下の壁一面が、書籍だらけだ。その本棚に、日本酒と洋酒の瓶も並んでいる。
本と、酒。これはなかなか味わい深い酒肴、いや趣向ではないか。
そこへ奥さんらしき人が、赤ちゃんを抱いて2階から降りてきた。
赤ちゃんはぐずっているようで、大声で泣いている。奥さんはその声に負けない声で、
奥様:「いらっしゃい! せっちゃんから聞いてます。わたし、節子と言います。」
青年:「え? あ、おんなじ?」
節子さん:「はい、せっちゃんと同じ名前なんです。性格は真反対で、わたしはぜんぜんマイペースなんですが。」
といって、赤ちゃんをあやしながら笑う。たしかに、せっちゃんと比べると、喋るスピードが遅めだ。でも、青年には理解しやすくて嬉しい。
節子さん:「鈴木さん、ですよね。今日はわざわざありがとうございます。まずはごゆっくり。お腹、空いてません?」
本来なら、ここはお構いなく。と笑顔で答えるところであるが、青年はかまっていただくことが、お互いの喜びになると強く信じている節があるので、遠慮しない。
青年:「実はもう、ペッコペコなんですう!」
節子さん:「キャハッ! よかった!」
じゃあ、あなた、お願いね。と言わんばかりの目配せを、節子さんはご主人に向かってした。
ご主人は、無言でうなずいて、腰にエプロンを巻く。
青年はここで違和感を感じた。
この2人は言葉を交わさないし、目も合わせていない。
無表情なのは白崎さんの性格かと思ったが、なにかあるのかな・・・?
そう思ったところで、ふと熱い視線を感じた青年。
うわ。真横の椅子に、さっき出窓で寝ていた茶トラ猫が座っている。
見るからにオスとわかる、がっしりとした体型。緑色の目を鋭く光らせながら、青年に挨拶を迫っていた。
カワちゃん
節子さん:「あ、来たね。その子、カワちゃんっていいます。裏の川で出会ったから、カワちゃん。」
青年:「そっか、カーワちゃん、お邪魔してるよー。よろしくね。」
三日月の目を見て、猫はゴロゴロと喉を鳴らして青年の腕にスリスリしてきた。これは「さわらせにゃんこ」と見て間違いない。
青年は小さい頃から猫を飼っていたので、すぐお友達になれるコツを知っている。それはまず、ちゃんと言葉で褒めること。
青年:「カワちゃんは、可愛いのカワちゃんでもあるね。ふんふん、君はこのお店の招き猫なのか! いつもありがとうね。」
青年は、縦模様の入った額を、指の腹でやさしく撫でる。猫と人間、ともに至福の時間だ。
するとまた青年の視線センサーが反応した。
またどこからか見られている!
熱視線ビームはすぐ横から放たれていた。
節子さんに抱っこされている赤ちゃんがいつのまにか泣き止んでいて、目をまん丸に開き、青年をじーっと見ていたのだ。
節子さん:「あら、ラナちゃん、お兄ちゃんにご挨拶したいのね?」
青年:「ラナちゃんっていうんだ! 未来少年コナンに出てきたお姫様のお名前ですよね!」
節子さん:「あ、ラナイって言います。ハワイ語で、ベランダのような気持ち良い風が吹くって意味。」
青年:「くわっこいい・・・。ラナイちゃん、はじめまして。」
赤ちゃんの目を愛おしそうに眺めて、ペコリを頭を下げる青年。
するとそれに応えるように、
ラナちゃん:「あーうー。ああ、あーあ。」
その言葉にハッとした青年は、慌ててせっちゃんから預かった紙袋をカバンから取り出して、節子さんに渡す。
節子さん:「わあ、ありがとう! ラナちゃんがほちいのは、これでちゅか〜?」
ラナちゃんは、紙袋を両手で頂戴頂戴をし、その小さな手でリボンをぎゅっと握った。
ラナちゃん:「ああ、ああ、あ、あー、あとっぷー。」
青年:「うん、そうかそうか! あーよかった。これでお母さんも少し楽になるんだね。」
奥さんは、目をまん丸にしながら、
節子さん:「お兄さん、この子の言葉がわかるんですか?」
青年:「いいえ、わかりませんけど、きっと奥さんは、もうすぐせっちゃんからとっても嬉しいものが届くよ。といった内容のことを、この子におしゃべりしたんではないですか?」
節子さん:「しました! 楽しみに待っておこうねって。ね。」
ラナちゃん:「ああ、あいあい、なぁ。」
これが「ありがとなぁ」と聞こえて、青年と節子さんは大笑いした。
早速、ベビーラップを袋から取り出す。
節子さん:「うわあ、ディディモスの。うれしいなあ。」
さっそく、鮮やかな萌黄色のラップを首から下げて、ラナちゃんを入れ、安定して抱っこができる様子をご主人に見せる。
節子さん:「ほら! こういうの、欲しかったんだよ〜!」
白崎さんは少し笑っただけで、また調理に戻る。
やはり、どうやらここには青年が苦手なケンアクムードが展開中のようだ。
少し困った顔をした青年の膝に、カウンターに乗っていたカワちゃんがドスン、と降りてきた。
青年:「あ、君も抱っこしてほしいんか〜。」
青年は立ち上がり、節子さんと同じような姿勢で猫を抱っこする。
膝を使って、カワちゃん、かわかわ〜〜〜。よし、よし。
ラナちゃんにカワちゃんを近づけると、大喜びで尻尾を握って振り回す。いやがる声を出すカワちゃん。
猫と赤ちゃんと戯れながら、まあ、でも、そりゃあ夫婦はいろいろあるよな。と思う青年。
消えゆく自然
何気なく本棚を見ると、様々な種類の本のタイトルの中に、ひとつ目を引くものがあった。
「日本の川を旅する」と書かれてある本。
青年は、猫をちょっとごめんね、と椅子に戻すと、その本をとった。
あれ?
青年は不思議な感覚に陥った。
記憶の片隅に出てくる。ヒゲの男の顔。
このヒト、高知の四万十川で出会った、犬を連れた、カヌーの男じゃないか!
著者は「野田知佑(のだ ともすけ)」。
犬の写真も、あの犬と同じだ。
白崎さん:「好きなんですね?」
気がつけば、白崎さんが横にいた。
青年は、いや、はじめて見ました、と言って、
青年:「この本とか、のんびり行こうぜ。川を下って都会の中へ。ゆらゆらとユーコン。ガリバーが行く。この方って・・・?」
白崎さん:「僕の師匠です。シーカヤックの。」
そう言って、指差した先にあったのは、真っ白な浜辺にシーカヤックを並べて写る、真っ黒に日焼けした男たちの顔。
その中に一人、見覚えのあるヒゲ。
青年:「ああ、この人、僕、四万十川で会った人かもしれません。」
それまでクールだった白崎さんは突然、大きな声を出す。
ご主人:「ええ? 会えたんですか? それは運がいい! 今、野田先生はどんどん忙しくなってきていて、のんびりと旅もできないとぼやいてましたからね。下ってました?」
青年:「はい。のんびり下ってました!」
さすが先生だと言わんばかりの頷き方で、そっかあ〜と感慨深そうに笑う。青年はここではじめて白崎さんがしっかり笑った顔を見た。
白崎さんはその笑顔のままでキッチンに戻ると、唐突につぶやいた。
白崎さん:「僕たちね、このお店、閉めるんです。」
青年は、一瞬、その言葉の意味がわからなかった。
節子さんを見ると、悲しそうな顔で下を向く。
あ、閉店するのか。。。
節子さん:「諫早湾の干拓事業が進んでるんです。これ、もう止まらないんです。だから主人は、もう諦めようって。」
青年:「干拓? って、実際何をどうするんですか? 進むと、何が起きるんですか? それでこのお店がなくなっちゃうんでしょうか?」
白崎さん:「まあまずは、これを食べてください。」
カウンターに出てきたのはお刺身だった。色と肉質は貝柱に見える。
促されてひと口。醤油をつけずに頬張る。
青年:「これは! 美味っしいです! ホタテですか? いや、ホタテじゃないな。」
節子さん:「たいらぎです。貝です。この有明でとれます。」
白崎さん:「これがそうです。」
と言って三角の二枚貝を青年に見せた。おわ・・・でかい。
白崎さん:「この貝に惚れて、私たちは神奈川からここに来たんです。これもどうぞ。」
そう言って出されてのは、たいらぎの炙りと、お吸い物。
「旨味ーーーっ!」
これも絶品だ。
しかし、諫早湾の干拓工事が進むにつれて、こんな大切な海の宝がいなくなっていくことに、2人は絶望していたのだ。
野田さんにこの現実を報告し、周りの人たちにも相談し、あらゆるご縁に連絡したが、どうしようもないと。
どんなに声をあげても、何も変わらないことと、大好きなたいらぎをお客様に提供できなくなってしまうこと。
シェフである白崎さんは特に、子どもをここで育てていく自信がなくなっていた。
白崎さん:「だからもう、限界だなって。」
節子さん:「まあ、主人がどうしてもって言うなら、しょうがないんですが・・・。」
青年:「あ、じゃあ奥さんはまだ続けていきたいんですね?」
ちらっとご主人のほうを見て、黙ってしまう節子さん。
そして全員が無言モード。
そんな中、ラナちゃん姫はぐっすりと寝てくれたようだ。
節子さんはカウンターに置いたクーファン(赤ちゃん用のかご)にラナちゃんをゆっくりと降ろした。
青年はこの場の雰囲気がやりきれず、また野田さんの本を適当に取って、パラパラとめくる。
そこで青年の手が止まった。
青年:「あの、この本(ゆらゆらとユーコン)にこう書かれてありますね。
読んだページは片っぱしから破って、焚火のタキツケにする。
雨後や霧で薪が濡れた朝の焚火など、タキツケはいくらあっても足りない。
以前、雨が降り続き、ガスが切れたことがあって、その時テントの中で、本を燃してメシを炊いたことがある。
白崎さん:「ああ。その部分。いいですよね。」
青年:「はい、ここに線が引いてあるんです。どうしてここに?」
白崎さん:「え? 線、引いてます? あ、ほんとだ。」
自分で線を引いた覚えがないという。でも、多分酔っ払いながら引いたのでしょう。きっと野田さんらしいなと思ったのだと思います。と照れた。
青年は、天井を見上げると、しばらく考えた風で、2人にこう伝えた。
青年:「もしかするとですが、これは、いまの白崎さんに、昔の白崎さんが伝えたいことだったんじゃないでしょうか?」
白崎さん:「・・・と、いいますと?」
青年:「野田さんの生き方のことです。
今まで経験してきたことを、そして使い終わったことやものを、次のステップとして役に立てるってところに感動したのではないですか?
寒い、木が全部しめってる。体温がなくなる。もうダメかもしれない。このままでは火がつかないかもしれない。しかし燃えるものは何もない。
あ、本がある。
よかった。旅を続けるために燃やすなら、それはそれで価値がある。と野田さんは考えたんだと思ったんです。」
節子さん:「旅を続けるために・・・。
そうよ。やっぱり私たち、お店を閉める必要なんてないんじゃないかしら? これで終わることはないよ。
この場所で、今までの経験を糧に、また新しい食材で、次の扉を開けばいいだけじゃない?」
白崎さん:「それは僕だって何回も考えた。だけど、僕は、どうしても明るい未来を信じられないんだ。だから、僕は・・・。」
うつむいて、肩と拳に力を入れる白崎さん。みんなが次の言葉を待つ。
信じること
白崎さん:「だから僕は今日、鈴木さんを迎えに行った。本当に来るのか。来るならいったいどんな人なのか、よく見てやろうと思って。」
青年:「え? 僕を?」
白崎さん:「はい、すいません。僕は正直、驚いたんです。せっちゃんからの電話で、旅する青年にお祝いを預けたから受け取ってくれって。
初めて会った見も知らない青年に、そんなことお願いするか? って。」
青年:「あ、そこ、僕もすごく同感です。」
白崎さん:「僕は思ったんです。せっちゃんは、はじめて出会った鈴木さんを信じた。鈴木さんも、会ったことのない僕達を信じた。節子も、鈴木さんを到着するのを信じた。僕だけです。信じていなかったのは。」
青年:「あの〜。それって、普通だと思いますよ。」
白崎さん:「いいえ、人間はすぐ変わってしまう。だから僕は人を信じる事ができない、これは僕の欠点です。自分のずっと嫌なところです。
だからこそ僕は、ずっと変わらない自然そのものに強く惹かれた。しかし、それも結局、こうやって人に壊され、形を変えていってしまうなんて。。。
もう、僕はどうしたらいいのか・・・。」
キッチンに両手をつき、体を震わせる白崎さん。節子さんが涙目でその背中を優しくさする。
青年はここで、このような重苦しい雰囲気にはまったくそぐわない、明るくて軽い声をあえて発する。
そういえば青年は、塾のバイトで子どもたちに「アンポンマン」と言われたことがあるが、あんぽんたんになる勇気があるという意味で、それは正しい。
青年:「あのですね、人を信じるって、そんな難しいことじゃなくってぇ〜。」
白崎さんは間の抜けた声を出す青年を睨みつけるように、
白崎さん:「いや、これは僕にとったら雲をつかむような話なんです。」
青年は「雲かあ〜。」と高い声で言ってまた天井を見上げて、ふんふんと頷くと、節子さんに問いかけた。
青年:「節子さんは、お分かりですよね。人を信じるって、どういうことなのか。」
節子さん:「わたし? わたしは、難しいことは分からないけれど、信じるっていうのは、『相談すること』だと思うんです。
主人はわたしに相談をしません。それって、すごく寂しいことなんです。わたしを信じてくれていないのかって。
相談は、相手を信じているからこそ、できると思うんです。違うでしょうか?」
青年:「信じるって、人に言うって書きますもんね。つまり、会話から生まれるんだと思います。
でも白崎さんのおっしゃることも分かります。相談って、たしかに重い会話です。
でもだからこそ、それをきっかけに、胸の内を語り合うことができて、強い信頼が生まれてくるんじゃないでしょうか?」
白崎さん:「なんでも本音で語り合え、と? でもそれじゃあ、節子を心配させてしまいます。」
節子さん:「心配なんてしないわよ。これは2人で決めた道なんだから。相談がないほうが心配なの!」
青年:「自然は、残念ながら、どうしても変わっていきます。人の営みが変わっていくからです。でも、人間には、絶対に変わらないものがある。僕はそう信じたいです。」
白崎さんは青年の言葉を噛み締めているようだ。
そのとき、3人のちょうど真ん中のカウンターで寝ていたカワちゃんが、大きく伸びをして、あくびをする。
そうしてゆっくりと3人の顔を見回すと、ラナちゃんが眠るクーファンに近寄り、ラナちゃんの足元にのっそりとかぶさって丸くなった。
青年:「ほら、ラナちゃんを見てください。かわいいあんよの上に、カワちゃんが寝ていますよ。」
節子さん:「うふふ。かわいい。」
青年:「白崎さん、読めませんか?」
白崎さん:「・・・なにがですか?」
青年:「ラナちゃんと、カワちゃんです。言葉を足すと?」
白崎さん:「ラナ、カワ?」
青年:「いいえ、上から読むんです。」
白崎さん:「カワ、ラナイ。あ・・・カワラナイ、変わらない。
ああっ!!!」
その瞬間、節子さんも短く叫んだような声を出した。そして両手を顔に当てたまま、言葉が出ない。
白崎さん:「節子・・・・・・。」
白崎さんは男泣きに泣いた。2人とも泣きながら、お互いの背中をさすり続ける。
白崎さん:「やっと分かりました・・・。
ずっと変わらないものが、ここにありました。
一番大切なことに気がついていない、僕がバカでした。
これから僕は、節子を信じて、相談しながら、再度挑戦してみます。
節子とラナイを、必ず幸せにします。」
青年:「3人はもう幸せだと思います。こんなに愛情豊かなご家庭なんですもの。
これから白崎さんたちは、どんなピンチが来ても、お師匠の野田さんのように、そのときに使える知恵を総動員して生き抜いていけると思います。」
白崎さん:「はい。柔軟に、どんな経験でも、燃料に変えて、次のステップへ進んでいきます。」
節子さん:「これからまた新しい海へ、みんなで漕ぎ出していきます。」
青年はご夫妻に、ご馳走になったお礼をして外に出る。
ダックス号のシートの上には、カワちゃんが乗っていた。
青年:「あっ、カワちゃん、運転してくれるってことなんやね。ありがとう! でも君はこのお店の招き猫だし、ラナちゃんの面倒も見なきゃいけないでしょ?」
そう言うと、カワちゃんはさっと地面にジャンプして、あっさりとクーファンに戻った。
白崎さんご夫婦とは、玄関先で強く握手をして別れた。
2人はお互いの肩を抱きながら、青年が角を曲がるまで、大きくゆっくりと手を振ってくれた。
折り鶴の想い
午後4時過ぎ。
青年の次なる目的地は、長崎平和公園の、平和祈念像だ。
ここからは40分もあれば到着するはず。
走りながら、青年は決めた。
野田さんの著書を、大阪に帰ってからすべて読もう。
余談だが、大学卒業時の卒論は、椎名誠氏と野田知佑氏の論文を書いたほど、この日以来、この二人の著書を読み漁った青年であった。
長崎平和公園に到着。陽はまだ高い。
ダックス号を駐車場に停めて、長い階段を登っていく。観光客はひっきりなしだ。外国人も多い。修学旅行生もわんさかいる。
青年は、オレンジ色のヘルメットを片手にぶら下げて歩く。
だんだん見えてくる雄大な像。すごい。
実をいうと青年は、バイト先の子どもたちとの約束を果たすために来たのだ。
青年は歩きながら、リュックの中にある小さな折り鶴を出す。
これは、当時アルバイトをしていた学童保育で子どもたちと折った鶴だ。
ある日、原爆の悲しい絵本を読み聞かせたあと、みんなが折り鶴を折りたいと言ったので、できる限りの鶴を折って、いつか長崎に飾ろうということになった。
折ったのはたった22羽だったが、青年にとっては、子どもたちの心がこもった大事な鶴だ。
これは青年の「行きあたりばっ旅」のセオリーとは反するが、約束を守ることで子どもたちに言えることが一つできる。
「みんなの思いは、世界に届く!」
平和祈念像の横、三角屋根の折り鶴の塔に飾ることができた青年はホッとして、手を合わせ、首を垂れる。
その時、青年は、床に落とし物を発見してしまった。
24枚撮りのカラーネガフィルムだ。
今はほとんどがデジタル化しているので、フィルム形式のカメラなどは過去の遺物となっている。しかし、当時は全部フィルムだったのだ。
それを拾ってカバンに入れた。ええっと、どこに届ければいいのだろう。
悩みながら青年は、カバンに入れたことを忘れて旅を続けてしまう。さすがアンポンマン。気づいたのは、大阪に帰ってからという情けなさ。
そのお話は後ほど。
青年は、記念像に近づく。
やはり圧巻だ。
涙ぐみ、万感の思いで像を見上げている青年に、突然後ろから声がかけられた。
家族連れのお父さんが、奥様とお子様を入れて、一緒に写真を撮ってほしいとのこと。良いでしょうか? と恐る恐る聞くお父さんに対して、
青年:「お茶漬けサラサラですよ〜!」
お子様がぼそっと「お茶の子さいさい」と言う。
青年は、ヘルメットとリュックを地面に置き、親子の記念撮影を開始する。縦向きと横向きの2枚。撮りますよ〜カシャ。
ではない。
こういう場合、まず青年はヒアリングからはじめる。
青年:「何枚撮りますか?」
1枚で。と言われたら、その1枚に全力を投入。2枚と言われたら縦横で1枚ずつ。これも全身全霊で撮影だ。
青年は、その親子連れの写真を1枚撮ったがために、違う旅行客からも声をかけられることになる。
メガネの男性:「あのお、スンマヘン。あっしの写真も1枚よろしいでっか?」
青年はもちろん断らない。そうやって撮っていると、思ってもみない事態が生まれた。
なんとそこに、行列が生まれ始めたのだ。
青年の撮影方法が独特なせいもあるのだが、後からくる人は、無料で写真を撮ってくれる公園のサービスだと思っている節があったのも否めない。
中でも、松葉杖をしたお母さんと、その旦那さんは、5枚撮ってくださいということで、いろんなポーズで撮影したものだから、そこから後のお客様には、素敵なポージング考案時間も追加され、さらに行列ができていってしまった。
そこに、地元の小学生で、社会科見学だった女子が2人並んだ。青年は、撮影しつつ、あとに続くお客様の列も眺めているので、2人のことも観察していた。
青年は、その2人組の様子に、なにか違和感がある。なんの違和感かはまだわからない。
青年の嗅覚は、子どもに関わることとなると、急激に敏感になるのだ。
その2人の後には誰も並ばなかったので、最後のお客さんの予定だ。
炎天下で、大きな声で大汗をかきながら、祈念像を確実に構図に入れて笑顔の観光客を撮影し続けるのは、なかなかの重労働である。
撮られた方は、長崎に来てよかった。変なボランティアカメラマンに撮ってもらった。あんな撮り方なら必ずみんな笑顔になるよね。発明だよね。などと言いながら、順番は最後の女の子2人組に近づいてくる。
1人の女の子は嬉しそうにジャンプしている。待ちきれないようだ。しかし、もう1人は全く青年を見ようとしない。
いよいよ2人の顔を間近に見たとき、青年はようやく、違和感の理由を理解した。
〜つづく〜
ここから先は

KAMI ing out マガジン
「僕のアニキは神様とお話ができます」「サイン」の著者、アニキ(くまちゃん)が執筆。天性のおりられ体質を活用し、神様からのメッセージを届けま…
ご支援ありがとうございます。このnoteはサポートのお志で成り立っております。メッセージにお名前(ご本名とご住所)も入れていただけると、感謝とサチアレ念をダイレクトに飛ばさせていただきます。
