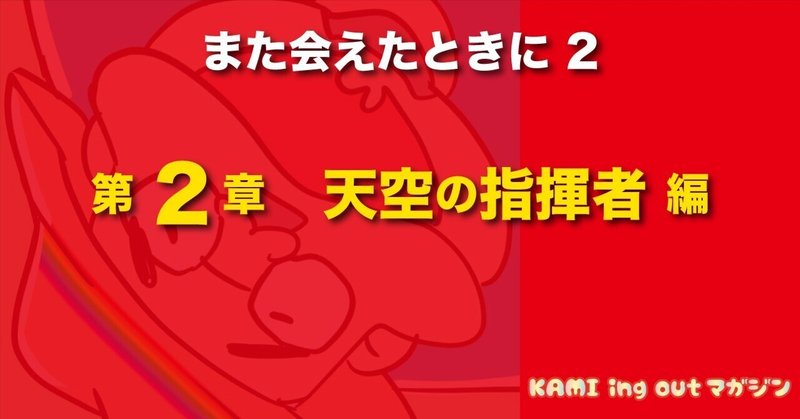
ロードムービー原作「また会えたときに 2」 第2章(天空の指揮者編)
本日もようこそいらっしゃいました。
ロードムービー原作の第2章は、みなさまを香川県にお連れします。
八幡様:「では、今回も頑張りましょう。アニキ、大丈夫ですか?」
僕:「はい、不安になる準備OKです!」
八幡様:「おやおや、ネタはあるでしょう。ほら、香川県と言えば?」
僕:「そりゃあ、なんといっても讃岐うどんですよね! 」
八幡様:「さらに?」
僕:「あ、金毘羅さんです!」
八幡様:「からの?」
僕:「えっと、香川なので、あれ? ドカベンって関係してましたっけ?」
八幡様:「それは元プロ野球選手の香川伸行さん。香川さんは徳島県生まれです。」
僕:「や、ややこしいっ!」
八幡様:「大ヒント。合唱です。」
僕:「ああ〜っ! 思い出した! あれはそうだ、香川県でしたね。懐かしいです。めっちゃ合唱、しました。」
八幡様:「あれは愉快でしたね。」
僕:「はい。そこで僕は学校の先生になりたい、と本気で思ったんです。」
八幡様:「大事な話です。早速原作にまとめていきましょうか。」
僕:「かしこまりました。」
「また会えたときに 2」 第2章
天空の指揮者
高松港に着いたのは午後2 時前。
薄水色の空の下、黄色いダックス号で「讃岐街道」と呼ばれる道を鼻歌まじりでゆっくりと徳島方面に向かって走る青年。
この旅をはじめる前、青年が描いていた旅プランはこうだ。
まずは下宿のある大阪から岡山まで、とろとろと走る。
以上。
あとは青年が「いきあたりばっ旅」と呼ぶ、無計画モードに突入する。
そしていつだって、何かが起こる。
その証拠に、岡山から気まぐれにフェリーで四国を目指したところ、海上でちょっとした事件があり、なかなか際どいところだったが、ありがたいことに無事生還。
高松からは、徳島・高知・愛媛とゆっくり走破するつもりだ。
その後、愛媛からまたフェリーに乗り、九州に上陸するのも楽しそうだと思っている。
その先は? それはまたその時々で考えよう。
小回りの効くダックス号の特性を活かし、島から島へと〜♪と、母がよく歌っていた歌を口ずさむ青年。
ちなみに我らのダックス号は、時速60キロまでは出るが、スピードは30キロまでしか出してはいけない。
※原付きの法低速度は時速30km
高速道路に乗るなんてのはもってのほか。天下御免の下道専用車なのだ。
逆に言えば、スピードはカンタンに落とせるので、なにか気になるものがあればすぐに止まって、すぐに降りることができる。
おかげで、レアな風景を楽しめたり、人の生活を至近距離で見たり、その土地でしか食べられないものを見つけたり、それを笑顔で物欲しそうに見ているだけで食べさせていただいたり。
青年はことあるごとに、ダックス号をパートナーに選んで良かった! と感謝している。
この日も、気になったお店や、気になった人に遠慮なく話しかけながら、のんびりと進む。
青年は元来、生まれついての人見知りだと認じていたが、なぜかいつも旅に出た瞬間から、恐れを知らぬ人好きライダーに変身するのだ。
「今回はどんな出会いがあるのかなあ〜。お腹へったなあ〜。」
と思いつつ山の中を走っていたら、2本の別れ道に鹿が立っていた。飛ぶように逃げていった道を選んだらすぐ製麺所が見えてきて、迷わず生醤油ぶっかけうどんを2 杯食べてご満悦の青年。
坂道を気持ちよくくだり、ちょっと拓けた平野の小さな川沿いの県道をひた走っている最中、左手の川向こうで目に止まった風景がある。
そこは小高くて平たい丘のようになっていて、古びた木製の鳥居が見える。そしてその奥には小さな神社があった。
その神社に向かって立つ、白いワイシャツの男性の背中。
ひとり両手をあげて、神社の屋根の方を向いて・・・。
さて、なにをしているんだろう?
青年は道端にダックス号を停めて、目を凝らす。
どうも手の動きを見ると、指揮者のような動きをしているようだ。
なぜ?
でもあの動きはどう見ても指揮だ。なんで神社で、ひとりで指揮をしている?
青年は思った。
「興味ジンジン!!!」
すぐさま小さな橋を渡り、丘を駆けのぼって鳥居のそばにダックス号を停める。オレンジ色のヘルメットをサイドミラーにかけ、鳥居で深く一礼をし、くぐる。
古ぼけた神社は、トタンの壁でできていた。
青年は社殿の前に立つ、天空の指揮者に近づいていく。
後ろ姿しか見えないが、細身。白い半袖のワイシャツ。グレーのスラックスに、黒い革靴。髪の毛は艶のある黒で、少し長めだ。
青年は指揮者に近付いて、さらに驚く。
指揮をしながら、歌ってる!
そのとき、指揮者は空にかかげた手をピタっと止めた。青年の気配に気が付いたのだ。
ゆっくりと、青年に向かって振り向く指揮者。
あれ、おじいさんだ。青年はてっきり若い方と思っていたので驚く。
黒縁の太いメガネをかけたおじいさんは、青年の三日月の目を見て、微笑む。そしてニカっと笑う。前歯がない。青年も負けじと歯を大きく出して笑う。
青年:「こんにちは! 何の歌を指揮されていたんですか?」
おじいさんはうんうんと頷いて、コホン、と咳払い。ちょっと待たれい、という手振りをする。
そして、トタンの社殿に向き直り、居ずまいをただし、丁寧に敬礼をした。続いて、踵をつけたまま回れ右をして、青年の方にきゅっと振り向いた。
揺れるループタイを右手でキュッと締め上げる。
「こんにちは。」
おじいさんはそう言ってから、深々と礼をする。
な、なんて美しい所作なんだ! 青年は見とれてしまい、危うく返礼をするのを忘れるところだった。
おじいさん:「これは歩兵の本領、という昔むかしの曲ですな。うん。ご存知ないと思いますよ。」
おじいさんは昔、仲間と共にこの歌を繰り返し歌ったものです。と言う。
よくよく話を聞くと、今度、生き残った戦友たちと同窓会をしようということになり、その時みんなで一緒に歌を歌おうということになったそうな。
それが嬉しくて、おじいさんは指揮の練習をこの神社でひとりやっていたというわけだ。
おじいさんは、
「ちょっとお尋ねするが。」
と口を開いた。青年はここにきた理由を聞かれると思ったが、違った。
「あなたは、うん。歌はお好きかな?」
青年は、相手からどんな質問がきたとしても即答する妙技を持っている。
青年:「はい! 歌は大好きです。えっと、僕が歌える曲は、蛍の光、故郷、仰げば尊し、とかです。」
メガネの下、おじいさんの目がキラリと光る。
仰げば尊し。蛍の光。うんうん。わしらは、その歌も何度も何度も、戦地で歌ったもんじゃ。
学校でも子どもたちとも一緒に、うん、何回ものう。そう言って、遠い目をする。
懐かしさと、切なさが入り混じった、なんともいえない表情だ。
戦争の悲劇を思い起こしているのかもしれない。あるいは、このおじいさんは地元の先生だったのかもしれない。
いずれにしろ、これもなにかのご縁だと感じた青年はこう言った。
青年:「では、歌いましょうか! 指揮をお願いしてもよろしいですか?」
おじいさんはうれしそうに、
「そうか! うん、では僭越ながら。」
と言うと、威勢よく両手を上げた。
歌い始めの伴奏を口にするおじいさん。ラーラ、ラーラーララー。
口で歌う三拍子のピアノ前奏。「仰げば尊し」だ。
ふくらむ合唱
2 人の歌声が、小さな神社を包んだ。
【 1番 】
仰げば尊し わが師の恩
教えの庭にも はや幾年(いくとせ)
思えば いと疾し(とし) この年月(としつき)
今こそ別れめ いざさらば
【 2番 】
互いに 睦(むつみ)し 日頃の恩
別れるる後にも やよ忘るな
身を立て 名をあげ やよ励めよ
今こそ別れめ いざさらば
【 3番 】
朝夕慣れにし 学びの窓
蛍の灯火(ともしび) 積む白雪(しらゆき)
忘るる間(ま)ぞなき ゆく年月(としつき)
今こそ別れめ いざさらば
おじいさんは懸命に指揮をしながら、青年と一緒に歌った。
最初は小さく、かすれた声だったのに、だんだん張りのある声になっていく。それにつられて、青年の声もますます太く大きく伸びる。
しばらくするとおじいさんはまるで青年将校のようなハツラツとした表情になり、清々しい笑顔で指揮し、さらに喉を震わせた。
そうなると青年の声も競うように大きくなっていき、2 人の歌声は絡み合い、神社を越えて、丘の上から村中の家々に飛んでいった。
歌は、不思議と人の心をつかむ。
その歌声に気がついた畑仕事の人や、道ゆく人。公園で遊んでいる親子が一斉に顔を上げる。どこから聞こえてくるのか、キョロキョロと探る顔が増えていく。
早速、神社にやってきたのは、軽トラに乗った足の悪いおばあさんとその息子さんらしきおじさんだ。鳥居の外でププッと軽いクラクションを鳴らす。
おばあさん:「小野村さーん! ちょっとなんしょん! 誰が歌ってるんか思て! どうしてここで歌いよるん?」
青年がすかさず答えた。
青年:「あーっ、ごめんなさい! うるさかったですか? 今度同窓会で一緒に歌を歌うかもしれないので、ここで一緒に練習していたんです。」
息子さん:(母を見て)「ええやん。おかんも歌えば?」
おばさん:(嬉しそうに)「えー?(青年に向かって)あたしも、歌うてもええの?」
青年:「もちろんですー! 一緒に歌いましょう!さあ、こちらに!」
小野村さんと呼ばれたおじいさんは、ますますうれしそうに、
「ようこそようこそハシモトのばあさん。さあそれでは、始めますよ。うん。前奏からね。ラ〜ラ〜♪」
携帯電話もない時代、公衆電話もない場所だ。その歌声だけがワクワクする謎情報として周囲に発信され、人が引き寄せられる連鎖が生まれていた。
ひとり、またひとりと、一体何をやっているのかと興味本位で覗きに来る。すると、みんなが楽しそうに歌ってるのを見てしまい、これはエライコッチャと自分も思わず参加してしまうのだ。
気がつけば神社の境内は、多種多様な人々が20 人以上集まっていた。明らかにガスか電気メーターの確認仕事の途中で来たような人もいる。
それらみんなが一丸となって、トタンの壁も震えるくらいの大合唱の渦を作っているのだ。
蛍の光。ふるさと。みんなが歌える曲を何回も歌う。集う人々の顔はみな、晴れやかだった。
青年は感動していた。音楽って本当に素晴らしい。こうやって心がひとつになるんだ。
1 時間以上はゆうに歌い続け、そろそろ太陽が傾いてきた。
みんな三々五々帰っていくかと思われたが、誰もその場を去ろうとはしない。笑顔でおしゃべりに花を咲かせている。
すると、小野村さんが「みなさん、セーシュクに!」と指揮棒を高く掲げた。そしてみんなをじっくり見回すと、
小野村さん:「どうや、このまま今晩、公民館で宴会しようやないか!」
そう言って、歯のない笑顔でニカッと笑う。わあーっとみなさん、地鳴りのような大拍手。青年もとりあえず、やったーのポーズ。
しかし、群衆の中からこんな声があがる。
「でも、なんの目的の宴会や?」
「合唱の反省会でええやないか。」
「反省なんか誰がする! 今日はなあ、夕涼み会じゃ!」
「おおええな!それはええわ!」
「おおいに涼んだろやないか!」
この村はじまって以来だという新しい宴会の名称に、みんなは興奮する。
たまたま合唱に参加していた村の会計方の了承も即刻得たようで、話は決まった。さっそく宴会の準備活動にうつる。
小野村さんは村の中心人物のようで、手際よく、集まった人の中で宴会準備の人足をあてがい、料理の担当も決め、お酒の担当も決め、今年出来たばっかりの自慢のスイカまで用意すると言ってくれた。
夕涼み会
宴会場所となる公民館は、神社のすぐ横手にあった。みんな駆けるように公民館へ大移動する。青年もニコニコしながらその流れに乗った。
公民館は木造の平屋建てだ。大正時代に建てられたという。小さいが、風格がある。中に入るとさすがに傷みが目立ち、埃も目立った。とりあえずは宴会をする大部屋だけ窓を開け、空気を入れ替える。
暑い。青年は汗だくになりながら、おばさまたちに指示されるとおり、長机を組み立てて座布団を配し、ありったけの扇風機も各所に設置する。
徐々に、家々から料理や酒やクーラーボックスが運ばれてきて、1 時間後にはみんなきっちり着席。小野村さんが言う。それでは僭越ながら。
「夕涼み会。うん。好きにはじめてくれえ〜!」
これが乾杯の音頭となった。
みんな大はしゃぎで、飲む、食う、喋る、泣く、笑う。特におじいちゃんたちは、好きなだけ酒が飲めるという無上の喜びを隠しきれない。それを遠目で見る奥様軍の目は氷のようだが。
周囲が急速に陽気な酔っ払いになっていく中、青年は隣に座ったおばさまに「あの、小野村さんって、どんな方なんですか?」と聞いてみた。
「ああ、小野村先生はの、この村の有名な校長先生や。」
とのこと。
校長先生か! やはり。道理で言葉遣いも姿勢も真面目で堅苦しい。なのに、ノリが良い。さぞかし子どもに愛された先生なんだろうな。
参加者のお酒は、無限に進んでいく。思い思いの場所で、思い思いの姿勢で、思い思いの人とおしゃべりを楽しんでいる。
大阪からバイクで来たというハタチの青年は、この場の人気者だった。あっちこちで呼ばれて話をしている最中、ふと、小野村先生が目に入った。
宴会場の出口近く、端っこにいらっしゃる小野村先生も良い感じにお酒が回っているようで、遠目からみてもお顔が赤いのがわかる。しかし相変わらず、素晴らしく姿勢が良い。
正座を崩さずにお酒が入った湯呑みを持ち、もう片手にはスルメを持ちながらこの姿勢を維持していることにも青年は静かに感動していた。
青年はコップを持って、先生ににじり寄る。
青年:「あの、小野村さんは校長先生だったと伺いました。」
小野村先生:「うん。いかにも。」
青年:「実は僕、教師を目指していて、いずれ小学校の先生になることを夢見ているんです。」
小野村先生:「ほうほう。それはそれは。」
青年:「小さな学校でもいいので、子どもたちのそばにいたいんです。」
そう自分の夢を語り始めた青年。
すると小野村先生の目がまた、キラリと光る。
良い先生
先生は片手でメガネをくいっと上げて言う。
小野村先生:「で、うん、つまりあなたは、どういう先生になりたいんかね?」
青年:「はい。子どもの声をちゃんと聞いて、誰も落ちこぼれにしない、頼もしい先生になりたいと思っています。」
小野村先生:「そうか。うん。それはいい。それはいい。」
その先生の言い方に、あれ? ほんとにそれでいいとは思っていないっぽいぞ、という雰囲気を感じた青年は、座り直した。
小野村先生と同じく、正座だ。
そして、顔を突き出し、神妙にこう尋ねた。
青年:「教えてください先生。『良い先生』とは、いったいどんな先生なのでしょう。僕は先生になったことがないので、まだ本当の先生というものを、知らないのです。」
小野村先生:「うん。そりゃそうじゃな。では言おう。
良い先生というものは、この世に、おってはならんのじゃ。」
青年は予想外すぎる答えに驚いて、思わず背中がのけぞった。
良い先生が存在してはいけないという理由が、全く頭に浮かばず、混乱している。
青年:「えっと、良い先生になってはいけない、と言うことですか?」
小野村先生はそこで、少し顔をしかめた。
すぐ横でその問答を見ていた、タケゾウと呼ばれる男がいる。お相撲さんのような体格だが、気配りが細やかで、村の青年団を仕切るリーダーだ。
彼は青年と先生が不穏な空気になったのかと思ったのであろう、笑顔で割って入ってきて、
「まあまあまあまあ、校長先生もお兄さんも、まあ飲んで。ジュースもありますでね。まあまあどうぞどうぞ。」
そう言って、話題をそらそうとした。しかし、先生は笑いながらタケゾウの制止を軽くいなし、
小野村先生:「タケゾウ。この人だったら、大丈夫じゃ。わしの言うことを、ちゃんとわかってくれると思う。
うん。
本当の教育というものが、これからのこの世の中に、しっかりと根付いて行かなきゃならんのに、そのことをわかっている人がまだ少ない。
この人なら、実践してくれると思う。なぜなら。」
そう言って先生は、背筋をさらにぐっと伸ばし、湯呑みのお酒をぐいっと飲み干した。タケゾウが心得たとばかりに、なみなみとお酒を注ぐ。
小野村先生:「見てみい。この青年はこんなにたくさんの人を、その歌声とこの笑顔で、集めてしもうた。この人なら、いい先生になろうよ。うん。」
その言葉を聞いていたのは、神社に最初に駆けつけてきたハシモトのばあさん。
「それあ、そうにきまってるで!」
と、いきなり拍手。周囲にも、
「なあ! ほれ、みんな、この大阪のお兄ちゃんに拍手や! ありがたいこっちゃで!」
とせかす。
それにつられて、周囲がパラパラと拍手を始め、次第に大きなうねりのある喝采となる。
先生もうれしそうに拍手をしてくれた。青年は、くすぐったいような顔して、正座したまま照れまくっている。
青年:「ありがとうございます。嬉しいやら、恥ずかしいやらです。」
しかし、青年はそれで終わらせない。
青年:「実際、本当の教育って、難しいものなのでしょうか? 良い先生になってはいけない理由はなんでしょうか。本当に知りたいです。」
と食い下がった。
本当の教育とは
先生は両手で湯呑みを持ち、青年を見据えて即答する。
小野村先生:「本当の教育と言うものは、頭の中をこねくり回して、考えさせて、答えを出させることではないってことじゃ。
子どもの心を熱くさせて、目標を決めさせるだけで良い。うん。それが本当の教育。
強く厳しく教え込むことでは全くない。
しかし、勉強を覚えさせるために一から百までを教え込むことが、今の時代は『良い先生』と言われるようになっている。そのようにはなってはならん、ということじゃ。」
青年は、なるほど。と思ってはみたものの、まだ完全には理解できない。
青年:「しかし、教え込まずに、どうやって学ばせればいいのでしょうか。心を熱くさせて、目標を決める。という事ですけど、目標を決める事はまあ、できるような気がします。
でも、心を熱くさせることって、難しくないでしょうか。」
小野村先生:「そうか。うん。ならば証明してしんぜようぞ。」
そう言って湯呑みを机に置いて、よっこらしょと立ち上がる。
そしてまっすぐに立ち、両手を天空にすっと上げた。あれだけ騒がしかった会場が、一瞬で静寂を取り戻す。
そしてはじまったのは、仰げば尊しの前奏だ。
みんなコップを置いて、先生に合わせてまた大合唱。皆、目をつぶり、歌っている。じんわりと泣きながら歌う人もいれば、友達同士なのか、手を握り合って歌っている女性もいる。
青年もなんだか思わず涙が浮かぶ。
歌が終わってシーンとした余韻があって、拍手が巻き起こる。
小野村先生の「続けてくれえい!」の一言でまた乾杯。
宴の再開だ。
小野村先生はまたよっこらしょと座って、湯呑みを傾ける。青年はすぐにお酒を注ぐ。
小野村先生:「な。今のが答えやな。うん。」
青年はまだ腑に落ちない。
青年:「心を熱くさせるためには、みんなで一緒に歌を歌えばよい、ということですか?」
そこでちょちょい、と青年の肩をつついたのは、さっきから隣で酔っ払って揺れていた、白ひげのおじいちゃん(ワカナさん)だ。
ワカナさん:「だからあ、あんたやん。あんたが、火ぃ付けたんやんか。あんたが最初に歌ったんやん。神社で。やけん、みんなをここに寄せたんはあんたやんか。」
小野村先生は、うんうんとうなずきながら、青年の顔をじいっと見つめた。
しばらく目が合う2 人。
すると突然、先生は、ちょっと外の風に当たろか。と言って、青年を促し、スタスタと外に出ていく。慌ててシューズを履き、外に出る青年。
玄関前には、軽トラがぎゅうぎゅうに詰まっていて、まるで品評会のようだ。2 人はその隙間を縫い、横手の小さな公園に出た。
日はすっかり落ち、丘の上に吹く風が気持ちがいい。星もうっすらとだが見えてくる。
青年は、はあ〜〜〜っ! と間の抜けた声をあげて、澄んだ空気を胸いっぱい吸い込みながら、手を伸ばしてぐるっと一回り。360度の方角から、虫の鳴き声が聞こえてくる。
先生もゆっくりと深呼吸をしたあと、やさしさのこもった声でこう言った。
小野村先生:「ほらお聴きなさい。虫も大合唱をしとる。うん。」
青年:「はい。綺麗な声です。」
小野村先生:「わしは今日、神社で一人、指揮の練習をしとったやろ? そこへあなたが通りかかった。気持ちよさそおに指揮しとるわしをみて、あなたは何かしら興味を持った。じゃろ? 」
青年:「そうです。面白そうな方がいるな、と思って思わず。」
小野村先生:「うん、それや。子どもは皆、自分に興味を持ってもらいたい。そう思うとる。興味を引くためにいろんな悪さもするし、すっとこどっこいもする。自分の存在を認めてほしいんやな。」
青年:「なるほど。。。」
小野村先生:「それはこの虫たちも同じ。誰かが最初に鳴き出して、自分はここにおるぞ、と。それで、この合唱が生まれるんじゃの。」
先生はそういうと、公園にある小さなブランコに座った。青年も隣のブランコに座り、ゆっくりと小さく漕ぐ。ブランコなんか、久しぶりだ。
先生は、ブランコに座ったままこう言う。
小野村先生:「わしもそうなんじゃ。
わしはな、この神社の、うん、神さんに見て欲しかった。すでに死んでしまった戦友たちと、一緒に歌いたかったからじゃ。」
青年:「ああ・・・。そうだったんですね。」
小野村先生:「あなたはそこで、わしになにをしとるんか、興味を持って尋ねてくれた。わしは嬉しかった。
歌う曲を引き出してくれて、それを一緒に歌おうとまで言ってくださった。嬉しかった。で、ほら。」
と、小野村先生はすぐ横の公民館を眺める。
小野村先生:「村のみんながどんどんこうやって集まってきた。歌に惹かれて、わざわざ坂を登ってまでここに集まってきた。この暑いのに。本当に、うん。わしは嬉しかった。」
青年:「はい・・・。」
ようやく、小野村さんの心を熱くしたのは自分だったことを理解し始めた青年。しかし、これが教育なのかと、まだ解せない。
小野村先生:「もう一回言うが、教育とは、心を熱くさせて、目標を決めること。今日、わしの目標が決まった瞬間がある。それは・・・。」
そこで2 人を迎えにきた人影がある。ワカナさんだ。
ワカナさん:「やっぱりここにおったんか。せっかくみんな集まってきて、おもろい兄ちゃんがおって。せっかくやけん、せいぜい飲まんとあかんやろ。校長。ガハハ。」
先生は笑ってブランコから立ち上がり、青年に向かって言う。
小野村先生:「つまりは、あなたがきっかけを作って、合唱が生まれた。
そして、そこで胸を熱くしたわしが『こうしたい!』と切望した。
そうするとどうなるか。ワクワクした気持ちが生まれてきて、それを感じた周りの人たちをも巻き込んで、そのワクワクを実現させとうなって動く。
その目標はやがて、全体の目標になっていく。」
青年:「先生の、その目標とはなんだったのですか?」
小野村先生:「え・が・お。笑顔じゃ。見てみい、今日は皆がわろうとる。ワカナの顔なんぞ、ほれ、わしも久しぶりに見た底抜けの笑顔じゃ。うん。」
ワカナさん:「がはは。暗いところで見たら・・・高倉、健です。」
どこがですか! というセリフはなんとかとどめた青年であった。
一番大事なこと
3人は宴会場に戻り、飲み直す。
青年はしかし、まだ肝心な答えをもらっていない気がしていた。心を熱くさせれば、目標も自然にできてくることはわかった。しかし・・・。
常人なら、これ以上の質問は遠慮して、諦めるだろう。しかし今、人好きライダーに完全変身している青年には、怖いものはないのだ。
正座をして両手を前につき、張りのある大きな声でこう尋ねた。
青年:「先生、どうか教えてください。教育において、一番大事なものはなんでしょう?」
すると、その質問を聞いた周囲の人たちが一斉に、花火が弾けたように笑う。
青年はみんなを見渡して戸惑う。なにがおかしいのだろう?
小野村先生もニカニカと笑っている。前歯がない顔がやはり可愛い。しかし今、青年の頭は疑問符だらけだ。
ひとしきり笑いが収まったあと、先生はええ質問や!というと、周囲の人にこう聞く。
「みんな、この子に教えてやってくれ。教育というもんは何が一番大事かというと・・・?」
すると、ワカナさんとタケゾウ、さらに数人の人が同時に、同じタイミングでこう言った。
「パッション!じゃ。」
「パッション!ね。」
「パッション!でしょ。」
「パッション!でーす!」
ワカナさん:「な。校長センセーはこれが言いとうてしゃあないねん。」
その一言でみんなはまた大爆笑。
そうか、先生はいつもみんなに情熱の大切さを説いていたのか。青年は笑っていない。ただひとり、胸を熱くしている。
小野村先生:「いや、いきなり笑ってしまって驚かせたな。すまんかった。
つまり、あなたがいつも当たり前のようにやっていること。
それが全ての人の喜びになるんや。
出会った人の心に、嫌味なく入り込み、それを支えて増幅させて、その人がやりたいことを認め、手伝う。
支えられた人は、自信を持って動き出す。
それを見ていた周りがまた輪をかけて動き出す。結果、どうなる?」
ワカナさん:(両手を広げて)「こおなる!」
タケゾウ:「無理矢理押し付けたり、頑張って教え込まんでも、自分から動きとうなる!」
小野村先生:「そうや。そんな情熱に満ちた人生。そのきっかけも、たったひとりの情熱から生まれる。
だからパッションを、心から愛すること。それが教育で一番大事なことなんや。
つまりあなたは、あなたのままでいいってことやな。」
パッションを、心から愛すること。
そして、僕は僕のままでいい。。。
青年は、自分のためにこうして心を傾けてくれて、話題に乗せてくれて、教育の入り口であり本質を、実際の行動で教えてくださっている先生をはじめ村の皆様に、心から感謝した。
特に、小野村先生。彼に出会わなかったら、この場はなかったのだ。
もし、
「あ、指揮をしてる変なヒトがいる」
と思っただけで素通りしていたとしたら、この宴会も学びもない。
旅というものは、見過ごせない出来事の連続で、何か素敵な風景をただ見にいくためだけの移動時間ではないのだ。そんな旅は、この青年にとっては面白くない。
胸を熱くするものを探し、見つけたらそれを観察し、相手の欲しているものを見つけ出し、一緒に体験し、そこで必要なものを考え、臨機応変に行動し、結果を残していくこと。
それはパッション、つまり情熱があってこそ可能になる。
そしてそれが教育にとっても一番大事なことだと知った青年。
しかし青年は、最後に小野村先生に言われた言葉が少し心残りではあった。
小野村先生:「あなたは小さな学校に収まるかねえ。よほど大きな学校か、何か違う先生になってもええんと違うかなあ?」
青年は、子どもの教育にこだわった。
それが一番自分のやりたいことだと信じていたので、小さな学校こそ、自分が輝ける場所だと決めていたのだ。
フェリーで子どもの命と向き合った時に、漠然と感じた自分の役割。
もしかすると自分は将来、今大学で学んでいる人形芝居の世界や、教育関係の機関で、子どもと触れ合っていくこと。それで、自分も大きく成長していけるのではないか。
この旅で、果たしてその答えが得られるかどうかはわからない。しかし、青年は学びたくて学びたくて、仕方がないのだ。
一宿一飯の恩義
宴会は夜更けに終了し、その日は先生のご好意で、公民館で泊まらせていただくことになった青年。
小野村家に泊まっていけという申し出をお断りした理由は、公民館を掃除したかったからだった。
埃っぽい床も壁も、「道具室」と書かれた部屋にある運動用の小道具などもあまり整然としておらず、何かお礼ができるとしたら、公民館の大掃除と決めていた。
わざわざお布団を家から持ってきてくれた小野村先生の娘さんは、お風呂だけでもうちに来てくださいな。と言ってくれたが、それもお断りし、皆が帰った後、掃除を開始。
泊まるところを決めていなかったので、夜中の移動に備えてお酒を飲んでいなかったのも幸いした。結局、掃除には5 時間以上かかった。
汗ばんだ体を貸していただいた布団に埋めることが申し訳ないと、大部屋の一番奥で、ビニール製の体操用マットで眠った。
虫たちの大合唱が、青年を数秒で夢に誘った。
お礼のお礼
朝、目が覚めると驚く青年。
公民館に、朝ご飯が並んでいた。畑で採れた新鮮野菜と、ハシモトのばあさん特製炊き込みご飯と、大量の手打ちうどんだ。本当に美味しい。それをみんなでワイワイ食べた。
食べた後も、お母さん方が笑顔で働いてくれている。そして、きれいになった公民館を見て、皆嬉しそうに驚いてくれる。
子どもたちも朝から集まってきてなかなか賑やかだ。そうか、今日は日曜日なんだ。
青年は流し台で顔を洗い、外のトイレに行くときに、ダックス号を見てさらに驚いた。
「え、なんで。。。」
思わず口からこぼれる。
あれだけ汚れていたダックス号が、ピカピカになっているではないか。
聞けば、タケゾウさんはじめ青年団のお兄さんが洗ってくれて、ワックスもかけてくれたとのこと。
青年:「あんなにドロドロだったのに、こんなにピッカピカにしていただいて!!!・・・なあ。良かったなあ。良かったなあ。」
そう言ってバイクを撫でて、みんなに心からのお礼をいう青年。
小野村先生:「昨晩遅く、まだ電気がついとると言ってあいつ(娘さんを指差して)が様子を見てくると言ってのう。そうしたら、うん。あなたの姿を見たと。大掃除で汗をかいていたと。」
娘さん:「なんか、声がかけれんと、すみません。。」
青年が外に出て、錆びついたトタン作りの神殿を触って、ボロボロと落ちるサビに対し、
「ごめん。これは今日、綺麗にならないわ。。。ごめんなさい。」
と謝っている姿も見られたそう。
そんな姿を知った小野村おじいさんは、早朝に有志を募り、そのお礼にと、朝ご飯の振る舞いと、バイクの洗浄とピカピカ研磨をしてくれたということだった。
青年は首を垂れた。
パッションだけじゃない、小野村先生には、いや、この村の人々には、「愛」があるんだ。。。
僕は、先生の教育の芯には到底辿り着くことはできないだろう。しかし、このやりとりは生涯忘れないでおこうと心に誓う。
ピカピカのバイクに乗り、エンジンをかけた青年。その軽快な音は、村中に響き渡った。
30 人もの村人たちが、青年を見送った。
丘を下り出してすぐ聞こえてきたのは、あおげば尊しの合唱だった。誰かが歌おうと言ってくれたのであろう。いやきっと、小野村先生が指揮をしているんだ。
青年は、微かに聞こえるその歌を聴きながら、込み上げてくる涙とともに、ヘルメットの中で大声で一緒に歌いながらその土地を離れた。
ジリジリ暑い太陽の下を青年は、ただ感謝の念でひた走った。
〜つづく〜
おわりに
僕:「ありがとうございました。しかし八幡様は本当によく覚えていらっしゃいますね。僕も追体験できて嬉しいです。」
八幡様:「いえいえ。こちらこそ、忘れがたき思い出をありがとうございます。」
僕:「小野村先生は、生きていれば100 歳を超えてますが、お元気だったらいいな。。。」
八幡様:「今頃、戦争で一緒だったみなさんと共に、天の歌声を響かせていると思いますよ。」
僕:「そうですか。。。はい。
思えば、あの当時、僕はまだまだ青くて、幼くて、何も知らず、旅で出会える全く知らない人の素敵な人生に魅せられて、そしてそんな人たちに出会えることが嬉しくて、会話することに全然恐れを知らない男でした。
本当に不思議なんです。八幡様も仮面ライダーにかけて説明してくれていましたが、旅に出ることで、自分のキャラクターが変わったんですよね。」
八幡様:「これは大学での、くまの着ぐるみでも学んだことでしたね。」
僕:「そうだ。自分のキャラクターは、持っているアイテムとか、着ている服で一瞬で変えることができて、それも本当の自分であるという面白さですね。」
八幡様:「はい。ここに気づければ、人生をさらに楽しくできるということを、このロードムービー企画でも掘り下げていけたらいいですね。」
そうなんです。八幡様のおっしゃる通り、僕の旅は、さまざまな人間模様を生で体験するものになります。
実際に起きたことを、八幡様の目線で淡々と書いていただいています。
しばらくは、僕の青年時代が続きまして、出会いと別れがたくさん出てきます。
その中で、現在と繋がっていくドラマもあったりして・・・。
長くなりますが、どうぞのんびり旅気分でお楽しみください。
ではまた次回、お愛しましょう♡
ここから先は

KAMI ing out マガジン
「僕のアニキは神様とお話ができます」「サイン」の著者、アニキ(くまちゃん)が執筆。天性のおりられ体質を活用し、神様からのメッセージを届けま…
ご支援ありがとうございます。このnoteはサポートのお志で成り立っております。メッセージにお名前(ご本名とご住所)も入れていただけると、感謝とサチアレ念をダイレクトに飛ばさせていただきます。
