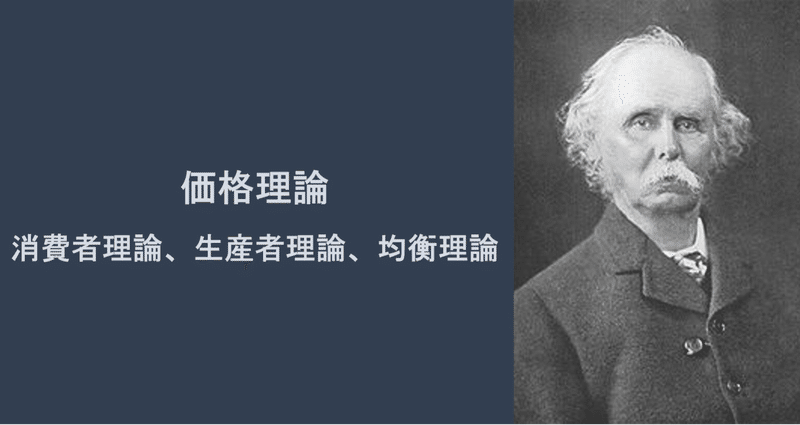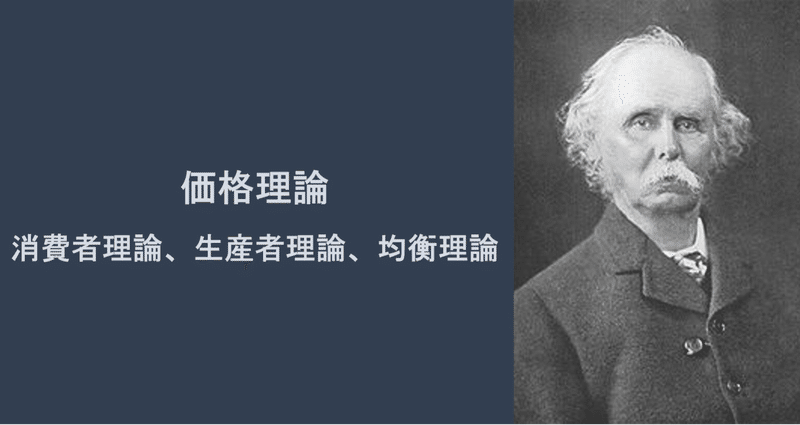生産者理論(2):生産の効率性
前回は、生産者が技術的に選択可能な生産ベクトルからなる集合を生産集合として定義した。今回は生産の効率性の概念を導入し、生産集合のうち効率的な生産ベクトルが満たす性質を学ぶ。また、効率的な生産ベクトルを扱う上で利便性の高い変換関数、生産関数を導入する。連載はこちら。
効率生産集合狭義効率生産集合
$${N}$$種類の商品が存在する経済において、生産ベクトル$${y}$$は純産出量の組として$${y=(y_1,\cdots, y_N)\in \mathbb{R}^N}$$とし