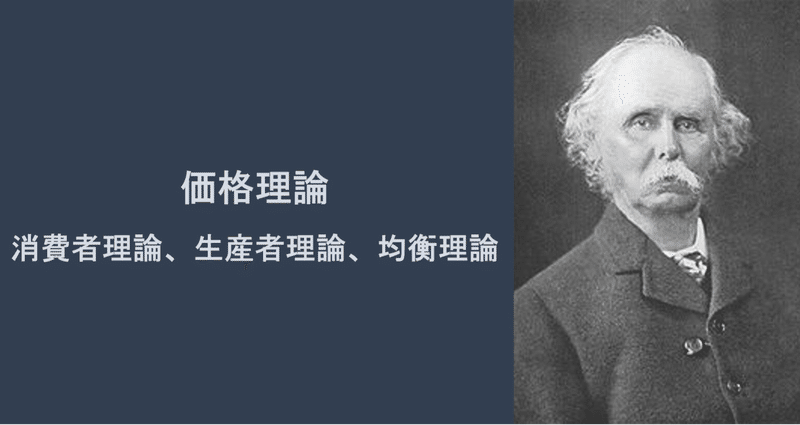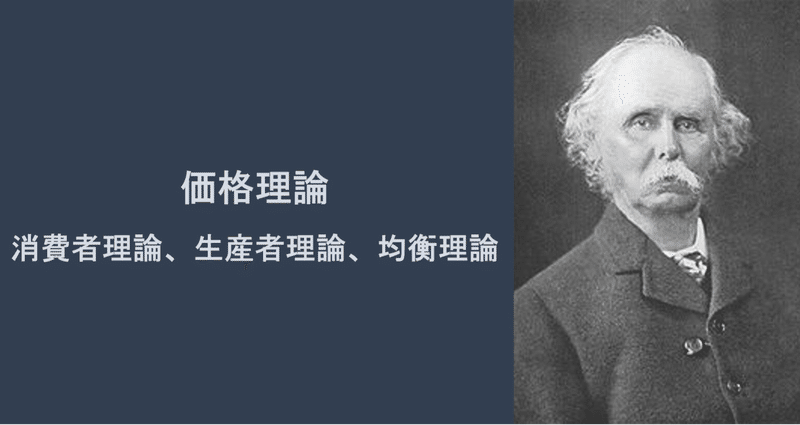消費者理論(2):効用関数
今回は、前回定義した合理的な選好関係を数値的に表現し、選好の量的比較を可能にする効用関数の概念を導入する。連載はこちら。
消費集合と消費ベクトル選好関係$${≿}$$の合理性を定義する際、「選好関係が定義される集合$${X}$$に属する任意の$${x, y}$$」を導入した。より正確には、$${x, y}$$は$${N}$$種類の財(商品/サービス)からなる経済を想定した時、消費者が直面する個々の選択肢を表現した$${N}$$次元の消費ベクトル、$${X}$$は消費者が選択