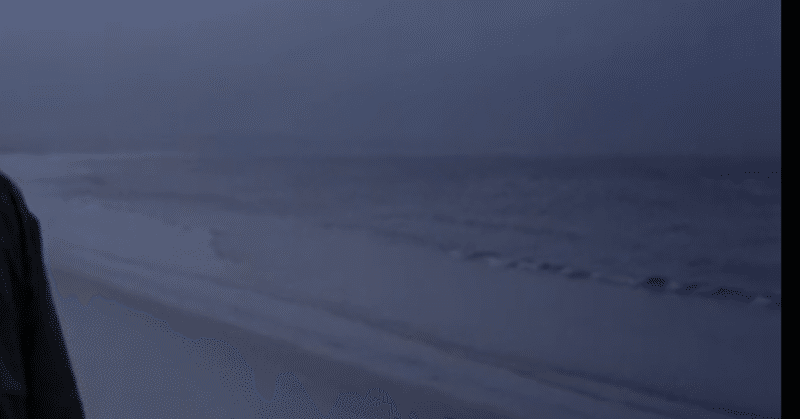
船
ぼくが欲しいと思うものは、昔を振り返ってもそんなに沢山は無かった様に思う。しかも大抵のものは時間が経てば要らない気がしてきたし、興味さえ失ってしまった。
さほど贅沢なものを欲したわけでは無かったけれど、手に入らなくて仕方の無いものばかりだったのかもしれない。その線引きみたいな事が、勿論ぼくに出来る筈も無かったのだけれど。
消費されるだけの物なら許されたり、代価を支払えば権利みたいなものが生まれる対象は、手に入れた途端に色褪せる。
およそ、欲という感情はその程度のものでしかないのかしらと、いつの間にか距離を置いて眺める風にぼくはなっていた。必死に求めるという事が、ぼくには虚しさを募らせるだけの行為に思えた。欲しいという感覚はまるでぼんやりと見える遠くの景色だった。蜃気楼にちょっとだけ似ているのかな。本物を見たことは無いけれど。
殆どのものはぼくのものには無らなかったし、これからもきっとそうあるのかもしれない。
自分のものにするというのは、征服とか支配とか、そういった嫌な言葉を喚起させる。それは考え過ぎのきらいもあるから、とりあえずは脇に置いておこう。
人間の欲っていうものの正体はぼくにはよくわからないけれど、誰かが欲しがっているからといってそれを手に入れたいとは思わない。たまにはあるのかもしれないけど、そういう感覚はきっとニセモノに見えちゃうんだろうな。
ホンモノが何かなんてのだってわからない癖してね。
そんなぼくだけど、今は心から求めているものがあるようだ。
これは驚異であり脅威でもある。今までの自分を脅かすし、更には自虐癖のある人間にとってみれば、全く以って不釣合いな欲求だと慄いてしまうからだ。
ぼくはキッチンで食事を作る母に問う。
「ぼくの欲しいものをどう思う?理解できる?」
「うーん、私にはわからないけど」
困った顔をして、母は鍋に視線を戻す。
「ねえ、ちゃんと考えてよ」
「――じゃあ、あなたの好きにすればいいと思うわ」
ぼくはうんざりした。
いつも彼女は放棄する。そして、ぼくの味方という顔をする。面倒を嫌っているだけなのは判っているのに。反対でもいい、母なりの答えをぼくは聞きたいだけだと云うのに。
食卓に皿を運び、母の作った料理に適当に感想を述べ(ぼくは母の料理が好きだ)、普段どおりに夕食を摂る。父が席に居ない事にほっとする。あの人が居るとぼくは落ち着かない。声が頭に響くし、租借する音さえ不愉快に感じるのだ。でも、それを言うことはぼくには出来ないでいる。いつか言えたらいいなとは思うけど、傷つけたいわけじゃあないから永遠に無理かもしれない。
ぼくの求めているものは、あなたたちの船から降りることなんだ。
決してこの船を否定してるわけじゃあない。寧ろ感謝しきれないほどだし、役立たずなぼくじゃあ恩返しは一生出来そうにないとさえ思うくらいなんだ。
この船から下りる。その言葉が通じるだろうか。
ぼくの背中をそっと押してくれるだろうか。励ましてくれるだろうか。
ねえ、ぼくはどうしたらいいのかわからなくて、いっそ航海さえ止めようとまで悩むんだ。
いっときはこの船で生涯を終えるのも構わないと思っていた。今でもそれが間違いだとも思っていない。でも僕は外を見てしまった。知ってしまった。違う船に乗ることを欲してしまった。
ぼくは、あなたたちから言葉が欲しい。
そうすれば、こんなぼくでも頑張れるような気がするんだよ。この船以外で生きていく為に。
あなたたちの言葉がなければ、ぼくはいつかつぶれてしまう気がするんだ。
もう、とっくに手遅れなんだとは思いたくはないんだ。
過ぎたる望みだと、そう云われたら、――そうだな、ぼくはどうしたらいいのかな。
それでも欲するのは仕方が無いと、噛み付いてやろうかな。
こんなぼくでも思うんだ。だって、生きるってそういう事なんでしょう?
ぼくに言葉を与えたあななたちが、それを伝えることが出来ないなんて、生きるっていうのはパラドックスで溢れかえっていて、全く手に負えない。
だけど、パラドックスなんてのは、たかが概念で、たかが言葉という記号なんだ。
手に負えないのは、ぼく自身なんだって本当は気づいているんだよ。
すべてはぼくという個の肩に責があり、けれどもぼくは一人では生きていたくない。生きられない。
『海の上のピアニスト』の主人公のように、ぼくは船という世界だけで生きてきた。
色んな客が乗っては下船していったように、色んな人たちが通り過ぎて行った。
彼の事は大好きだけど、ラストだって勿論悪くはないけれど、そこまで自分に重ねる必要だってぼくには無い。
きれいで、哀しくて、楽しい音を奏でるピアノもぼくは持ってはいない。才能もない。
しかもぼくはピアノなんて欲しくない。
ぼくは彼じゃあない。
どんな生き方だってぼくは選べるんだと、そんな夢想を抱く。
やはり大それた願いなのだろうか。だけど、大それたってなんだろう。
頭で考えて終わるのは卒業しなければ。だって、ぼくは水槽の中の脳みそじゃない。
確信は無いけれど、ぼくはちゃんと実在してる。
じゃなきゃあ救いがないじゃあないか。
このおもいや、情けないけど肩こりなんかが錯覚だと言い切られたら、ぼくはこわれてしまう。
ぼくに限らず、人はとても弱い生き物なんだもの。
皆、何をそんなに懸命に守っているのだろう。意固地になっているのだろう。それとも、それこそが大事なのかしら。
誰かおしえてはくれないだろうか。
たぶん、その言葉をぼくは信じないだろうけど。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
