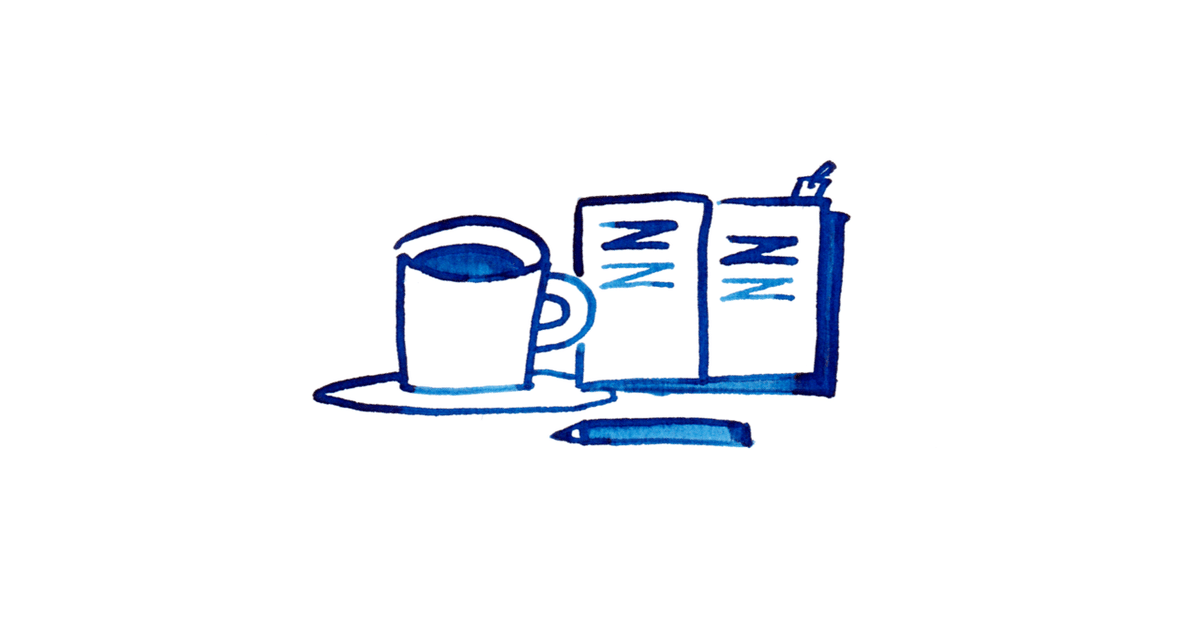
読書記録「同志少女よ、敵を撃て」
noteのアカウントを作った当初、アウトプットの意味合いで読んだ本の記録をまとめていたのだけれど、最近は全然できてない。
自分の考えを整理して言語化する。それこそがアウトプットであり、得た知識や感情を自分の中に落とし込むための要。
だと言うことは分かってはいるんだけども、気力がない〜!
というわけで、しばらくは「気負わず、さらっと」を心がけて、日記がてら読書記録をつけてみる。
今回読んだのは、説明不要の話題作。
刊行は2021年。そして翌年の4月に本屋大賞を受賞。
この作品は第二次世界大戦中の独ソ戦を舞台に、前線で戦う女性狙撃手の姿を描いたものだけれど、この物語を過去の歴史として受け止めた人は少ないのではないかと思う。
テレビをつければ、いつでもそこには現実の戦場が映し出されている。ただ、その瓦礫の山や疲れ切った人々の姿は完全なリアルではない。その奥に、地下に、戦火の中に、本当の地獄があることを、私たちはおぼろげに理解している。
地獄のなかに、女性がいる。
2022年の当初から、私は戦争に関する報道を見れなくなった。断片的に、扇状的な言葉でもって伝えられる情報のなかには、いつも戦争の被害者になる女性の姿が垣間見えた。
自分のなかの、同情や悲しみの奥にある感情。それは、彼女たちに起きたことが、いつか自分の身に起きるのではないかという言いようのない恐怖と、それをもたらす「敵」への憎悪のように感じられた。
本屋大賞として話題になったこの作品を、一年近くも読めなかったのは、この恐怖と憎悪から逃れなかったから。
悲しいことに侵攻が始まって一年が経ち、自分の気持ちが少し落ち着いてきたことで、この本を手に取ることができた。
(春とヒコーキのぐんぴぃさんがこの作品を推してたのもかなり大きな理由。ミーハーだけども、信頼できる読書家の言葉の力は大きい…)
戦争で村を焼かれ、家族や友人を皆殺しにされた少女が、復讐のために狙撃手となる。女と戦争。あらすじを読むだけで、やっぱり恐怖は湧いてくる。
ただ、一度読み始めると夢中になってしまった。一日も立たず、物語を読み終えた。
それはやっぱり、息を呑むような戦闘の描写や、職人としての狙撃手たちの心の有り様、そして、魅力的なキャラクターたちの活躍、といった小説としての面白さもあったからだと思う。
一方で、自分の中にあった恐怖と憎悪、そしてその出来事を引き起こす戦場での心理的な要因に、物語が正解を与えてくれたようにも感じる。
それは、もちろん倫理としては正解ではない。限られた異常な空間でのみ通用する常識、仕方のないもの、として看過されるべきことでもない。
ただ、敵は、非道な振る舞いを見せる「得体の知れない奴ら」でもなく、性を褒賞や連帯のためのツールとして扱う「男ども」でもない。
この作品の感想を読んでいると、作中の登場人物の悪行を「本性」や「愚かさ」として評価する言葉を見かける。
だけど、私たちが憎むべきは、あえて「敵」と表現するのだとしたら、その対象はやっぱり「戦争」という概念に他ならないのだと思う。
(同時にハンナ・アーレントの関連本を読んでいたので、なおさらそう思わされた)
そんな感じで。二の足を踏んでいたけれど、読んでみると、確かに面白く…そして自分の気持ちを少し明らかにきてくれる、良い本だった。
答えは出ないけれど、少なくともこの本の中やテレビの向こうで起きている出来事を、止めたい、2度と繰り返したくない、という気持ちだけは、確かなものとして感じ続けていられる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
