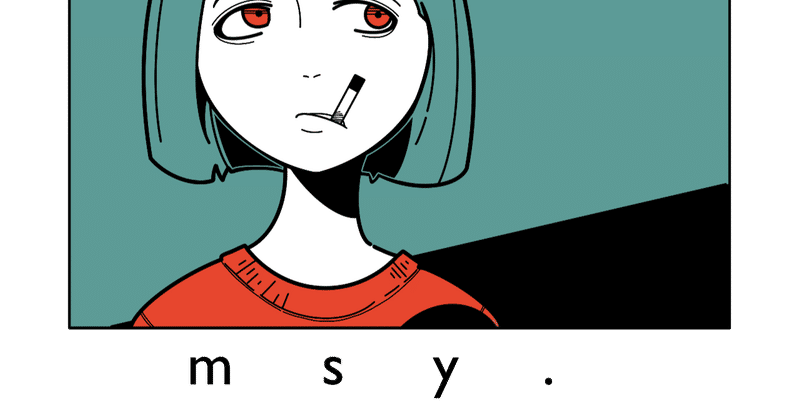
SB Flat Call 戦略(前編)
前回の記事はこちら↓
◇はじめに
500NL以上のステークスになると、レーキの関係上、SBにおいてCallを行うレンジが出現しますが、多くのプレイヤーはこのSB Flat callの難易度が高いためか、戦略の一部として導入をしていないように思えます。
一方、500NL以上の世界で名をあげているプレイヤーたちは、この戦略を上手に扱っています。
つまりそれは、高みを目指すプレイヤーにとってSB flat Call戦略を学ぶ意義があるということです。
そこで今回、SB flat call戦略を紹介していきたいと思います。
SB flat call戦略を学ぶことで、あらゆるシーンで役に立つはずです。
例えば、ライブキャッシュなどの6max以上の卓では、UTGオープンはかなり強固なレンジであり、お互いがDeepStackの場合がほとんどことから、5bb以上のオープンを受けることも多々あります。
そこに対して、JJsなどで3betするのではなく、コールを選択するというオプションが生まれます。
また、MTTのようなBBアンティのあるゲームへのコンバートもできる可能性もあります。
今回は、わかりやすいように、ぱいにゃんさん開発のハンド履歴メーカーを用いて解説をしていきます。
http://pokertrainer.jp/StoryMaker/edit.html

◇プリフロップ
◎プリフロップから見るSB Flat Callレンジの構築
それでは早速、プリフロップを見ていきましょう。
ここでは、主に
「500NL、ES100bb」を題材にしています。
GTOwizardのプリフロップレンジをもとにそれぞれのポジションに対しての対応を比較します。
SB vs UTG 500NL,ES100bb

SB vs HJ

SB vs CO

SB vs BU

これらのプリフロップレンジを元に、Call、3bet、Foldの3つのアクション頻度を表にまとめました。

vs UTG〜BUまでのプリフロップを見てみると
Open Raiserのポジションが浅ければ浅いほど、Callする頻度が増えています。
さらに注目すべきはCallと3betの比率です。
vs UTGの時のみ、比率が9:16となっており、フォールドせずにSBから参加する場合のレンジのうち、約40%がCALLという結果になりました。

これは、UTGのopenレンジがかなり強いことから3betではなくCallに留めておく方が利益的になる場合があるということです。
他のCALL比率も見てみましょう。
HJが25%、COが17%、BUが10%となりました。
やはり、vsポジションが浅いほど、3betではなく、Call頻度の割合が高くなるようです。
また、CO以降のOpenに対してはCallする比率が20パーセントを下回るのもわかりました。
以上の内容から
vs UTGとHJのOpenに対してのみ、Callレンジを設けるという戦略が汎用性が高いと考え、今回の記事では、この2つのポジションに対してのSB flat Call戦略として深堀をしていきたいと思います。
◎プリフロップのCallと3bet混合ハンドレンジを偏差値による分類わけ
次に、具体的にどのようなハンドを3betではなくCallに回すのかを考えていきます。
vsUTGを想定して考えてみましょう。

※3bet率100%のハンドレンジは除外しています。
上の図では、それぞれのアクションする頻度が30%Fq以上のスポットを色付きにしました。
CALL頻度の高い順に注目し上からで並べると
ATs>AJs>TTs>88s>99s>77s>AQo>JTs>JJs>KJs>QTs ….
となりました。
次に3bet頻度の高い順に並べると
AQs>QQs>KQs>AKo>QJs>KTs>A5s>KJs>JJs>99s>AQo>A4s …
となりました。
ここで、それぞれのハンド事に偏差値を求め、偏差値が50以上のハンドにも色つけを行いました。
その結果、CALL頻度における優性なハンドは
「JJs〜66s、AJs〜ATs、A5s、KJs 〜KTs、QJs〜QTs、JTs、AQo」となり、
3bet頻度における優性なハンドは
「QQs〜99s、AQs〜ATs、A5s〜A4s、KQs〜KTs、QJs〜QTs、65s、AKo〜AQo」となりました。
この二つの偏差を比較するとCall向きのハンドと3bet向きのハンドの選択が簡単になります。
(あくまでもバランスを取る上での感覚的な補助の指標となるものと捉えてください。)
これらの偏差値を元に、ハンドを選んでいきます。
それぞれのアクションに対して、偏差値が59以上のハンドをピックアップすると、次のような形になります。
まとめ
・CALL
TTs〜77s、AJs〜ATs、JTs
・3bet
QQs〜JJs、AQs、A5s、KQs〜KTs、AKo
・混合ハンド(3bet・CALL混合)
JJs〜99s、AJs〜ATs、KJs〜KTs、QJs〜QTs、AQo
一旦、これらを頭の中にいれておけば、戦略として機能しそうですね。
ここまででもよいのですが、今日はおまけに別のGTOツールを用いて、より精度の高いものにしていきます。
◎プリフロップのソースによる違いから戦略精度を高める
ここまではGTOwizardのレンジをもとに戦略を組み立てました。
次はGTObase社の集合分析を使いながらみていきます。
これらのGTOツールの細かい違いや傾向を見比べることで、より精度の高い戦略を構築していきます。
参考までにGTObaseのvsUTGレンジを掲載しておきます。
vs UTGのみ掲載

GTObaseに関しても、先ほどのようにCall、3bet、Foldの3つのアクション頻度を表にまとめました。
下にGTOwizardの頻度表も載せていますので、比較してみていきましょう。

GTOwizard

GTOwizardとGTObaseのプリフロップを比較すると
GTObaseの方が、SB においてのCALL頻度がやや多くなり、3betの頻度が若干減少しています。
では、更に分析をするために、GTObaseのSB vs UTGでのプリフロップをGTOwizardの時と同様に表にまとめます。

上記のような表になりました。
更に、GTObaseと先ほどまとめたGTOwizardの表を比較してみます。

注目すべきは、上図の一番右の表です。
CALL頻度と3bet頻度の差をとり、GTOwizardとGTObaseを比較した際に、GTObaseの方がCALL寄りになるハンドと3bet寄りになるハンドを比較してみました。
上の表で言うと、ΔCall Fqの欄で、濃い緑になればなるほどCALLになっており、
Δ3bet Fqの欄で、濃い赤になればなるほど3betになっていることを表しています。
具体的に見てみると、以下の様な傾向があるようです。
CALL寄りになるハンド:JJ〜99s > AJs >>> AQs〜
3bet寄りになるハンド:A3s
少しマニアックな分析をしてみましたが、このことを踏まえた上で実戦を立ち回るのも良いかもしれません。例えばGTOwizardでは3betが推奨されていたJJをタイトなUTGを相手にする際はCallに変えることや、ルースな相手に対してはA3sを3betすることで、期待値を高めるなどです。
このような形でSBからのflat call戦略を導入することで、貴方のポーカーの幅が広がるはずです。
以上でプリフロップの解説は終了なのですが、問題はこの後ですよね。
SBでCallをしてしまったことで、フロップ以降はOOPが確定した状態で戦う必要があります。
BBの時のように立ち回ればよいと思いきや、BBとはcallレンジが違うため、独自の戦略を学ぶ必要があります。
次回の記事はSBでflat Callをした後のポストフロップについてを解説していきます。
前編はここまでとなります。是非次回もご一読ください。
後編はこちら
◇告知〜POKER GYM〜
パーソナルトレーニングジムをイメージしたポーカーのトレーニングサービスを正式にリリースいたします
その名は 「Poker GYM」 本サービスの特徴は以下です!HPはこちら↓


特徴
・GTObaseでのトレーニングサポート
・簡易戦略の構築を支援
・パーソナルな空間
・圧倒的なコストパフォーマンス
GTObaseでのトレーニングサポート
本サービスでは、GTObaseというサービスのトレーニングツールを使っての学習をコーチングしていきます。 従来のサービスでは、オンラインポーカーなどを打ちながらコーチからフィードバックを受ける形が殆どでした。 したがって、普段オンラインポーカーをやらないorオンラインポーカーに抵抗がある方にとっては敷居が高いものであったかと思います。 本サービスではオンラインポーカーを使用しない方法を用いることで、このような課題を解決しています! アミューズメント大会での上位を目指す方や海外ライブゲームで活躍したい方にも質の高いサービスを提供いたします!


簡易戦略の構築を支援
従来のコーチングサービスでは、具体的なプレイに対してスポット事のフィードバックのようなものが多い印象です。 ある程度の実力を有した方であれば、これでも良いのですが、戦略が定まっていない初中級者にとっては、その場の暗記になってしまい、応用力が身につきません。 したがって、本サービスでは、GTOを基礎とした簡易戦略の構築をゴールとしたコーチングを実施いたします! 座学で簡易戦略を考え、コーチからフィードバックをもらい、トレーニングを通して簡易戦略を自分のものとして身につけていくようなサイクルでレベルアップをはかります! これまでに中途半端に知識を身につけてしまった方も、一旦リセットしていただき、0から簡易戦略構築をしていきましょう!


パーソナルな空間
本サービスはパーソナルジムをコンセプトとしているため、各種トレーニング環境もパーソナルなものになることを大切にしております。 コミュニティ環境にて、自由に歓談いただくことは可能ですが、ハンドレビューやコーチングに関しては全てパーソナルな環境をご用意しております。 例えば、「強者の集まるコミュニティで質問がしずらい」や「レベルが低い自分が議論に加わると迷惑になってしまいそう」のように感じた経験はございませんか? 本サービスでは、ハンドレビューや質疑応答に関してもパーソナルコーチが個人のワークスペースでご対応いたしますので、周りの目を気にせず学習に集中していただけます!


圧倒的コストパフォーマンス
国内における従来のポーカーコーチングサービスと比較した結果、当社は圧倒的なコストパフォーマンスです!
類似サービスの例:
S社 コーチング1時間 25000円
P社 MTTコーチング1時間 14000円
P社 リングコーチング1時間 8000円
当社 簡易戦略構築コーチング1時間 5500円
1時間あたりのコーチング時間で考えるとかなりお得で、しかもコーチのレベルも高いため圧倒的なコストパフォーマンスでお届けいたします!

各種リンク・申込/相談はこちらから
HP
Twitter &無料コミュニティ


監修: NSY
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
