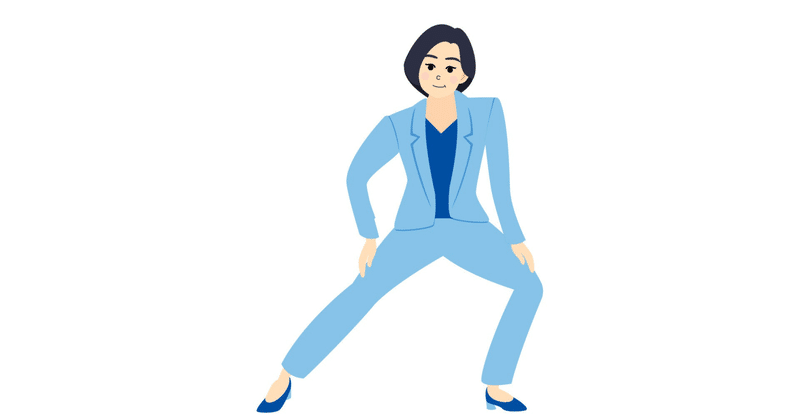
訂正です【自己負担限度額】元ビジネスアナリストが人工股関節置換術を受けるとVol.7
注)2022年7月13日午前に投稿した記事に間違いがありましたので、修正致しました。訂正箇所はわかるようにしてあります。訂正してお詫び申し上げます。
こんにちは!KeyT(ケイティ)です!今日もぶっ放しますよ〜♡
(私のぶっ放しますよ〜!はアントニオ猪木さんの「元気ですか!」と同じものだと思ってください)
さて、前回は入院・手術に関する負担額カテゴリーの中で、自己負担額とは
について書きましたので、今回は似て非なる『自己負担限度額(以下限度額)』について書きますね!
まず、病院で入院することが決まると、会計の方に「手術日までに限度額認定証をもらってきてください」と言われます。なんせワタクシ手術初なので、「ポカン…」でした(笑)。
限度額認定証を得るには、ご自身の加入している健康保険にあらかじめ申請が必要です。
申請する窓口は、国民健康保険なら国保給付係等、会社なら健康保険組合です。会社の場合、発行までに2週間程度かかるところもあるそうなので、早めに申請しましょう。
限度額認定証がなぜ必要かというと、それがあると会計時の支払いを所得・給与に応じて支払う上限額が決まるので、後から高額療養制度で申請する必要がない、ということです。
例えば、あんまり考えたくないですけど、出先で交通事故にあって救急車で運ばれたことにしましょう。なかなか大きな事故で大掛かりな手術になりそうです。まさか自分が事故に遭うなんて思っていないから、限度額認定証を発行してもらっていないですよね。交通事故じゃなくても、病気の発覚から入院手術までに限度額認定証の発行が間に合わないケースってありますよね。
そういう場合は、退院時に3割負担分をお支払いして、後日高額療養費の申請をすることにより、払い過ぎた分を返してもらうことができます。
私が受けた人工股関節置換術のように、手術日程を計画的に決める場合は、限度額認定証の申請して、先に備えておくことで、退院時に3割負担より少ない限度額で支払いを済ませることができます。
限度額認定でお伝えしたいのは、
支払う限度額は所得区分によって異なる
月をまたぐと月数分支払わなければならない
の2点です。
まず
■支払う限度額は所得区分によって異なる
ですが、
この限度額認定における限度額は一律同じではなく、所得区分によって異なります。下記表の健保・国保をご覧ください。

健保の場合は標準報酬月額、国保の場合は年間所得で決まります。
ご夫婦共働きで、ご主人が年収370〜約770万で、奥様が年収訳770〜1160万円で、奥様が手術をする場合、奥様の年収で限度額が計算されます(このとき、世帯主がどちらでかは関係ありません)。
また、同居のお子さんが就職していて、ご両親の保険に入っておらず、ご自身の保険に加入なさっていて、お子さんが手術する場合はお子さんの年収で限度額が計算されます。
つまり、手術をうける人がどの保険に加入していて、年収がいくらかで限度額が決まってきます。
上記表内に計算式があるので、真ん中の年収370〜約770万のケースで限度額を計算してみますね。
【正】用いる式は、
80,100円+(医療費-267,000円)×1%です。
仮に医療費が200万円だったとすると、
80,100円+(2,000,000円-267,000円=1,733,000円)×1%
=80,100円+17,330円
=97,430円
がひと月あたりの限度額になるわけです。
医療費200万円の3割負担で60万円の医療費を支払わなければならないところ、97,430円で済む、ということです。
(noteを読んでくださったFPさんが修正の連絡をくださいました。訂正して重ねてお詫び申し上げます)
【誤】用いる式は、
80,100円+(医療費-267,000円)×1%です。
仮に医療費が60万円だったとすると、
80,100円+(600,000円-267,000円=333,000円)×1%
=80,100円+3,330円
=83,430円
がひと月あたりの限度額になるわけです。3割負担だと60万円の医療費を支払わなければならないところ、83,430円で済む、ということです。
ちなみに。
この医療費には差額ベッド代や食事の自己負担額、その他の自己負担額は含まれません。
ですので、支払う額は
=限度額(上記の例だと83,430円)+差額ベッド代や食事の自己負担額、その他の自己負担額の合計になります。
が!が!が!が!
これ、入院・手術・退院が同月内で終わる場合、のお話です。
今日お伝えしたいことの2点目、
■月をまたぐと限度額は月数分支払わなければならない
です。
私、6月30日入院で7月6日退院だったので、6月はたった1日ですが、限度額を2倍支払わなければならなかったのです・・・。
ですので、命に関わることや、急を要すること、どうしても自分の都合が合わない、そのスケジュールじゃないと希望の先生に手術してもらえない等という場合でなければ、その月に入院・手術が全て終わるようにできた方が支出は抑えられる、ということです。
利用回数や疾患によって異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村の国保給付係等やご加入の保険団体に個別にお問い合わせくださいね。
3割負担全額支払うところから、限度額で支払うところまで支払い額を減らすお話をしてきましたが、別途医療保険にも入っている場合、保険金を受け取ることができます。
(ちなみにKeyTはS保険ではございません)
ということで次回はCMでみかける、「手術1回◯万円、入院日額△千円!」の医療保険(プラスちょこっと確定申告)ついて書きますね!
本日も最後までお読みくださり、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
