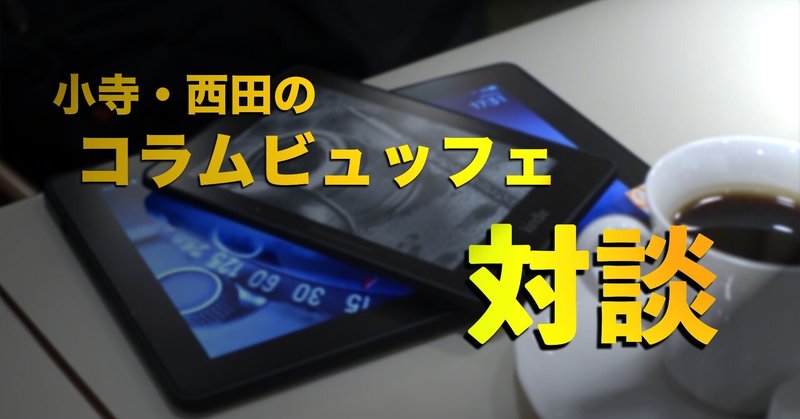
「リモート授業」その光と影(最終回)
毎回専門家のゲストをお招きして、旬なネタ、トレンドのお話を伺います。
![]()
大阪工業大学 知的財産学部 准教授の関堂幸輔先生に、リモート授業の実態についてお話を伺う最終回。以前全5回とご案内していたが、どうもうまい切りどころがなかったので、ちょっと長いが今回で最終話とさせていただく。
関堂先生の試験は、以前からパソコン・スマホ持ち込みで調べながら回答あり、あるいはみんなと相談してもいいという、斬新な方法で行われてきた。そんな試験もオンラインになり、Google Formsを使うことになったという。
元々記述式ではなく、マルバツ式の試験だったため、移行しやすかったところはあるのだが、オンラインになることで「試験の意義」を改めて再認識する事になるという、そういうお話である。
「リモート授業」その光と影(最終回)
![]()
小寺:一方で、学生のほうはいかがですかね。学生が学業の過程で動画を作る必要性とか、どういうケースが考えられますかね。
関堂:もともと大阪工大の知的財産学部は、学生は入学するにあたってパソコンを自分で持ちなさい、ということを指示してるんですね。実際に授業でも使う場面がある。このコロナになる前の話から、ちゃんとパソコンは持ちなさいと。だから、パソコンは一応持ってるはずなんです。
ですから、パソコンを使って何か動画を撮るとかっていうんだったら、できなくはないと思うんですよね。ただ問題は、さっきおっしゃったような、効率的な編集をするとか、ってなると、何かしらガイドというか、導くのは必要なんじゃないかな、というのは思いますね。あとは、一応パソコンを持っているとはいいものの、せいぜい授業でちょろちょろっと使うだけで、もっぱら自分はスマートフォンでやってます、という学生もやっぱりいる。そうすると今度は、スマートフォンで動画を撮って編集して、ということが、こういう方法でできるよとか、アプリを使えばできるよ、とかっていうことが分かるといいんじゃないかな、思いますね。

大阪工業大学 知的財産学部 准教授の関堂幸輔先生
小寺:学生でも研究発表会みたいなものって、以前はホールとかに教授を集めてプレゼンする、みたいなのがあったと思うんですけど、今はもうできなくなってますよね。そういう時、ライブのプレゼンテーションに代わって研究発表動画を作る、みたいなことってあるんですかね。
関堂:私の知ってる範囲では、そこまで積極的なことはなされてないと思います。もしかしたら理系の学部とかですと研究成果の発表というのは非常に重要で、もう既にそういうのをしてるかもしれません。
ただ、どうでしょうね……もしかしたら2021年度ぐらいからは、学生にプレゼンをさせる時に、リアルのプレゼンじゃなくて動画を作ることで、それをもってプレゼンテーションとする、ということも今後は考えられるんじゃないかな、というのはありますね。
ここから先は
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
