
「競馬の教科書」ってぶっちゃけどうなの? #5
こんにちは。競馬予想家 ノアです。
このマガジンでは〈玉嶋 亮氏が出版する「競馬の教科書」に競馬予想家 ノアが個人的見解や批評をぶつけちゃおう!〉という趣旨のもと、購読者、非購読者それぞれにコミットできるような内容をお届けしていくことを目的としています。
要は「競馬の教科書」をまだ買っていない人も、既に読破している人にとっても、このマガジンは読んでみる価値あり!ということですね(^_-)-☆
※このマガジンは完全無料公開とさせていただきます。よって私、競馬予想家 ノアには一切の収益が発生しておりません。
今回#5ではこれまでの#1~#4(導入編)で取り上げたトピックスのまとめをお送りしようと思います。
毎回この「『競馬の教科書』ってぶっちゃけどうなの?」をご覧いただいている方はこれまでの復習と整理に、今回はじめてご覧いただく方はこの記事を読むだけで次回以降に追いつけると思うので、是非ご覧ください。
#1では「競馬の教科書」を買っても意味のない人がいますよ!というお話をさせていただきました
えっ( ゚Д゚)
1,500円も払って買ったのに意味がないの。。。
驚きですよね。もう既に「競馬の教科書」をご購入されている方も、これから買おうと思っている方もご自身にとって本書が意味を持つものなのかどうかを再度確認してみましょう!
・「競馬の教科書」を読んでも意味のない人
「競馬は当てることが楽しい!」「的中率重視」
「好きな競走馬を応援する!」
これらに1つでも当てはまる人にとって「競馬の教科書」は全く意味をなしません。残念です…。でも結構こういう方多いんではないでしょうか。だからといって、これらに当てはまる方がダメというわけではありません。競馬の楽しみかたは人それぞれ。ただ「競馬の教科書」を買って意味があるかと言われると微妙なラインだということをご認識ください。
では一体、どんな方にこの「競馬の教科書」を読んで欲しいのか?
・「競馬の教科書」を読んで大きく成長出来る人
・競馬で回収率100%越えを目指したい!!
・競馬で勝つ為の考え方やノウハウを知りたい!
競馬で儲けたい、回収率100%越えを目指したい!
そんなハングリーな競馬ファンにこそ「競馬の教科書」はオススメできる著書になっています。
つまり「競馬の教科書」は競馬で勝ちたい人に向けた実践書だということ。
でも、競馬で勝つ(回収率100%越え)ってそんなに簡単じゃないでしょ?って思いますよね。
たしかに簡単なことではありません。恐らく年間ベースでプラス収支を叩き出せるのは全競馬ファンの10%にも満たないでしょう。
しかし「競馬の教科書」を読めば、そんな勝ち組への第一歩を踏み出すことができます。
勝ち組への第一歩ってなんなのか。それは「正しい少数派」へのなり方を知るということなんです
競馬はギャンブルである以上、負け組が全体の大半を占めてしまいます。その中で他者より優れた回収率を叩き出し、控除率20%の壁を越えて勝ち組で居続けたいと思うならば、多くの人と違った方向を向くしかありません。(少数派になるしかないということ)
更にここで大事なのが「正しい」ということ。
「みんなが右に行くから左に行けばいいんだ!」という安直な考えではダメ。しっかりとしたロジックと裏付けのもとで「左に行く」ことが大事なんです。
ここまでを読んだだけでも皆さんが絶対にしてはいけないことが1つお分かりいただけたと思います
そう。それは人気馬を買うこと。
先ほどの例でいうところの「右に行く」という選択こそが「人気馬を買う」ということ。これでは「少数派」にはなれません。
1日に行われるレースのうち半分以上は人気馬が馬券に絡んでしまいます。
むやみやたらに全レースで穴馬から勝負しても勝てません。
それでも「どういったレースでは穴が出るのか」「穴馬はどうやって探したらいいのか」などしっかりとしたロジックを身に付けていれば「勝負どころ」がわかるようになり「正しい少数派」に近づけるんです。
この「競馬の教科書」ではそんな「正しい少数派」へのなり方を独自のメソッドで教えてくれています。皆さんも実際に「競馬の教科書」を読むとき、このコラム連載を読むときは「なぜその考えに至るのか」の根底にある「正しい少数派にならなきゃいけないんだ」という考えを持ち続けてください。
#2からはいよいよ、本書の内容に切り込んでいきます。
「正しい少数派」になるためにはしっかりとしたロジックを持ってレースを吟味し、穴馬から勝負をする必要があるとお伝えしました。
本書は本当にこの「少数派になる」「みんなが右なら左に行く」という考えを一貫して徹底しています。
このコラム連載では大きく2つのポイントをピックアップしてその徹底ぶりをお伝えしてきました。
① 予想ファクター
② 馬券の買い方、オッズの見方
まずは①予想ファクターから。
競馬で勝ち組、「少数派」になるためには予想ファクターも大多数の競馬ファンとは異なったものを使っていく必要があります。
少し前に箱根駅伝かなにかで、もの凄く速く走れるシューズが話題になりましたよね。あれはほとんどのランナーがそのシューズを履いていないからこそ有利に立てたもので、全員そのシューズを履いていたら別になんてことはない単なるシューズに成り下がってしまいます。
「競馬の教科書」でも似たようなことが書かれています。
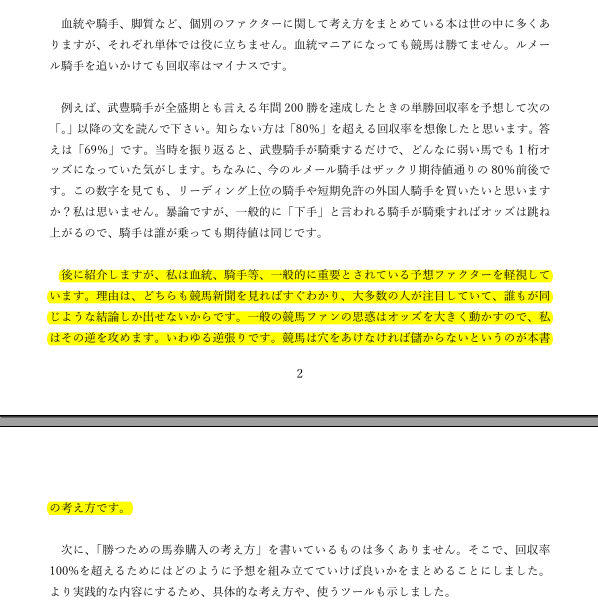
(本書より抜粋)
具体的には戦歴(着順)に頼ったものや血統・調教など人気のある予想ファクターや競馬新聞などの大手メディアで簡単に手に入るものはダメというのが本書の(著者の)主張です。
では、そんな「競馬の教科書」がオススメする予想ファクター、他人より速く走れるシューズとは一体なんなのか?
その答えがトラックバイアスとコーナリング能力(Cr能力)です。
まずはトラックバイアスについて。
ここでのトラックバイアスとは各競馬場ごとのコースレイアウトの違いや開催時期の違いによる馬場コンディションの差に着目するということで、「競馬の教科書」では各競馬場をスピードタイプの馬が走りやすいコース/スタミナ・パワータイプの馬が走りやすいコース、という2タイプに根拠と共に分類してくれています。(★★★★★~★☆☆☆☆)
特に面白いのは中山競馬場について述べている部分。
春開催と9月開催、年末開催とでは同じ中山競馬場でも全く異なるタイプの競走馬が走るという事実を教えてくれています。
これに関してはこの連載コラム#2でも取り上げていますし、興味のある方は実際に本を手に取って読んでみてください。
この競馬場ごとの違いや共通点をしっかりと把握すると、過去の凡走に理由付けができたり、人気になっている過去の好走を疑ってかかることができたりします。これが穴狙いにはとても大事な指標となりうるんです。
例えばこの記事を書いている時(2021/3/19)は中山・阪神・中京の3場開催なんですが、この3場はいずれもスタミナ・パワー寄りのコースだと紹介されています。
逆にスピード寄りのコースとして紹介されているのが東京、新潟競馬場で、この2場での好走実績を評価されている人気馬はスタミナ・パワー寄りのコースでは疑ってかかることができます。
この最たる例にアーモンドアイが当てはまりますね。
アーモンドアイがキャリアのなかで唯一着を外したのが有馬記念。12月開催の中山競馬場は「競馬の教科書」ではスタミナ・パワー寄りの馬場に分類されています。歴史的名牝であっても馬場バイアスの前には歯が立たなかったということで、予想する際に「近走で走っている競馬場がどのタイプに該当し、そこでの結果がどうなのか」を馬柱と「競馬の教科書」を両手に比較・検討すると皆さんの予想力がグーンと上がると思いますよ!
次にCr能力について。
Cr能力とは3,4コーナーで馬場の良いところ、好きな位置を好きに獲りに行ける能力のこと。「競馬の教科書」ではこのコーナーは椅子取りゲーム状態。Cr能力が低い馬だとコーナーで後方に置かれ、進路も大外しか残っていないという不利な状況に立たされることが多いそうです。
人間の椅子取りゲームでいうところの「瞬発力」「条件反射」みたいなことなんですかね。曲が止まってから椅子に座るまでの瞬発力が遅い人はすぐに脱落してしまいます。
このCr能力が少数派になるためには持って来いの予想ファクターで、判断材料は過去のレース映像を観るしかなく、競馬新聞には載っていないし、定量的に評価することができない。
まさに誰とも被らない予想ファクターと言えます
「競馬の教科書」ではCr能力を測る為にはどのようにレース映像を観ればいいのか?そのポイントを4つ紹介してくれています。
これに関してはぜひ本書をご覧いただき、確認してみて欲しいと思います。
百聞は一見に如かず。行動あるのみです!
ここまで紹介してきたトラックバイアスとCr能力の他にもう1つ、「競馬の教科書」では穴馬を見つける際に有効なファクターを教えてくれています
それが#3で紹介したレース回顧。今回のレースでなんらかの不利や明らかに適性が合わないコースを走らされた馬を見つけ出し、次走のねらい目としてストックしておくことが大事だと教えてくれています。
これは私をはじめ、多くの競馬予想家の方々が恐らくやられている作業ではあるんですけど、そうではない競馬ファンの皆さんはあまりやってこなかった作業なんではないでしょうか。
「競馬の教科書」ではどのような馬が次走以降のねらい目になりうるのかを解説してくれている部分がありますし、連載コラムでも丸々1回を使って解説していきました。実際にこの記事を読んでレース回顧をはじめて、万馬券を獲ったなんていう嬉しいお声をいただけたりしてます。結構、即効性もある予想法なので皆さんもぜひ使ってみてください!
#3に関しては下にリンクを貼っておきますのでよかったら覗いてみてください。
そして前回(#4)では②馬券の買い方、オッズの見方を取り上げました。
私は「競馬の教科書」を買って勉強になったなぁ~と1番感じたのがこの部分でした。本書で取り上げている馬券のすすめは大きく4つあります。
単勝や1着買いの馬券を厚めに買う、穴狙いのときこそ難しい馬券(馬単や3連単)を買う、均等買いをする、マイルールを決めて購入金額を定めることで当てに行かない予想ができる
それぞれの理論にはしっかりとした根拠が示されていて、読んでいてなるほどなぁ~と感心させられることばかりです。
特に穴狙いの時こそ難しい馬券に挑戦するというのは、なかなかできることではありません。しかし「競馬の教科書」はしっかりと理にかなった根拠を用いて読者の背中を後押ししてくれます。
穴狙いをする以上、当たった時に大きく回収したいもの!!
そのために必要なノウハウをこの本から学びましょう!
以上がここまで(#1~#4)の「『競馬の教科書』ってぶっちゃけどうなの?」で取り上げさせていただいたトピックスになります。
もちろん本書にはまだまだ皆さんの予想力、馬券力向上に役立つ情報が山のように詰まっています。だからこそAmazonでは常に競馬本ランキングの上位に位置し、根強い人気を博しているのでしょう。
これまでは「競馬の教科書」のなかでも【導入編】にフォーカスをあてて記事を書いてきましたが、次回#6~#10ではいよいよ実践編、ケーススタディーへと進んでいきます。
実践編、ケーススタディでは毎週の重賞について「競馬の教科書」を使いながらレース回顧をしていけたらなと思っています!
記事公開前に皆さんも「競馬の教科書」を片手にどのトピックスを活用すればあの馬券は取れたのか、考えてみると面白いんではないでしょうか。
●最後に
この記事が「参考になった」「面白かった」という方は記事へのスキをよろしくお願いします!
そしてこのマガジンシリーズでは「競馬の教科書」著者である玉嶋 亮氏たってのリクエストによりTwitterでマガジン読者からのコメントを募集させて頂きます。
皆さんからのツイートには実際に玉嶋 亮さんからリアクションが来たりしますよ!
コメントは以下ツイートのリプ欄にお願いします
この記事を読んでみて「競馬の教科書」読んでみようかなという方は下にAmazonの商品ページも貼り付けておきますのでリンク先から是非、購入してみてくださいね。
それではここまでご覧いただきありがとうございました。
また次の記事でお会いしましょう!
競馬予想家 ノア
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
