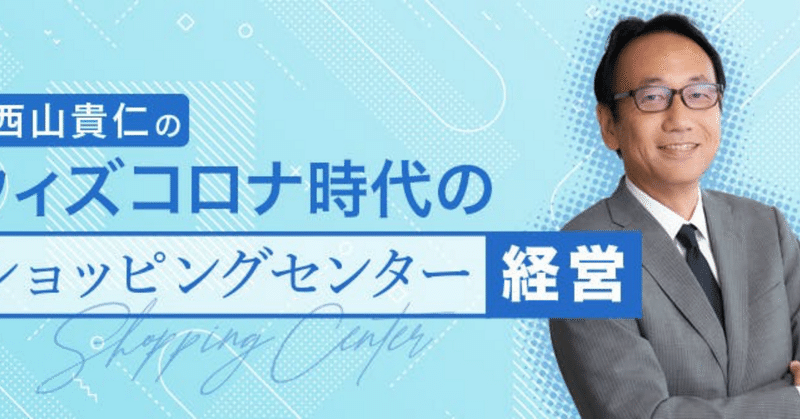
ウィズコロナ時代のショッピングセンター経営8 家計の現預金1,031兆円は誰の手に行くのか
ウィズコロナ時代のショッピングセンター(SC)経営第8回は、ECが売上を伸ばすなかで、改めてリアル店舗の価値、ECの価値とは何かを考えたい。多少厳しい論調となるが、いまビジネスモデルの在り方を刷新しないとSCの将来は暗いものになると案じているがゆえ、であることを理解してほしい。だが、お客さまは正直だ。それが数字に表れているのである。
リアル店舗の価値とECの価値
コロナ禍による緊急事態宣言が解除されたにも関わらず、ショッピングセンターの売上は戻らない(図表①)。この理由として、人の移動、消費者の意識、不要不急の自粛など多面的な要因がある。しかし、その一方でECは伸び、生活に必要な物資の売上も安定している。消費者は決して買い物をしていないわけでは無いのだ。
この事実を踏まえて今後のリアル店舗の行く末に対する処方箋を前号で提示した。
その前回の連載で、「ネット時代において店舗は商品の受け渡し場所に過ぎない」と書いたところいくつかのお叱りをいただいた。
これまで店舗運営を商いにしてきた方にはやや表現が厳しかったようだ。
しかし、古来、市(いち)も商店もすべて商品の受け渡し場所であったはずだ。店舗に商品を並べ、客が来れば金銭と交換し商品を受け渡す。
今はそれがネットで決済を済ませたものを店舗で受け渡したところでそれは金銭の授受がネットで完結しただけであって、店舗の機能は何も変わっていない。
反論のほとんどが「店舗では実体験(フィッティングや接客)があるからただの受け渡し場所じゃない、そこにはコミュニケーションが存在する!」なのだが、それが店舗機能の価値であることは理解できる。しかし、ECであれば出かける必要もなく、自宅で買い物ができ、自宅まで配送される。こうした利便性こそがECの価値である。
さて、顧客はどちらに利便性(価値)を感じるのだろうか。人ぞれぞれだとは思うが、今、SCも百貨店も売上が減少していることに反してECが伸長している事実を見ればその答えは明らかではないだろうか。
続きは、
↓無料です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
