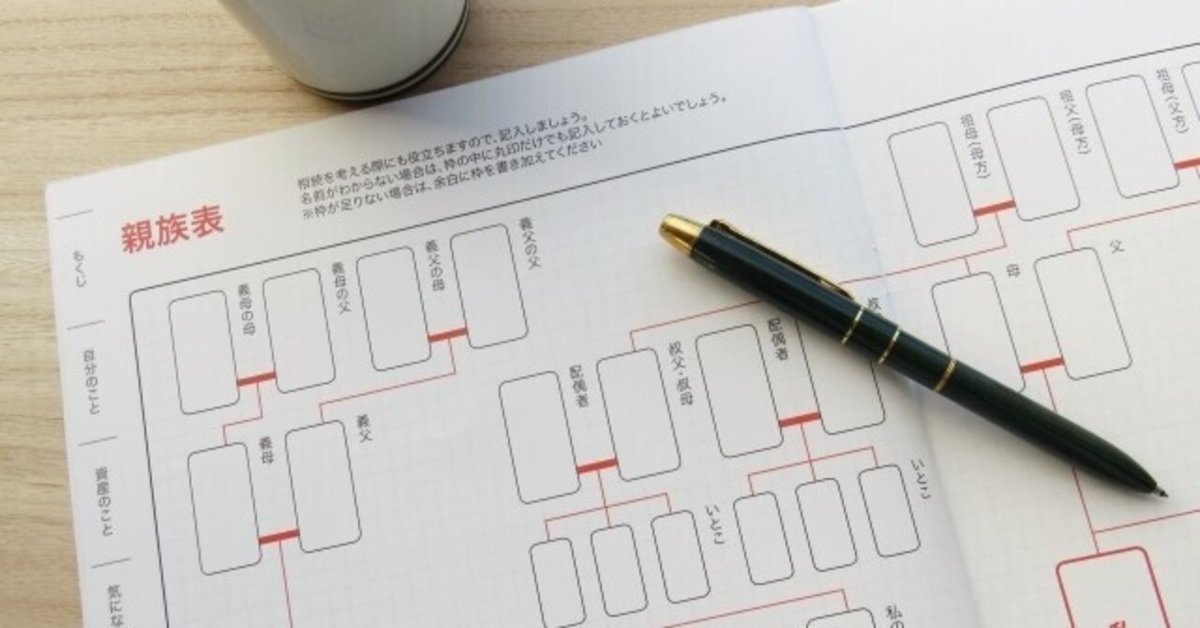
養子縁組と相続
(普通)養子縁組の件数が年間10万件以上あることを皆さんはどう思いますか?
かつては(現在でも少なからずあるようですが)、家系を絶やさないために、養子縁組が行われていました。
今回は、相続と養子縁組について少し書きたいと思います。
誰が相続人になるの?~相続人の範囲と順位
このあたりは、もうあまり書くこともないと思うのですが。
配偶者は常に相続人になります。
① 子がいる → 配偶者と子
② 子なし。両親健在 → 配偶者と子
③ 子も両親もなし → 配偶者と兄弟姉妹(いれば)
④ 配偶者がいない場合は、子→親→兄弟姉妹となります。
代襲相続~孫が相続人
被相続人の子が、相続開始前に死亡している場合、あるいは欠格事由(891条)もしくは、廃除されている場合、その子の子(つまり孫)が相続人となります。
あまり現実的ではありませんが、場合によっては「ひ孫」が相続人ということもあり得ます。ちなみに、兄弟姉妹の場合は子(甥、姪)までが代襲相続の対象となります。
養子縁組~今日から親子
相続関連の書籍などで、ときおり「相続税対策のための養子縁組」などについて書かれているのを見かけますが、みなさん、ご存じですか?
相続税には「基礎控除」という制度があります。ここでは、詳細は割愛させていただきますが、要は、相続人の数に応じて、課税財産から控除ができる制度です。
「養子縁組」は、届出を行うことで比較的簡単に行うことが可能です。
【民法809条】
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
つまり、血のつながった実の子と「養子」は、相続に関してはまったく同じ扱いになります(2時間サスペンスでこじれるやつです)。
問題は、この「養子」にすでに子供がいる場合。
養子縁組前の子は、先にご説明した、「代襲相続」の対象とはなりません。縁組の日から嫡出子なので、縁組前の人間関係は養親との間では関係ないことになります。
逆に、養子縁組後に生まれた養子の子は、「養親の孫」になるので、代襲相続の対象となります。
さいごに
現在、「家系(血筋)を絶やさないために~」という理由で養子縁組をするケースは、かつてに比べれば少ないかと思われます。
たとえば、娘婿を養子にしたい、お子様のいらっしゃらない個人事業主の方が、有望な社員を養子にして~とか、(あまり、具体例がうかびませんが・・・)でしょうか?
ただ、親族(特に相続権がある人)にとって、少なからず、期待というか関心があるのが相続です。そこへ、血縁関係のないあかの他人が入り込むわけですから、養子縁組の理由が何であれ、なにかしら対策を打つべきです。
これから「養子縁組」をお考えの方は、ぜひ「弁護士」に事前に相談の上、慎重に縁組を含めた相続対策をお考え下さい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
