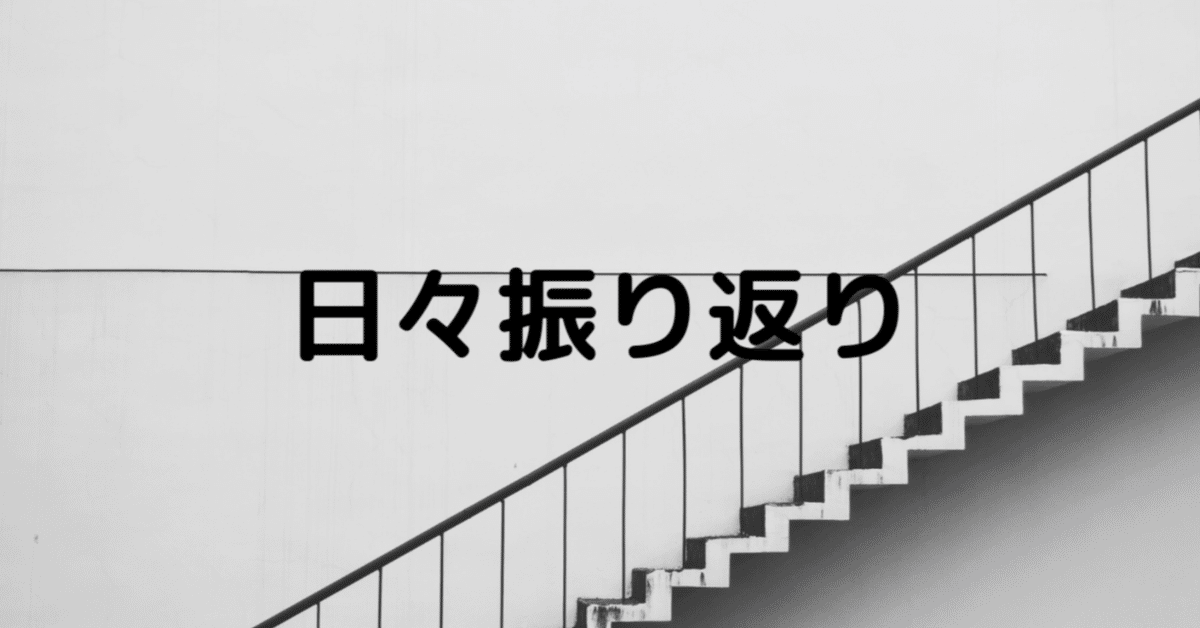
症例振り返り9 赤沈と脊椎インプラント感染
赤沈のベースラインは判断に困る
赤沈はリウマチ疾患や膿胸などでの病勢の評価に使われるものの、貧血や年齢など色々な要素で大きく変動するパロメーターになる。
赤沈は年齢が高くなるにつれて高くなる。
正常値は男性なら年齢/10、女性なら年齢/10+10。
貧血での補正式はHt/45×赤沈速度となる。
脊椎インプラント感染では抗生剤投与期間は?赤沈やCRPはどういった指標になる?
人工物感染の治療の原則は、人工物の抜去である。
しかし脊椎固定術後などではインプラント抜去による脊椎の不安定性が致命的となるため、インプラント抜去できない場合が多い。
その場合の抗生剤の投与期間をどのように設定するかについては、明確な基準はない。
経験豊富な上級医曰く、原則は
できる限り検体採取し菌体を捕まえる。
エンピリック治療はnarrowに初めて必要に応じてescalation
最低6週間の抗生剤静脈投与
最低6か月の抗生剤継続。
6-12カ月で抗生剤offをトライしてみるか検討
だそうだ。
その中でCRPや血沈が陰性化しないケースは多く経験するとのこと
血沈80以上がベースと思われる方は、その状態が続いたとしても抗生剤offをトライしていくこともあるとのこと。それはその人のベースが不明であり、年齢や貧血以外の多くの要素が血沈というパロメーターを動かしているため個別に考えていくしかないのだと。
血沈は陰性化を目指すのではなく、プラトーになったか見極めるのが有用であると教わった。
CRPも同様に持続的に軽度高値の場合があり、その時にもプラトーになっているかどうかを基準としていると。
この基準を用いると、以下のような判断ができる
点滴抗生剤6週間時点でまだ赤沈は基準値以上だがプラトーに達しているため内服に切り替える
点滴抗生剤6週間時点でまだ赤沈は低下傾向のベクトルである。プラトーに達するまで点滴抗生剤で粘る
内服に切り替えて合計6か月完遂した。3カ月時点から赤沈もCRPもプラトーに達しているのでともに軽度高値ではあるが、抗生剤offをトライしてみる
まとめ
かなり高度な判断ではあるが、人工物温存での感染症治療は基本的に「終生感染が持続してしまうもの」という考えをベースに、それでも抗生剤offができないかという希望をもってI度は抗生剤offをトライしてみることが必要である。
しかし、その前段階として原則の期間が完遂されていることが重要である。
赤沈やCRPの値に振り回されないように症状ベースで経過を追いつつ、冷静にプラトーに達したかどうかを見極める目を持つ必要がある。
記事内容が良ければサポートよろしくお願いします。記事作成の意欲向上になります!
