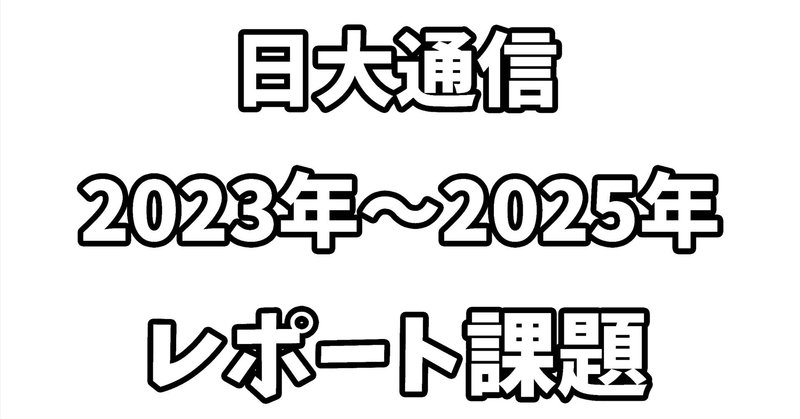
【日大通信】貨幣経済論 2023年~2025年(科目コードR31900)課題2
貨幣経済論(科目コードR31900)課題2
横書解答
ケインズにおける貨幣のトランスミッションメカニズム(金融政策の効果が波及
する経路)を説明しなさい。また,古典派の貨幣ヴェール観との違いを考察しなさい。
〈ポイント〉
ケインズの『一般理論』にもとづき,貨幣量の変化が利子率の変化を経由し,投
資量など実物経済に影響を与えることを確認しよう。トランスミッションメカニズ
ムは,有効需要の原理にもとづくケインズ型消費関数,ケインズ型投資関数を用い
て説明しよう。また,古典派の貨幣ヴェール観,あるいは貨幣の中立性を確認し,
ケインズの『一般理論』との違いをまとめましょう。
〈キーワード〉
有効需要の原理,ケインズ型消費関数,ケインズ型投資関数,貨幣ヴェール観,
古典派の二分法
ケインズの『一般理論』において、貨幣量の変化が実物経済にどのような影響を与えるかが重要な課題として扱われている。具体的には、貨幣量の増加によって利子率が低下し、投資や消費が促進されるというトランスミッションメカニズムが存在することが示唆される。
このトランスミッションメカニズムを説明するためには、有効需要の原理に基づくケインズ型消費関数やケインズ型投資関数が必要となる。ケインズ型消費関数は、所得水準が上昇すると、消費支出も増加することを示唆し、ケインズ型投資関数は、利子率が低下すると、投資支出も増加することを示唆する。これらの関数を用いることで、貨幣量の変化が実物経済にどのように影響を与えるかを明確に説明することができる。
ここから先は
1,893字
¥ 500
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
