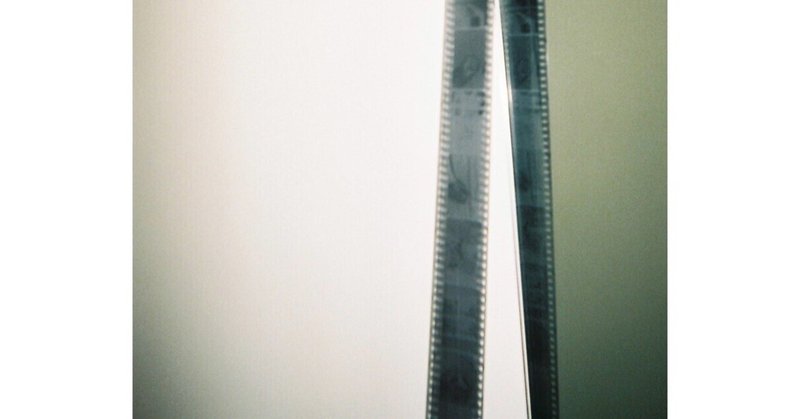
他人になっても世界で一番幸せになってほしい人の話
※約8000字あります※
これこそが運命の恋だと思ったあの人も、今ではすっかり思い出のアルバムの一ページに馴染んでいるし、あんなに大好きだったはずの声も匂いもいつのまにか思い出せなくなっている。案外そういうもんだ。
だけど、いつまでもアルバムの一ページに収めたくない人もいる。
思い返せば、あれは愛というよりは信仰だった。
この人を失ったら、もう生きている意味がないとさえ本気で思っていた。
彼と初めて一緒に見たミュージカル映画のラストシーン。スクリーンに映る二人は幸福に包まれていた。私と彼も、こうなっていた世界線もあったのかな、なんて考えると、今でもちょっと泣けてきたりする。
大学生の時に出会った、少し年上の彼。
彼と私は、よく朝まで話をした。窓の外が白んでくるまで、そんなに長い時間が経っていたなんて、気が付かないことがほとんどだった。隣で寝転ぶ彼の綺麗な横顔を眺めながら、このまま朝が来なければいいのにな、と何度も考えた。眠る時間が惜しかった。もっと聞きたかった。知りたかった。
彼は当時、もっぱらフィルムで写真を撮ることに力を注いでいて、フィルムのフの字も知らない私に、いろんな話を聞かせてくれた。
自宅に暗室があって、そこで夜な夜な現像やプリントをしていること。撮影した時は失敗したと思っていた写真が、いざ現像してみると思わぬ成功を収めていたりすること。暗闇の中で真剣に写真と向き合っていると、まるでこの世界には自分一人しかいないように感じられてくること。今度、合同写真展に自分の写真を出展すること。
どれも私の知らない世界の話だった。
彼はよく「自分が、こんな話を誰かにする日が来るなんて思わんかったなぁ」としみじみ呟いていた。
彼は私と出会う前、数年ほど自室から出られない時期があり、他人と関わることが得意ではないようだった。
だけど、その分、これでもかというほど広大なひとりの世界を持っている人だった。その世界は、私にはとても魅力的に映った。
二人の会話は今日も止まない。
「さっき見た映画のさ、最初のシーンってこういう意味かな?」「あ、確かにそうかも」
「ね、昨日読んだ本の話していい?」「うん、聞きたい聞きたい」
「この歌詞、良くない?」「えー、私はちょっと苦手かもしれん。男側が情けなさすぎる」「それがええんやって」
私たちは、お互いの「わかる!」と「どうして?」をとことんぶつけ合った。意見が食い違うことすらも楽しいと思えるのは、初めての感覚だった。彼と話していると、世の中の解像度がどんどん上がっていく気がした。
私が長年、なんとなく心に持っていたもやもやを彼がスッと言語化してくれたとき、私は机をばんばん叩いてその感動を伝えた。家族以外の他人と、本当の意味で「わかり合えた」と思えたのは、彼が初めてだった。
周囲の女の子が、彼のことを「××さんってかっこいいけど、無口で話しかけづらいよね〜」と評しているのを聞いて、はん、わかってないなあ、と一人心の中で得意げになったこともある。
自分が彼にとって唯一心を許せる存在であることに、私はとてもつもない優越感を感じていた。誰にも理解されなくていい。むしろ理解なんてされてたまるか。彼の良さは、私だけが知っていればいい。
時には、もういっそ、彼の目や脳に生まれ変わりたいな、なんて気持ちの悪いことを考えたりもした。彼の考えてること、見てるものを、余すことなく全部全部知りたかった。
彼がおすすめしてくれた本は必ず読んだし、彼が作った最強のプレイリストは、時代が時代ならテープが擦り切れるくらい何度も聴いた。
反対に、私が好きな作家の新作がいつの間にか彼の家の本棚に追加されていたこともあったし、彼が洗い物をしながらフンフン歌っていた鼻歌が、私が教えた音楽だったこともあった。
今まで別々だった人生が、少しずつ交差していた。
ただ、彼は、前触れもなく1週間ほど連絡を断つことがあった。今まで他人と関わることを避けて生きてきた彼にとって、特定の人物と近付きすぎることは大きなストレスとなるようだった。
「急に心がダメになって、何もできなくなるときがある。」そんな風に言っていた。
初めこそ、悲しくて怖くて不安で仕方なかったけれど、話し合いを重ねていくうちに理由がわかり、私も受け入れざるを得なかった。
私は、自分を「彼のそんな特性を理解している良い彼女」だと思っていた。
でも、実のところは全然、ほんとに全然、理解できていなかった。その時の私はまだまだ子どもで、自分の努力次第で相手を変えられると信じていたからだ。相手のために真摯に向き合うことが負担になるかもしれないなんて、わかるはずもなかった。
だから、彼が連絡を断っている期間も、必死で彼に自分の存在をアピールし続けた。
どうしたの?
何かあった?
ちゃんとご飯食べてる?
ゆっくり休んで。
私は味方だから。
無理しないでね。
待ってるね。
私なりの気遣いのはずのメッセージは、おそらく、彼の心理的負担を倍増させていた。
ただただ彼の気持ちが上を向く日を、気長に待っていればそれでよかったのだと思う。でも、まだ若かった私には、ただ待ち続けること、それがどうしてもできなかった。
大学4回生の冬。彼からの連絡が、1ヶ月以上途絶えた。
心配も悲しみも怒りも呆れも悟りも、もう何周目かわからなかった。あー、さすがにもうこれは本当に終わりかも。そう思っていた時、久しぶりに、彼のTwitterアカウントが動いた。
「来週からです。見に来てください。」
勝手に頭の中で彼の声で再生されるその一言と共にアップロードされていたのは、写真展のポスターと、彼が自宅の暗室でプリントしたであろういくつかの写真。そのツイートはどうやら、彼が出展する合同写真展の宣伝のようだった。
私のLINEは既読無視するくせに、という気持ちと、生きていたことへの安堵、そして、久々に彼の作った世界に触れられる嬉しさが混在して、頭はこんがらがっていた。
画像をタップして拡大する。彼がプリントした写真の中に、ひとつ、見覚えのある姿があった。
これ、私の写真だ。
顔は写っていない。でもわかった。
これは紛れもなく、彼が撮った私の写真だ。
ああもう。
こういうことするんだ、この人は。
こういう、自分に酔っているようなところがどうしようもなく憎い。そして、ちょっと喜んでしまっている自分も憎い。私が彼のTwitterを毎日穴が開くくらいチェックしていることなんて、彼はわかっているはずなのに。
彼からの連絡は一向にない。
一体、どういうつもりなんだろう。
翌週、私はその写真展に足を運んだ。
彼からの連絡は、相変わらずなかった。
家を出る前、何となく、自分が持っている靴の中で一番ヒールが高く鋭利なブーツを選んだ。使い方によっては人を刺せそうだった。さながら戦闘服。
もし、彼本人がいるなら余裕ぶってニコッと笑いかけてやろうと思い、ヒールを鳴らして会場へ入ったが、あいにく彼は在廊していないようだった。
受付でアンケートが挟まったA4のバインダーとボールペンを受け取り、会場内に入る。その写真展はこじんまりとしていたものの、それでも10名ほどが出展しているようで、出展者ごとにエリアが区切られていた。
さて。
彼のエリアはどこかな、とくるりと会場を見回そうとした。だけど、見回すまでもなかった。素人目に見ても一番目立つであろう入り口真正面の壁に、見覚えのある名前のプレートがあった。
途端、ぐらっと地面が揺れるような感覚がした。そして、思わず目を逸らしてしまった。さっきまでの威勢の良さが嘘のように、彼の写真を見ることができない。
あれ、わたし、どうしたの。見たい。見れない。見たい。見れない。見るのが怖い。
でも、見なきゃ。人を刺せるブーツを履くような女は、ここで写真を見ずにすごすご帰るなんてこと、絶対にしないんだから。
葛藤の末、意を決して、目の前の写真たちを見た。
──あぁ。
私やっぱり、この人の撮る写真、好きだな。
連絡を断たれている間に彼が一人で見ていたであろう世界を、時間差でも、感じられることが嬉しかった。
もっと近くで見ようと壁に近付こうとしたその時、視界の端に、偉そうに腕を組み首を傾げているおじさん二人組が映った。二人は、壁に貼り付けられた彼の写真をジロジロと見回している。
嫌な視線だった。
「ハハ、なんかなぁ、んー、自分に酔ってるっていうか」
「どこかで見たことあるような写真ばっかりに感じるし、特に伝わってくるものがないな」
おじさん達は、技術がどう、光量がどう、と彼の写真を批評している。その声に含まれた嫌な湿度と下品な笑いは、私の頭にカッと血を上らせた。そのオジサン達がどれほど偉い人だろうが、どれほど写真を撮る技術が優れていようが、そんなのはどうでもいいことだった。
え、何ですか?
どなたですか?
何様ですか?
別に見なくていいよ、てか見んなよ。
何も知らないくせに偉そうに。
私の心の声は、お門違いも甚だしかった。そう、勝手に聞いたオジサン達の会話に、彼本人でもない他人の私がキレるなんて、ほんとうにお門違い。
でも、私は怒りで今にも震え出しそうだった。
気安く彼を消費しないで。
こんな人たちに、一体、彼の何がわかるというんだろう。
もし、私に理性というものがなければ、いますぐ彼の写真を壁から剥がして根こそぎ持ち去っていたと思う。彼が切り取った世界を、誰にも汚されることなくきれいなまま、ひとつ残らず。
彼を傷つけるものすべてから守りたかった。
彼にとっての唯一の安全な場所でありたかった。
しかし、私はそんなに綺麗に狂ってはしまえない。人を刺せるブーツを履いたところで、何も言えないし、何もできない。変われない。
私は、どう足掻いても私のままだった。
そんな私には、彼が1ヶ月以上も連絡をよこさない理由が、やっぱりわからなかった。
春になり、いつのまにか、私の肩書きは学生から社会人になっていた。
就職した会社はそれなりの企業だったが、文系の私は何故か理系ひしめく技術職に配属された。いきなりプログラム言語の分厚い教材だけを与えられ、こんなことも知らないのかという目で見られ、心身ともに限界だった。加えて世間はコロナ騒動でパニックの真っ最中。もう生きているのがやっとだった。
入社して何度目かの金曜日の夜、帰宅してスーツを脱ぎ散らかし、一人何をするでもなく部屋でぼーっとしていた。土日は休みだったが、もうすでにその次の月曜日が憂鬱だった。
そのとき、急にスマホが鳴った。
画面を見た瞬間、どくんと心臓が波打った。
数ヶ月待ち続けた名前がそこにある。
考える前に、指がボタンを押していた。
そして、押した瞬間に悟った。
わかりたくないけどわかってしまった。
たぶん、これが最後の電話になる。
「ッ、もしもし」
数ヶ月ぶりにかけた電話の相手がまさか数コール程度で出るとは思わなかったのか、電話の向こうからは、一瞬息を呑むような気配を感じた。
聞きたいことは山ほどある。でも、絶対に私から話しかけてやるもんか、と思った。お前がかけてきたんだから、お前が切り出せよ。
しばらく沈黙が続いたが、数分後、彼はやっと話し始めた。
「久しぶり。まずは、ごめんね。心配かけて、本当に、本当にごめんなさい。ちょっと、話したいことがあって。」
彼は時折黙り込みながら、ゆっくり時間をかけて、たくさんのことを話してくれた。
おそらく、他人に、ましてや私にはあまり言いたくなかったであろうことを、ちゃんと、自分の口で伝えてくれた。
ある日急に、自分の心が、気持ちが、全部ダメになったこと。昔のように、自室からなかなか出られなくなってしまったこと。人と関わることが難しくなってしまったこと。
だから、もう会えないということ。
彼がポツリポツリと話している間、私は「うん」意外の相槌を発さなかった。
そうでないと、泣いてしまいそうだった。
「〇〇の友達が楽しそうに彼氏の話をしてる時、〇〇は一体、どんな気持ちでそれを聞いてるんだろうって想像すると、本当に自分が情けない。
今の俺では、普通の彼氏が彼女にするようなことを、何もしてあげられない。
〇〇は優しいから俺には一度も不満なんて言ったことなかったけど、俺のせいで嫌な思いしたこと、いっぱいあると思う。
例えば結婚したり子供が生まれたり、そういう普通の幸せに対する憧れはあるけど、多分、無理だと思う。自分は幸せになっていい人間じゃない。
でも〇〇にはそういう普通の幸せを手に入れてほしい。こんなに優しい子が幸せにならないなんて、そんなのおかしいって本気で思う。」
ああ、この人はいつもそう。勝手に先回りしてぐるぐる一人で考えて、ダメになって、潰れて、それで申し訳ないごめんねって、ほんとになんなんだよ。
私はそんなの気にしてない、大丈夫、あなたと別れる方がずっと辛いって、今まで連絡を断たれる度に何度も何度も伝えてきたのに。
でも、多分そういうことじゃないんだよな。
もう本当にダメなんだな。
終わらせなきゃいけないんだな。
いい加減、この人を、解放してあげなきゃいけないんだな。
「本当はちゃんとしたいって思ってる。こんな状態おかしいって思ってる。わかってんねん、誰に言われんくたって。俺だってちゃんと生きたい。まっとうに生きたい。
でも、無理やった」
叫び声とも泣き声とも受け取れるその言葉を聞いて、私は何も言えなかった。
「〇〇は優しすぎる。俺にはもったいないくらい、ほんとうにいい子やった。俺なんかが関わって、めちゃくちゃにしてごめんね」
ちがう。
私は優しくなんてない。私の心の中は黒い感情でいっぱいで、ぐちゃぐちゃで。あなたが褒めてくれるから、ポジティブないい子を演じてただけ。
私はやっと、「うん」以外の言葉を口にした。
「そんなことない。わたし全然ダメなんだよ。××さんが思ってるようないい子じゃない。仕事も全然ダメで、もう全部どうでもいい、逃げたい、辞めたいって思ったりもする。全然ちゃんとしてない。なんもできてない」
「そんなこと言わんで。
〇〇は、絶対に大丈夫。この先もずっと大丈夫」
『〇〇は大丈夫』、それはよく彼が私に言ってくれた言葉だった。
「……何を根拠にそう思うん?」
「今まで、一番、近くで見てきたからかな」
見てた。私だって見てた。
いつも一番近くであなたのことを見てた。
全部が全部、眩しくて、憧れで、大切だった。
考えてること、見てるもの、全部知りたかった。
だけどもう、ダメだ。
やっぱり手放したくない、まだ何とかなるんじゃないか。そんな邪な気持ちもあったけれど、でも、相手からの真っ直ぐな言葉には、真っ直ぐな気持ちで応えないといけない。
私はたっぷり時間をかけて深呼吸した。
言いたくないけど、ちゃんと言わなくちゃ。
「わかった。今までありがとう。幸せになってね」
精一杯の強がりと、最大限の本心からの言葉だった。
彼の喉がくっと鳴る音が聞こえた。
「ありがとう。〇〇もしあわ……」
聞き取れたのはそこまでだった。電話の向こうからは彼の嗚咽が聞こえた。それを聞いて、私も、泣いた。
やっと、泣けた。
「今までありがとう、〇〇のこと絶対忘れへん。これから何があっても一生忘れへん。出会えてよかった、ほんとによかった」
これは彼の言葉だけれど、この言葉がそのまま私の口から出てもおかしくなかった。私も同じ気持ちだった。
それから、お互い馬鹿みたいに泣いて、泣いて、泣き疲れて、どちらからともなく照れ笑いして。
そこからは、なんてことない話をした。
今日で最後の会話なんて嘘でしょ、と思うくらい、いつもの二人だった。
あの日の二人だった。
あまりにも夜更けまで話し込んでしまったせいか、途中、どうやら私は一瞬寝落ちしてしまったらしい。
「ごめん、私、いま一瞬落ちてたかも」
「ううん。大丈夫? 疲れてるのにごめんね」
この「ううん」の言い方が、優しい声が、わたしは大好きだった。
これも、もう聞けないんだな、
もう、本当に最後なんだな。
そう考えると、完全に引っ込んでいた涙がまたぶり返してきた。彼は、私が泣き終わるまで、何も言わず待っていてくれた。
無言がこんなにあたたかい人と、この先また出会えるのだろうか。出会えないだろうなあ。こんなにも好きになれた人は、彼がはじめてだった。自分のことがどうでも良くなるくらい、この世界で一番大切だった。
もう、今日が最後なのだとしたら。
今日のことを、ずっと抱きしめて生きていこう。
もらった言葉も、気持ちも含めて、
この時間をずっとずっと忘れないでいよう。
彼がいない世界でも生きていけるように。
そして、いつの間にか、私は本当に眠りに落ちていた。
目が覚めると、外は既に明るかった。
手元の電話はまだ繋がっている。ぼーっとする頭のまま、音量を最大にして耳に当ててみた。だけど、電話の向こうからは何も聞こえなかった。
彼も寝ていたのかどうかは、わからない。
私は、何も聞こえない電話を耳に当て続けながら、今までの思い出を反芻した。
初めて出会った日、彼の横顔に一目惚れしたこと。付き合う前のデートの帰り道、話し足りずに同じ道を何周もしたこと。「俺、こんな風に誰かに祝ってもらったの初めて」とひとしきり感動していた誕生日。コンビニでいつも手に取る紫色のジュース。リボン結びが縦になっていたコンバース。「〇〇と一緒にいると安心する」と言う惚けた笑顔。
目を閉じて、全部をぎゅっと抱きしめた。
ずっと忘れない。全部抱えて生きていく。
「バイバイ、今までありがとう。もう切るね」
それだけ呟いて、自分の手で、自分の意志で、通話を終了させた。通話時間、8時間と2分。
私は、枕元の引き出しの奥から赤い煙草の箱を取り出した。
彼の鞄にいつも入っていた赤い箱。
彼が置いていった赤い箱。
いつか、彼がこの煙草はルパンに出てくる次元と同じ銘柄なんだって言ってた。あの時、私は彼になんて相槌を打ったんだっけ。
私に煙草を吸う習慣はない。むしろちょっと嫌悪してたくらい。でも、今日は、いい。ベタなことでもやっちゃおう。
昨日から今日にかけての電話を、
この一世一代の恋愛を、
彼のことを、
彼のことを好きだった自分を、
一生忘れないように。
ベランダの柵にもたれかかりながら、煙草に火をつける。何回か横で見てたから、吸い方だけは一丁前に知っている。ちょっとむせたけど。
耳にはイヤホン。だけど、今、スマホから流れるのは、もう彼の声ではない。
チャットモンチーの「染まるよ」を聴きながら、こんなベタなことができるんだから、私、思ったより大丈夫かもな。そんなことを思いながら、ベランダから広い道路を見下ろす。
うーん、今ここから飛び降りて死ぬのもいいな。
前触れもなく、脈絡もなく、唐突に、そんな思考がふっと浮かんだ。
でも、私は死ねないし、死なない。
どうせ明日からも、普通の顔して生きていく。
『いつだって そばにいたかった
わかりたかった 満たしたかった』
こんな風に、どうしようもない時にそっと寄り添ってくれる歌がある。
私たちはそれで生きていると思った。
『あなたのくれた言葉 正しくて色褪せない
でも もう いら ない』
『いつだって あなただけだった
嫌わないでよ 忘れないでよ』
すごいな。いやもう笑っちゃうよ。
こんなのさ、私の歌じゃん。
一体、世の中の何人が、この曲を聞いて同じことを思ったんだろう。
ひとしきり感傷に浸っていると、次の曲が流れ始めた。せっかくなので歌詞に注力して聴いてみようと耳を傾けていると、思わず、まじかよ、と呟きが漏れた。
『君に会わなくたってどっかで息しているなら
それでいいななんて思って煙を吐いている』
はぁ、私のシャッフル機能、誰か操ってますか?
人生って、たまにこういうことあるよなぁ。
タイトルを見る。yonigeの「リボルバー」。
あとで一軍のプレイリストに入れよう。
そう決めて、空に向かってふぅと息を吐いた。
ねぇ、どっかで息しててよ。
生きててよ。
それだけでいいから。
私の口元からゆらゆら昇っていく紫煙は、ゆっくりゆっくり空へ近づいて、やがて、少しずつ消えていった。
あなたを知らない人生なら、私はいらなかった。
私のこと見つけてくれて、ありがとう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
