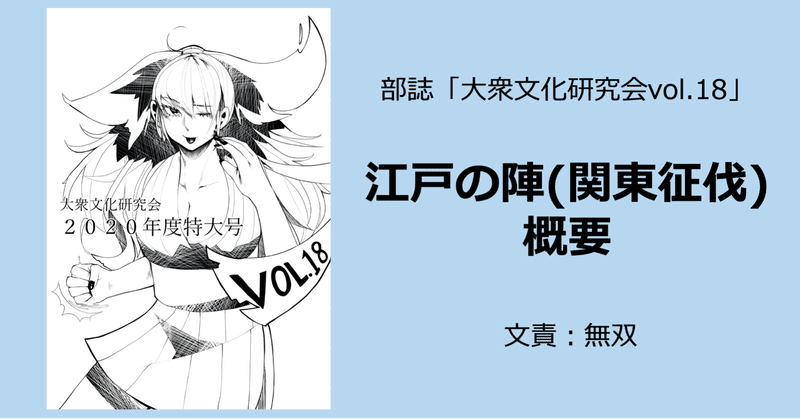
江戸の陣(関東征伐) 概要
注意:関ヶ原の戦い、西軍勝利後の架空合戦を自分で勝手に考えて書きました。全て史実とは異なります。
関ヶ原の戦いは、正午過ぎに小早川秀秋の軍勢が東軍に襲い掛かったことで、大打撃を受けた東軍は敗走し、西軍の勝利に終わった。この頃、九州では黒田如水、加藤清正らが島津領以北をほぼ制圧。西軍首脳は九州統一を優先目標とし、小西行長を先鋒に毛利軍を主力とする軍勢を九州に派遣し、苦戦の末、勝利を収める(慶長九州征伐)。一方、徳川家康は関東で態勢を整え、再度決戦に臨まんとしていた。1602年春の、富士の戦いから徳川秀忠降伏までを江戸春の陣(第一次関東征伐)、1607年秋の、徳川家滅亡の一連の戦いを江戸秋の陣(第二次関東征伐)と呼ぶ。
「江戸春の陣(第一次関東征伐)」 1602年
富士の戦い
関ヶ原の戦い以降、東軍から西軍に転じる武将は多く、九州が完全に西軍の手に渡ってしまったことは家康にとって大きな誤算であった。徳川軍は得意の野戦に持ち込んだものの、関ヶ原以降に家康の味方となった豊臣恩顧大名たちの士気は低く、戦闘開始以降、東軍で実際に戦っているのはおよそ半数にすぎなかった。正午過ぎ、東北戦線で伊達勢寝返りの報が東軍に届く。徐々に東軍の戦線が崩れ始めたことを機に、藤堂高虎、山内一豊、田中吉政らが西軍へ寝返り。東軍は総崩れとなる。家康は真田勢による猛追を受け、真田幸村によって討ち取られた。
箱根峠の戦い
西軍は東軍を追撃しつつ、関東の入り口である箱根へと迫る。先鋒は小早川秀秋らが務めていたが、功にはやり、強引に力攻めを行おうとしたことで、逆に井伊直政、松平忠吉率いる徳川軍奇襲部隊により反撃を受けてしまい敗走した。
小田原城攻防戦
徳川軍の予想外の反撃で、不意を突かれたものの、箱根峠を越えた西軍は東軍の重要拠点である小田原城を包囲する。城主、大久保忠隣は鉄壁の守りで攻撃を跳ね返し続けるも、富士の戦いで家康が討ち取られてしまったことで兵士の士気の低下は激しかった。一方で、上杉、佐竹、伊達の連合軍は北関東に侵攻し、多くの城を制圧。その大軍が江戸城に迫ったことで、ついに徳川秀忠は西軍に降伏。10日後に小田原城も降伏開城した。
春の陣の後、徳川家は大減封の末、かろうじて存続を許される。数年後、石田三成らの西軍首脳は禍根を完全に断つために、徳川征伐の大号令を全国に発する。この戦いでは豊臣秀頼も西軍総大将として出陣した。領地を大幅に減らされていた徳川家は浪人衆を雇い入れ、戦力の増強を図る。この結果、豊臣家によって取り潰しにあった多くの大名やその家臣たちが江戸に参集した。浪人衆の中で特に活躍した五人を後世、江戸五人衆と呼んだ。江戸五人衆とは、真田昌幸長男であるが東軍に属し、春の陣の後に流罪となっていた真田信之、家康の娘婿で元三河吉田城主の池田輝政、元黒田家家臣の後藤又兵衛、賤ヶ岳の戦いで活躍した佐久間盛政の弟である、佐久間安政、春の陣の後に取り潰しとなった最上家の元当主である最上義光の嫡男、最上義康、の五人のことを言う。徳川家譜代家臣と浪人衆の間の意見の対立が秋の陣での徳川軍敗北の一因とも言われている。
「江戸秋の陣(第二次関東征伐)」 1607年
鎌倉遭遇戦
浪人衆や一部の譜代家臣が積極的な出撃策を主張した結果、本多正純らとの対立が深まり、徳川軍は全兵力を効果的に使うことができないまま、戦いを始めることとなってしまう。江戸城から出撃した徳川軍であったが、濃霧の影響で足並みが揃わなかったことで、徳川軍先鋒の佐久間安政らは鎌倉で豊臣軍の大部隊と遭遇、激戦となる。豊臣軍主力は宇喜多秀家、毛利秀元ら。安政は孤立無援の状況ながら、奮戦し、後続部隊の榊原康政らと合流。反撃に転じ、豊臣軍の進軍を大幅に遅らせることに成功する。
白金・高輪の戦い
局所的な抵抗はあるものの、豊臣軍は徐々に包囲網を狭めていく。徳川軍は残存兵力を結集させ、乾坤一擲の戦いを挑むが、圧倒的兵力差を生かした豊臣軍の波状攻撃の前に、井伊直政、榊原康政、酒井家次ら徳川軍の主力武将は次々と討死していった。その中で結城秀康は毛利軍主力を終始圧倒し、後退させ、毛利勢救援におもむいた吉川、長宗我部勢が加わってもなお秀康は優勢を保った。さらに後藤又兵衛が毛利輝元勢の側面を急襲したことで、毛利勢壊滅まであと一歩に迫るが、宇喜多、島津勢が救援に駆け付けたことで、押し返され、秀康も討死にした。この日の戦闘で大損害を受けた豊臣軍の毛利勢、宇喜多勢ら中国地方の大名たちは軒並み翌日の最終決戦に参戦できず、後備えとなった。
赤坂・四谷最終決戦(江戸城外最終決戦)
江戸城南東に大規模な野戦築城を施した徳川軍は、最後の戦いに挑む。徳川軍の勝利する唯一の方法は豊臣軍総大将の秀頼を討ち取ることであった。真田信之は後に真田丸と呼ばれる砦を建造し、押し寄せる豊臣軍に対して大打撃を与える。さらに、池田輝政の猛攻により、前田利政勢が大混乱に陥ったことを機に、真田信之は配下の忍びに伊達勢が徳川軍に再度寝返ったとの虚報を喧伝させ、本多忠勝とともに豊臣本陣へ突撃する。豊臣本陣近くに布陣していた立花勢がこれを防ごうとしたときに起こった、立花宗茂と本多忠勝の一騎打ち(東西無双一騎打ち)は有名。信之は秀頼配下の七手組に討ち取られるものの、その活躍は「真田日の本一の兵」と後世に語り継がれている。信之が討死した後も徳川軍の攻勢は凄まじかったが、兵力差はいかんともしがたく、時間が経つほど追い詰められていった。その後、池田輝政は敗残兵をまとめつつ、江戸城内へ撤退。翌日に江戸城は大炎上し、徳川家は滅亡した。
<文責:無双>
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
