
純正音程にリーチ!53平均律!【005】
こんにちは、こんばんわ、ユートピア!
変拍子兄さんです!
前回触れた平均律比較の話ですが、
かなりの精度で純正音程を拾える音律があります
それは「53平均律」
数が多すぎてなんのこっちゃ???というレベルにはなりますが
今日のテーマは53平均律ということで踏み込んでいきましょう!
・3度と5度の精密さ
前回の復習です、純正音程の完全5度、長3度、長2度のセント値はいくらでしょうか?
今回は厳密に1200*log2_(3/2)という風に対数を使ってガチで求めていきます
3/2 完全5度=701.955000865
9/8 長2度=203.910001731
5/4 長3度=386.313713865
という風になります、
一方、53平均律上の この3つに対応する音程は…?
31step:完全5度=701.8867925
9step:長2度=203.7735849
17step:長3度=384.9056604
と、かなり近い値を出しています
また53平均律、各音程は次のとおり
見やすいように、整数で表示しております

・53平均律の各音を理解しよう!
さて、53音もあると各音を把握するのも大変そうですが
まずはシンプルに幹音(ナチュラル)の7音とその間の音数を把握しましょう
こうなります。

となると、結構話はシンプルですね
全音は間に8音あるわけですから、全音=9ステップ
半音は間に3音あるので半音=4ステップということになります
なんと半音+半音=全音ではなくなるんですね
これは面白いことになってきた!
・コンマ
1ステップがこれほどに細かいと今までのように
1ステップ=半音 1ステップ=半々音 ということはできなくなります
1ステップ=22.64150943セントとなりますから
もう一段階細かいのです。
そこで導入される音程ステップの概念「コンマ」です
コンマとはもともと、シントニックコンマやピタゴラスコンマといった
純正音程を2通りの方法で積み上げた結果、同じ音程のはずだが微妙なズレがある!
というズレをさすときに使われる微小単位のことです
53平均律の1ステップは幅が狭すぎるため、コンマとしての役割を果たします。
コンマを生かした話といえば、
異名同音よりも細かい話で「同名異音」という現象をご存知でしょうか??
たとえば、
53平均律のミ(408セント)と純正音程のミ(386セント)
同じ「ミ」ですが 微妙に異なります
通常の平均律ではこの差を、どっちも同じジャン!ってことで
シカトしてしまいます。(これをテンパーアウトと呼びます)
しかし53平均律はすぐれもの、ちょうど1コンマ低いピッチ(385セント)で純正音程のミをとることができます。
5倍音系統の純正音程をとるには1コンマ下げるという手法が使えるようになるのです。
これが、53平均律の最大の特徴 !!
平均律と純正律は基本相性が悪いですが、1コンマ下げるという手法で53平均律は解決してしまうという
・調号を決めよう
53平均律の最小ステップの名前がコンマと決まれば
そのほかの調号も決めていきましょう
まずは実際のWikiを参照したところ
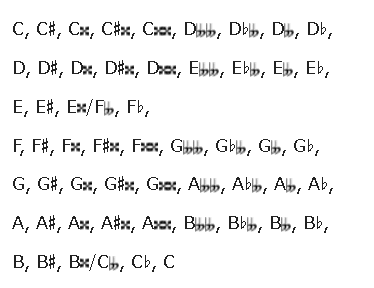
このようになってます
1コンマ=# としたわけですね、こうなるとクアトロシャープまで出現してしまい、煩雑ですね
#=5コンマとして Dの次にCが出現するような記法もありますが
Dより高い位置にCが出てくるのは困るということで
僕の記法案です

・基本2コンマ刻み
ジャンプ→シャープ→ジャンプシャープ→ダブルシャープ
ドロップ→フラット→ドロップフラット→ダブルフラット
・#系と♭系ですれ違いがおきて、間が埋まる
・1コンマ上げ下げする際は「’」「.」
・キ’ OverJumpのように組み合わせても一応OK
・ジャンプシャープは「⩨」書いてますが、理想はこれの横向き(縦3本横2本)
この調号システムのもとに作った53平均律キーボードがこちら↓

(↑ここのリンクね!)
六角形で順番がよくわからないこともあるので
やはりこういうのが見やすい

・その他いろいろ決めてみた!
一応ですが、音名も考えました
音名は各自自由に考えて下さいといった感じなので参考までに

「サリグマパディヌサ」というインド式の呼び方にしました。
・半音あがるごとに母音がY→O→A→I→U→Eと変化します
・半々音は二重母音としています(僕独自ルール)
・E'とB'の位置ではすれ違いが起こらないので、別の子音Ch、Jを導入しています。
・12音階の事情も含めてドレミファソラシド=サリグマパディヌサ となっているそう
参考:https://www.mahaananda.jp/sangiit/index.html
サリグマパディヌサの正当なルールだと
本来4分音用の子音があるが、法則性がわかりづらくなるので使わなかった(代わりに二重母音)
次に、インターバル名(クオリティ名)

これもすれ違いシステムを活用して作ったが補足を少々
・半々音ごとにi(インフラ)→m(マイナー)→N(ニュートラル)→M(メジャー)→U(ウルトラ)
・完全音程系統はD→m→P→M→A
・「.」→1コンマ低い:アンダーのクオリティ接頭辞は「サブ」
つまりM.1はサブメジャー1
・「’」→1コンマ高い:オーバーのクオリティ接頭辞は「スーパー」
M'3はスーパーメジャー3rd
・次に「y」これはイエローと呼ぶ
M3を1コンマ下げることで5倍音系の純正音程になることから
「カラーノーテーション」からの流用
ここまでやっといてなんだが、使わないだろうな…って感想
だがね!53平均律について、迷ってる方はぜひ参考にして
自分の納得のいくノーテーションを開発してほしい
(一応。パッと調べたノーテーションよりは明快なノーテーションのつもり)
コンマの考察もしてたんだけど、今日はこの辺にしておきましょう!
最後にSevishアニキの53平均律を張っておきます
________________________________
