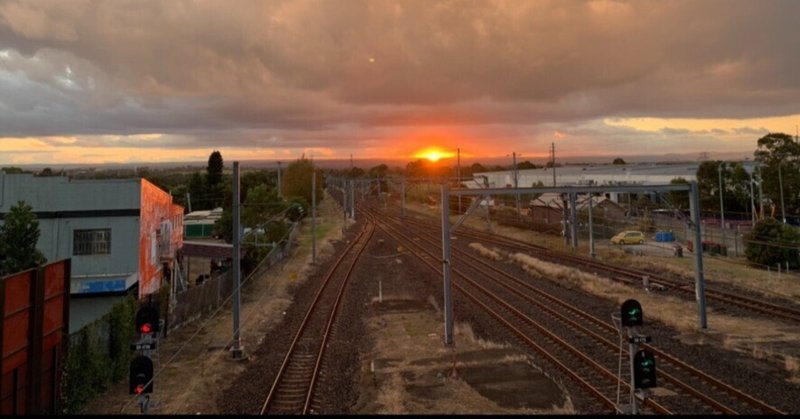
ナチュロパシーのOSCEを終えて
シドニーでの学生生活についてブログなどを書こう書こうと思ってはいてもあまり乗り気のしないままになっていました。が、今日卒業試験を終えたので自分への記録として書いていこうと思います。ふと、今のこの初心を忘れたくないなーって思ったのです。
そしていつかオーストラリアでNaturopathyを専攻したい!と思っている方に少しでも最終試験のアイディアが伝わればなと思っています。
OSCEとはObjective structured clinical examinationの略で、日本でも医学部や歯学部、薬学部の生徒が臨床実習に入る前にやるとかやらないとか。その辺は私はよくわかりませんが。
私たち自然療法士ことナチュロパスはお医者さんみたく人の命を預かるお仕事ではないので、医学部などで行われるような難しい試験はありませんが、患者さんを目の前にしたときに、処方で害を与えてはいけない、そしてもし何か病気などのサインが隠れていた場合に病院に送れるようにみっちりしっかり解剖生理学から病理学まで勉強します。一応。
で、この試験はsafety issueを第一にexamineされるので、高度な能力とか処方は特に加点されず、合否のみで判断される、いわゆるhurdleと言われる類の試験です。
では早速試験の構成について書いていきまーす!
初めに症例が書いてあるノートを渡されます。患者の飲んでいる常備薬のinformation sheetも一緒に。ハーブや栄養素とのinteractionも書かれています。
で、Stationと言われるセクションが6つあり、それぞれのセクションでsupervisorに口頭で答えていきます。
Stationは
1から順に
1: Biomedical and naturopathic/holistic examination
2: Naturopathic/holistic/Biomedical Differentials
3: Communicating naturopathic/holistic understanding
4: Communicating the prescription
5: Safety issues
6:Ethics
に分けられています。生徒によって割り当ては異なり、私は3から順に始まり、2で終わりました。
初めにケースを読む時間を20分与えられ、その後それぞれのstationに与えられる時間は10分、ステーションの間は5分の時間が与えられるので、そこで次のトピックの準備をします。最後のreflectionの時間も合わせて合計2時間。
1のexaminationは、biomedicalとholistic examinationsそれぞれ2つほど行います。なぜこの症例にこのexaminationを行うのか、を口頭で試験官に説明し、その後モデルの生徒にexaminationをします。(ボランティアしてくれた子、ありがとー!)
私はbiomedicalは血圧と脈拍
holisticは爪と結膜を見ました。
holistic examinationは信憑性に欠けるとも言われることが多いですが、私は結構自分の診断のback upに利用していて、亜鉛欠乏、胃酸が少ない、鉄不足、リンパが滞っている、マグネシウム不足、食物不耐性等々が見れます。あとはstation 3でやる、いわゆるholistic understandingという特殊な考え方が出来るので、そこである程度の予想を立てて
あ、この人亜鉛足りてなさそうだな、
と思ってholistic examinationをすると、
あ、やっぱり
ってことが多いかな。
これはケースをとって初めて使えるものかなって思うので、素人がやってもそりゃ信憑性に欠けるわな、っていうのが4年間勉強した人の感想です。←え
そして私たちも処方を決めるツールとしてしか使っていないので、これは診断ではありません。
Station 2は differential diagnosis!
個人的に病理学は過去の科目で死に物狂いで勉強したので、我ながら上手くできたと思っています。
working diagnosisと、possible differentialを挙げてなぜそれを選んだのか、どう違うのか、等々の質問をされて口頭で答えていきます。
私はworking diagnosisがリウマチでdifferentiaが変形性膝関節症でした。ややこしーやつきたああああああ。
(もっと単純な高血圧とか消化不良とかにしてほしかったよ。)
リウマチが自己免疫疾患であるのに対して変形性膝関節症は加齢などにより関節に負荷がかかり炎症を起こす症状。患者はまだ若く、産後三ヶ月ということもあり、ホルモンバランスの変化や出産時の負荷から免疫に影響を受けている可能性が高く、postpartum arthritisを発症している可能性が高い、診断にはautoimmune antibodiesの有無の検査、痛みが身体の左右対称で感じるか、それともランダムに関節に感じるか、によってどちらかの可能性を導き出せる。でもその辺はお医者さんに見てもらうように話しまーす、ってことを口頭で試験管に説明してって感じで終了。
そうです、私たちは診断はできないけど、病気について理解できなければならないので、症状などをみて患者さんに説明をして最後は、じゃあお医者さんと話ししてね!ってなります。
よくnaturopathyを勉強しているというと、
あ、あの癌でも治療しない人たち?
とか
医者否定してホメオパシー処方する人たち?
って言われることが多かったけどそんなことないですよー。
オーストラリアのqualified naturopathはいわゆるComplementary medicine、補完療法であってalternative、代替え療法ではないです。
この辺りはまた違う記事をおいおい書いていけたらなと思います。
Station 3はこの1年間の実習で私が一番苦労した部分、holistic understanding
実習内ではsupervisorの先生にこまかーーーーーーくbiomolecule単位のお話などをするのですが、この試験では患者に説明をすることを程にしているので、本当にざっくり。
私の与えられた症例は産後からある関節痛と痛みによる不眠症とそれに伴う日中の疲労感。寝られないとそりゃあ疲れも取れないよねー、でもまだ産後数ヶ月だし、疲労感は鉄欠乏性の貧血からくるものかもしれないよね、的なことを繋げてざっくり話していきます。
今でこそ結構すらすらーって話せるけど、一年前は全然できなくて!だいぶ叩きのめされてました。
なんでできないかって、きっと英語も操れていない、そして病理学をこまかーーーーーーーい規模で理解していないことに気がついて、コツコツ取り組んできました。クラスメイトに表現の仕方を教えてもらったり、ひたすら教科書を読み込んで。
この前も、脂肪肝について復習してた時に、あれ、インスリン抵抗性ってなんで脂肪肝になるんだ?あれ、なんで血圧高めなのがリスクなんだ?お?PCOSあるぞ?あれ、全部繋がるぞ、って。
前までは、あー、糖尿気味で肥満だからPCOSね、って勝手に繋いでいたけど、今はなぜそうなるのか、までしっかり落とし込んで勉強することの大切さを学びました。(←今更)
症状だけにとらわれずに全体像で見ることをholistic pictureって言うのですが、その絵が見えた時の感動は何にも変え難いです。はい。
もしこれを読んでいるOSCEをこれからやる!と言う方が見えたら、しっかり、勉強してください!←ざっくり
その行動の積み重ねがきっとあなたに自信を与えてくれますよ!♡
今日はなんといってもね、試験内容同行っていうよりも、今までお世話になった先生方が試験官としていて、顔見ただけで泣きそうになり、そしてこれらのタスクをブワーーーーーって英語で説明できてる自分に感動しました。自画自賛。過去4年間の自分、本当に頑張ってくれてありがとうって思いました。努力は裏切らないっていうのを信じてよかったね。
いやー、日本語でこんなに長い文章を打ったのはいつぶりだろうか。誤字脱字、お許しくださいませ。
長くなりそうなので後半に続きまーす。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
