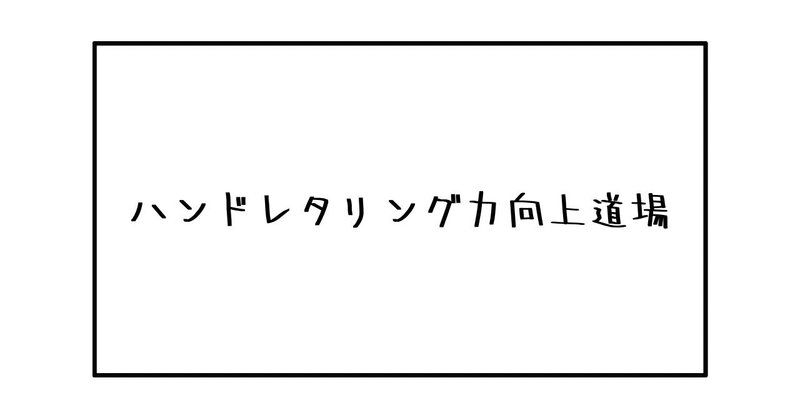
ハンドレタリング力向上道場
◆やること
・参考文献の読み込み
◆やったこと
有馬:それを聞いて思い出したのが、アニメの予告編のムービーの仕事をしていたときに、公開した5分後くらいに「dumb quote(垂直のダブルクォートのこと。通常は使用しない)入っていますよ」ってDMが来たんですよね。
●『dumb quote』は、通常は使用しない
「dumb quote(垂直のダブルクォートのこと。通常は使用しない)入っていますよ」
さらに参考文献
●『dump quotes』は、「まぬけ引用符」。英語の原稿では、正しい引用符に直す
英語の原稿をもらってレイアウトするときは、垂直になっている引用符「”」「’」が紛れていたら、必ず正しい引用符に直しましょう。
A4などといった白銀比
●コピー用紙のA4は、白銀比である
さらに参考文献
白銀比
縦:横=1:1.414・・・(√2)
どこまで半分にしていっても、同じ形、相似形の長方形であること。紙の規格寸法など。
●白銀比は、1:√2のこと
タイポグラフィ、すなわち活字版印刷術は、金属活字(鋳造活字、メタル・タイプ)であれ、写植活字(写真植字用活字、フォト・タイプ)であれ、また電子活字(デジタル・タイプ、フォント)であっても、活字版印刷術創始以来550年以上にわたって「活字」を用いて言語を組み、配置・印刷し、テキストを描写・再現させる技芸であり続けている。
●タイポグラフィは、活字版印刷技術である
タイポグラフィ、すなわち活字版印刷術は、
●活字版印刷技術は、金属活字・写植活字・電子活字に分けられる
金属活字(鋳造活字、メタル・タイプ)であれ、写植活字(写真植字用活字、フォト・タイプ)であれ、また電子活字(デジタル・タイプ、フォント)
いずれにせよ「活字」は、文字の複製原形、つまり規格化された文字の「型(タイプ)」をもとに、繰り返し同じ形象で再生されることを前提とする公的文字のことを指す。
●活字は、公的文字のこと。繰り返し同じ形象で再生されることを前提とする
「活字」は、文字の複製原形、つまり規格化された文字の「型(タイプ)」をもとに、繰り返し同じ形象で再生されることを前提とする公的文字
それまで1段組、2段組、3段組など縦の段組だけを考慮し分割されていたブック・フォーマットを、縦横共に細分割し、写真や図版(視覚情報)とテキスト(言語情報)のレイアウトを支援するために生まれたのが、「グリッド・システム」と呼ばれる格子状のガイドラインである。
●『グリッド・システム』は、格子状のガイドラインのこと
グリッド・システムは、ナチの迫害を逃れ中立国スイスに身を寄せていた周辺諸国のグラフィック・デザイナーが、第二次世界大戦後に確立したシステムである。彼らはグリッド・システムを用いて視覚情報と言語情報を統合させ、さらに技術と美学を同時に結び付け、分析的かつ機能的で秩序だったデザインを展開していった。
●『グリッド・システム』は、視覚情報と言語情報を統合した
彼らはグリッド・システムを用いて視覚情報と言語情報を統合させ、さらに技術と美学を同時に結び付け、分析的かつ機能的で秩序だったデザインを展開
またその利点を以下のように示した。
「視覚伝達において論拠を客観的に組み立てることができる」「本文や図版を規則正しく論理的に組み立てることができる」「本文と図版とが調和を保ちながら、簡素に編集・構成することができる」「わかりやすく、高度な均衡性を組織化するための視覚要素を組み立てることができる」。
●グリッド・システムの利点は、たくさんある
「視覚伝達において論拠を客観的に組み立てることができる」「本文や図版を規則正しく論理的に組み立てることができる」「本文と図版とが調和を保ちながら、簡素に編集・構成することができる」「わかりやすく、高度な均衡性を組織化するための視覚要素を組み立てることができる」
スイス・タイポグラフィとは1950年代から60年代にかけて発展した左右非対称のレイアウト、グリッド構造、サンセリフ体、左揃え・行末なりゆきの文字組を特徴とするタイポグラフィのスタイル。
●タイポグラフィの世界には、『スイス・タイポグラフィ』という分野がある
スイス・タイポグラフィとは1950年代から60年代にかけて発展した左右非対称のレイアウト、グリッド構造、サンセリフ体、左揃え・行末なりゆきの文字組を特徴
◆次にやること
・参考文献を読む
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
