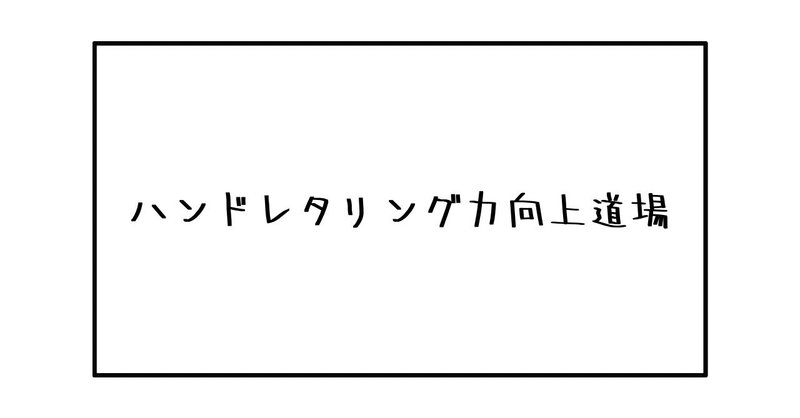
ハンドレタリング力向上道場
◆やること
・参考文献を読む
◆やったこと
私は言葉や文字のような記号を用いたもの、そしてその延長にあるものはすべてタイポグラフィの範疇として捉えている
●タイポグラフィは、言葉や文字のような記号を用いたもの
言葉や文字のような記号を用いたもの、そしてその延長にあるものはすべてタイポグラフィ
私の知る限り、この言葉の解釈に関しては、河野三男氏の『タイポグラフィの領域』に最も良くまとめられている。
●タイポグラフィの研究を行った人物は、河野三男。著書は、『タイポグラフィの領域』
この言葉の解釈に関しては、河野三男氏の『タイポグラフィの領域』に最も良くまとめられている
マーシャル・マクルーハンが言うように、電気回路技術は私たちを変えた。私たちは電子メディアを扱うとき、物質的な側面以上に、観念的な側面を強調するようになった。type は金属活字である以前に、型・形式・様式といったような意味合いを持っており、type がもつ観念は活字であることを越えて、あるいは遡って、ただの「型」となった。対して graphy は今でもよく使われるように、描く方法・形式・画法・書式・写法・記録法というような意味合いをもつ。
●『typography』は、『typo』が型・形式・様式、『graphy』が描く方法・形式・画法・書式・写法・記録法を意味する
type は金属活字である以前に、型・形式・様式といったような意味合いを持っており、type がもつ観念は活字であることを越えて、あるいは遡って、ただの「型」となった。対して graphy は今でもよく使われるように、描く方法・形式・画法・書式・写法・記録法というような意味合い
テクストの書き手もまたタイポグラファ(言葉の組み手)と認識される。
●テクストの書き手をタイポグラファと呼ぶ
テクストの書き手もまたタイポグラファ(言葉の組み手)
現代におけるタイポグラフィとは「型による形成法」と書き換えることができる。ここで「形成」するものは、フェルディナン・ド・ソシュールの言うところのシニフィエ(意味されるもの)であり、「型」というのはシニフィアン(意味するもの)である。シニフィエはイメージや概念、シニフィアンは文字や音声すべてを含んでいる。これらが表裏一体となったシーニュ(記号)の考え方の実践形こそが、来るべきタイポグラフィの姿
●シーニュ(記号)がタイポグラフィ
フェルディナン・ド・ソシュールの言うところのシニフィエ(意味されるもの)であり、「型」というのはシニフィアン(意味するもの)である。シニフィエはイメージや概念、シニフィアンは文字や音声すべてを含んでいる。これらが表裏一体となったシーニュ(記号)の考え方の実践形こそが、来るべきタイポグラフィ
私が生まれたとき、既にそこに字はあり、紙もあり、広告も、建築物も、映画も、音楽も、コンピュータもあった。今日、身の回りにある記号をすべて、自分自身で一から作ることは到底できないが、それらについて読むことは出来る。出来るというよりも、読まずにはいられなくなってしまっている。
もはや、私たちは読み手であるのか書き手であるのかすら曖昧な、記号に溢れた世界を生きている。
●生まれたときから記号に囲まれて生活している
今日、身の回りにある記号をすべて、自分自身で一から作ることは到底できない
記号に溢れた世界を生きている
アンパサンド: ampersand &
●ラテン語の et の合字からできた and の省略記号
●フランスでは & は「エット・コメルシアル」
● @ は「ア・コメルシアル」
アポストロフィ: Apostrophe
●パンクチュエーションマークの一種
●名詞の所有格を示すとき
●数字や文字が複数であることを示すとき
●省略・所有格・複数であることを示す符号do not rArr; don’t
1998 rArr; ’98
nine of the clock rArr; nine o’clock
●「 ′″」は基本的には「分と秒」を表し
●欧文モードで、
‘ = option + [
’ = option + shift + [
を使ってシングルとダブルの正しいものにおきかえ
ウイドウ: widow
●欧文組版においてパラグラフの最後の行が、一単語あるいは一音節だけのとても短い行になった状態
●日本語組版でしたら
わたしは山田太郎で〈改行〉
す。
ウムラウト: umlaut

(引用元:ウムラウト: umlaut)
●音 laut が変化 um することを示す変母音記号
活字書体の判断における三原則
レジビリティ、リーダビリティ、インデユーシビリティ:
legibility, readability and inducibility
《判別性 Legibility 》
◆次にやること
・参考文献の読み込み
活字書体の判断における三原則
レジビリティ、リーダビリティ、インデユーシビリティ:
legibility, readability and inducibility
《判別性 Legibility 》
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
