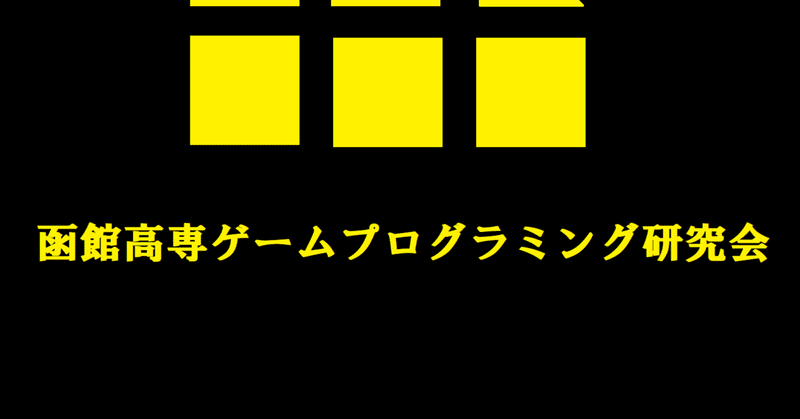
ゲームプログラマーを目指して、松〇健と共にドラゴンを倒すゲームを作った話
始まり
宮原良太です。4年前からゲームプログラミングを始めて様々なゲームを作ってきました。
ゲームプログラマーになろうと思ったきっかけ
自分がゲーム制作をしてみたいと思い始めたきっかけは、中2の頃に見た「ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-」というアニメ映画でした。当時から高専に入りたいという気持ちがあったのですが、どんなことをやりたいかは考えていませんでした。そんな中、この映画を見て、劇中内に出てくる「オーディナル・スケール」というゲームの様なものを作ってみたいと思い始めました。その後は高専に入学してすぐにゲームプログラミングの研究会に入部し、いくつかのゲームを作ってきました。
初めて作ったゲーム
研究会入部後すぐに、新入生全員で、顧問の先生の指導の下ブロック崩しを作りました。当初はプログラミング未経験だったこともあり、私は先生の指導についていくので精いっぱいで、わからないところは指導の後に個人で聞きに行ったり、ネットで調べて解決したりしました。しかし、それ以上に自分のやりたかったことがやっとできたという喜びと、自分の手で作品を作っていく充実感でとても楽しかったです。
ゲームの部分を作り終えた後は、タイトル画面を作成したり、画面遷移ごとにBGMを変更する処理を実装したりと自分なりに工夫をしてみました。
初めての展示
入学して半年後、ついに自分の作ったゲームが学校祭にて展示されることになりました。その時、嬉しくて涙を流したことは今でも覚えています。
そして迎えた学校祭当日、私のゲームは多くの人にプレイしてもらいました。プレイして頂いた人達からは、「1年で作れるなんてすごいね!」「ちゃんとゲームとして成り立っていてすごいね!」といったプラスの意見や、「操作が少し難しい」「背景とゲーム画面が同化してて見づらい」といったマイナスの意見を多く頂きました。
私は、自分の作品を褒めてもらって嬉しい反面、もっと改善できるところがあったなという気持ちになりました。今でもこの経験は、ゲーム作りの時の精神的支柱になっています。
コロナ
学校祭から数か月後、新型コロナウイルスが世界中で流行し、2年生が始まるころにはオンライン上での授業をせざるを得ない状況に陥りました。自粛期間中はとても暇で、1年の頃にあったモチベーションも消えかけていました。しかし、このままではだめだと思った私は、何か行動を起こそうと試みました。そう、ゲーム制作です。
早速私はグ〇ディウスもどきのシューティングゲームの制作を始めました。以前作ったブロック崩しとは全然違い、作業量がとてつもなく多く、特に敵キャラの弾の発射軌道の調整にはどれほどの時間を費やしたか覚えていません。ある程度ゲームが完成したところで顧問の先生に見せたところ、「これコンテストに出してみないか?」と提案されました。正直自分にはまだコンテストに出せるほどの腕前があるとは思いませんでした。しかし、私はコンテストに出場することを決めました。今の自分がどこまで通用するか、自分の作ったゲームがどこまでいけるかが知りたかったのです。
初めてのコンテスト
そこからは更に過酷を極めました。敵キャラの攻撃パターンを増やしたり、キャラ動いたときに少しアニメーションを加えたりなど、たくさんの壁がありました。対面授業が始まってからは夜まで学校に泊まり作業をすることもありました。
そして、12月上旬、選考結果が来ました。結果は本選出場決定!このメールが来た瞬間、嬉しさのあまり教室で叫んでしまいました。そこからは急いで発表用のスライドを作ったり、質疑応答の練習を顧問としたりして対策を取りました。
12月13日、遂にコンテストは始まりました。本選出場の作品は、マルチエンド形式のゲームやオープンワールドのゲーム等、クオリティが高いものばかりで、自分はどこまでいけるのだろうかと不安になりました。そして回ってきた自分の番。親や顧問の先生が見守る中で、緊張で口の中が乾きながらもなんとか質疑応答まで終わらせることが出来ました。
そしてどんどん発表が続いていき、表彰式の時間がやってきました。次々と入賞者の名前が呼ばれる中、自分の名前は呼ばれませんでした。正直、このクオリティのゲームなら入賞はないだろうとは思っていましたが、どこかで期待してた部分もありました。コンテストの後はファミレスで打ち上げをしたのですが、悔しさのあまりその時食べた料理をちゃんと味わうことが出来ませんでした。悶々とした気持ちの中、私は次は絶対入賞すると心に決めました。
リベンジ
コンテストから2か月後、早速私は新たなゲームを作り始めました。
今回作ったゲームは、制限時間内にミッションをクリアして目的地に到着するというものでした。前回の反省点から生かし、今回はちゃんとストーリーを取り入れ、クオリティの向上を狙いました。また、今回のコンテストは、年齢的に出れる最後の大会なのでより一層気合が入っていました。
しかし、開発開始から3か月後、思いもよらぬ問題が発生してしまいました。クオリティを求めすぎた余り、締め切りまでギリギリになってしまったのです。どうにかするにはクオリティを捨てて他のステージの開発に移るか、他のステージは諦めて1つのステージの開発に集中するしかありませんでした。どうするか悩んだ結果、私は後者を選びました。そして、締め切りギリギリまでクオリティの向上を追求し、何とか提出することが出来ました。
10月中旬、運営から選考結果が来ました。結果は1次予選敗退。私は声が出ませんでした。前回と比べて開発時間も十分にあったのに、私は落選してしまったのです。審査員からは、「操作性が悪い」「バグが多い」と散々な結果でした。クオリティを追求したはずなのに、欠陥だらけだったという事実に私は涙を流しました。その日は食事が喉を通らず、しばらくゲーム開発からも距離を置いていました。
一年間
あれから約一年間、私はほとんどUnityに触れることなく4年後期を迎えました。この時私はゲーム開発に対する情熱はほとんどなくなっていました。
そんな中入ってきた、3年ぶりの学校祭を開催するという知らせ。そこで私はゲームを展示してみないかと提案されました。久しぶりの学校祭だったので展示することにしましたが、ちゃんとしたゲームを作れるか、そもそも完成させれるか不安でした。
とりあえず私は、去年のコンテスト用に作ったゲームを改良し学校祭様に作り直そうと試みました。しかし、多すぎるバグ、崩壊したゲームバランス等また私は壁にぶち当たりました。やはりまた駄目なのか、そう思い始めました。
転機
ゲーム開発が進まない中、ストレス解消とアイディア探しのために私はYouTubeを見漁りました。その中で、バカゲーの実況動画を見つけました。そのゲームはとにかく勢いで笑わしてくるゲームで、私は自然と笑いがこみ上げてきました。自分もこのようなゲームを作ってみたい、そう思い始めたのです。
情熱を取り戻した私は早速作業に取り掛かりました。「一刻も早くバカゲーを作りたい」という思いを胸に、まず目の前のバグの解決に勤しみました。モチベーションを取り戻した途端、バグはどんどん解決されていきました。その時の快感は今でも忘れていません。
バグをあらかた解決したところで、次にどんなバカゲー要素を入れようかと考えました。そして考えに考えた結果…
上様、出陣

私は上様を出陣させることにしました。このほかにも、





等といったカオスな要素が受け、お客さんからは大好評!今までで一番作り甲斐があるゲームでした。
このゲーム作りを通して、まず自分が楽しめないと面白いゲームは作れないということを学びました。
現在
現在は、卒業研究の一環で学習用のARゲームを制作しています。自分のやりたかったARゲーム開発の第一歩を最近やっと踏み出せました。私は今までの挫折と喜びを胸に、このゲームを完成させ、夢に向かっていこうと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
