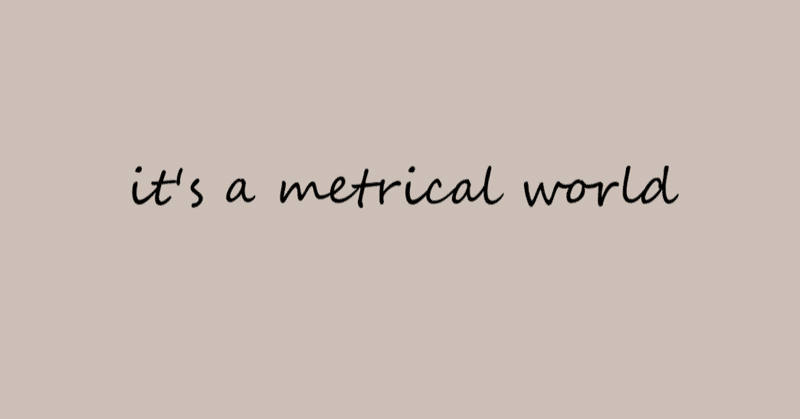
韻律的世界【11】
【11】九鬼周造─押韻論・偶然論・時間論(続)
『時間論』もそうでしたが、今回とりあげる『偶然性の問題』(岩波文庫)はとりわけ、小浜善信氏の注解が詳細精緻をきわめていて、その充実した解説とあわせると、あたかも二書を同時に読むがごとき体験を味わわせてくれます。
しかも注解どうしが緊密にリンクを張り合っていて、それらをたどり読み進めていくと、いくつかの論述の筋道が、まるで絡まった蜘蛛の糸がほぐれるようにして紡ぎ出されてくるのです。これに似た感じは、入不二基義氏の『現実性の問題』で味わいました。註が註に言及し、あたかもシナプス結合が増殖していくように、複数の議論が紙上で自律的に展開していく…。
(私が‘別のところ’で考えている「拡張されたアナグラム」は、二連音や文字を最小単位とするのみならず、組み立てればひとまとまりの論考となるジグソーパズルのピースのような断章(注解を含めて)を単位とし、かつ異なるテクスト群にまたがって現象する。)
さて、その『偶然性の問題』第2章「仮説的偶然」に、「頭韻、脚韻、掛詞、枕詞、折句、廻文などの形で文学上に一定の価値を有っている」偶然性をめぐる議論が出てきます(63-64頁)。
九鬼周造は偶然性を次の三つに区分していて、ここで論じられる偶然(「鉢」と「蜂」と「八」にみられるような言語の音韻上の関係)は「仮説的偶然」のうち「継起的偶然」に該当します(『時間論』解説、349-352頁)。
①定言的(論理的)偶然:個物および個々の事象の存在の偶然性
②仮説的(経験的)偶然:二元の邂逅の偶然性
・同時的偶然(二元の出来事の偶然の邂逅)
・継起的偶然(同時的偶然の反復→回帰的偶然(過去⇔現在)→無限回帰)
③離接的(形而上的)偶然:「無いことの可能」に関わる存在そのものの偶然性
小浜氏は『偶然性の問題』のこの個所(63頁)に、次の注解をつけています。「本章注解(6)の「またしてもまたしても」…もそうであるが、九鬼の押韻論が偶然論と時間論(形而上学的時間・回帰的時間)論と密接な関係をもつことが暗示されている。(本章注解(60)、「第三章」注解(45)参照」(316頁)
別の注解への言及や参照指示が三つでてきました。第一の注解は、「アルキメデスのπ」を少数であらわした値(3.142857142857……)の循環節(142857)が「またしてもまたしても」(xaná kai xaná)繰り返されるという本文の記述(61頁)に付されたもの。「「またしてもまたしても」という表現、とくにそのギリシア語表現には「偶然論」と「回帰的時間」(永遠回帰)の思想との関連、あるいは「偶然の必然」という思想が示唆されている。…(本章注解(60)参照)」(315頁)
第二は、循環小数や前回とりあげた「一韻到底」の押韻の例(“奥つ鳥…”)にみられる「単一の同時的偶然が同一性をもって「またしてもまたしても」…無限回反復されることによって成立する継起的偶然」をめぐる本文(146頁)につけられた長文の注解です(337-339頁)。
ここには、前回抜き書きした議論──九鬼哲学の三大テーマ、“奥つ鳥…”の歌の音韻分析、「時間の真の構造は、継起的・水平的時間に同時的・垂直的時間が交差するところに成り立っている。」(339頁)云々──や、「九鬼が無限回帰の時間を象徴するものとして何度か引用する」芭蕉の句“橘やいつの野中のほととぎす”をめぐる九鬼の注釈──そこでは、「九鬼流の形而上的想起説」(339頁)が述べられる──が紹介されています(芭蕉の句をめぐる九鬼周造の注釈は次回とりあげる)。
第三の注解は、第3章「離接的偶然」で言及された「押韻の起源」(239頁)[*]に付された注解で、九鬼押韻論の背景と内容を紹介し、簡潔に要約したもの(『時間論』解説の「押韻論」の項に活かされている)。これも長文(368-372頁)。
以上、小浜義信の注解的世界の一端をトレースしてみました。基本的には、前回抜き書きした議論と重なっていて、偶然論との関係のもとで九鬼押韻論の実質を掴むためのほんの入り口に立った程度で終わっています。九鬼偶然論のなかで魅力的な概念だと思う「原始偶然」(離接的偶然の極限、「この世界・宇宙の存在(の始原)そのものの偶然性」(421頁)──この境位の偶然性にまで達しないと、九鬼押韻論のほんとうの凄みはおそらく掴み切れない)に説き及ぶことは叶いませんでした。
[*]『偶然性の問題』の同じ頁に、ヴァレリーによる押韻の定義が紹介されている。
《ポール・ヴァレリーは一つの語と他の語との間に存する「双子の微笑」…ということをいっているが…、語と語との間の音韻上の一致を、双子相互間の偶然的関係に比較しているのである。なおヴァレリーは詩を形式的見地から定義して「言語の偶然(運)の純粋なる体系」…といいまた押韻の有する「哲学的の美」…を説いている。また、オスカー・ベッカーは「果無[はかな]さ」…「壊れやすさ」…が美的のものの基礎的特質であるといっている…が、偶然ほど尖端的な果無い壊れやすいものはない。そこにまた偶然の美しさがある。偶然性を音と音との目くばせ、言葉と言葉の行きずりとして詩の形式の中へ取入れることは、生の鼓動を詩に象徴化することを意味している。そうして「言霊」の信仰の中に潜在している偶然性の意義を果無い壊れやすい芸術形式として現勢化することは詩の力のゆたかさを語っていなければならない。要するに偶然性が文学の内容および形式の上に有する顕著なる意義は、主として形而上的驚異と、それに伴う「哲学的の美」に存している。》(『偶然性の問題』239-240頁)
──ここでもまた九鬼周造は「うた」っている。この哲学的思索に匹敵する強度と熱量をもった具体の詩歌作品、あるいは表現(吟誦)の実例はあるのだろうか。小浜氏が文中の「「言霊」の信仰」に付けた注解の中で挙げている例歌──“しき島の日本[やまと]の国は言霊のさきはふ国ぞまさきくありこそ”(柿本人麻呂)や“そらみつ 倭の国は皇神の 厳しき国 言霊の 幸はふ国と 語り継ぎ”(山上憶良)──がそれなのだろうか。
おそらく実例は(書物の中で言及(印刷)されるようなかたちでは)挙げられないのだろう。「日本詩の押韻」の最終局面で、九鬼周造は次のように書いている。「私は未来に於て、天才的詩人が出て来て、日本語の有する可能性の中から、真に美しい押韻詩を生んでくれることを希望してやまない。私はこの希望を抱きながら、またこの希望の実現される日の到来を信じながら、単に理論的指針のようなものを提供することで満足する。」(『九鬼周造全集 第四巻』450頁)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
