
「THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!!!! 2023」前夜
ドラクエ2で初めてロンタルギアの大地に昇りつめた時、全員のレベルはカンストしていた。最高レベル、最強装備。そうでなければいけなかった。今考えれば、それはゲームと呼べる代物だったのだろうか。わからない
子供のころの私は、そうしなければ不安で仕方がなかった。正直怖かった。祠まで戻ればなんとかなる。復活の呪文をメモっておけばなんとかなる。低いレベルでもトライ&エラーを繰り返しながらハーゴンまで辿り着ける。運が良ければシドーを倒すこともできるだろう。だがそれを許さなかった。
怖かったんだ。なにかを取りこぼすことを。なにかひとつでも失うことを。ブリザードのザラキや、サイクロプスの痛恨の一撃にやられてはいけない。臆病な私が選んだ手段が、それだった。他に良い案が思い浮かばなかった。はぐれメタルが出現する場所にわざわざ戻ってレベル上げに勤しんでいた。
ゲームは本来楽しむべきものであるが、その作業には随分と苦痛を伴った。シドーを倒したときに達成感はあったか?今となってはそれも実に怪しい。ただ放心とした状態で最後のエンドロールをしばらく眺めていた気がする。
困ったことに、アイドルの子たちにそのような時間をかけられなかった。時間は有限。結果は非情。初回バッドエンドはアイマスの華。甘美な蜜。失うことが怖かった私が、バッドエンドを得てしまったがゆえに囚われた。
特にアイマス2のバッドエンドであるアカペラ「i」には心が引き裂かれた。彼女たちの時間は限られている。最高レベル、最強装備を待ってられない。1年間という短いプロデュース期間に得られるものは、正直たかが知れている。
私は彼女たちに、最高を与えてあげられなかったことがとても悔しかった。ふざけるな、次こそは必ず最高を与えてやる。最高に輝かせてみせるんだ。何かを得られなかった私が、代わりに何かを得ていた。言葉にはできない。
初回バッドエンドはアイマスの華。まんまと囚われた私が、そこにいた。その甘美で蠱惑的な蜜の味を知ってしまったのだ。アイマスという蜜を。贖罪という言葉は、その頃から使うようになっていたのかもしれない。
そういえば、アカペラ「i」の時も放心しながらエンドロールを見ていた。
幼かったころの私とは違う。これはゲームと呼べる代物なのだろうか。
そもそもアイドルというものは不完全だ。完全性を伴うアイドルがアイマスの中ではしばしばライバル役として登場するが、それをアイドルと呼んでしまっていいのだろうか。完全性を持てば持つほどプロデュースする必要性がなくなってしまう。黒井プロがプロデューサーを置かずにアイドル自身にセルフプロデュースさせるのはそれが理由だ。単純に必要がないからだ。彼ら彼女らをアイドルと呼ぶにはいささか抵抗がある。私には黒井社長になれない。
そもそもアイドルというものは不完全だ。だから成長する。自身のみで成長することもできるだろうが、彼女たちに与えられた時間は短い。限られた時間の中で、まっすぐ効率的に進めるよう道を照らし、背中を押すのがプロデューサーの役目だ。それを望まれて、プロデューサーになってくれと、プロデューサーでいてくれと望まれたからアイマスのプロデューサーをやっている。理由が必要だ。不完全であるからこそ成長物語が成立する。完全であればあるほどそれは成長物語ではなく登場物語であり、変化球にしか頼れない。
望まれる、自分を必要としてくれるのは実に気持ちがいい。それもそのはず、現実の世界ではなかなかそういう場面に出会えないからだ。少なくとも四角い画面の向こう側から自分を望んでいる姿を見かけるたびに嬉しくなってしまう。人間なんて簡単なものだ。隠れている自尊心や自己顕示欲をくすぐられるのに弱い。自分が必要としていたことに気づくには私も結構時間がかかってしまった。
だから、劇場版アイドルマスターを見た時は随分と苦労した覚えがある。成長し、付きっきりで面倒を見なくても自主的自発的に活動する彼女たちに、プロデュースは必要なんだろうか。私はどうふるまえばいいんだろうか。そんなことを考えながら足繫く映画館に通ったが、結局答えが出ることは無かった。
私は本当に彼女たちの成長を望んでいるんだろうか。半人前なアイドルと一緒に屋上広場を巡って営業するのがお似合いなんじゃないだろうか。
そんなこと、口が裂けても彼女たちには言えない。誰も望んでいない。
欺瞞の成長物語の中で、ごっこ遊びに興じていた私の姿はどう映るのか。

New Me, Continued は、MA4のCDで既にソロバージョンを聴いていたはずなのに、SUNRICH COLORFUL の765プロ単独ライブで聴いたときは全くの別物に感じた。その重さに足が震えた。あれは1曲を全員で歌ったわけではない。全員分の13曲を一つに束ねたものだった。見えてる景色が、聞こえる景色が、歌う者聴く者全員違う。
1曲1曲にプロデュースがあり、思い出ボムがあり、悔しさや嬉しさがあり、楽しさや寂しさがあり、その繰り返しがあり、それが束になって覆い被さってきた。どおりで重いわけだ。なんとか背負いきった自分を褒めてあげたい。
イントロとアウトロで奏でるピアノのメロディ。なんだか入学式と卒業式みたいだな、そう思った。ともすればアイマスからの卒業、アイマスの終焉を連想させるが、そうじゃない。あれは、拒絶の歌だ。
具体的な話なんてなにも言ってない。全てが抽象的な言葉で埋められている。だけど、映像が鮮明に頭の中を駆け巡る。言葉のひとつひとつ、その全てがトリガーとなって頭の中から記憶を強制的に引きずりだす。その嘔吐感にたまらず嗚咽が漏れ、その胸の苦しさに涙する。
嬉しかったプロデュースの思い出。腹が立ったプロデュースの思い出。哀しかったプロデュースの思い出。楽しかったプロデュースの思い出。津波のように襲い掛かってくるそれを、アイマスでは「思い出ボム」と呼ぶ。
奇跡という言葉を調べると、人間の力や自然法則を超えて超自然のものとされる出来事、らしい。私がライブで見たあれは、奇跡なんかじゃない。軌跡だ。成し遂げた帰結だ。人の力で、人の意思で作り上げたものだ。感謝の言葉なんて言っていたか?彼女たちは現状に満足していない。
私は、私のプロデュースが正しかったのか不安だった。彼女たちにとって正しかったのか不安だった。何度もプロデュースを繰り返しているうちにトップアイドルというべき成功を収められるようになっても、それまでの失敗や後悔を拭えることは無かった。アイドルなんて道を選ばせないほうが幸せなんじゃないか?
後ろめたい気持ちを引きずりながら次のプロデュースを始めるころには、彼女たちはまた「はじめまして」という。苦い顔をしながら「はじめまして」と返す。正しかったのか、回答なんて聞く気にもなれなかった。それを無かったことになんかできないのだから。
回り続ける螺旋の中で、彼女たちが「はじめまして」を何度言ったか覚えてるなんて思いもしなかった。それを覚えているのは私たちプロデューサーだけだと勝手に勘違いしていた。おくびにも出さずに「はじめまして」と彼女たちが何度も言っていたという事実に、妙に気恥しくなってしまった。
なんだ、お前たちも覚えているんじゃん、私のプロデュースを。じゃあもう回答なんて聞かなくていいや。彼女たちがそこにいて、何も知らないふりをして嫌な顔もせずに「はじめまして」と言う。それが全てだ。
夢の大橋で春香が拒絶したリセット。取り残される春香。「はじめまして」。はじCさんの「わた春香さんと普遍論争」は、New Me, Continued に帰結していた。馬鹿野郎、そんな真似しやがって。ループの外から俯瞰できるならそう言ってくれよ、とは思うが、それも野暮。ごっこ遊びを興じ続けるのであれば、それも必然。春香の問いにはまだ答えていないが。
死ぬことを拒絶したアイマスが、永遠を否定する。永遠なんてありはしないから、今が存在して未来が存在する。その見果てぬ未来を渇望する限り、彼女たちは、私たちは歩み続けられる。満足などとは程遠く、彼女たちの「わがまま」が聞こえた。思い出の中ならいくらでも甘美でいられるが、彼女たちはそれを拒絶した。
新作が出るたびに、プロデュースを繰り返すたびに、トップアイドルに登り詰めた彼女たちの世界線がリセットされて、またゼロに戻してしまうというアイマスにおける業と呪い。そして「はじめまして」。それがNew Me, Continued によって新たに塗り替えられた。
祝福と肯定に包まれ奏でられたその曲は、13個でもなく13倍でもなく、13乗。それが、彼女たち担当アイドルからのプレゼントだった。私たちも生まれ変わる、強くてニューゲーム。最初のファンのあの人からプレゼントされた思い出深いアクセサリー。忘れたりなんか、しませんよ。するわけないじゃないですか。春香は、そう言っていた。忘れ難い初回バッドエンドの記憶と共に。
なんだか、私たちのプロデュースに対するアンサーソングみたいだな。そう思った。

アイドル達はいろんなものを犠牲にして成り立っている。例えば時間。普通の女の子であれば得られる人生、経験を得ることができない。学校生活、知識、部活動、青春、家族愛、恋愛、自立、その他諸々。普通の女の子であれば世界の大多数の女の子が得られない人生を得て、普通の女の子であれば世界の大多数の女の子が得られるであろう人生を得ることができず、人はそれを犠牲、あるいは自己犠牲と呼ぶ。それは搾取と言い換えても成立し、私たちプロデューサーはその女の子たちの人生を搾取している。ビートたけしが芸能事務所を女衒と評したが、その認識は正しい。
アイドルとプロデューサーは等しく苦労をしなければならない。苦労の平等性。だが現実にはアイドルばかり苦労させてしまっている。あまつさえ、そのアイドルの人生を搾取するのは、苦労の不平等。それらを失ってまでも彼女たちがアイドルを続ける理由はなんだろう。ともすれば、自己実現と自己犠牲の間の境界線が見えなくなる。
アイドルという1人の人間を搾取しながら生きているというグロテスクさを実感する一方、アイドルになった以アイドルであるうちは、アイドルとしていかに搾取されるかが自らの成功を測る指標になってしまっているからこそ担当アイドルのためには搾取をやめられないグロテスクな構図。
気付いたところで、どうしようもない。
少なくとも私はそれに対して不甲斐なさと申し訳なさと後ろめたさで溢れかえる。それに見合うアイドル人生を用意してあげられただろうか。螺旋を紡ぎながら、どれだけ与えてあげられただろうか。トレードオフにならないままでライブを楽しんでいるのが私だ。苛まれれば苛まれるほど甘美な蜜の濃度が上がってくる。
アイマスは人生?やめてくれ。こんな格好悪い私を見ないでくれ。私のアイデンティティを見ないでくれ。
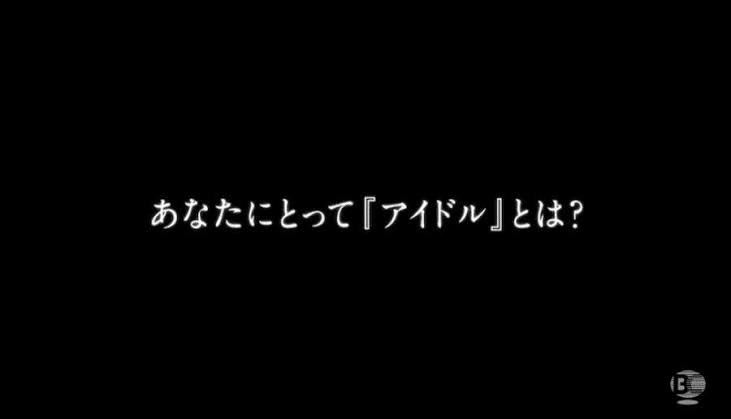
春香がアイドルとしてのアイコンという立場を得て、もう随分と長い月日が経ったように思う。アイドルのリファレンスモデルとして、行動指針として、メンターとして、そしてセンターとして。平凡で何の取り柄もなかった1人の女の子の小さな肩に、そういったものを当たり前のように春香の肩に背負わせている。春香、その荷物は重くないか?
トップアイドルになれるのは、ほんの一握り。不動のエース、あるいは切り札としてのジョーカー。センターという位置は真ん中。エースやジョーカーにいちばん遠い場所のように思える。歩む先の未来に、お前の望んだトップアイドルはあるのか?リファレンスモデルである限り、トップアイドルになれないのではないか?他のアイドルやプロデューサーに聞かれたら殴られかねないその贅沢な悩みを許されるのか?
劇場版アイドルマスターからもう9年も経っているのに気がついた。M@STERPIECEにかけられた強烈な呪縛も、私の中ではだいぶ軽くなってきたような気がする。だけど、そんな気分でいられるのも今日までだ。明日にはきっと、春香のあの言葉が東京ドームに響き渡る。眩暈がするほど恋焦がれ、気が遠くなるほど待ち焦がれ、西武ドームでは物足りなかった、あの言葉だ。
2回目なんだから耐えられるだろうと強がってはみるが、無駄な努力だろう。春香はその瞬間、特大の思い出ボムと共にその背負ってきた重い荷物も一緒に最大火力をもって客席に投げつけてくるのはもう分かりきっている。耐えられるわけがないし、そんなの耐える必要もない。ただ無心に浴びればいい。
たぶん、私と春香が思い描いているトップアイドル像というのは、他のプロデューサーやアイドルが思い浮かべているものとはちょっと違う気もする。幸いなるかな、それは私と春香の2人だけの宝物だ。特に共有することもなく墓場まで持っていこう。なんか照れくさいし。
君たちだってそんな宝物を一つや二つは持ってるものだろう。プロデューサーを何年やってんだ。なに?持ってない?始めたばかり?おめでとう、あなたと担当アイドルとの宝物探しが今始まった。それはとても羨ましいことなんだ。
ドーム公演がアイマスのゴールではなくなって、早幾年。次のゴールは、私の興味が尽きるのが先か、私の寿命が尽きるのが先か。まぁ、寿命だろうな。彼女たちは宣言しちゃったし。
すげー楽しそうな顔して付き合ってやるよ。ゲームというのは本質的に楽しむべきものだからな。ゲームは本来楽しむべきものだろ?

2023.02.10
