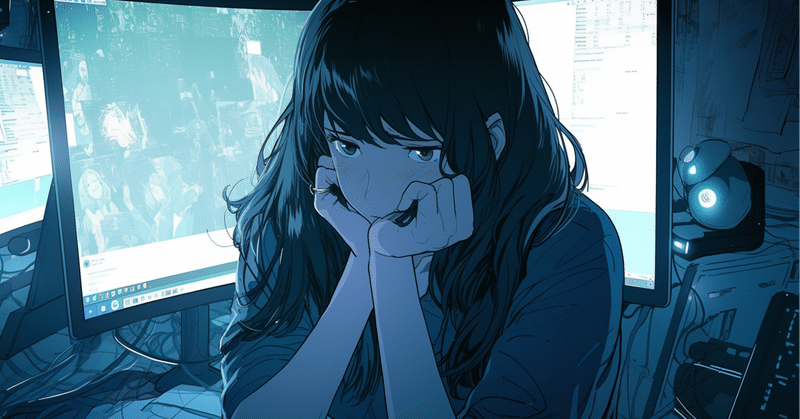
【ChatGPT-4】AIが答えやすい質問とは?What質問とHow質問の比較と活用方法
こんにちは。
カンガルーさんです。
様々な企業やビジネスシーンで活用され始めたChatGPTですが、「情報の精度に不安がある」「ファクトチェックが必要」など、新しい情報の取得には向かないという声がよく聞かれます。
これには私も同意です。ChatGPTの精度はどんどん向上していますが、学習した情報から”それらしい内容”を出力するに限るため、どうしても情報の精度に不安があります。
つまり、「~は何でしょうか?」「何か~な情報を教えてくれますか?」のような[What型]の質問だと微妙な回答が返ってくるということです。
この微妙な回答を避けるために、質問の内容を変えて「どのようにしたら~でしょうか?」「どうすれば~でしょうか?」のような[How型]にすることがChatGPTから良い回答を得るひとつの手段として私からご提案いたします。
そんなことで変わるの?と思ったのではないでしょうか。せっかくなので、直接ChatGPTに聞いてみることにしました。
※本noteではChatGPT-4を使用しています。別バージョンでは異なる回答が返ってくる可能性がありますので、ご了承ください。
最初に下記の質問をChatGPTにしてみます。
同じような内容を、What型とHow型で比較し「どちらのほうが答えやすいか」を聞いています。
これからあなたに二通りの質問をします。どちらも同じような内容ですが、聞き方が異なります。どちらのほうが答えやすいか、点数と評価した基準、解説を含めて教えてください。
①友達の誕生日の祝い方を教えてください(What)
②友達の誕生日をどのように祝うのがよいか教えてください(How)
回答は下記です。
ChatGPTからは「答えやすさの点では質問②が優れていると評価できます。」と出力されました。
両方の質問は似ていますが、質問の焦点が異なります。それぞれの質問について、答えやすさを5点満点で評価し、基準と解説を含めて説明します。
①友達の誕生日の祝い方を教えてください(What)
評価:4点
基準:この質問は具体的な祝い方について尋ねており、答える際には様々な例を挙げることができます。ただし、相手の好みや関係性によって最適な祝い方が変わるため、答えに対して一概に正解とは言えません。
解説:この質問に答える際には、例えば「パーティーを開く」「プレゼントを贈る」「サプライズを企画する」など、一般的な誕生日の祝い方を挙げることができます。ただし、最適な方法は相手の好みや関係性によって異なるため、あくまで例として提示することが適切です。
②友達の誕生日をどのように祝うのがよいか教えてください(How)
評価:5点
基準:この質問は祝い方に焦点を当てつつも、どのように祝うことが最適であるかという観点から尋ねています。答える際には、相手の好みや関係性を考慮した適切な方法を提案することができます。
解説:この質問に答える際には、まず相手の趣味や興味を把握し、それに合わせた祝い方を提案することが重要です。例えば、映画が好きな友達であれば「お気に入りの映画を一緒に観る」、スポーツが好きな友達であれば「一緒にスポーツを楽しむ」など、個別の状況に応じたアドバイスが可能です。また、関係性に応じてパーティーの規模やプレゼントの選び方も提案できます。
総合的に見ると、質問②のほうが答えやすいと感じます。これは、質問②が相手の好みや関係性を考慮した適切な方法を提案する余地があるためです。一方、質問①は具体的な例を挙げることができますが、相手の好みや関係性によって最適な祝い方が変わるため、一概に正解とは言いづらい点があります。質問②では、個別の状況に応じたアドバイスが可能であり、より具体的で適切な提案ができると考えられるため、答えやすさの点では質問②が優れていると評価できます。
もうひとつ、質問を追加しました。
”共通点と相違点を答える”という点は同様ですが、How型には「どのように設定すべきか」というHowを追加しています。
①仮定のA社とB社の共通点と相違点を考えてください(What)
②仮定のA社とB社の共通点と相違点をどのように設定すべきか仮定したうえで、その設定から改めて共通点と相違点を考えてください(How)
回答は下記です。
ChatGPTからは同様に「総合的に見ると、質問②のほうが答えやすいと感じます。」と出力されました。
両方の質問は共通点と相違点に焦点を当てていますが、質問のアプローチが異なります。それぞれの質問について、答えやすさを5点満点で評価し、基準と解説を含めて説明します。
①仮定のA社とB社の共通点と相違点を考えてください(What)
評価:3点
基準:この質問は具体的な共通点と相違点を挙げることを求めています。ただし、A社とB社についての具体的な情報がないため、答える際には状況を想像する必要があります。
解説:この質問に答える際には、まずA社とB社がどのような業界や規模の企業であるかなどの背景を想像する必要があります。その上で、共通点として「同じ業界で事業を展開している」、「顧客層が似ている」などを挙げることができます。また、相違点としては「企業規模が異なる」、「経営戦略が異なる」などを考えることができますが、具体的な情報が不足しているため答えにくい部分があります。
②仮定のA社とB社の共通点と相違点をどのように設定すべきか仮定したうえで、その設定から改めて共通点と相違点を考えてください(How)
評価:4点
基準:この質問では、まずA社とB社の共通点と相違点を設定する方法について考え、その設定に基づいて共通点と相違点を挙げることが求められています。具体的な情報は不足していますが、状況を仮定することで答えやすくなります。
解説:この質問に答える際には、まずA社とB社がどのような業界や規模の企業であるかを仮定します。例えば、A社とB社が共にIT業界の企業であると仮定した場合、共通点として「IT業界で事業展開」、「技術者を主なターゲットにしている」などが挙げられます。一方で、相違点を設定する方法としては、A社が大規模な企業でB社がスタートアップであると仮定し、相違点として「企業規模が異なる」、「経営戦略が異なる」、「リソースの量と質が異なる」などを挙げることができます。このように、まず状況を仮定してから共通点と相違点を考えることで、答える際の具体性が増し、答えやすくなります。
総合的に見ると、質問②のほうが答えやすいと感じます。これは、質問②ではまず状況を仮定してから共通点と相違点を考えることで、具体的な情報が不足している状況でも答えやすくなるためです。一方、質問①では具体的な情報が不足しているため、答える際に想像が必要であり、答えにくい部分があります。
これまでの2パターンともChatGPTはHow型の質問のほうが答えやすいと回答しています。この点について、ChatGPTに直接同意や異論はあるか確認したところ、下記の回答が出力されました。
同意します。一般的に、「How」の質問は、「What」の質問に比べて答えやすい傾向があります。その理由は以下の通りです。
1. 問題解決のプロセスや方法に焦点を当てるため、答える際に具体的な手順やアプローチを提案することができます。これにより、回答者がより具体的で適切な提案を行いやすくなります。
2. 「How」の質問は、問題の背景や状況を考慮することが求められるため、回答者はより深く理解し、適切な回答を提供することができます。
3. 「How」の質問は、具体的なアクションや方法に関する提案を求めるため、回答者は問題に対してより具体的な解決策を提供することができます。
ただし、質問の内容や状況によっては、「What」の質問が答えやすい場合もあります。例えば、基本的な事実や知識に関する質問の場合、「What」の質問のほうが答えやすいと感じることがあります。しかし、上記の2パターンの例では、「How」の質問のほうが答えやすいと感じました。これは、具体的な情報が不足している状況であっても、「How」の質問が問題解決のプロセスや方法に焦点を当てることで、答えやすくなるためです。
これらより、「どのようにしたら~でしょうか?」「どうすれば~でしょうか?」のような[How型]にすることがChatGPTから良い回答を得るひとつの手段であると言えるのではないでしょうか。
直接How型に変更できない質問も、途中の判断基準をHowで聞くことで、回答の精度が上がる可能性が十分あります。
ChatGPTでの質問・回答精度向上に役立てば幸いです。
2023.4.21
カンガルーさん
[トップイメージは筆者がにじじゃーにーで出力したAIアートです]
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
