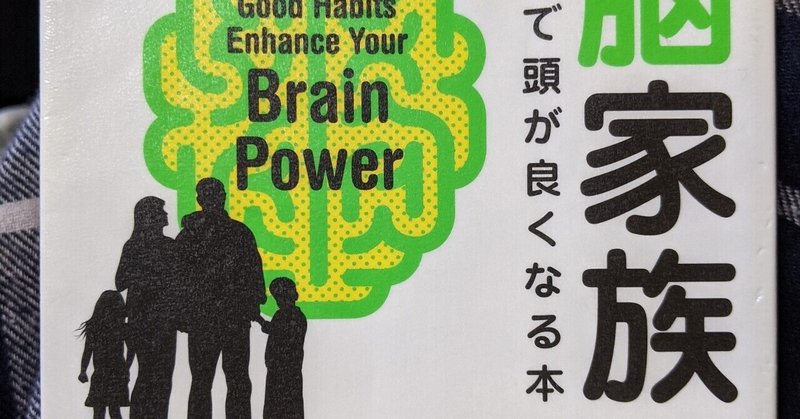
3_2.育脳家族(久保田競)のメモ
くぼた式 育脳7箇条
・規則正しい生活を送る
→毎日同じ時間に起床就寝、食事も決まった時間に
・ストレスを避ける
→原因を取り除く、ストレスをためない
・運動の習慣
→毎日15分以上、汗が出るくらいのエクササイズ
・ワーキングメモリーを鍛える
→計画を立てて予想し覚えてから実行。結果を記録に残す
・毎日ひとつ以上、自分以外の人のために頭をつかう
→育児、介護、家事、ボランティアなど
・毎日書かれたものを読み、誰かに伝える
→新聞雜誌ネットなど。心に残ったことを人に伝える
・ときどき、上記をすべて無視してハメをはずす
頭が良い、とは
前頭前野がよく働き、問題解決ができること。
食事の準備で手順を自分で組み立てられて、できあがりに合わせてごはんが炊きあがるような複雑なタスクをクリアできる。
上記ができるようになるには、脳のあらゆる場所がうまく働く必要がある。産まれたらすぐたくさん刺激を受けるほうが良い。
3歳くらいまではシナプスの発達ピークなのもあるため、子どもが自分で何かやりたがったら尊重すること。『〇〇を食べたい』など自発的なものはできるだけ用意してあげることで幼いうちからひとりの人間として認めることになり、個性を持った大人になっていく。
子どもの意見や考えに耳を傾けず、親が何でも用意してあたえてしまうと逆効果になる。
子どもが将来自分自身で考え自立できるようになるためには、幼児期に適切に鍛えておくこと。小学校にあがるころには、親は自分の人生と子どもの人生を分け、それぞれ自分でレベルアップしていくこと。
ワーキングメモリーと褒めて育てる
生後半年から過去と今の区別ができるようになってくるので、例えば鈴がなったら片付ける、などルールをつくり覚えさせる。いないいないばあ、も有効。
道順を子どもに説明し覚えさせ案内させる、などを日常的に行う。
小さい目標達成につき褒めちぎることでドーパミンがでる。ドーパミンがでると、自らすすんでやるようになる。できないから怒る、は逆効果なので上手にやらせるために褒めることを心がける。
理由もなく褒めたりご褒美を渡すよりは、待たせたり片付けさせたり、やっと手に入った、と思わせるほうが喜びが大きくなる。
叱り方
『積極的にやらない』という回路がある。赤信号で止まる、などのときに『してはいけない』と禁止するだけよりも、『積極的にやらなかったことを褒める』こと。
我慢して!とストップ信号を出すときは強い言葉を使って問題ないが、あとで『よく我慢できたね』と声をかけること。また、我慢する理由や代替案を見せて、強要するだけでなく子どもも納得できるように知恵を絞る。
ミラーニューロン
手本やプロ選手の映像を見せることで上達が早まる。見たあと、頭の中でどう動けばできるようになるかイメトレするとよりよい。言葉の習得にも当てはまる。
気持ちの理解力にもミラーニューロンが関わる。相手をよく見ることで予測分析し、トライエラーを繰り返す。親が叱るときも、目線を合わせ顔を見せることで意図が伝わりやすくなる。
身体を鍛える
早足で1時間歩かせる=ランニングのあとには記憶力が高まる。小学生のうちに長期休暇のときは自宅以外の場所で生活させる。受験勉強よりも身体全体を使って遊ぶことが脳の成長につながる。
水泳、剣道、柔道などの個人競技は小さい頃に。おおきくなったら団体競技でチームワークを学ぶ。
テレビ、ゲーム、ネットとの関わり方
好きなこと、やりたいことを禁止させるよりはやらせたほうがよいが、特にテレビについては、思春期(中学生くらい)は1日1時間で時間制限を設けるほうが良さそう。その後の集中力に差が出るらしい。受動的な情報収集なので刺激が少ないため、テレビよりも運動、芸術、読書などに時間を使わせるべく褒めたり工夫をする。
ゲームについては、脳を使うため悪いとは言い切れないがそればかりにならないようにするため、スポーツや勉強などのご褒美として与えるのはどうか。
男の子と女の子
脳みその作りが違うので好むものや怖がることが違う傾向が高い。男の子は戦隊ごっこが好きだけど、女の子はお人形遊びが好き、というもの。女の子は公正さを好むため、他の人とおもちゃを分け合うことに抵抗が少ない場合が多いが、男の子には難しいなど。
生まれたときから、ちがうのだからそれに逆らう必要も特にない。異なる意見をディスカッションすることはのうにとって非常に良い刺激になるため環境が違う友達や外国人との交流もためになる。
男親と女親が共同して子どもに接することで、それぞれの反応や考えが違うことを学習させる。また、恋愛(片思い)をすることで相手によく見られたい、と考え行動するためいくつになっても恋愛はレベルアップにつながる。
食事のこと
家族揃って食事をとることでコミュニケーションの場となる。食事の作法を覚えさせることといっしょに、今日の出来事などを人に伝えたり、食べすぎないことを教える。4歳5歳までに脂肪細胞の数が決まるため、この頃に太らせない(正しい食習慣をみにつけさせる)ことが大事。
砂糖やスナック菓子の中毒性に気をつける。肥満体型になると、脳みそは肥満状態を維持しようと働く。
ストレスとの向き合い方
ストレスを長期間受け続けないこと。会社の上司など嫌いな相手は早めにいいところを見つけて好きになること。3食美味しいものを食べてゆっくり眠ること。ストレスがたまっている家族がいるときは、刺激を与えずリラックスできるように接すること。
ストレスを定義すると『生体の恒常状態が崩れそうになる脅威』。うつ状態のときは散歩や運動が効果的だが時期を見極めて誘うようにする。アドバイスはせず、ひたすら話を聞き、理解しようとすること。専門医の診察を受けること。
老化を促進させるには寝たきり老人になること。身体を動かすことをやめると一気に脳の萎縮が進行する。孫の世話をすることは老化防止にとても良い。
感想
前もって知っておくことって大事だしありがたいな!と思えた。褒めて褒めて本人に考えさせる方向で接していきたい。まあ思い通りにはならないんだろうけど。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
