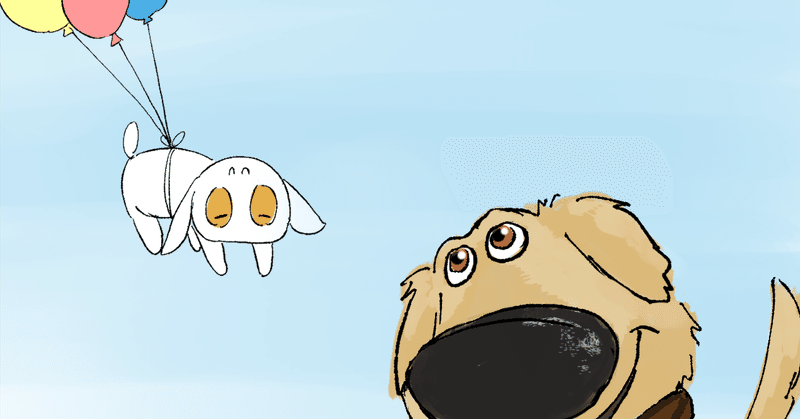
死ぬ気のじいさん、家ごと飛ぶ「カールじいさんの空飛ぶ家」
公 開:2009年
監 督:ピート・ドクター、ボブ・ピーターソン
上映時間:96分
ジャンル:アドベンチャー/ファンタジー/コメディ

最終的にはハッピーエンドになり、その後日談が描かれる「カールじいさんのデート」まで作られた本作品ですが、ハッキリとは明言していませんが、かなり後ろ向きな前向きさから物語ははじまっています。
カールじいさんが子供の頃から始まり、そこで出会った自分とはタイプの異なるわんぱくな女の子エリーと出会います。
同じ冒険家が好きで、冒険に憧れる2人は結婚し、生活し、やがて、年老いていく。
冒頭の10分ちょっとの映像で、2人の人生がダイジェストで描かれます。
最期まで仲睦まじい2人ですが、カールじいさんだけが、一人残り、2人で過ごした家で生活します。
子供こそいない夫婦ですが、ありふれた、でも心温まる人生。
しかし、連れ合いを無くしても人生は続くもので、すっかり偏屈なじいさんになったカールは、近所の光景が変わってしまっても、奥さんであるエリーとの思い出の詰まった家からでることができないところが、結果として、
しているところでもあるのです。
グラン・トリノ
偏屈なじいさんであるカールのもとに現れた少年、ラッセル。
アジア系の少年である彼は、老人にお手伝いして、ボーイスカウトのバッジをもらうことを目的としています。
おせっかいな少年と、老人を描いた名作といえば、クリント・イーストウッド監督「グラン・トリノ」を思い出すところです。
「グラン・トリノ」は、フォードに長年勤めて、アメリカを支えてきたという自負の塊である主人公がすっかり時代に取り残され、もはやご近所の人たちも白人ですらなく、違和感を感じながら生きています。
そんなとき、隣に引っ越ししてきたモン族の少年と仲良くなり、彼が大切にしていた車であるグラン・トリノを渡す、という物語になっています。
アメリカ人の魂は、必ずしも白人に渡す必要がない、ということも込められた大変素晴らしい作品なわけですが、じいさんと少年の話ではあるものの、伝えてくるものは、当然違っています。
ファンタジーとの匙加減
冒頭でちらっと書きましたが、本作品は、全年齢対象の、ほんわかした映画でありながら、カールじいさんが、決意していた気持ちは大変重たいものだったと思います。
大好きだった奥さんとの思い出のあるポストが壊されかけて、気が動転して工事現場の人に怪我を追わせてしまい、家から出ていかなくてはならなくなってしまったカール。
老人ホームに連れていこうとしている人たちの性悪な感じ。
このまま老人ホームに行ったとしても、「83歳のやさしいスパイ」のような別の物語がはじまってしまいそうですが、カールの心情は明らかに不味い状態です。
家に風船をつけて、南米まで飛ばすという狂気としか思えない行動。
人を傷つけることに恐怖するような老人が、まわりの迷惑とかを考えないで家ごと飛ばしながら、建物を壊したりする時点で、もう捨て鉢状態だといえるでしょう。
明らかに、帰って来る気もないですし、ちゃんと南米についたところで、そこで生きられるとは思えません。
死地に赴くついでに、やりたいことをやってやろうという気持ちが裏に読み取れるあたり、本来であれば、重い内容といえわざるえません。
しかし、ラッセルという少年が乗り込んできたことで、そのファンタジーは現実との接点を持ち始めます。
いくら強力な風船だったとしても、あの量では飛べないでしょうが、そんなあたりも含めてファンタジーの匙加減が絶妙だったりします。
色彩や犬について
「カールじいさんの空飛ぶ家」は、色彩設計も素晴らしいものがあります。
鮮やかな思い出や、奥さんとの思い出が詰まった家で過ごすカール。
ラッセルとのやり取りの後で、家に入ると、明らかに家はくすんだ色になっています。
特にアニメーションというのは、人物だけではなく、画面そのものが演技や演出として重要な役割をもっているわけですが、「カールじいさんの空飛ぶ家」は、そのあたりが分かりやすいです。
キャラクターも愛嬌がありまして、バウリンガルの進化系のような犬語翻訳機で面白可笑しくしゃべってくれる犬、ダグは、スピンオフ作品もでるほどの人気っぷりです。
ラピュタ感
テニスボールを利用した杖で歩くカールですが、物語後半になるに連れて、本作品は、スタジオジブリ「天空の城ラピュタ」を彷彿とさせる、冒険活劇へと変わっていきます。
特に、飛行船でのドンパチなんかは、ラピュタでありそうなシーンのオンパレードとなっています。
よぼよぼだった老人がどんどん元気になっていく姿は、それだけで、勇気を与えてくれるものであったりもします。
ラッセルの成長や、何より、カール本人の心の変化も丁寧に描かれています。
妻 = 家のように感じていたカールは、ラッセルを助ける為に、家の中にあった思い出の品物を外に出し、2人で見に行こうと言っていたパラダイス・フォールに行くための資金も投げてしまいます。
こだわりを捨てる
本作品は、道具が象徴的にわかりやすく使われています。
「グラン・トリノ」であれば、車がその象徴でしたが、カールからラッセルに渡されたものは、グレープジュースの瓶の蓋でつくられたバッジでした。
それは、亡くなった妻エリーが彼に渡したものであり、それを彼が、ボーイスカウトのバッチをかわりにつけてあげるところが、想いそのものの象徴になることによって、よりカタルシスを生み出すことになっています。
貯めていた貯金箱代わりの瓶であったり、家そのものであったり、それぞれが集めてきたものも、大なり小なり象徴的な道具となっています。
ディズニー・ヴィランズであったチャールズ・F・マンツもまた、自分で集めたコレクションを大事にしていました。
対外的な価値の大小はありますが、チャールズも、カールも、似たようなものであったりします。
2人とも過去にこだわりはしましたが、ラッセルやエリーという存在のおかげで、過去から未来へと目を向けることができたカールは、78歳という年齢なんて関係なく、素晴らしい人生が続くことを予感させるラストです。
ピクサー初のデジタル3D作品ということで、当時も話題ではありましたが、内容が空飛ぶ家と、おじいさんの話しか、と思って敬遠していた人が万が一いらっしゃいましたら、見ないと損な作品だったりしますよ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
