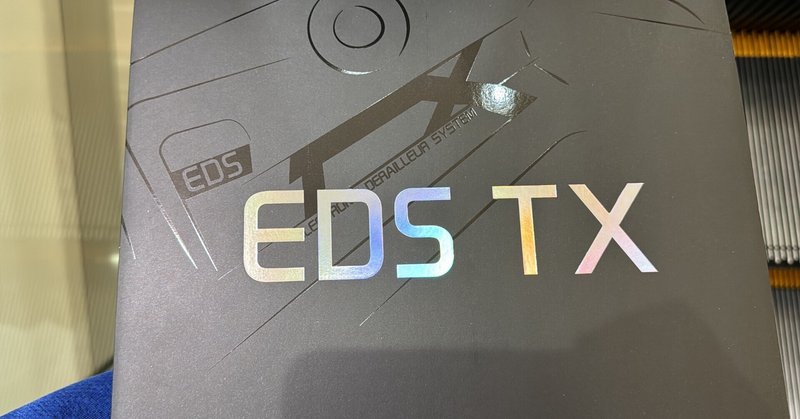
WheelTop EDS TX 自腹レビュー
日本のホダカが代理店になって出てきた、4月発売と言いつつ5月の下旬にようやく手元にデリバリーが始まった電動コンポーネントである。
いくつか種類があるが、手元に購入したのはワイヤー式ブレーキ向けのドロップハンドル型、カーボンレバー仕様である。型番で言うと TX-RA6000。
4月の頭に注文して、手元に入手できたのは5月19日だった。
フレームに取り付ける
対象のフレームは 2011年式の ANCHOR RFX8 である。購入が2012年なので12年選手のフレームだ。
当然ながらリムブレーキ。なので必然的にクイックリリースになっているわけだが、こいつが非常に曲者(後述)だった。
まあ取り付け自体は作業自体は慣れていれば大して難しくはない。
今回の変更ポイントはサドルとシートポストをアリエクで買った合計1万円くらいの3Dプリンターサドルとカーボンシートポスト。およびハンドルとステムも併せて交換にしたのだが、ポジションを他のロードバイクと近づけるために90mmから80mmへステム長を変更(両方アルミ)、ハンドルはアルミの400mmから GORIX のエアロハンドルに変更した。
しかしこの GORIX のハンドルがちと問題あり、というか出来がイマイチで、ケーブルを通すための穴が開けられているが、とりあえずあけてあるだけでケーブルがそこを通ることをちゃんと考えてないような開け方になっていて、仕方ないのでペンサンダーを3000円くらいで買ってきて削る羽目になった。強度はおそらく問題はない、と信じたい…。
元々はCARBONEX SLD用にと思って買っておいたのだが、諸事情でこちらに流用である。
EDSのセットは前後のディレイラー(以下FD/RD)、および左右のシフター、WheelTopはブリフターと呼んでいるようだが、その4点と充電ケーブルが2本が付属していた。
とりあえず元々変速ワイヤーが通っていたガイドとかはそのまま残しつつ、FDとRDを交換した。
元々は 6800 系の Ultegra が付いていたわけだが、今回全部撤去した。
今回、これまた新品のまま使わずに保管されていた R8100 系のクランクとスプロケットがあったので一気に12速化も併せて実施した。
クランク交換時にBBの右側が見逃せないほど渋くなっていたので、SM-BBR60(2500円くらいだった)を急遽買ってきて装着している。

右のブリフターはシマノと同じでギアの上げ下げでそれぞれ向けにスイッチが2個ある。しかしどういうわけか、Di2とアサインが逆で、手前側が軽く、奥側が重くなる初期設定になっていたので、私はアプリの方で Di2 と同じにアサインしなおした。
左のブリフターはSRAMのようにスイッチは1個しかない。
FDを上げるか下げるかしかできないシンプルな仕様のようだ。ここはちょっと癖がある。
問題点1
さて、早速だが走り出す前に気になることがあった。
EDS には最初からブレーキ用のワイヤーが入った状態で送られてきているのだが、海外仕様になっている。具体的には右手がリアブレーキ用、左手がフロントブレーキ用の長さのケーブルが刺さっていた。まあ交換なんて1~2分で左右入れ替えはできる構造になってるのだが、ペアリングまでして動作確認もして出荷してくるんだったら、ここも併せて日本仕様の右前、左後で出して来てほしかった。
問題点2
トライクルが動画にしてくれたのでとても分かりやすくなっているが、やはり汎用品なので変速時の移動幅は微調整が要る。フロントはまだいいのだが、問題はリア側。
スルーアクスルの場合、リアエンド幅は 142mm でほぼ統一されている。
旧式の、今回の RFX8 のようなフレームはクイックリリースなので130mmと言われている。しかし実際のところ、クイックリリースは左右から力でフレームを押さえつけて締め付ける。するとフレームによっては(たわむ位置が悪いと)ディレイラーの位置が微妙に変わるのだ。
実は変速調整をタイヤを付けてからやらないといけない、ということに気づかず作業を進めた結果、トップ側から基準を作るときにギア1枚分くらいは内側にズレた。アプリで位置調整をかけたがそれでもロー側(=内側)に寄ってしまっていたので、仕方ないからディレイラーハンガーを力で押して外に曲げて無理やり基準点に持っていった。
本来はハブの幅とフリーボディの幅でサイズは決まっているはずなので問題は起きないハズなのだが、リアのクイックの締め付け具合によっては変速基準点がズレる可能性があるのでご注意いただきたい。
シマノがディスクブレーキの Di2 しか作りたがらないのはこれのせいか? と今日思い始めた次第。
確かに横幅のサイズが歪まないスルーアクスルのほうが精度の高い変速はできそうな気がする。
問題点3
シマノ用、SRAM用ではなくあくまで汎用品なので、シマノが推奨されているといってもスプロケットに合わせて微調整をしなければならない。
12s の初期設定のままストレスなく走らせられるか、というとそうではないので、根気よく調整する必要がある。
基準点を作った後はロー側もトップ側もだいたいバシッと位置は決まるので、そこはあまり問題にはならない。しかし重い側から1,軽いギアを12としたら7とか8のギア辺りでピシッと決まっていない状態になっていた。
その辺のギアだけ弄ればいいかな、と最初は思っていたが、結局は後方からガイドプーリーの位置とスプロケットの位置関係を確認しつつ、微調整を30分くらいかけてやる羽目になる。
実走してみた
比較対象
うちにある電動コンポは R8100 系のアルテグラの Di2 と R7100 の Di2。
それと知人の SRAM RIVAL eTap AXS が己の中の物差しとして利用できるだろうか。
さて、100mくらいのヒルクライムも含めて7kmくらい、各所の精度を確かめながら実走してみた中で、気づいた点を記す。
RDとFDとも変速の速さ自体はカジュアルモードであっても必要十分というレベル。体感的には RIVAL と同じくらいかな、という印象はあった。
ただまあ、シマノの変速の速さと正確さには逆に乗ってないのに驚く、という程度には質感に違いがある。コンマの世界でしか秒数は違わないが、それでもやはりDi2のほうが変速は早いしフィーリングもよい。
ブリフターのクリック感は多少剛性不足を感じなくはないが、まあ十分だろう。ブラケットの長さは指2本分は入る。3本入るアルテグラとの一番の感触の違いはここかも、と思った。なのでDi2経験者はハンドルの握り方が多少変わってくるかもしれない。
ブレーキ自体もちゃんと引けはするのだが、いわゆる上ハンの時にブレーキレバーへの指のかかりは必ずしも良くはなさそうだった。
ブレーキを掛けられなくはないので「気が利いてない形状」というほうが正確かもしれない。
問題点4
さて、最大の問題点がここ。
走っているときに2回チェーン落ちした。これにはパターンがあり、FDがインナー、RDが12速(=いわゆるロー、一番軽い)の時に FD をアウターにしようとすると、うまくアウターに掛からなかった。
仕方ないのでインナーにギアを戻すとめでたくチェーン落ちである。
もう一度同じパターンで試したが、アウターにちゃんとチェーンがかかることもあるのだが、チェーン落ちをもう一度したので確信に至った。
Di2 や eTap 経験者ならご存じ、シンクロシフトというものがこれらにはある。ギアを重くする、または軽くするという操作をすると自動的にインナーローからアウタートップまで、前と後ろのギアを変速ショックが小さいギア比の時に自動的に前も後ろも連動してギア操作してくれる、とても便利な機能だ。
私も嫁もこのモードで使っていて、私はほぼ変えたことがなく、妻に至ってはこれ以外のモードがあるとおそらく知らないレベルでヘヴィに使っている。
EDS TX には今のところこのシンクロモードが無いので、ワイヤー式と同じように手動で前後のギアの組み合わせを調整しなければならない。
そして通常、アウターとローの組み合わせはたすき掛けになっているので推奨されていない。なのでそういう非推奨の操作を行ったときに上記のような残念パターンにハマる。アウターに入りにくいのである。
なので一番軽いインナーローからシフトアップしていくなら、5~6速くらい重くしてからフロントを変えるとスパッとアウターに入る。
逆に重たいギアからシフトダウンしていく場合、アウターには12速になってからではなく、9とか10速くらいの時点でインナーに入れる操作を忘れずに手動でやらないといけない。
まとめると、シンクロもセミシンクロも無いので、紐引きで操作しているときのように気を付けながら前後の組み合わせをうまく調整しなければならない。しかも Di2 の経験があったほうがいい。
フィーリング
まあ元々がクランクやスプロケットはUltegra、チェーンもシマノ純正なので走行フィーリングはBB交換の効果もあり軽快さはあった。
ヒルクライム中のトルクがかかった状態での変速も、とりあえずキチンとスパッと決まっていたので、そこは大トルクはともかく300wくらいなら気にしなくていいだろう。
しかしFD側は上述のように癖があるので、今自分がどのギアに入れてるのかを気にしなければならないので、レースで疲れた時などは致命的な操作ミスをしてしまう可能性はありそうだ。
故に私はレースでの使用は相当使い込むまでオススメしないでおく。
しかし前後のディレイラーにそれぞれバッテリーを積んでいるので、後ろが重い感じはある。シートポストにバッテリーを積む Di2 とはそこが違い、重量の重心も前後で見ると位置が少し変わっている気がした。
構造的にもバッテリーが FD や RD にくっついていることからもわかるように、雰囲気は SRAM に近い。言葉で説明しにくいが、例えばブリフターのスイッチの溝の切り方だとか、変速でギアが変わった後のガチャンって感じの音や体に感じるアレコレが、である。
時々動画レビューで「もうこれでいいじゃん!」てよく言ってる人がいるが、半分くらいは同意できる。ただそれは上記のような変速時に気を付けるべきを気を付けて走れる人だけで、疲れたりして集中力が弱まった時に助けてくれる電動変速の良さが、一部欠けているので私は強い推奨は致しかねる。
もしかすると将来的にファームウェアのバージョンアップとかでシンクロシフトが実装される可能性もありそうだが、それまではワイヤー式の運用を完全に忘れることはできないだろう。ワイヤーと同じギア操作を順番にしていかないとFD側でギアが入らなかったり、チェーン落ちの恐怖が常に付きまとうことになる。
なのでポタリングしかしません、とか50kmくらいまでしか乗りませんという手軽な運用を想定している人には良いかとは思うものの、私のように古いフレームを電動化したいと思う人は、Di2と完全に同じことが出来ると思って使うと裏切られることになるので、そこは注意しておいた方がよいだろう。
だいいちクランクやスプロケット、チェーンは別に用意する必要がある。もちろん紐式を買ったらブレーキもそうだ。そうなると一式そろえるころには 105 の Di2 の値段(だいたい17万くらい?)が見えてくるので、のせかえにはハマるが新規で購入すると値段も性能もちと微妙、というのが今のところの私の評価になった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
