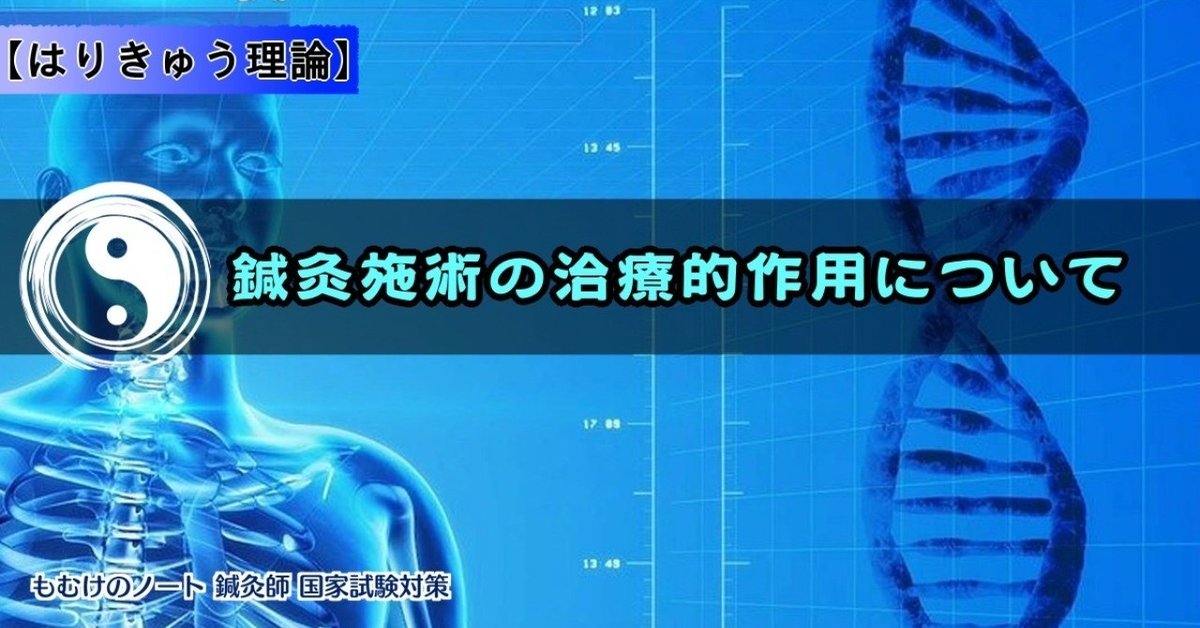
【はりきゅう理論】聞いたら覚える8個の鍼灸施術の治療的作用
【2020/02/18 更新】このノートは鍼灸師の国家試験対策用にまとめています。
はじめに
こんにちは、🐔もむけ@鍼灸師柔道整復師国家試験対策です。
このノートは
【はりきゅう理論】鍼灸施術の治療的作用
についてをまとめてます。
国家試験で出てくる誘導作用や免疫作用などの〇〇作用を8個お伝えします。
結局の所、施術者が〇〇作用を狙って刺鍼施灸したといえばそれが答えになるため最近の国家試験問題では出題されにくくなっています。
鍼灸施術の治療的作用について
生体の組織・器官の機能の異常を調節し、本来の生理的な状態に回復させる作用があり、疾病の状態と治療目的により分ける。
【治療的作用一覧】
▶調整作用
▶誘導作用
▶鎮痛作用
▶防衛作用
▶免疫作用
▶消炎作用
▶転調作用
▶反射作用
順番に説明していきます。
調整作用について
器官や組織に一定の刺激を与えて、その機能を調整する作用のこと。
興奮作用と鎮痛作用の2つがある。
【興奮作用】
▶知覚の鈍麻・消失
▶運動麻痺などの真剣機能の低下減弱
興奮作用は上記のような条件を持つ部位に鍼灸を行い興奮させる作用のことです。
【鎮静作用】
▶疼痛・痙攣
▶興奮状態
鎮痛作用は上記な条件を持つ部位に刺激を与えて鎮静させる作用のことです。
誘導作用について
患部に直接刺鍼施灸するか、または遠隔部に刺鍼施灸して、その部の血管に影響を及ぼし、充血をお越し、患部の血流を調整するものである。
誘導作用も2つあります。
【患部誘導法】
局所の血行障害に対して、直接その幹部に施術して、血流を他の健康部から誘導する方法
【健部誘導法】
局所の充血または炎症などの際に、その部位より少々隔たった部に施術し、血液をそちらに誘導し、患部の血量を調整する方法
誘導作用に関していえば「血液」のコントロールを目的としています。
鎮痛作用について
内因性モルヒネ様物質あるいは加工性抑制などの機序により、鎮痛作用が発現する
鎮痛作用と鎮静作用を間違えないようにしておけばOKです。
防衛作用について
白血球や大貪食細胞などを増加させて、各種疾患の治療機能を促進させ、生体の防御力を高める作用である。
免疫作用について
免疫能を高める作用のこと
消炎作用について
施術により白血球は増加し、施術部位に遊走する。または血流改善により病的滲出物などの吸収を促進させ、体内の防衛能力を高める作用のこと
防衛作用と消炎作用の違いがいまだによくわかりません。
転調作用について
自律神経失調症やアレルギー体質を改善して,体質を強壮にする作用
転調作用は自律神経失調症・アレルギー体質と名称が出ているのでそれらの選択肢が出たらこれを選ぶ可能性が高くなります。
反射作用について
痛み刺激あるいは温熱刺激による反射機転を介して、組織・臓器の機能を鼓舞あるいは抑制する
転調作用と間違わないようにしたらOKです。
特に灸施術の治療で作用が高いもの
灸施術については、施灸後の血液像、血液凝固時間の短縮あるいは循環系に対する作用が認められている
【灸施術の治療的作用】
▶増血作用
▶止血作用
▶強心作用
3つあるので出るかもしれませんね。
無料記事も多数用意しております。 サービス継続のため、 役に立ったと感じましたら未来の受験生のためにもサポートをお願い致します。
