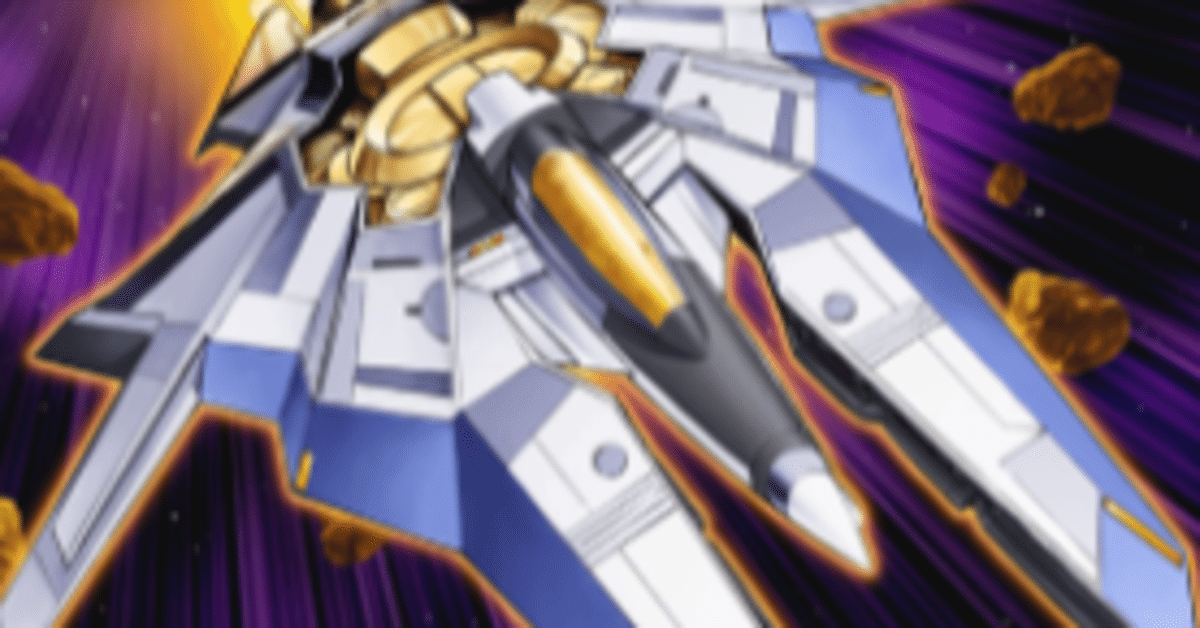
ビクトリーバイパーデッキ開発史
始めに
《ビクトリー・バイパーXX03》
「グラディウスⅤ」の設定資料でのみその存在が言及されている、知る人ぞ知る幻の機体であり、扱えるのはいまだ遊戯王OCGのみという稀有な機体です。
実は私はこのカードを長らく使っており、今も定期的に研究している1枚です。
今回は、今までいくつも試作されてきた構築の中でも、とりわけ安定していた構築を2つほど紹介したいと思います。
この機体のスペック
まずは《ビクトリーバイパー》自体を見てもらいましょう。
たった攻撃力1200という当時ですら下級としては明らかに弱い攻撃力を持ちながら、戦闘破壊をしなければ効果が使えないという矛盾から一見弱そうに見えます。
しかし、このカードの真の力は《オプショントークン》にあります。
常に《ビクトリーバイパー》本体と同じステータスを持つ《オプショントークン》は本体の攻撃力などの数値が変化した時、瞬時に同じように変化していきます。その瞬時の変化によってまるで本体が2回攻撃を行うかのようにふるまうのがこのカードの強みです。
その強みを最大に生かす方法として特に有名なのは《団結の力》と《オネスト》でしょう。
疑似2回攻撃とはいえ、明確に《オプショントークン》が増えているので《団結の力》の上昇値はトークンで攻撃する際のほうが800ポイント上昇します。
《団結の力》自体の上昇値も高水準なため、元の攻撃力の低さを補えて非常に相性がいいわけです。
一方《オネスト》の場合は《オネスト》自体の上昇値の高さと確実な戦闘破壊が肝になっています。《オネスト》と《阿修羅》とのコンボでも分かるように疑似2回攻撃を行えるこのカードとの相性は抜群です。
また、連続で2回攻撃を行えるカードを利用すれば、疑似4回攻撃も可能になり、そういったカードとの相性も良いです。例としては《奇跡の軌跡》でしょうか。
《奇跡の軌跡》は2回攻撃付与+1000アップによって打点を補いつつ連続攻撃を可能にしてくれます。また、このカードの効果を受けているモンスターによる戦闘ダメージは発生しませんが、《オプショントークン》は対象にしたモンスターではないので、生成した《オプショントークン》2体に至っては1000アップの恩恵だけもらって普通に戦闘ダメージを与えることができます。
逆に、あくまで疑似なので、例えば《エアークラック・ストーム》のような他のモンスターが攻撃できなくなるデメリットを持つカードはもろにデメリットが効くのでコンボには使えません。
このように、別のモンスターがステータスをまるっとコピーしている状況を生み出すというこのカードの特殊な点をうまく使っていくのがこの機体の戦術になっています。
ちなみに、この機体の前世代の機体である《超時空戦闘機ビック・バイパー》と《オプション》も別のモンスターがステータスをまるっとコピーしているので、似たようなことが可能です。
《ビクトリーバイパー》は試作機とはいえ次世代機なので、《オプション》をサーチする手間がない点で勝っています。
しかし《オプション》を瞬時にいくつも生み出しやすい点ではかないません。このあたりは次世代機らしく合理的なデザインになった弊害ですね。
その代わりとして、専用サポートカードの《パワーカプセル》が存在し、戦闘を行った際の効果を瞬時に適用して、《オプショントークン》を瞬時に増やしたり、状況によっては攻撃力アップや破壊効果も使えます。
また、トークンなので《オプション》とは異なって4体まで出現できる点も個人的には強調しておきます。
※詳しくは原作(GRADIUS)を確認してください。
この2機は戦術こそ互いに応用できますが、実際には《オプション》の存在や若干のサポートの違いにより似てるようで違う構築を要求されます。
特に一度《オプション》を展開した後に体制を崩されると《オプション》の再構築が難しいため、《ビックバイパー》は一撃で決める確実性を求められます。
一方で自身の効果でトークンを生み出している《ビクトリーバイパー》は究極的には《ビクトリーバイパー》さえ回収すればコンボを再構築できる可能性があります。この点は後述の構築でも出てくる重要なポイントです。
なお《ビクトリーバイパー》の《オプショントークン》も公式の専用トークンカードがしっかり存在しているのでぜひとも使っていきたいですね。

プレイ用も別で持ってます
《ビクトリーバイパー》のステータスはサポートに恵まれており、特にその代表例となるのが《ギアギガントX》の存在です。
このカードの存在によって、《ビクトリーバイパー》はサーチ・サルベージが非常に容易になっています。
ただし、このカードは機械族2体を要求するエクシーズなので、ある程度考えられた展開方法が必要になります。
この《ギアギガントX》をいかにエクシーズするかが、今回紹介するほぼすべての構築において常にキーとなる部分になります。
このカードの出現以前では《シャインエンジェル》《召喚僧サモンプリースト》《ジェイドナイト》といったカードが《ビクトリーバイパー》を呼び出す布石のカードとして利用されていました。今となっては懐かしい面々ですね。
開発史 ー先史遺産編ー
この構築は2014年に成立し、5年ほど使用していたかなり安定した構築です。
この構築の中心となっているのが《先史遺産ネブラディスク》《先史遺産クリスタルスカル》《先史遺産クリスタルボーン》です。
《先史遺産ネブラディスク》はオーパーツカードをどれでもサーチすることが可能ですが、特に《先史遺産クリスタルスカル》とは相性がいい上相互サーチが可能な関係にあり、サーチした《クリスタルスカル》をすぐに捨てて2枚目の《ネブラディスク》をサーチするというどこぞのガジェットのような動きができます。
《先史遺産クリスタルボーン》は召喚権無しで《ネブラディスク》を蘇生でき、2枚目の《ネブラディスク》などから《ギアギガントX》を展開できます。
しかし、このデッキにおいてはそれよりも重要な戦闘補助の役割があります。なぜなら、このカードは召喚権無しで《ゴルゴニック・ガーディアン》を展開できるためです。
このカードはフリーチェーンで攻撃力を0にする効果を持っているので、どんな攻撃力のモンスターが立っていても《ビクトリーバイパー》による戦闘破壊が狙えます。また、このカードを出すために召喚権を使わないおかげで《ビクトリーバイパー》に召喚権を残せて即座に並べられる点も重要です。
このような事情から実際には《クリスタルボーン》は温存したいカードなので、当時のカードプール内を模索し《ギアギガントX》を出すために別の手を用意していました。それは《サイバードラゴンコア》《サイバードラゴンドライ》です。
《サイバードラゴンコア》はサイバー魔法罠のサーチができ、ここからサーチできる《サイバーリペアプラント》は《ビクトリーバイパー》《ネブラディスク》のサーチができるカードになっています。
またその墓地効果によってレベル4である《サイバードラゴンドライ》を展開し、《サイバーリペアプラント》からサーチした《ネブラディスク》を召喚すれば、《ネブラディスク》のサーチ効果を使いつつ《ギアギガントX》の展開までつなげることができます。
以上のような組み合わせを使いつつ、《ビクトリーバイパー》の供給と戦闘補助を可能としていますが、この当時の大きな問題はどうやって勝負を決めに行くかでした。
この構築の場合は戦線維持をしながら複数枚の《団結の力》や《オネスト》を待ち1キルを狙うという選択を取っている状態だったので、《団結の力》を2枚サーチするために《ヴァイロンキューブ》と《ヴァイロン・デルタ》を採用し、上記の《サイバードラゴンドライ》展開を行って《ヴァイロンキューブ》を召喚してシンクロを狙うという戦略を用意していました。
当時は装備魔法のサーチ方法が限られており、このあたりの苦慮がうかがえます。
しかし、理論としてはしっかりしていたため、この先史遺産を用いた構築は長らくベースとなりました。
後に優れた機械族の展開方法として《超重武者テンB-N》とそれをサーチする《超重武者装留イワトオシ》が登場しました。
この2枚の組み合わせは
1.《テンB-N》の効果で《イワトオシ》を蘇生し《イワトオシ》の効果で《テンB-N》に装備。
2.他のレベル4機械族とともに《ギアギガントX》を展開、《イワトオシ》の効果で次の《テンB-N》をサーチ。
という動きが可能なため、特殊召喚できて《ネブラディスク》のような継続供給可能な機械族レベル4というまさにもってこいなカードでした。
後続は持ってこれないもののそのまま《ギアギガントX》を出すこともできるので状況に応じた動きがしやすいのも強みでした。
特に《アームズホール》を使ったターンでも《ギアギガントX》が出せる点は革命的です。
このように《ギアギガントX》を酷使しにいくような構築ですが、実は当時《ギアギガントX》を1枚しか持ってなかったので、ジェネリック《ギアギガントX》として《重装甲列車アイアンヴォルフ》を採用していることもありました。《アイアンヴォルフ》が未登場の時期は《サイバーリペアプラント》でなんとかしていました。
最後に現代カードプールで再構築を試したものをサンプル構築として紹介します。

当時でもシナジーを持つ《サイバードラゴンコア》でしたが、新たに《サイバードラゴンズィーガー》が追加されており、より相性が良くなっています。
《ビックバイパーT301》も手軽に展開でき、特に《ネブラディスク》の打点を3000にしつつメイン2に《ギアギガントX》が展開できる点で相性がいいです。
《アームズコール》とこれをサーチできる《トラップトラック》の追加も大きいです。
《トラップトラック》は《スノーマンエフェクト》や《墓地墓地の恨み》といった強力な戦闘補助罠を即座に使える状態で用意できるのも強みです。
開発史 ーコンテニュー戦法編ー
先史遺産型を開発して以後、1キル重要パーツであった《団結の力》をどう簡単にサーチするかが次なるブレイクスルーになると考え研究していました。しかし、リンク召喚の登場に続き《リナルド》の登場もあったものの、大きな成果がなく研究は難航していました。
そんな折、現在の構築理論を生み出す発端となるカードが登場しました。
それこそが《ビックバイパーT301》です。
前述の現代構築にも投入されているこのカードですが、攻撃宣言時に手札・墓地から特殊召喚でき、さらに《ビクトリーバイパー》の打点を1200も上昇するというまさしく超時空戦闘機の鑑というべき最強サポートカードです。
ちなみにここだけ語らせてほしいのですが、この効果はT301が主人公機として登場する「グラディウスⅤ」の特に印象的な2面および最終面の演出を再現するような効果であり、2機のビックバイパーT301が共闘することで戦力が倍になる(ゲームプレイ上でも凝った演出を取っており、フリーズオプションを悪用して本当に倍にできます。)という、しっかり原作を再現しつつOCGでの強化につなげるというアホみたいに賢いデザインです。
ありえない。何かの間違いではないのか?
さて話を戻しますが、ここで注目してほしいのは上昇数値です。
《団結の力》の上昇効率はモンスター1体につき800です。
《団結の力》は装備モンスターもカウントしますが、そもそも《団結の力》自体を発動していることを考えれば、カード1枚につき800の打点上昇効率と言えます。
それに対して《ビックバイパーT301》を1体展開すると《団結の力》の1.5倍打点が上昇します。
《ビクトリーバイパー》はトークンを生み出すので最終打点は《団結の力》が上回りますが、同じ1枚のカードの消費で見ると《ビックバイパーT301》の打点上昇効率は悪くない数値を出していると考えました。
この考え方をもう一枚にも当てはめました。
その対象となったのは《サイバードラゴンズィーガー》です。
《サイバードラゴンズィーガー》は《サイバードラゴン》を必要とするリンク2のモンスターで、攻撃力2100以上の機械族の攻撃力をバトルフェイズ中にフリーチェーンでさらに2100アップさせる効果を持ちます。
つまり、このカードの打点上昇効率は2枚消費で2100を生み出しているので、《団結の力》がカード2枚で生み出す打点1600より500多く、こちらも同様に悪くない打点上昇効率というのが分かります。
ちなみにこのカードの効果は《ビクトリーバイパー》の元々の数値では適用できませんが、《ビックバイパーT301》を使えばできるようになります。
ここでまとめとして、この《ビックバイパーT301》《ズィーガー》を使った場合と《団結の力》1枚を使って同じカード消費の場合を比較してみます。
《ビックバイパーT301》《ズィーガー》を使う場合、《ビックバイパーT301》1枚と《ズィーガー》を出すための素材2体が必要なのでカードの消費は3枚となります。この3枚消費で打点は1200+2100=3300アップします。
次に同じカードの消費3枚、すなわち《団結の力》1枚とモンスター2体を用意した場合、打点は800×3=2400アップします。ただし、《ビクトリーバイパー》がトークンを生成することで800プラスされるので、最終数値は2400+800=3200アップになります。
さて、数値を比較してみてください。
実は《ビックバイパーT301》《ズィーガー》を使った場合のほうが同じカード消費枚数で《団結の力》1枚を使う場合と比べ、わずか100上回ることができます。
この驚異の事実に気づいたことで、サーチ性・再利用性が低い《団結の力》が不要なのではないかという考えが浮かびました。
3300もアップしていれば《ビクトリーバイパー》の攻撃力は4500に到達しており、あの《オベリスクの巨神兵》すら粉砕する攻撃力です。
また、この4500という数値を生み出すために利用しているのは《ビックバイパーT301》《ズィーガー》というモンスターです。
《ビックバイパーT301》は自身の効果で特殊召喚すると除外されるデメリットがあるものの、《ビクトリーバイパー》と合わせてエクシーズ召喚してしまえば回避でき、もう一度効果が狙えます。
《ズィーガー》は「サイバードラゴン」モンスターであり、特に《サイバードラゴンネクステア》の効果で容易に蘇生できるカードです。
また両者とも光属性・機械族であり、《ビクトリーバイパー》のサーチや展開を補助するカードとサポートを共有できるのです。
こうして誕生したのが、現在の構築理論になります。
端的に言えば、1回でやれないなら何回でも《ビクトリーバイパー》を攻撃力4500にしてぶち抜けばいいというコンテニュー戦法です。
OCGの世界における《ビクトリーバイパー》のコンテニューポイントからの復帰手順を見出したのです。
実際にどういった方法でコンテニューを行うかを紹介します。
盤面の復元には墓地に《ビックバイパーT301》を維持し、手札に《ビクトリーバイパー》と前述の《サイバードラゴンネクステア》を用意する必要があります。
《ビクトリーバイパー》の召喚と《ネクステア》の自身の効果による特殊召喚+蘇生効果で《ズィーガー》を蘇生すれば、あとは攻撃宣言時に《ビックバイパーT301》が復活して復元完了です。
《ネクステア》は場では《サイバードラゴン》として扱われているので、《ズィーガー》を出していない最初のタイミングでも蘇生したモンスターを使って《ズィーガー》をリンク召喚できます。
つまり、蘇生対象さえ用意すれば墓地に《ズィーガー》がいなくても復元方法と全く同じ手札でコンボを始動できます。このカードを使う最も優れたポイントはここです。
《ネクステア》の特殊召喚にはコストが必要なので、必要な手札枚数は3枚です。しかし、コストはモンスターなら何でもOKであることから非常に緩く、専らの焦点は《ビクトリーバイパー》と《ネクステア》の2枚を墓地から回収する方法です。
前述したようにメイン2で《ビックバイパーT301》と《ビクトリーバイパー》でエクシーズ召喚を行うので、この時《ギアギガントX》を出して《ビクトリーバイパー》を取り除きつつ効果を使えば片方は回収できます。
よってもう1枚何か回収する方法を生み出せればいいわけです。
ここで注目した手段が《機関重連アンガーナックル》と《弾丸特急バレットライナー》です。
《アンガーナックル》は手札・場のカード1枚をコストに蘇生でき、相手メインフェイズ中に手札・場のモンスター1枚をコストに《バレットライナー》を蘇生できます。この後半のコストは自身でも可能です。
そして、《バレットライナー》には墓地に送られたエンドフェイズに墓地の機械族1体を回収する効果があります。
この2枚を使うことで《バレットライナー》を相手ターン中の壁にして守りつつ、《バレットライナー》が墓地に行けば機械族を回収するという優秀な回収サイクルを毎ターン生み出すことができます。
仮に《バレットライナー》が生存しても、次の自分のターンで《アンガーナックル》の蘇生コストにすれば1ターン遅れるものの回収効果は発動できます。
《ビクトリーバイパー》のコンボを終えた盤面では、《ビクトリーバイパー》《ビックバイパーT301》《ズィーガー》が存在しています。
このうち、《ビクトリーバイパー》《ビックバイパーT301》を《ギアギガントX》にして1枚を回収し、《ギアギガントX》《ズィーガー》を使って《アンガーナックル》のリンク召喚が可能です。
後は事前に墓地に《バレットライナー》が準備されていれば、上述の回収サイクルによってもう1枚を回収し、《ビクトリーバイパー》と《ネクステア》の回収が完了するというわけです。
ここまで紹介してきましたが、元ネタのSTGに残機があるように、もちろんこの方法は無限ではありません。
この方法を実現するために《ギアギガントX》を利用しているので残りの《ギアギガントX》が使える回数=《ビクトリーバイパー》の残機になります。
それでも、その残機1つごとに攻撃力4500の《ビクトリーバイパー》がトークン含めて実質2回攻撃できるので十分な破壊力があります。
最悪足りなければ《アンガーナックル》《バレットライナー》のサイクルで回収する手も取れるので個人的には問題ないと考えています。
また、個人的にこの戦法が優れていると考えている点は、やはりこのコンボに使われているパーツが全て機械族モンスターである点です。
《ビクトリーバイパー》《ネクステア》の2枚を手札に、《ビックバイパーT301》《バレットライナー》の2枚を墓地に送る手段を用意できる機械族デッキならどういった形でも対応でき、これらは最低限1枚あれば機能するので動きの基本形は比較的柔軟に構築できます。
《ネクステア》の蘇生対象には《旋壊のヴェスペネイト》が含まれており、ランク4さえ組めれば蘇生対象も簡単に用意できる点もポイントです。
これからも様々な機械族が出るたびに、構築の更新や発展が期待できるという点では大きな可能性を持っていると言えるでしょう。
最後にこの構築でのサンプルとして、実際に現在の構築を紹介します。

かつては《ユニオンキャリアー》によって簡単に《ビックバイパーT301》《バレットライナー》にアクセスできていたのですが、禁止化を受けて特に《バレットライナー》をどうやってサーチするかが鍵になっています。
そこで注目したカードが《クリフォートゲニウス》と《タリホー!スプリガンズ!》となっており、この2枚のコンボによって《バレットライナー》のサーチを狙いつつ、《ギアギガントX》で他のパーツも集めるという形になっています。
《ギガンティック”チャンピオン”サルガス》は《タリホー!》のサーチに必須なカードですが、《ギアギガントX》をバウンスし、再利用するという役割も持ちます。この行為は《ビクトリーバイパー》の残機を増やす行為につながるため非常に大きいです。
《ギアギガントX》を事前準備でも使いたいものの、コンボ内でも利用したいというネックになりやすい部分をカバーしてくれます。
《サルガス》の効果は自身以外のエクシーズが持つ素材が取り除かれても反応できるので、《タリホー!》で展開したレベル4の機械族スプリガンズを素材に《ギアギガントX》をエクシーズ召喚し、サーチ効果を使った後に《ギアギガントX》をバウンスさせます。
このような動きができるので基本的には《サルガス》の展開を狙っていきたいため、メインはその下敷きになる《スプリガンズメリーメイカー》の展開を狙って行く構築になっています。
《サルガス》からもサーチが可能な《セリオンズ”キング”レギュラス》は防御として使いますが、《バレットライナー》との相性が優れており、その点も踏まえた採用になっています。
《スプリガンズインタールーダー》にはエクシーズが離れた時に相手場の全てのモンスターの攻撃力を1000ポイント下げるという効果があるため、《サルガス》をトリガーに《ビクトリーバイパー》でのリーサルを取りやすくするという考えで採用しています。
マシンナーズは《マシンナーズギアフレーム》から1枚で即座に《メリーメイカー》や《クリフォートゲニウス》を生み出せる他、攻防ともに非常に優秀な《マシンナーズカーネル》や墓地効果で機械族回収ができる《機甲部隊の超臨界》の存在が大きく、これらを利用したいため採用しています。
マシンナーズを入れておくと各種効果で手札や場の《バレットライナー》を能動的に墓地に送りやすくなるため、その点も考慮されています。
《サイバードラゴンコア》は現在の構築でも重要なポジションにあり、このカードの召喚からサーチした《サイバーリペアプラント》で《ビクトリーバイパー》or《ビックバイパーT301》をサーチができ、さらに墓地効果によって《ネクステア》をデッキから呼び出せるため、このカードをサーチすると実質上2枚分のサーチが完了できるといえます。
自分の場を空ける必要はありますが、《サルガス》や《カーネル》といった自ら退場しやすいカードが多いため、満たしにくいという事はありません。
最後に
今回は《ビクトリーバイパー》の運用方法・デッキ構築について書きました。
かねてより、《ビクトリーバイパー》に関してはどこかでまとめる機会があっていいと考えていました。
このカードを知る多くのプレイヤーは《ビクトリーバイパー》といえば《オネスト》と《団結の力》だと考えていると思うので、違うアプローチも生み出せているという一石を投じてみたかったのです。
一時期は装備魔法の再利用性が乏しかったものの、昨今は「御巫」の追加によって改善されている可能性があり、《団結の力》を軸とした構築も新たなステージへ到達できるのではないかと考えています。
御巫の場合《ベアトリーチェ》の展開が容易なため、《ビックバイパーT301》も用意でき、天使族サポートの最有力候補である《祝福の教会-リチューアルチャーチ》や《サイバー・エンジェルー弁天》が組み込みやすいため、《オネスト》のサーチ・サルベージがしやすい環境を作れるかもしれません。試したわけではないですが、かなり可能性は感じております。
今回は番外編的な記事になりましたが、たまにこういう記事も書いていくかもしれません。
紙では様々なコンセプトのもとデッキを組んだりしているのでネタはなくはないんですよね・・・。
(代表例:異世界転生ヒーエリ、男子モンスター禁制エクソシスター)
【水属性運用実録】や【医学会報告書】も不定期ですが順次更新していきますので、今後ともよろしくお願いします。
それでは長文読んでいただきありがとうございました。
また次回の記事でお会いしましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
