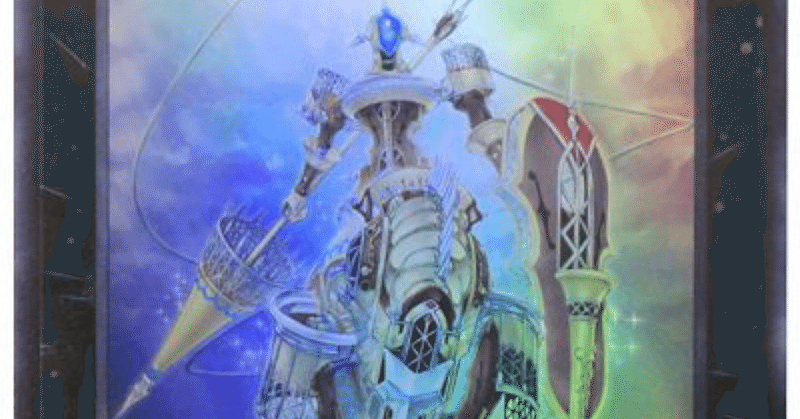
【ティアライロオルフェゴール】について(マスターデュエル2023.7.13〜)
皆さん初めましての方は初めまして、そうでない方は前回までの記事を読んでいただきありがとうございます。その辺の決闘者の衣玖(いく)と申します。
今回記事にするのは、会社の同僚とデュエルしている間に生まれた謎のデッキ【ティアライロオルフェゴール】です。
あらかじめ書いておきますが、2023.7.13〜のマスターデュエルのリミットレギュレーションでのみ使用でき、同じ構築を遊戯王OCGあるいは遊戯王TCGですることはできないので留意してください。
また、半月後には組めなくなっている可能性もあります。
そして制限時間900秒のルームマッチで使用し、《増殖するG》を使った相手のデッキを枯らすためにおよそ450秒消費したため、ランクマッチに持ち込むことも非推奨です。
身内でわいわいやる時にだけお使いください。
それではデッキレシピを見ていきます。
デッキレシピ

デッキコンセプトは見ての通り、「ティアラメンツ」と「ライトロード」によって高速で墓地を肥やし、「オルフェゴール」展開に繋げることとなります。
《隣の芝刈り》なんか無くても、運さえ良ければ30枚近くデッキを掘ることもできます。
回し方も至極単純で、「ティアラメンツ」と「ライトロード」でデッキを掘り進めた後に「オルフェゴール」の展開をするだけです。
最悪「オルフェゴール」でしか動けないこともありますが、その時はやたらデッキが多いだけの【オルフェゴール】なので何も問題だとありません。
通常の【ティアラメンツ】【ライトロード】【オルフェゴール】では見られない採用枚数のカードもあるため、各テーマのカードの中でも特徴のあるカードを確認しつつ、その他のカードにも触れていきます。
解説するカードは太字で書いておきます。
またEXデッキについては後ほど触れます。
メインデッキ
「オルフェゴール」カード

先に書いておきますが、《宵星の騎士ギルス》以外の「オルフェゴール」カードおよび関連カードは引くこと自体がディスアドバンテージと呼べるほど手札としての質が低いです。
既に【オルフェゴール】を使われている方は理解できると思いますが、念のため書いておきます。
以下が採用している「オルフェゴール」カードおよび関連カードになります。
×2 《宵星の騎士ギルス》
×2 《オルフェゴール・ディヴェル》
×2 《オルフェゴール・スケルツォン》
×2 《オルフェゴール・トロイメア》
×2 《星遺物-『星杖』》
×1 《オルフェゴール・カノーネ》
×2 《オルフェゴール・バベル》
×1 《オルフェゴール・プライム》
×1 《オルフェゴール・クリマクス》
《宵星の騎士ギルス》

【オルフェゴール】の初動札であり必須カードです。
①の効果で着地時に墓地肥やししながら、条件が揃っている場合にはチューナーとなります。
②の効果との併用は難しいですが、発動できれば他のカードの補助が無くとも《オルフェゴール・ガラテア》へアクセスできます。
現在のマスターデュエルでは準制限カードに指定されており、マスターデュエルで【オルフェゴール】を握る利点のひとつとなっています(遊戯王OCGでは制限カードのため)。
このことから2枚積みは必須です。
枚数が増えたことでやれることも増え、《オルフェゴール・ディヴェル》から2枚目を引っ張ることでレベル8のSモンスターへ繋ぐこともできるようになりました。
これは《終末の騎士》だけが準制限カードとなった遊戯王OCGではできないことであり、単純に墓地肥やしからの展開という点では同じであるものの、「オルフェゴール」の名を持つことが利点となるため《終末の騎士》の上位互換として活躍します。
《星遺物-『星杖』》

【オルフェゴール】の中では引くと困るため忌み嫌われていますが、必須カードのため抜けない困ったちゃんです。
通常【オルフェゴール】では絶対に引きたくないことに加えて、ピン挿しでも《オルフェゴール・ガラテア》から使い回せることからピン挿しが基本となっています。
しかしデッキを厚くしたことに加えて「ティアラメンツ」カードを採用したことで、ランダムな墓地肥やしでも必ず墓地へ落とせるようにあえて2枚の採用に踏み切りました。
手札に来た場合は《ダーク・グレファー》《ティアラメンツ・シェイレーン》《警衛バリケイドベルグ》などのコストや効果、あるいは《壱世壊に澄み渡る残響》などで墓地へ送ることで処理します。
2枚引いた時は知りません。
なお、《星鍵士リイヴ》を採用していないため墓地に温存しておく必要もありません。
素直に「オルフェゴール」モンスターの帰還のために使用して大丈夫です。
ちなみに、『私は「オルフェゴール」の仲間です』と言わんばかりの効果ですが、こいつ自身は「オルフェゴール」ではありません。
《オルフェゴール・バベル》でスペルスピードが上がることも、《オルフェゴール・スケルツォン》で蘇生することも、「オルフェゴール・カノーネ》で手札から吐き出すこともできません。
だから引くと困るんですね。
《オルフェゴール・カノーネ》

「オルフェゴール」の手札から特殊召喚する担当です。
《宵星の騎士ギルス》とは異なりデフォルトでチューナーとなっており、レベル1、攻撃力1000以下ということで各種リンク1からの起点ともなるカードですが、リンク1は採用していません。
このデッキにおけるこのカードは《琰魔竜 レッド・デーモン・アビス》のS素材になることに価値があります。
人によっては採用すらしないこのカードですが、割とどこからでも飛び出てくるという強みを活かしてピン挿しという形で採用しています。
引いてしまった場合でもそれなりに召喚権は余るので適当に召喚するといいでしょう。
《オルフェゴール・バベル》

「オルフェゴール」モンスターの効果のスペルスピードを2に引き上げるというトンチキ効果で【オルフェゴール】を環境クラスまで押し上げた、狂ったフィールド魔法です。
さらに自力でサルベージまでできます。
《オルフェゴール・ガラテア》によりデッキから直接セットし、墓地へ送られても自力で使い回せることから、純正【オルフェゴール】においても基本的にはピン挿しとなるカードです。
ではなぜこのデッキでは2枚も積まれているかというと、自身をサルベージする効果が墓地へ送られたターンに使用できないためです。
ランダムな墓地肥やしによってデッキのおよそ半分が削れるため、何の前触れもなく平気で墓地に直行することもザラです。
改めて書きますが、このカードの存在が【オルフェゴール】を環境クラスまで底上げしてきました。
言い換えると、このカードが無い場合「オルフェゴール」モンスターは前時代的な起動効果しか持たないガラクタ集団と化すのです。
このことから1枚でもデッキに眠っていれば《オルフェゴール・ガラテア》から引っ張り出せるため2枚の採用に踏み切りました。
なお2枚とも墓地へ落ちた場合は《宵星の機神ディンギルス》を相手ターンに蘇生させ妨害として機能させる従来の【オルフェゴール】の動きができないため、素直に「ティアラメンツ」に妨害の役割を担わせてください。
【オルフェゴール】としての妨害ができるのは、このカードをサルベージできるようになる次のターン以降です。
「ティアラメンツ」カード

現環境でも活躍する、墓地肥やしに長けた「ティアラメンツ」カードを利用することで、デッキを無理やり回していきます。
採用カードの総数が「オルフェゴール」よりも多いですが、あちらは元々少数精鋭という名の人材不足なので問題ありません。
以下が採用している「ティアラメンツ」カードおよび関連カードになります。
×2 《ティアラメンツ・メイルゥ》
×2 《ティアラメンツ・ハゥフニス》
×2 《ティアラメンツ・シェイレーン》
×3 《ティアラメンツ・レイノハート》
×3 《壱世壊を劈く弦声》
×1 《壱世壊に渦巻く反響》
×1 《壱世壊を揺るがす鼓動》
×1 《壱世壊=ペルレイノ》
×1 《壱世壊に軋む爪音》
×1 《壱世壊に奏でる哀唱》
×1 《壱世壊に澄み渡る残響》
数が多いので、モンスターと魔法・罠カードに分けて見ます。
「ティアラメンツ」モンスター

積めるだけ積んでいます。
積めば積むほどお得ですからね。
真面目に話すと、一番大事なのは《ティアラメンツ・シェイレーン》です。
引いてしまった「オルフェゴール」や《現世と冥界の逆転》に関するカード群を処理しながら墓地肥やしを加速させることのできる、強力な初動札となります。
次点で重要なのは《ティアラメンツ・レイノハート》です。
《ライトロード・セイント ミネルバ》のX素材になることに加え、召喚から《ティアラメンツ・キトカロス》にアクセスできるため、こちらも初動札として強力な存在になります。
残りの2枚は雰囲気で使っていきましょう。
レベルも合わないので適当に処理して融合素材にします。
「ティアラメンツ」魔法・罠カード

便宜上《壱世壊=ペルレイノ》もここに含めます。
何よりも墓地肥やしを加速させるため、《壱世壊を劈く弦声》は有無を言わさず3枚積み確定です。
手札を捨てるために出した《警衛バリケイドベルグ》でエンドフェイズに拾うこともできるため、落ちても引いても使える神カードとして君臨します。
制限カードの2枚は特に言うことはありません。
残りの「ティアラメンツ」魔法・罠カードですが、いずれも墓地に落ちた場合に同名カードで重複しないことを理由にピン挿ししています。
それぞれ《おろかな埋葬》《サイクロン》《月の書》《神の宣告》などの類似カードと比較すると、墓地へ落ちた場合のメリット効果が存在する上で墓地へ送る効果を「オルフェゴール」カードに適用することで次へ繋げることもできるため、各種ピン挿しという結論に至りました。
「ティアラメンツ」がサポートカード込みで対応力に溢れたカード群であることに非常に感謝しています。
「ライトロード」カード

「ティアラメンツ」と同様に墓地肥やしに長けたテーマです。
しかしその墓地肥やしのスタイルは若干異なるため一応触れておきます。
以下が採用している「ライトロード」カードおよび関連カードになります。
×3 《ライトロード・ビースト ウォルフ》
×3 《ライトロード・アサシン ライデン》
×2 《ライトロード・アーチャー フェリス》
×3 《ソーラー・エクスチェンジ》
×3 《光の援軍》
《ライトロード・ビースト ウォルフ》

古より【ライトロード】を支えてきた主力モンスターです。
どんな手段でもいいのでデッキから墓地へ送られた時に自己再生する、強制発動の誘発効果を持っています。
各種素材に使えるのはもちろんのこと、攻撃力も2100とやや高いためLPを削りにいくために殴ることも視野に入れられます。
ただし必ず蘇生してしまうことから、うっかり墓地へ落ちて展開の計算が狂うこともあります。
持ち前のアドリブ力でなんとか軌道修正しましょう。
《ライトロード・アーチャー フェリス》

登場以降、【ライトロード】の潤滑油として活躍してきたカードです。
こちらは《ライトロード・ビースト ウォルフ》と異なり、モンスター効果でデッキから墓地へ送られた時に強制効果で自己再生します。
「ライトロード」関連カードの中には魔法・罠カードの効果で墓地を肥やすものもあり、このデッキでは《壱世壊を劈く弦声》でも墓地を肥やせます。
そのようなカードに反応しないことがネックとなるカードです。
なお本体スペックとしては、レベル4チューナーのため各種素材に使いやすく、相手モンスターを破壊してからデッキトップを3枚落とす効果も持ち合わせているため使い勝手が良いです。
優秀ではあるものの《ライトロード・ビースト ウォルフ》ほどフットワークが軽くないことは覚えておきましょう。
《光の援軍》

説明不要の「ライトロード」用サーチカードです。
説明不要と書きましたが、説明が要るからここに挙げているわけですね。
このカードはやや異質で、デッキトップ3枚を落とすことがコストであり、カード効果としてはサーチしか行わない点が特徴です。
つまり《ライトロード・アーチャー フェリス》はおろか、「ティアラメンツ」カードも一切反応しないということになります。
運用上はこれに留意してください。
なおデッキの主役である「オルフェゴール」は墓地に落ちれば何でもいいので1ミリも関係ありません。
《現世と冥界の逆転》に関するカード

公式がこんな感じの名称で呼んでいた、通称「イシズカード」です。
漫画『遊☆戯☆王』およびアニメ『遊戯王デュエルモンスターズ』にて、バトルシティ編のボスであるマリクの姉イシズ・イシュタールが使用したカード群のリメイクであることからこのように呼称されます。
もはや説明が要るかはわかりませんが一応採用カードを記しておきます。
×2 《古尖兵ケルベク》
×1 《古衛兵アギド》
×1 《祝神像ケルドウ》
×1 《剣神官ムドラ》
前者2枚は手札・デッキから墓地へ送られた場合にお互いのデッキトップを5枚ずつ墓地へ送れる誘発効果を、後者2枚はフィールド・墓地の自身を除外することでお互いの墓地のカードを合計3枚まで選択してデッキに戻せる効果を持ちます。
汎用性の高いカード群のため身をもってその強さを体感している人も多いとは思いますが、このデッキでも当然のように墓地肥やしの加速のために採用しています。
特に前者2枚は《光の援軍》で落ちても効果を発動できる点が優秀であり、手札からコストで吐いても墓地肥やしできることから「ティアラメンツ」をも凌ぐ汎用性を誇ります。
その他のカード

上記のいずれにも該当しなかったカード群です。
概ね「オルフェゴール」+「ティアラメンツ」+「ライトロード」で完成しているため、書くことはあまり多くありません。
以下が採用しているその他のカードになります。
×2 《フォトン・スラッシャー》
×1 《終末の騎士》
×1 《ダーク・グレファー》
×1 《妖精伝姫-シラユキ》
×2 《隣の芝刈り》
×1 《増援》
《フォトン・スラッシャー》

自分フィールドにモンスターが不在であれば特殊召喚でき、他にモンスターがいると攻撃できない各種素材のために生まれたカードです。
最近【オルフェゴール】に入れるのが流行ってるらしいですね。
目的としては、《増殖するG》を打たれた場合あるいは手札事故を起こした場合に《No.41 泥睡魔獣バグースカ》で止まりお茶を濁すためです。
なおこのデッキでは《ライトロード・セイント ミネルバ》のX素材に化けました。
というものの、よほどデッキの中身が偏ってさえいなければ一度の墓地肥やしから連鎖する形で墓地肥やしが続くことも多く、《ティアラメンツ・キトカロス》にさえ繋がればさらに8枚の墓地肥やしまで狙えることから、立派な起点作りのカードとなったのです。
無論、無理に動かずに《オルフェゴール・ディヴェル》などと一緒に《No.41 泥睡魔獣バグースカ》の素材になることもあります。
特に再利用する予定の無い光属性ということで《混沌魔龍 カオス・ルーラー》のコストで除外する光属性の筆頭でもあり、肉から骨までその全てを素材にすることができます。
初手で来るとまあ強いカードですが、必ずしも初手に来なくてもいいため2枚の採用としています。
《妖精伝姫-シラユキ》

無限に自己再生する墓地肥やしデッキのお供です。
60枚デッキでは2〜3枚採用されることが多いですが、このデッキではピン挿しに留まっています。
理由としては3つあります。
まず1点目として、光属性である点です。
何度も自己再生できる強みこそありますが、一度「オルフェゴール」の効果を使用し始めると今後の展開が闇属性のみに縛られるため、そのターン中は自己再生できなくなります。
この縛りは相手ターンに《オルフェゴール・スケルツォン》の効果を使用しても発生することから、その後の妨害札としても機能しなくなります。
若干の噛み合いの悪さから、このカードはほとんど妨害として期待していません。
次に2点目として、引いてしまった場合は召喚権を割く必要がある点です。
ここまでほとんど触れてきませんでしたが、実は召喚権をどこに割くかが大事なデッキとなっています。
というのも召喚権の消費は明確な弱点のひとつであり、ここに相手の誘発が飛んでくることも稀ではありません。
そんな急所とも呼べるタイミングであるにも関わらず、アドバンテージを稼げないこのカードを安易に出すことはそのまま負けに繋がる恐れがあるのです。
ただし後攻であれば《フルール・ド・バロネス》などの妨害持ちを確実に消費させられることから、一概に悪手とは呼べません。
ただ先攻では欲しくない、後攻でも場面を選ぶという感じですね。
最後に3点目として、大量の墓地リソースを消費してしまう点です。
「ライトロード」はともかく、他のカード群は墓地に落ちていること自体がメリットになります。
墓地からの再利用も前提に考えると、安易に除外することはリソース切れからの負けに繋がりかねません。
そのため大量に墓地肥やしをしていても、自己再生できるのは1回か2回が限界です。
以上の3点によりピン挿しという結論に至りました。
複数枚積むのも悪くはないと思いますが、筆者は過剰だと考えています。
《増援》

説明不要のサーチカードです。
しかしサーチ先が多いため一応書いておきます。
×3 《ティアラメンツ・レイノハート》
×3 《ライトロード・アサシン ライデン》
×2 《フォトン・スラッシャー》
×1 《終末の騎士》
×1 《ダーク・グレファー》
いずれも起点となるカード達のため、手札に合わせたモンスターをサーチしましょう。
エクストラデッキ

一般的な【オルフェゴール】とは異なったEXデッキの構成になります。
一応パーツ分けして確認してみましょう。
「オルフェゴール」カード

以下が採用している「オルフェゴール」カードになります。
×1 《宵星の機神ディンギルス》
×1 《オルフェゴール・ガラテア》
これだけです。
まず根本的な問題としてEXデッキの枠がありませんでした。
《オルフェゴール・ガラテア》の2枚目はおろか、《オルフェゴール・ロンギルス》すらも採用を検討して不採用になったほどです。
それほどまでにEXデッキが激戦区だった理由は後述します。
「ティアラメンツ」カード

以下が採用している「ティアラメンツ」カードになります。
×1 《ティアラメンツ・キトカロス》
×1 《ティアラメンツ・ルルカロス》
×1 《ティアラメンツ・カレイドハート》
EXデッキに入れられる「ティアラメンツ」が全員集合していますが、他のテーマ外の融合モンスターは一切採用されていません。
これも枠の都合です。
マジで入る余地がありませんでした。
「ライトロード」カード

以下が採用している「ライトロード」カードになります。
×1 《ライトロード・セイント ミネルバ》
×1 《ライトロード・ドミニオン キュリオス》
総数が少ないこともありますが、《ライトロード・セイント ミネルバ》の2枚目を採用する余地もありませんでした。
EXデッキから出てくる墓地肥やし要員のため、隙を見て出して墓地肥やしを加速させましょう。
シンクロモンスター

はい、こいつらがEXデッキ圧迫の原因です。
以下が採用されているSモンスターになります。
×1 《PSYフレームロード・Ω》
×1 《混沌魔龍 カオス・ルーラー》
×1 《琰魔竜 レッド・デーモン・アビス》
そもそもこのデッキの着想は「《オルフェゴール・カノーネ》でS召喚したいな」というところから始まっています。
さらにレベル4チューナーになれる《宵星の騎士ギルス》の存在もあり、「《混沌魔龍 カオス・ルーラー》で墓地を肥やしてから《琰魔竜 レッド・デーモン・アビス》にすればいいや」というオリジナリティの欠片もない結論に辿り着いたのです。
また、爆速で墓地を肥やして《オルフェゴール・カノーネ》を調達するために「ティアラメンツ」を、《混沌魔龍 カオス・ルーラー》の自己再生のコストの捻出のための光属性かつレベル4チューナーとして「ライトロード」を見繕った結果、それぞれのEXデッキのカードの採用枠が大幅に狭まってしまいました。
ただし得られた対価は非常に高く、以下のようなパターンが散見されました。
・《ティアラメンツ・シェイレーン》を手札に加えて手札の「オルフェゴール」を処理しながら「ティアラメンツ」展開が始まる
・《ライトロード・ビースト ウォルフ》が落ちることでフィールドにレベル4が揃い《ライトロード・セイント ミネルバ》からの墓地肥やしが始まる
・他の闇属性モンスターを並べて《ライトロード・ドミニオン キュリオス》のL素材になる
・狙った通り《琰魔竜 レッド・デーモン・アビス》が場に着地する
デッキを5枚も掘れ、手札に加えることさえも任意のため幅広く活躍できる強力なカードでした。
ついでに採用した《PSYフレームロード・Ω》も除外した「オルフェゴール」カードの再利用に一役買っていますが、こいつは別のレベル8シンクロでいい気がします。
代替案のある人は意見ください。
エクシーズモンスター

以下が採用されているXモンスターになります(紹介済みのものは除く)。
×1 《No.41 泥睡魔獣バグースカ》
お茶濁し用のカードです。
手札事故を起こした際や《増殖するG》を突っぱねられそうにない場合は出しておきましょう。
リンクモンスター

以下が採用されているLモンスターになります(紹介済みのものは除く)。
×1 《I:Pマスカレーナ》
×1 《警衛バリケイドベルグ》
×1 《トロイメア・フェニックス》
×1 《トロイメア・ユニコーン》
【オルフェゴール】ではよく見るLモンスターですね。
一応《警衛バリケイドベルグ》についてだけ触れておきましょう。

闇属性Lモンスターであるため「オルフェゴール」モンスターの効果発動後の誓約をすり抜け、L召喚時に手札を1枚捨てることができます。
適当なモンスター2体から手札の「オルフェゴール」カードを処分できるということですね。
そのまま生きてターンを返すことはほぼ無いため魔法カードへの耐性付与はほとんど役に立ちませんが、エンドフェイズ時に永続魔法かフィールド魔法をサルベージできるため《壱世壊を劈く弦声》や《壱世壊=ペルレイノ》を次のターンに使うこともできます。
マスターデュエルでは処理するか否か聞かれるので忘れることはないと思いますが、墓地にそれらのカードが落ちている場合は回収できてラッキーと思っておきましょう。
このデッキの強み/弱み

デッキを運用する上で、やはり強い部分と弱い部分を意識しておくことは重要でしょう。
大雑把かつありきたりなことしか書きませんが、もしこのデッキを使おうと考えている人がいるなら参考になれば幸いです。
このデッキの強み

まず、墓地肥やしの速度が尋常じゃないです。
デッキの半分が1ターンで消し飛びます。
《隣の芝刈り》なんて使わずとも相手のデッキよりもデッキが薄くなることもザラです。
もちろん墓地で発動する効果も連鎖的に発動するため、連鎖がストップするまでは「ティアラメンツ」と「ライトロード」でデッキを掘り続けることになります。
連鎖が止まってもEXデッキの「ライトロード」モンスターを出すことで継続できる可能性があるため諦めないでください。
そうして出来上がる盤面としては、
《ティアラメンツ・ルルカロス》
《琰魔竜 レッド・デーモン・アビス》
《I:Pマスカレーナ》
《オルフェゴール・バベル》
《壱世壊に軋む爪音》
さらに墓地に
《オルフェゴール・スケルツォン》
《宵星の機神ディンギルス》
のような形になります。
《壱世壊に軋む爪音》から「ティアラメンツ」水族モンスターを落とすことで《ティアラメンツ・カレイドハート》に繋げてさらなる妨害を足すこともできます。
これ「ティアラメンツ」が強いだけでは?
極端な手札事故もあまり発生せず、とりあえずレベル4を2体揃えられればデッキ掘りが開始できるため、どうすればデッキを掘れるかを最優先でプレイしていきましょう。
また、「ティアラメンツ」魔法・罠カードがカバーする範囲が広いため、《ティアラメンツ・キトカロス》さえ立てられれば欲しいカードをサーチできます。
対象耐性&破壊耐性を持つようなモンスターが存在していても《宵星の機神ディンギルス》による対象を取らない墓地送りが通用するため、採用カードとしては非常に多くのデッキを見ることができることもこのデッキの強みです。
このデッキの弱み

会社の同僚にどう足掻いても勝てなかったのは、《次元の裂け目》《マクロコスモス》のような全体除外カードや、《威光魔人》《虚無魔人》のような封殺系モンスターです。
永続の全体除外カードについては《壱世壊を揺るがす鼓動》で、封殺系モンスターについては《壱世壊に軋む爪音》や《壱世壊に奏でる哀唱》で対処できないこともないですが、それぞれピン挿しのためピンポイントで引けているかは別問題です。
また《トロイメア・フェニックス》や《トロイメア・ユニコーン》という解決札も用意してありますが、手札のみでそれらを出して一方的にディスアドバンテージを負う形になるため極力避けたいです。
墓地に依存した展開型のデッキでは共通した弱点ですが、凄まじい速度で墓地を肥やすことが基本となるこのデッキでは、より顕著にブッ刺さることとなります。
あとは高打点&超耐性のカードにも弱いです。
《宵星の機神ディンギルス》という対象を取らない墓地送りが可能な高品質除去が存在するため完全な詰みになることは少ないですが、無効効果まで所有している《ヴァレルエンド・ドラゴン》は割とどうしようもないレベルで詰んでいます。
別のカードで効果を釣り、確実に《宵星の機神ディンギルス》の効果を通すことを目指しましょう。
最後に

以上が筆者の【ティアライロオルフェゴール】となります。
適当にささっと組んでから一部を組み替えたもののため、まだ改善の余地はあると思います。
基本思想の《オルフェゴール・カノーネ》でS召喚したい、という欲望さえ捨て去れば、EXデッキの枠を確保できるため柔軟性を確保できる可能性もあるでしょう。
即席デッキであり改善の余地があるため、今回はおまけの不採用カードのコーナーはありません。
皆さんも好きなカードや気になるカードで是非デッキを組んでみましょう。
いつもとは違う、新鮮な気持ちで遊戯王に向き合うことができるでしょう。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
