
【遊戯王】偶然カテゴリ入りしたカード群
皆さん初めましての方は初めまして、そうでない方は前回までの記事を読んでいただきありがとうございます。その辺の決闘者の衣玖(いく)と申します。
今回は雑学ネタということで、意図しない形でカテゴリ入りしたカード群について解説します。
リメイクあるいは派生カードとして作られたものは別とし、偶然にもカテゴリの定義内に収まることからカテゴリに属することになったカードのみに絞って解説していきます。
あ行
「ヴェノム」モンスター

既存の「ヴェノム」モンスターに仲間入りしたカード群です。
《スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン》
《グリーディー・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン》
《覇王眷竜スターヴ・ヴェノム》
《覇王紫竜オッドアイズ・ヴェノム・ドラゴン》
《スターヴ・ヴェノム・プレデター・フュージョン・ドラゴン》
元々はアニメ『遊戯王GX』でプロフェッサー・コブラが使用したモンスターを指定したカード群でしたが、爬虫類族を指定していなかったことから《スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン》が偶然にもカテゴリ入りし、その派生モンスターも仲良くカテゴリ入りしました。
最も大きな恩恵としては《ヴェノム・スワンプ》による弱体化を受けることなく戦線を維持できることでしょうか。
それまでの「ヴェノム」モンスターは全体的に攻撃力が低く《ヴェノム・スワンプ》の弱体化があっても戦闘破壊されやすいことが欠点でしたが、それを補ってくれることでしょう。
ただしメインデッキに入る闇属性の「ヴェノム」モンスターは《ヴェノム・サーペント》しかいないので構築には気をつけましょう。
「エレキ」カード

新たに登場した「エレキ」に含まれたカードおよび、偶然「エレキ」に仲間入りしたカード群です。
《エレキッズ》
《エレキテルドラゴン》
《エレキック・ファイター》
《電送擬人エレキネシス》
S召喚を行う雷族のテーマとして「エレキ」は登場しましたが、カード名の指定のみだったことから偶然にも何枚かのカードが意図しない形でカテゴリに属することとなりました。
《エレキカンシャ》や《エレキングコブラ》の効果でサーチでき、《エレキトンボ》の効果でリクルートでき、《エレキーウィ》や《エレキリギリス》の効果で守ることができるなど受けられる恩恵はやや多いですが、直接攻撃を主体とする【エレキ】に採用できるカードはほぼありません。
逆に偶然「エレキ」に属することになったカードを使用する際はサポートカードを駆使することで強みを引き出すことができるでしょう。
か行
「ガーディアン」カード

新たに登場した「ガーディアン」に含まれたカード群および、偶然「ガーディアン」に仲間入りしたカード群です。
《ゲート・ガーディアン》
《メタル・ガーディアン》
《ローガーディアン》
《王室前のガーディアン》
《ピクシーガーディアン》
《守護者スフィンクス》
《守護天使 ジャンヌ》
《ガーディアン・スタチュー》
《ロストガーディアン》
《ナチュル・ガーディアン》
《コアキメイル・ガーディアン》
《インフェルニティ・ガーディアン》
《ガーディアン・オブ・オーダー》
《トラスト・ガーディアン》
《牙城のガーディアン》
《先史遺産トゥーラ・ガーディアン》
《巨竜の守護騎士》
《ディメンション・ガーディアン》
《ガーディアンの力》
《ファイアウォール・ガーディアン》
《黄金郷のガーディアン》
《ガーディアン・スライム》
《王家の守護者スフィンクス》
アニメ『遊戯王デュエルモンスターズ』でラフェールが使用したモンスターをサポートする目的で作られたカードである《ウェポンサモナー》の効果でサーチできるカード群でしたが、「ガーディアン」という単語が扱いやすいことから全く関係ないカードまでカテゴリ入りしました。
カテゴリ自体が《ウェポンサモナー》でサーチできること以外に共通点が無いため、《ゴヨウ・ガーディアン》や《ガーディアン・キマイラ》はカテゴリに含まれません。
魔法・罠カードもサーチできますが、リバース効果であることからサーチ自体が非常に遅く、【ガーディアン】を組むことは難しいでしょう。
ラフェールのファンの方は頑張って組んでください。
「ガジェット」モンスター

新たに登場した「ガジェット」に含まれたカードおよび、偶然「ガジェット」に仲間入りしたカード群です。
《ガジェット・ソルジャー》
《ガジェット・ドライバー》
《ガジェット・トレーラー》
《ガジェット・アームズ》
《サイバース・ガジェット》
《ガジェット・ゲーマー》
本来は原作『遊☆戯☆王』およびアニメ『遊戯王デュエルモンスターズ』で武藤遊戯が使用した《グリーン・ガジェット》を筆頭とする3色の「ガジェット」を指す俗称であり、《起動兵士デッドリボルバー》の登場によってその攻撃力をアップさせることができる存在としてカテゴリ化しました。
そのため《○○(色)・ガジェット》という名称のモンスター以外は全て偶然カテゴリ入りしたということでここに分類しました。
《ガジェット・ソルジャー》と《サイバース・ガジェット》以外の「ガジェット」モンスターはは「D(ディフォーマー)」のサポートカードとして登場しており、意図して命名されていると考えられますが、肝心の「D(ディフォーマー)」に「ガジェット」を指定するカードが無いため特に意味のない命名となっています。
《○○(色)・ガジェット》を中心とした【ガジェット】はかつて環境を席巻したこともあり、アドバンテージの稼ぎ方やリソースの管理などのお手本のようなデッキとして初心者に薦めやすいデッキです。
「カラクリ」カード

新たに登場した「カラクリ」に含まれたカードです。
《カラクリ蜘蛛》
S召喚を主体とするテーマである「カラクリ」に偶然加わりましたが、共通効果から命名規則まで全てが一切関係無い存在となっています。
偶然にも種族および属性が「カラクリ」と合致していたため、仮にそれぞれの指定があっても仲間入りするという不思議なカードとなりました。
【カラクリ】に採用する必要性はありませんが、効果自体は全く無意味なものではないことから、受けるダメージや相手の属性の問題をクリアすれば採用の余地はあるでしょう。
「カラクリ」のサポートカードを使わなければおおよそ《ヴァンパイア・キラー》に軍配が上がると思われますが、《カラクリ蜘蛛》に愛着のある人はデッキを考えてみましょう。
「ギャラクシー」カード

新たに登場した「ギャラクシー」に含まれたカード群および、偶然「ギャラクシー」に仲間入りしたカード群です。
《No.83 ギャラクシー・クィーン》
《ギャラクシー・ウェーブ》
《ギャラクシー・クィーンズ・ライト》
《超次元ロボ ギャラクシー・デストロイヤー》
《No.42 スターシップ・ギャラクシー・トマホーク》
《ギャラクシーサーペント》
《ギャラクシー・サイクロン》
アニメ『遊戯王ZEXAL』で天城カイトが使用したカード群であり、当初は「フォトン」使いとして登場していたものがいつの間にか「ギャラクシー」までテーマ化していました。
そのためカイトが使用することを前提としていない「ギャラクシー」カードをここに記載しています。
このうち半数近くは同作品にて登場した奥平風也の使用したカードであり、ある程度意識したのかもしれませんが偶然名前が合致したものと思われます。
サポートカードが豊富である【ギャラクシー】にXモンスター以外のそれぞれのカードを組み込むことは容易であり、Xモンスターでもサポートを受けられることから活躍させることはできるでしょう。
それぞれのカードを使う際には「ギャラクシー」の名前を持つことを利用した構築を意識してみるといいのではないでしょうか。
「幻獣」モンスター

新たに登場した「幻獣」に含まれたカード群および、偶然「幻獣」に仲間入りしたカード群です。
《幻獣王ガゼル》
《有翼幻獣キマイラ》
《幻獣機テザーウルフ》
《幻獣機ドラゴサック》
《幻獣機ハムストラット》
《幻獣機ブラックファルコン》
《幻獣機メガラプター》
《幻獣機レイステイルス》
《幻獣機ウォーブラン》
《幻獣機コルトウィング》
《幻獣機コンコルーダ》
《幻獣機ハリアード》
《幻獣機ブルーインパラス》
《幻獣機タートレーサー》
《幻獣機グリーフィン》
《幻獣機サーバルホーク》
《幻獣機オライオン》
《幻獣機ヤクルスラーン》
《幻獣機エアロスバード》
《幻獣機ライテン》
《幻獣機アウローラドン》
《幻獣王キマイラ》
《幻獣魔王バフォメット》
突如登場した獣戦士族テーマである「幻獣」がカード名のみを指定していたことから偶然にもカテゴリ入りしたカード群です。
大別すると「幻獣機」モンスターと《有翼幻獣キマイラ》を中心としたカード群が巻き込まれています。
「幻獣」をサポートするカードに有意義な効果を持つカードは少ないですが、《幻獣クロスウィング》での打点底上げと《幻獣サンダーぺガス》による戦闘破壊耐性付与は役立つ場面があるかもしれません。
特に後者は「幻獣機トークン」を破壊から守ることで「幻獣機」モンスター全体を守れるため、戦闘が主体となる環境では頼りになるでしょう。
なお獣戦士族モンスターの「幻獣」を主体とする【幻獣】は現環境では力不足感が否めず、エースモンスターである《幻獣ロックリザード》を相手の除去に巻き込む形で特殊召喚してそのバーン効果で勝利を狙う構築が現実的になるでしょうか。
マイナーなカードを使いたい人はデッキを考えてみましょう。
さ行
「サイバー」カード

新たに登場した「サイバー」に含まれたカード群および、偶然「サイバー」に仲間入りしたカード群です。
《サイバー・ボンテージ》
《サイバー・レイダー》
《サイバース・ビーコン》
《サイバーサル・サイクロン》
《サイコ・ギガサイバー》
《電脳エナジーショック》
アニメ『遊戯王GX』に存在する流派である「サイバー流」に属するカードが中心となるテーマですが、その範囲指定に偶然含まれたことからカテゴリ入りしたカード群です。
具体的には「サイバー」魔法・罠カードおよび機械族またはドラゴン族の「サイバー」モンスターになります。
同作品では天上院明日香が「サイバー・エンジェル」およびサイバー・ガールを使用しており、作中のカードで「サイバー」カード全般をサポートするものが登場していることから、現実よりもサポート範囲が広いです。
なお彼女の使用したカードは戦士族か天使族なので、現実では「サイバー」に属さないこととなります。
アニメでもカードでも人気の高いテーマであり、断続的に新規カードが追加されているため、高火力で相手を叩き潰す戦い方が好きな人は組んでみてはいかがでしょうか。
「サイファー」カード

新たに登場した「サイファー」に含まれたカードおよび、偶然「サイファー」に仲間入りしたカードです。
《サイファー・スカウター》
《ストームサイファー》
アニメ『遊戯王ARC-V』で天城カイトが使用した光属性テーマである「サイファー」がカード名のみを指定することから偶然にもカテゴリ入りすることになりました。
基本的に【サイファー】はランク8の《銀河眼の光波竜》をX召喚することが中心のデッキであり、レベル操作も展開もできないこれらのカードをあえて採用する必要はありません。
しかしタイミングはやや遅いものが多いものの、サーチ手段自体はそれなりに豊富なため、これらを使用する際のサポートとして「サイファー」カードを利用するのは悪くないでしょう。
中でも《光波鏡騎士》はステータスが低く墓地へ送られることでサーチ効果が使えるため、相手に送りつけてからこれらのカードで攻撃すれば相手に大きなダメージを与えつつ後続を用意できるため高相性です。
戦士族のため《サイファー・スカウター》の効果が適用される点も大きいですね。
「紫炎」モンスター

新たに登場した「紫炎」に含まれたカードです。
《天下人 紫炎》
後発の「六武衆」に関連したカードとして「紫炎」は登場しましたが、「紫炎」効果モンスターという指定範囲から偶然にもカテゴリ入りすることになりました。
《六武の門》による強化や《紫炎の道場》によるリクルートに対応していますが、同じことは《大将軍 紫炎》にもできます。
罠カードの効果を受けない利点を活かそうにも戦士族ではないデメリットの方が大きすぎて運用が難しく、「紫炎」を活かそうにも「六武衆」の展開力だけでゲームエンドまで持っていけることから活躍は厳しいと言わざるを得ません。
効果面でも《E・HERO ワイルドマン》の方が受けられるサポートカードの種類が非常に多いことから、思い入れのある人でなければ《天下人 紫炎》を輝かせることは難しいでしょう。
「銃士」モンスター

既存の「銃士」モンスターに仲間入りしたカード群です。
《鳥銃士カステル》
《魔鍵銃士-クラヴィス》
現状は《幻銃士》によって与えるダメージの参照元という点でしかカテゴリになっておらず、効果の使用後は「銃士」モンスターが攻撃できなくなることから【銃士】を組む意義はほとんどありません。
《幻銃士》そのものはトークンを生成できる効果を持ちリンク素材としては優秀なカードのため、各種素材にする前に効果を使うことで地味バーンが与えられるでしょう。
無理やり効果を活かすならば【魔鍵】に入れることで《魔鍵砲-ガレスヴェート》などのリリース要員として活躍させることになるでしょうか。
ランク4も比較的出しやすいデッキであることから《鳥銃士カステル》も無理なく組み込めるので、興味のある方は構築を考えてみてください。
「人造人間」モンスター

新たに登場した「人造人間」に含まれたカードです。
《人造人間7号》
《人造人間-サイコ・ショッカー》およびその派生モンスターのみを指定するつもりだったものと思われますが、偶然にもカード名のみを指定していたことからカテゴリ入りすることになりました。
ただし英語版のカード名は最初から《Jinzo #7》であり《人造人間-サイコ・ショッカー》(《Jinzo》)の7号という名称だったことに加えて、種族・属性も《人造人間-サイコ・ショッカー》と同じのため、いずれカテゴリ入りすることは必然だったのかもしれません。
肝心の効果面では《人造人間-サイコ・リターナー》と同じダイレクトアタッカーであり、あちらは墓地へ送られることで《人造人間-サイコ・ショッカー》を蘇生できるため基本的にはあちらに軍配が上がります。
ただしこちらは攻撃力500であることから《機械複製術》に対応し、豊富な機械族のサポートカードを駆使して3体で直接攻撃を仕掛けるという戦法が取れます。
《人造人間-サイコ・ジャッカー》によるサーチや《サイキック・ウェーブ》による墓地肥やしなどを駆使して相手のライフポイントを刈り取りましょう。
「スクラップ」カード

新たに登場した「スクラップ」に含まれたカードです。
《スクラップ・リサイクラー》
S召喚を行う地属性テーマとして登場した「スクラップ」ですが、機械族らしい見た目とは裏腹に種族が統一されておらず、カード名のみを指定していたことから偶然にもカテゴリ入りすることになりました。
当初は機械族サポートである《スクラップ・リサイクラー》に「スクラップ」の恩恵はほとんどありませんでしたが、カードプールの増えた現在では《スクラップ・ワイバーン》から宇宙を創造することが多くなっています。
《スクラップ・ラプター》からサーチでき、そちらも《化石調査》《スクラップ・エリア》からサーチできるため、初動としての安定性は比較的高めとなります。
なお海外版のみ《幻魔皇ラビエル-天界蹂躙拳》(《Raviel, Lord of Phantasms - Shimmering Scraper》)も「スクラップ(Scrap)」に属しますが、遊戯王マスターデュエルは日本語版準拠のためか英語版でプレイしても一切「スクラップ」サポートを受けられない状態となっています。
「スフィンクス」モンスター

新たに登場した「スフィンクス」に含まれたカード群および、偶然「スフィンクス」に仲間入りしたカード群です。
《アンドロ・スフィンクス》
《スフィンクス・アンドロジュネス》
《スフィンクス・テーレイア》
《先史遺産ウィングス・スフィンクス》
《トラミッド・スフィンクス》
《守護神エクゾード》の召喚コストになる点でのみ成立しているカテゴリであり、この運用を想定していない「スフィンクス」モンスターをここに記載しています。
実際に「スフィンクス」モンスターをサーチや蘇生するカードが存在しないため、デッキ構築の基本は岩石族サポートが中心となるでしょう。
肝心の《守護神エクゾード》がやたら使いづらいという欠点こそありますが、守備力4000の壁を適当に出せる点は優秀なのでうまく活用してあげましょう。
「聖騎士」カード

新たに登場した「聖騎士」に含まれたカードおよび、偶然「聖騎士」に仲間入りしたカード群です。
《聖騎士ジャンヌ》
《聖騎士の盾持ち》
《聖騎士の槍持ち》
アーサー王伝説およびシャルルマーニュ十二勇将をそれぞれモチーフとするテーマですが、「聖騎士」のカード名のみを指定することから偶然にもカテゴリ入りしました。
いずれも「聖騎士」がカテゴリ化するより前にアニメ『遊戯王5D's』でシェリー・ルブランが使用したカード群となります。
モチーフもかけ離れていることからカテゴリ入りは完全に偶然ですが、効果の一部がそれぞれ他の「聖騎士」カードのサポートにもなるため併用自体は可能です。
ただし純【聖騎士】の運用とは少々離れる点には留意してください。
「セイバー」モンスター

新たに登場した「セイバー」に含まれたカード群および、偶然「セイバー」に仲間入りしたカード群です。
《セイバー・ビートル》
《セイバーザウルス》
《セイバー・シャーク》
《剣聖の影霊衣-セフィラセイバー》
《オッドアイズ・セイバー・ドラゴン》
《電影の騎士ガイアセイバー》
《エレメントセイバー・アイナ》
《エレメントセイバー・ウィラード》
《エレメントセイバー・ナル》
《エレメントセイバー・マカニ》
《エレメントセイバー・マロー》
《エレメントセイバー・モーレフ》
《エレメントセイバー・ラパウィラ》
《驀進装甲ライノセイバー》
《ZW-天馬双翼剣》
元々「X-セイバー」の一部モンスターおよび《総剣司令 ガトムズ》によるサポートを受けるだけのカードであり「X-セイバー」をメインのサポート対象にしていたと思われますが、カード名のみを指定していたことから偶然にもカテゴリ入りすることになりました。
このうち「X-セイバー」の一部モンスターの効果は戦闘破壊されることが前提であるか戦闘破壊の身代わりとしてリリースされることがサポート対象となるため有効に活用できる場面はほとんどありません。
一方で《総剣司令 ガトムズ》による全体強化は比較的有用な効果であり、戦闘破壊で追加の除去を行える《オッドアイズ・セイバー・ドラゴン》や戦闘後に自身を墓地へ送る必要がある《驀進装甲ライノセイバー》などとはそれなりのシナジーを発揮します。
採用する機会はほとんど無いと思いますが、【エレメントセイバー】に隠し味として《総剣司令 ガトムズ》を採用することで《霊神の聖殿》に加えて全体強化ができるため、一考の余地はあるかもしれません。
た行
「堕天使」カード

新たに登場した「堕天使」に含まれたカード群です。
《堕天使マリー》
《堕天使ナース-レフィキュル》
《堕天使ゼラート》
漫画『遊戯王GX』で響みどりが使用したカード群であり、その後全く関係ないブースターSPにて正式にカテゴリ化しました。
その際にカード名のみの指定だったことから、上記3枚も偶然にもカテゴリ入りすることとなりました。
なお種族が異なるのは《堕天使マリー》だけであり、他のカードは全て闇属性・天使族となっています。
《堕天使ナース-レフィキュル》もアニメ『遊戯王GX』で鮎川恵美が使用したカードですが、この時点では【堕天使】として使っていたわけではなく、【キュアバーン】のキーカードとして登場しただけでした。
高打点の天使族を並べて制圧する【堕天使】に【キュアバーン】要素を混ぜる必要性は薄いですが、サポートカードが豊富であるため上記3枚を採用することもできます。
逆に【キュアバーン】に【堕天使】要素を取り込んでデッキの安定を図ることもできるため、構築の際に考えてみるのも良いでしょう。
「チェンジ」速攻魔法カード

新たに登場した「チェンジ」に含まれたカードおよび、偶然「チェンジ」に仲間入りしたカードです。
《スター・チェンジャー》
《ギアギアチェンジ》
本来は《E・HERO シャドー・ミスト》や《マスク・チャージ》に対応するカードを想定してカテゴリが作られましたが、《フォーム・チェンジ》を含めるために「チェンジ」速攻魔法カードをカテゴリ化した結果、偶然にもカテゴリ入りしました。
中でも《ギアギアチェンジ》は1枚でX召喚できるカードのため《E・HERO シャドー・ミスト》でサーチできることを活かしたいところですが、デッキコンセプトが合致しないカード同士をあえて組ませる理由はほとんど無いため気にしなくて良いでしょう。
【ギアギア】を使用し《死者蘇生》で相手の《E・HERO シャドー・ミスト》を奪った際にサーチできることだけ頭の片隅に入れておくといいと思います。
「デーモン」カード
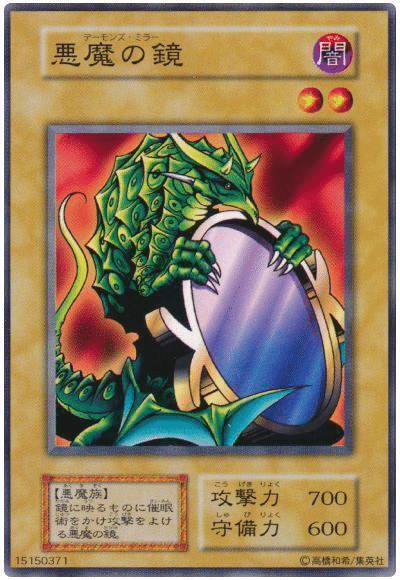
新たに登場した「デーモン」に含まれたカード群および、偶然「デーモン」に仲間入りしたカード群です。
《悪魔の鏡》
《デーモン・ビーバー》
《デーモンの召喚》
《ブラック・デーモンズ・ドラゴン》
《デーモンの斧》
《トゥーン・デーモン》
《暗黒魔族ギルファー・デーモン》
《デーモン・テイマー》
《デス・デーモン・ドラゴン》
《レッサー・デーモン》
《デーモンとの駆け引き》
《タルワール・デーモン》
《デーモン・ソルジャー》
《サイバー・デーモン》
《ミストデーモン》
《剣闘獣の闘器デーモンズシールド》
《レッド・デーモンズ・ドラゴン》
《メンタルスフィア・デーモン》
《マッド・デーモン》
《ナイトメア・デーモンズ》
《レッド・デーモンズ・ドラゴン/バスター》
《インフェルニティ・デーモン》
《アンデット・スカル・デーモン》
《インターセプト・デーモン》
《デーモン・カオス・キング》
《ランサー・デーモン》
《メンタルオーバー・デーモン》
《スクラップ・デスデーモン》
《ヘル・エンプレス・デーモン》
《トランス・デーモン》
《琰魔竜 レッド・デーモン》
《CNo.102 光堕天使ノーブル・デーモン》
《デーモン・イーター》
《悪魔竜ブラック・デーモンズ・ドラゴン》
《エキセントリック・デーモン》
《真紅眼の凶雷皇-エビル・デーモン》
《レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト》
《琰魔竜王 レッド・デーモン・カラミティ》
《琰魔竜 レッド・デーモン・アビス》
《琰魔竜 レッド・デーモン・ベリアル》
《レッド・デーモンズ・ドラゴン・タイラント》
《デーモンの呼び声》
《ベクター・スケア・デーモン》
《デーモンの降臨》
《デーモンの顕現》
《デーモンの招来》
《デーモンの超越》
《リンクメイル・デーモン》
《憑依覚醒-デーモン・リーパー》
《インフェルニティ・ヘル・デーモン》
《ディザスター・デーモン》
《デーモンの杖》
《悪魔の技》
《白銀の城の魔神像》
《同契魔術》
《カオス・デーモン-混沌の魔神-》
《スカーレッド・デーモン》
《ボーン・デーモン》
本来想定されていた「デーモン」は《万魔殿-悪魔の巣窟-》を主体とする、ライフコストを要求するいわゆる「チェスデーモン」を主体とするデッキと思われます。
それと同時に収録された《堕落》の維持コストに「デーモン」カードを指定していたことから、全ての「デーモン」カードが偶然にもカテゴリ入りしました。
上記のカード群はそのシナジーを想定していないと思われるカード群となります。
また後々の世代では「デーモン」カードを指定したカードも誕生しているため、「デーモン」カードとのシナジーを一切考慮していないであろうカードも上記に含まれています。
《万魔殿-悪魔の巣窟-》を主体とする【デーモン】はもはや時代の流れに取り残された存在であり、本格的な【デーモン】を組むならば新機軸の戦術を模索する必要があるでしょう。
な行
「ネオス」モンスター

既存の「ネオス」モンスターに仲間入りしたカードです。
《ダークネス・ネオスフィア》
アニメ『遊戯王GX』で主人公の遊城十代が使用する《E・HERO ネオス》を主体とするカテゴリであり、属するモンスターも上記を除き全て《E・HERO ネオス》の関連カードとなります。
《ダークネス・ネオスフィア》自体はアニメ『遊戯王GX』のラスボスであるダークネスが使用したカードであり、ラスボスのカードが主人公の使用するカードのカテゴリに属するというのは因縁めいたものを感じます。
その特性上、《E・HERO ゴッド・ネオス》の融合素材にすることも、その効果で効果をコピーすることも可能となっています。
アニメ『遊戯王GX』のキャラクターのカードを混成させたファンデッキを組む際には覚えておくといいでしょう。
は行
「ブレイズ・キャノン」カード

既存の「ブレイズ・キャノン」カードに仲間入りしたカードです。
《ゴッド・ブレイズ・キャノン》
アニメ『遊戯王GX』でオースチン・オブライエンが使用した「ヴォルカニック」と密接な関係にある永続魔法《ブレイズ・キャノン》を中心とするカテゴリでしたが、カード名のみを指定していたため偶然にもカテゴリ入りしました。
このため【ラーの翼神竜】では《ヴォルカニック・エンペラー》という大型モンスターを比較的軽いコストで出すことができ、それを《ラーの翼神竜》の生贄にできるというシナジーを発揮しています。
【ラーの翼神竜】を組む際にはピンポイントで《ゴッド・ブレイズ・キャノン》を用意する手段となるため、それを意識した構築をしても良いでしょう。
「ホルス」モンスター

新たに登場した「ホルス」に含まれたカード群です。
《ホルスの黒炎竜 LV8》
《ホルスの黒炎竜 LV6》
《ホルスの黒炎竜 LV4》
《ホルスのしもべ》
《ダーク・ホルス・ドラゴン》
《メタファイズ・ホルス・ドラゴン》
既に「ホルスの黒炎竜」カードはカテゴリ化していましたが、《王の棺》を中心とした「ホルス」がカテゴリ化するに際して偶然にもカテゴリ入りすることになりました。
ただしモチーフはエジプトにおける天空神であり、同じ名前の無関係な存在というわけではありません。
カテゴリ成立以前の「ホルス」カードも「ホルスの黒炎竜」カードおよびそのリメイクカードが中心であり、公式が意図した可能性を否定できないカード群となっています。
ただしカードパワーはそれほど高くなく、《カノプスの守護者》では召喚条件を無視できないことからあえて混成デッキにする必要性は薄いと言えるでしょう。
それでも組みたい人は組んでみるのも一興です。
ま行
「魔人」Xモンスター

新たに登場した「魔人」に含まれたカードおよび、偶然「魔人」に仲間入りしたカード群です。
《竜魔人 クィーンドラグーン》
《No.65 裁断魔人ジャッジ・バスター》
《CX 機装魔人エンジェネラル》
アニメ『遊戯王ZEXAL』で主人公である九十九遊馬が使用していたカード群ですが、カード名のみの指定だったため偶然にもカテゴリ入りしたカード群です。
ただし、仮に悪魔族を指定していても《No.65 裁断魔人ジャッジ・バスター》はカテゴリ入りしていました。
基本的にはランク3のXモンスターが中心ですが、ランク4の《交響魔人マエストローク》も属していることから、上記のカード群を混ぜることも不可能ではありません。
ただしランク2である《No.65 裁断魔人ジャッジ・バスター》の採用には一工夫必要です。
効果の面では高レベルのドラゴン族を採用すれば《竜魔人 クィーンドラグーン》を活用でき、《機装魔人エンジェネラル》も《機装天使エンジネル》をランクアップさせる形で運用することで現実的に使用できるでしょう。
いずれも正規召喚さえできれば戦闘面で役に立つサポートを受けられるようになるため、「魔人」のサポートを活用したい人は専用構築をしてみましょう。
「魔導書」カード

新たに登場した「魔導書」に含まれたカード群です。
《隠された魔導書》
《魔導書整理》
タロットカードをモチーフとした魔法使い族テーマである「魔導」と密接な関係にある「魔導書」に偶然にもカテゴリ入りしたカード群となります。
魔法カードである《魔導書整理》は相手ターンにデッキトップを任意のタイミングで操作できるカードとして活用できますが、《隠された魔導書》は「魔導書」であることを活かさない限りは《転生の予言》や《無欲な壺》の下位互換と呼べるカードとなります。
ただしどちらも【魔導書】では採用されることがほぼ無く、採用するならば専用の構築が求められるでしょう。
ら行
「リアクター」モンスター

既存の「リアクター」モンスターに仲間入りしたカード群です。
《古代の機械熱核竜》
《リアクター・スライム》
アニメ『遊戯王5D's』でボマーが使用した《ジャイアント・ボマー・エアレイド》の素材となる3体のモンスターを指定するカテゴリでしたが、カード名のみを指定していたことから偶然にもカテゴリ入りしました。
《ダーク・フラット・トップ》の効果で特殊召喚できるだけのカテゴリであり、そちらが闇属性チューナーを要求することから【古代の機械】で構築を捻れば《古代の機械熱核竜》を蘇生させるために《ダーク・フラット・トップ》を採用することもできるでしょう。
ただし「アンティーク・ギア」には蘇生手段が比較的多く存在し、わざわざ《ダーク・フラット・トップ》に頼る必要性も低いためネタの領域です。
一方の《リアクター・スライム》は種族・属性・効果の全てが噛み合っていないため、名前を活かすことは考えない方が良いでしょう。
「ロイド」カード

新たに登場した「ロイド」に含まれたカード群および、偶然「ロイド」に仲間入りしたカード群です。
《ダークジェロイド》
《E・HERO ネクロイド・シャーマン》
《マジカル・アンドロイド》
《HSR魔剣ダーマ》
《SR赤目のダイス》
《SRオハジキッド》
《SRシェイブー・メラン》
《SRタケトンボーグ》
《SRダブルヨーヨー》
《SRベイゴマックス》
《SR三つ目のダイス》
《SRメンコート》
《HSRチャンバライダー》
《HSRマッハゴー・イータ》
《SR電々大公》
《SRパチンゴーカート》
《HSR快刀乱破ズール》
《SR-OMKガム》
《SRバンブー・ホース》
《SRパッシングライダー》
《SRドミノバタフライ》
《ネクロイド・シンクロ》
《SRアクマグネ》
《SRビードロ・ドクロ》
《SR56プレーン》
《HSR-GOMガン》
《SRビーダマシーン》
《SRヘキサソーサー》
《HSRカイドレイク》
《転生炎獣ゼブロイドX》
《SRカールターボ》
《SRブロックンロール》
《SRデュプリゲート》
《SR吹持童子》
《SRマジックハウンド》
《SRルーレット》
《HSR/CWライダー》
《HSRコルク-10》
《SRスクラッチ》
《流星連打-シロクロイド》
アニメおよび漫画『遊戯王GX』で丸藤翔が使用したカード群で、通称「ビークロイド」と呼ばれています。
乗り物をモチーフとつつアニメ調の顔が描かれたコミカルなモンスターを中心としたテーマですが、カード名のみを指定していたことから偶然にも多くのカードがカテゴリ入りしました。
中でもアニメおよび漫画『遊戯王ARC-V』でユーゴが使用した「スピードロイド」は同じ機械族であり、同時に「ロイド」に属するカード群となりました。
機械族を指定するサポートカードも何枚かありますが、《エクスプレスロイド》や《キューキューロイド》は「ロイド」であれば全モンスターに対応することから、これらを活かしたデッキを組んでみるのもいいかもしれません。
最後に
長くなりましたが、以上が偶然にもカテゴリ入りすることになったカード群となります。
今後も遊戯王のカードプールが広がる度に巻き込まれるカードは増え、新たなカテゴリが世間を賑わすことになるでしょう。
おまけはカテゴリっぽいのにカテゴリに属さない例外的なカードの紹介と「煉獄」に関する話、そしてこの世から消滅したカテゴリの話です。
暇な人は読んでみてください。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
おまけ①カテゴリっぽいカード

ここではカード名を見ると「○○」に属しているように見えるものの、実際には「○○」に属さないカードを紹介します。
「オッドアイズ」カードではない

《覇王天龍オッドアイズ・アークレイ・ドラゴン》は「オッドアイズ」の名前を含んでおり、見た目では「オッドアイズ」カードとなっています。
しかしこのカードはルール上《覇王龍ズァーク》として扱うため、「オッドアイズ」カードとしては扱いません。
遊戯王のカードプールに《覇王天龍オッドアイズ・アークレイ・ドラゴン》なるカードは存在しないということです。
このため《オッドアイズ・アブソリュート・ドラゴン》で特殊召喚する、《覇王紫竜オッドアイズ・ヴェノム・ドラゴン》の融合素材にする、《螺旋のストライクバースト》の破壊効果の発動条件を満たすといったことは一切できません。
一方で《覇王龍ズァーク》として扱うことから、そちらのサポートの恩恵を存分に受けることができます。
その方向性で差別化し活用していきましょう。
「サイバー」カードになれない

《サイバー・ブレイダー》や《サイバース・クアンタム・ドラゴン》などはその種族を機械族あるいはドラゴン族に変えることで「サイバー」モンスターのサポートを受けることができます。
一方で《ハーピィ・レディ・SB》はカード名に「サイバー」を含んでいますが、種族を変更しても「サイバー」モンスターのサポートを受けることができません。
これは《覇王天龍オッドアイズ・アークレイ・ドラゴン》と同様で、ルール上《ハーピィ・レディ》として扱っているためです。
遊戯王のカードプールに《ハーピィ・レディ・SB》なるカードは存在しないことになっています。
他にも本家《ハーピィ・レディ》だけでなく《ハーピィ・レディ1》《ハーピィ・レディ2》《ハーピィ・レディ3》も全てルール上《ハーピィ・レディ》として扱うことから、肩身の狭いカードになってしまっています。
「No.1」カードではない

「No.」はアラビア数字の0〜107および1000とXXを擁する巨大なカテゴリですが、《No.100 ヌメロン・ドラゴン》および「No.101〜107」は見た目上「No.1」を含んでいますが、「No.1」としては扱いません。
また同時に「No.10」も含んでいますが「No.10」としても扱いません。
このため《No.78 ナンバーズ・アーカイブ》の効果では特殊召喚できず、また《No.100 ヌメロン・ドラゴン》以外のカードは《No.99 希望皇ホープドラグナー》の効果でも特殊召喚できません。
これは2桁以上の数字を分割することがないという慣例に則ったものであるためです。
攻撃力100のカードを攻撃力1や10とは読まないですよね。
ただし「No.」であることに変わりはないため、そちらのサポートカードの恩恵を受けることはできます。
適材適所、使えるものを使って、使いたいカードを輝かせましょう。
「ネオス」カードではない

「N(ネオスペーシアン)」はカタカナで「ネオス」の読みが入っており、《守護者スフィンクス》や《守護天使ジャンヌ》などの前例を考慮すれば「ネオス」に属するカード群となります。
しかし「N」は英語表記が「Neo-Spacian」であり、「ネオス」(Neos あるいは Neo Space)ではないという裁定が出されています。
あえて日本語で書き直すのであれば、「N(ネオ・スペーシアン)」になるのでしょう。
実際に「N」を使い「ネオス」カードと併用する場合は注意しましょう。
また、同様に《NEXT(ネオスペースエクステンション)》も「ネオス」カードとしては扱いません。
他の《ネオスペース》や《インスタント・ネオスペース》は《マジカルシルクハット》の効果で特殊召喚した場合は「ネオス」カードとなりますが、《NEXT》はその場合でも「ネオス」カードにならないため注意しましょう。
「ネオスペーシアン」カードではない

《NEX(ネオスペーシアンエクステント)》はカード名に「N(ネオスペーシアン)」を含んでいますが、「N」カードとしては扱わないという裁定が出ています。
《NEX》の英語名も《NEX》であるためなのかはわかりませんが、そういう裁定が下されている以上はどうしようもありません。
《コンバート・コンタクト》を使用する際はその効果で墓地へ送れないため留意しておきましょう。
おまけ②「煉獄」に関する話

「煉獄」はアニメおよび漫画『遊戯王5D's』にて鬼柳京介が使用した「インフェルニティ」をイメージしたカードとして登場しました。
初登場時はカテゴリではなく《無の煉獄》が登場した後は何の音沙汰もなく、《煉獄龍 オーガ・ドラグーン》が登場してもなお漫画版に登場した《煉獄の釜》などはOCG化しませんでした。
その後《煉獄の落とし穴》が登場し、そこでストーリー的に《インフェルノイド・リリス》が「氷結界」の三体の龍の力を得たことが理由からか、「インフェルノイド」のサポートカードとして「煉獄」が正式なカテゴリになりました。
そこから月日を経て、「インフェルニティ」のサポートカードとして漫画版に登場した何枚かの「煉獄」カードがOCG化し、《インフェルニティ・ポーン》がそれらをセットできるようになったことで「インフェルニティ」と関わりのあるカテゴリとなりました。
《クリスタル・ローズ》や《バリア・バブル》のようにアニメなどで共演した複数のカテゴリで使用できるデザインのカードは存在しますが、全く関係無い2つのカテゴリで共有するカテゴリというものは極めて珍しい例となります。
ただしどちらも地獄(Inferno)をモチーフとしたテーマであり、見当はずれのネーミングではないためイメージを損なうことはありません。
おまけ③「ジェネクス・コントローラー」カード

《ジェネクス・コントローラー》自体は【ジェネクス】におけるキーカードで、他の属性と共にシンクロすることで各属性の「ジェネクス」Sモンスターへと姿を変えます。
「ジェネクス・コントローラー」カードは《ジェネクス・ガイア》のエラッタ前のテキストでのみ存在したカテゴリでした。

所属するモンスターは《ジェネクス・コントローラー》のみであり、これは現在に至るまで変わっていません。
「ジェネクス」には何枚かカード名を《ジェネクス・コントローラー》に変えるカードが存在しますが、いずれも《ジェネクス・コントローラー》として扱うだけであり「ジェネクス・コントローラー」がカテゴリで存在する意味はほとんどありませんでした。
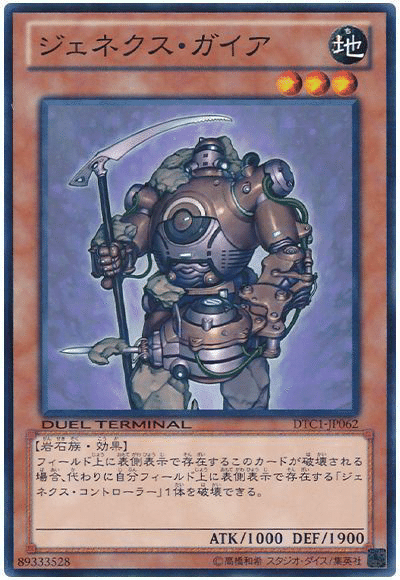
そして再録された際にエラッタされ、《ジェネクス・コントローラー》を指定するようになり、カテゴリとしての「ジェネクス・コントローラー」は消滅しました。
あえて復活させる理由も無いので、二度と蘇ることはないでしょう。
以上でおまけを終わります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
