
クロス・レヴュー 2024年2月号
「クロス・レヴューはミュージック・マガジンの重心を支える背骨みたいな存在だ。この雑誌は毎月発売されるレコードを幅広く取り上げ、できるだけ厳しく批評し、しかもその批評性を持続していくことで音楽の長い流れをしっかりと捉えるのを役目と心得ているが、その役目を集中的に象徴してきたのがクロス・レヴューの欄なのだと思う」――中村とうよう
『ミュージック・マガジン』誌上で1981年から続く、注目アルバム7枚について毎月4人が批評して10点満点で採点するコーナー、“クロス・レヴュー”のWEB公開を始めます。評者それぞれの聴き方の違いを楽しんでいただくもので、アルバムの絶対評価を示すものではありません。より充実した音楽生活を送っていただくきっかけの一つにしていただければ幸いです。
今月の評者は以下の4名です。
近藤真弥
1988年生まれ。クッキーシーン編集部を経て、フリーの編集/ライターとして活動中。幼い頃は、親にポスト・パンク、ニュー・ウェイヴ、ハウス、テクノなどを聴かされました。
清家咲乃
基本的にエクストリーム・メタルばかり聴いている音楽ライター。いわゆるZ世代らしくトラップやデジタル・パンク/ハードコアも好きです。
土佐有明
ライター。音楽以外に、書評や演劇評や映画評も執筆。近年は新旧問わずジャズを聴くことが多いです。今年はようやく単著が出ます。
渡辺裕也(本誌編集部)
1983年生まれ。福島県出身。ライターとして音楽関連の文章を雑誌/Webメディア等に寄稿。2021年9月からミュージック・マガジン編集部に参加。
※それぞれの評文についた○内の数字が点数です。(10点満点)
ベイルート『ハッセル』
Beirut "Hadsel"
ポンペイ〔インパートメント〕 AMIP0338

近藤真弥
ノルウェーの島にある教会で制作されたという本作は、俗世と浄土の間みたいな雰囲気を醸すスピリチュアルなサウンドが際立つ。オルガンやウクレレといった多くの楽器を使った曲群は憂いが滲む一方で、苦悩がほどけていく晴々としたフィーリングも顕著だ。多彩なメロディーも悪くない。これまでのベイルート作品と比べて飛びぬけたところはないが、稀有な味を堪能できる作品ではある。 ⑦
清家咲乃
チェンバー・ポップにこれまであまり親しんでこなかった自分が、一聴して惹きこまれてしまった。本作のキーであるノルウェーの教会のオルガンは凍みる空気をふるわせ、折り重ねられ保温されたコーラスと手を取り、その色を柔く塗り替えていく。泡が湧きあがるように立体的な加工が施されたパーカッションが隆起するさまに、どこかで行き合ったことがあるだろうかという懐かしさを覚える。 ⑨
土佐有明
シガー・ロスを連想する向きもある、というか筆者も最初そう感じたのだが、本作は彼らの作品よりも娯楽性に富み、大仰ではなく、音楽的な持ち札も豊富。ストイックになりすぎず、適度に肩の力が抜けているのもいい。荘厳で透徹した空気に惹きつけられるが、ノルウェーの島で教会のオルガンを使って制作されたと知って納得。アコースティックで柔らかな質感も魅力で音響の快楽に酔いしれた。⑨
渡辺裕也(本誌編集部)
滞在先のノルウェー北部ハッセル島でつくり始めたという本作は、結果としてベイルート=ザック・コンドンのソロ・プロジェクトという原点に帰る作品となった。バルカン音楽などを背景とした雄大な演奏と、古い電子楽器のミニマルなビート、そして気高いクルーナー・ヴォイスが醸し出す世界観はやはり唯一無二。コンドンのインナースペースから生まれた、孤高のフォーク・ミュージック。 ⑨
エレファントジム『WORLD』
ワーズ WDSR006
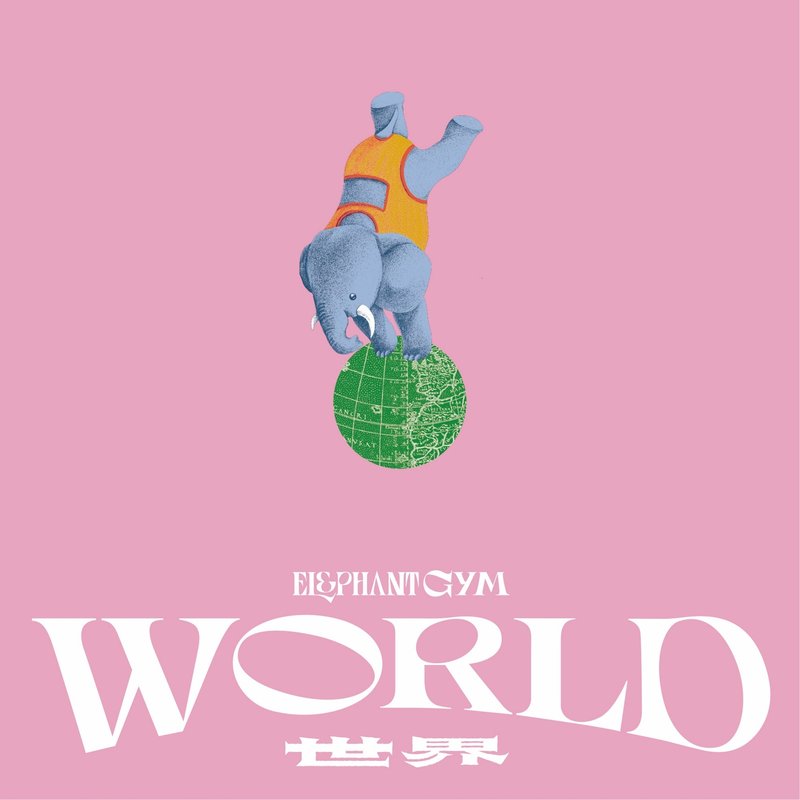
近藤真弥
予備知識なく聴いて、台湾出身のバンドによる作品だと瞬時にわかる人は少数ではないか。そう思わせるほど、さまざまな要素が綿密に絡みあった曲群はグローバルだ。ロックやジャズの要素を軸にしながらも、特定のスタイルにとらわれた固定観念とは無縁の開放的グルーヴを生みだしている。ベースで参加の亀田誠治を筆頭に、ゲストとのケミストリーもグッド。ライヴで聴きたい。 ⑧
清家咲乃
軽やかな3人のアンサンブルが見事。何かのお供にスピーカーから放てばひとかたまりの心地よさとして漂い、意識を集中して聴取に専念すればマス”ポップ”の複雑なリズムや小粋なフュージョン的ギター・フレーズ、景気よく曲をまわすホーン・セクションが繊細に混ざり合っているのがわかる。歌い手違いで変奏される二つの ‘Feather’ は、それぞれに流れる時間の速さがまるで違う。 ⑦
土佐有明
ポスト・ロック、マス・ロック、エモから出汁を取ったようなごった煮のサウンドだが、雑然とした印象はさほどなく、オーセンティックなロックとして非常に優れている。それでいて、リスナー体質であろう彼らの音楽的偏差値の高さがプラスに作用しているようだ。亀田誠治のベースをフィーチャーするセンスにも好感が持てる。立体的な音像も含めてよく練られたサウンド・デザインに唸った。⑨
渡辺裕也(本誌編集部)
脳内に積まれたテトリスのブロックが高速で次々と打ち消されていくような快楽へと聴き手をいざなう、極めて技巧的なマス・ロック。それでいて本作は全編にわたって流麗なメロディが展開される、非常にとっつきやすいポップスでもある。しかも、その印象はインスト曲でもヴォーカル曲でも変わらないという点に、このバンドの飛び抜けたセンスのよさを感じずにいられない。 ⑧
羊文学『12 hugs(like butterflies)』
F.C.L.S. 〔ソニー〕 KSCL3482

近藤真弥
3人組バンド、羊文学の最新作は、いまの3人が過去作の要素を鳴らしてみたらというサウンドに聞こえた。スーパーカーを想起させるシンセ使いなど、前作『our hope』で見られたおもしろい実験精神が若干後退したところに淋しさを感じつつも、ソニック・ユース的なラウド・ギターも鳴りひびく曲群は素直にカッコいいと思えた。時代と共鳴する言葉が輝く歌詞も、滋味が増していて素晴らしい。 ⑧
清家咲乃
洒脱に高低のメロディを紡ぐヴォーカルが、挫折を知り、後悔を恐れ、それでも倦まずにまた進もうと歌うことでリスナーを抱きしめる。冬の朝、少しだけ許しを与えてくれる布団のように。澄んだ水に揺蕩うかのごとく清廉な雰囲気の楽曲のなか混じる、ラフでノイジーな3曲目や6曲目、12曲目が印象に残った。インディー・ロックともノイズ・ロックともシューゲイザーとも断じられないサウンド。 ⑦
土佐有明
サブカル・カップルの悲恋を描いた映画『花束みたいな恋をした』の登場人物が、長谷川白紙らと並んで好きなバンドとして挙げていた羊文学。実はそれがきっかけで知ったのだが、あらためていいバンドだなと本作を聴いて思った次第。歪んだギターの音色が心地よいし、オルタナ成分高めなのもかなり好みだ。きのこ帝国やそのヴォーカリストだった佐藤千亜妃のソロ作に通じる感触もあり。 ⑧
渡辺裕也(本誌編集部)
焦燥と倦怠を纏った歌声の蒼く澄んだ響きと、ガレージ/オルタナを下地とした粗野なバンド・サウンドに触れていたら、そろそろ次作あたりでスティーヴ・アルビニと組んだりしないかなーなんて妄想まで膨らんできた。イーヴン・キックが高揚感を醸す「more than words」は、ライヴの出囃子にザ・XX「VCR」を毎回かけていた彼女たちのセンスが自作曲に結びついた成果だと思う。 ⑧
King Gnu『THE GREATEST UNKNOWN』
アリオラ〔ソニー〕 BVCL1352

近藤真弥
日本のロック・シーンを代表するバンドと言えるKing Gnu。メロディーやグルーヴは多彩で、バイセクシュアル的描写が顕著な「The hole」のMVなど、映像面も興味深い。そんな彼らによる本作を聴いて、よく出来た表現を生みだせる人たちだと改めて実感した。それでも、歌詞に見えかくれするマッチョさは、先述のMVとの整合性がないようにも感じられ、筆者の耳には合わなかった。 ③
清家咲乃
過半数が映像作品などの世界観に合わせて作られたタイアップ曲から成るためか、ベスト・アルバムを想起させるタイトルを冠している。多彩さは雑然としてしまう危険も孕むが、注意深く全体に配置されたインタールードで各セクションを切断/接続、この一枚のための新たな文脈を織りだした。小曲のサウンドがどれも魅力的なので、全弾遊び心のオリジナル作がそろそろ聴きたい。⑦
土佐有明
なるほど、こういうリッチな音がメジャーど真ん中で勝負できるのだろうな。ラジオで彼らの曲がかかった時にダイレクトに耳に飛び込んできたのを思い出した。とはいえ、無理やり音圧を高めた風ではなく、鳴りや響きの良さを彼らなりに追求した結果がこのサウンドなのだろう。ちょっと色々なエフェクトをかけすぎとは思うが…。ハイトーンなヴォーカルは最初は苦手だったがすぐに馴染んだ。⑦
渡辺裕也(本誌編集部)
Jロック特有の大仰な音作りと泣きメロとサビありきの構成がわりと苦手なんだけど、本作に関してはちょっと例外だと感じた。収録曲の大半がタイアップ付きの既発曲なのに、寄せ集め感ゼロ。効果的なインタールードとリアレンジによってシームレスな流れとストーリーを構築した、あまりにも見事な”アルバム”だ。日本のメインストリーム・ロックとして、これは近年稀に見る傑作だと思う。 ⑨
アナ・カルラ・マサ『カリベ』
Ana Carla Maza "Caribe"
ディスコ・カランバ〔アオラ〕 CRACD1123

近藤真弥
キューバ出身のチェリストが作りあげた4枚めのアルバム。端的に言えば大好きだ。ソンといったラテン音楽をはじめ、ジャズやクラシックなど多くの要素で彩られたサウンドは非常にモダン。跳ねるグルーヴはとてもダンサブルで、自然と体を揺らしてしまう。正直、よく名を聞くから勉強で聴いてきた程度のリスナーだったが、いまはそうした認識しか持てなかったことを恥じている。 ⑨
清家咲乃
今作から全面的にバンド・サウンドへとシフトしたとのことで、ラテン・ヴァージョンと銘打ってリメイク収録された前作の表題曲 ‘Bahia’ を聴き比べてみたところ、なるほど、門外漢にも明確な変貌を遂げている。生々しく削り出されていたチェロ弾き語り版では歌に合わせて自在に緩急が変化していたのが、パーカッション/ピアノによるリズム絨毯上での滑走に。鮮やかな景色が湧出している。⑦
土佐有明
とてもよくできたアルバムだと思う。テンポの速い曲にはテンションがあがったし、ヴォーカルの存在感の強さも伝わる。バックの演奏も個々の持ち味を十全に出し切っている印象だ。だが、全体的にこれというアクや個性がなく、優等生すぎて物足りない。予想以上にラテン色が濃いが、キップ・ハンラハンのディープ・ルンバのような妖しくて猥雑な曲がもう少しあったらなあ、と思ってしまった。 ⑥
渡辺裕也(本誌編集部)
タイトルそのままにカリブ及びキューバをテーマとする作品で、本人のルーツであるサンバやタンゴ、サルサなどを取り上げた陽気な歌唱とバンド演奏がまるまる堪能できる1枚だ。その多彩なリズムと曲調に耳を傾け、ただ身体を揺らしているだけでも十分に楽しいが、気になってライヴ映像を確認してみたら、チェロを弾きながら歌うアナの姿が思っていたよりもずっとかっこよくて圧倒された。⑦
ミーカ『ク・タ・テート・フルリース・トゥジュール~あなたの頭にいつも花が咲きますように』
Mika "Que Ta Tête Fleurisse Toujours"
ユニバーサル UICO1334
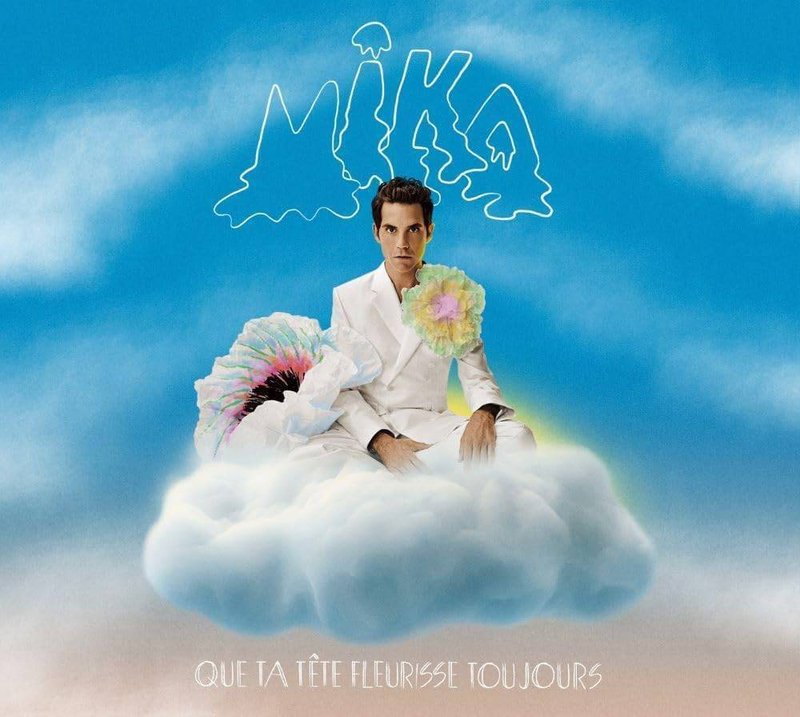
近藤真弥
レバノン出身のミーカの6作めは、脳腫瘍で亡くなった母親をモチーフに作られた。とはいえ、そのような背景の作品にありがちな哀しみや自己憐憫はほとんど見られない。ユーロビートの香りも漂うエレ・ポップと形容できるダンサブルなサウンドは、前向きな空気を醸している。ゲーム・チェンジャーになり得る革新性は皆無だが、若さだけでは辿りつけない熟練を楽しめる良作だ。 ⑦
清家咲乃
キャリア初の全編仏語詞アルバム。ひとつの単語やフレーズをリズミカルに反復してポップネスを起爆させる手法が武器になっていて、歌詞を追わずに音として聴いていても確実に耳に残る。特に1曲目と10曲目などは思わず意味を調べてしまったほど。縦に跳ねるダンス・ポップ・ビートと、カッチリ割れない軟体動物のようなフランス語の響きが合わさって、不思議で気ままな浮遊感を生む。 ⑦
土佐有明
残念ながら、どこをどう聴いてもこれという美点が見つけられなかった。アンサンブルはゆるゆるだし、単調なイーヴン・キックはひと昔前の質感。これといった特徴のないヴォーカルにも気分が萎えた。能天気なパリピっぽさ満載で、このひと悩みなさそうだなあと思わせるお気楽さもまた、しっくりこなかった要因だ。悪い意味で、作業しながら流しっぱなしにしていても邪魔にならない作品。 ③
渡辺裕也(本誌編集部)
歌詞がフランス語であることはもとより、ユーロダンス~フレンチ・ハウスなどを取り上げたエレガントなエレクトロニック・サウンドも含めて、徹底してヨーロピアンな仕上がりの作品だ。アッパーなダンス・チューンがつづく序盤の展開が個人的には好みだが、これが亡き母に捧げた作品であることを踏まえると、哀感を帯びたバラッドが並ぶ中盤以降の流れがむしろ本作のキモなのだろう。 ⑦
PinkPantheress “Heaven Knows”
Warner

近藤真弥
イギリスの注目アーティスト、ピンクパンサレスのデビュー・アルバム。曲の短さやY2Kリヴァイヴァルとの共鳴といった側面から語られるキワモノというイメージも強かった彼女だが、本作では上質な曲を並べる直球勝負が印象的だ。UKガラージやハウスの要素が色濃い曲群はそつがなく、とても耳馴染みが良い。珍妙さで目を引かなくても、創造力で戦えると示した力作だ。 ⑧
清家咲乃
アタックのはっきりしたトラックは時にブレイクビーツ的様相を呈し、そこへ流しこまれる可憐で甘やかなフィメール・ヴォーカル、スパイスとして挿入されるラップ、肌に感じるダークな雰囲気といった要素で構成されたコンテンポラリーR&Bは現行Kポップのトレンドともマッチするので、そちらのファンにもぜひ勧めたい。現に1曲目ではf(x)の ‘Ice Cream’ がサンプリングされている。 ⑧
土佐有明
ドラムンベースってこんなクールだっけ?が第一印象。いや、ドラムンベースだからじゃなくて、彼女だからなんだろう。EBTGがそうであるように。チャーミングでコケティッシュなヴォーカル、4ヒーローなどを連想させるオーガニックなビート、緩急をつけたアレンジと構成、すべてが素晴らしい。1月号で長谷川町蔵さんが書かれていたように、ネオアコ心をくすぐるのも堪りません。⑨
渡辺裕也(本誌編集部)
2年前の1stミックステープと聴き比べると録音やミックスは明らかに洗練されたが、”鮮烈なフックを搭載した内省的なダンス・ポップ”という路線はしっかり踏襲。その後のメインストリームに新たな潮流を生んだ、あの画期的なミックステープから至極真っ当な発展を遂げている。女性版リック・ルービンになりたいという彼女の発言が本気だとしたら、これもまだ通過点に過ぎないのだろう。 ⑧
●
以上の「クロス・レヴュー」も掲載されている2024年2月号、好評発売中!
詳細は下記リンクをご覧ください。
こちらから購入いただけます。
※本記事の無断転載は固くお断りいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
