
クロス・レヴュー 2024年7月号
「クロス・レヴューはミュージック・マガジンの重心を支える背骨みたいな存在だ。この雑誌は毎月発売されるレコードを幅広く取り上げ、できるだけ厳しく批評し、しかもその批評性を持続していくことで音楽の長い流れをしっかりと捉えるのを役目と心得ているが、その役目を集中的に象徴してきたのがクロス・レヴューの欄なのだと思う」――中村とうよう
『ミュージック・マガジン』誌上で1981年から続く、注目アルバム7枚について毎月4人が批評して10点満点で採点するコーナー、“クロス・レヴュー”のWEB公開を始めます。評者それぞれの聴き方の違いを楽しんでいただくもので、アルバムの絶対評価を示すものではありません。より充実した音楽生活を送っていただくきっかけの一つにしていただければ幸いです。
今月の評者は以下の4名です。
石田昌隆
1958年、千葉県市川市生まれ。フォトグラファー。CD/レコード・ジャケットを多数撮影している。7月に、写真190枚、文章23万字の新刊『ストラグル Reggae meets Punk in the UK』が出る。
つやちゃん
身体と音楽についてずっと考えています。こんな時代だからこそ、
ジャンル問わず、フィジカリティを強く感じる音楽にますます価値
を見い出しつつあります。
村尾泰郎
68年生まれ。音楽/映画ライター。
久保太郎(本誌編集部)
1971年生まれ。横浜市出身。編集者生活25年。本誌の前編集長で、いまは裏方です。
※それぞれの評文についた○内の数字が点数です。(10点満点)
アルージ・アフタブ『ナイト・レイン』
Arooj Aftab "Night Reign"
ヴァーヴ〔ユニバーサル〕 UCCV1199

石田昌隆
パキスタン出身で、ニューヨークを拠点に活動している。ライヴの動画を見たら、発声法は違うけど、表情や手の動きが醸し出す雰囲気などから、パキスタンの音楽、ガザルがルーツにあることが伝わってきた。ぼくには判らないが歌詞にも叙事詩としてのガザルの影響があるかもしれない。それでいて物憂げな歌い方と音楽との関係が、シャーデーやトリップ・ホップのようでもあり引き込まれた。⑨
つやちゃん
'Bolo Na' が異色で、始まった瞬間にこれベス・ギボンズだったっけ!?と反射的に確認してしまった。全体的に、緊張感と躍動感が押し合いへし合いするダイナミズムの中で、楽器はもちろんのこと、歌の表現力がひと際目立つ。作家のルーツは南アジアだが、拠点としているNYのムードがどんどん増してきているのか、どこか退廃と壮麗が編み出す都市的なドレスコードを感じるのが面白い。⑧
村尾泰郎
パキスタン出身でバークリーで学んだそうだが、そういった出自が音楽に反映されている。メロディーや歌唱法はオリエンタルで彼女のルーツが息づいているが、様々な楽器を使ってアブストラクトなアンサンブルを構築する演奏はモダンで知的。そして、低音で深みのある歌声が、水に垂らした墨のようにゆっくりと広がって曲に染み渡っていく。美しく詩情豊かで、夜の気配に満ちたアルバム。⑧
久保太郎(本誌編集部)
「私は伝統的なシンガーではない」と本誌6月号のインタヴューで言ってはいたものの、やはりこのパキスタン出身ニューヨーク在住の音楽家の背景には、ガザルをはじめとした広く深遠なインド系の音楽があり、そこに現在ジャズの仲間たちなどを加えて、蛇口をひねるように自由な音楽を奏でている、という印象だ。とにかく心地がよく、音の響きと流れに身を任せて浸っています。⑨
アジャテ『ダラトニ』
ライス〔オフィス・サンビーニャ〕 AER3146
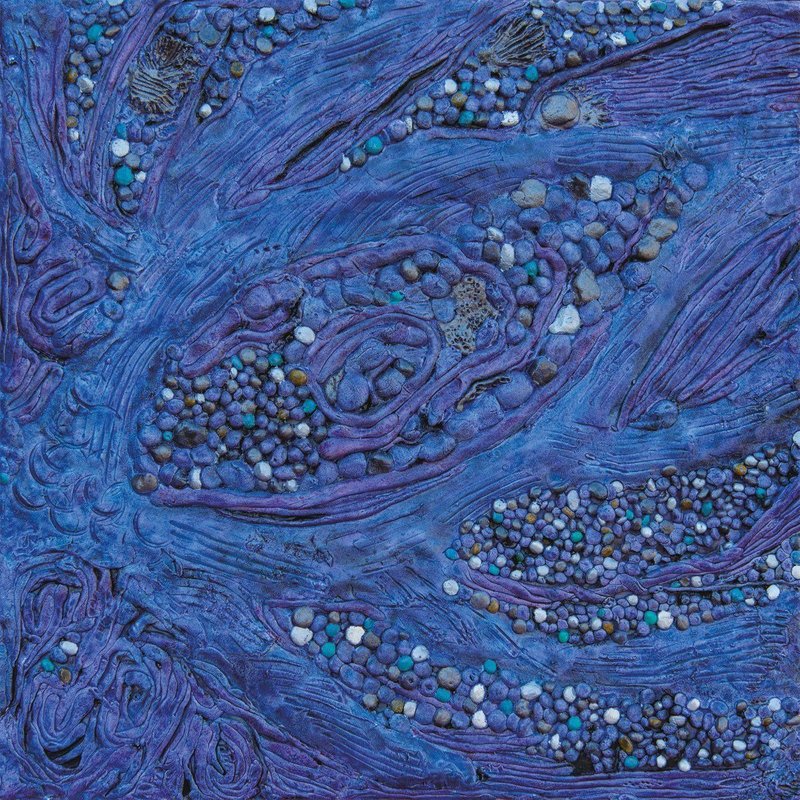
石田昌隆
フェラ・クティのアフロビートみたいな楽曲を、独自の和楽器で作り上げていくユニークな日本人のグループだった。「Kopi Lakanka」で意味不明の反復する歌詞の歌が“ジキジキジキアカラカラ”というフレーズに収斂していくところとか面白かった。ただし、じゃがたらのように表現の核に強いものがある感じではない。祭りの音楽っぽく聞こえてくるのは良いことだと思うが。⑦
つやちゃん
これはすごい! アフロビートと江戸祭囃子なんてそもそも全く遠いものでしょ、と考えていた自らの先入観を恥じてしまう。いやいや意外に共振してるものなのよ、と言わんばかりに通底で手を結ぶ両者。そこでは、柔軟にリズムを刻む和太鼓の果たす力が大きいように思う。AI時代、私たちに必要な音楽の発明とはこういうことなのではないか。全人類、これを聴いて身体を取り戻せ!⑩
村尾泰郎
アフロビートだがドラムやホーンなど力強い音は入らず、笛や太鼓の軽やかな音色が弾んでいる。お囃子の軽妙なグルーヴがアフロビートとこれほど馴染むとは。国境を越えて、ローカルでトラディショナルな音楽を現代的なミクスチャー感覚で捉えていて、アフリカでも日本でも、おそらく世界中で万民が踊れるダンス・ミュージック。21世紀の「ええじゃないか」はこんな音楽なのかもしれない。⑦
久保太郎(本誌編集部)
こちらも6月号の特集「ニッポンのトラディショナル・ポップの現在」に掲載したバンドで、「アフリカの葬式の音楽と日本の祭囃子に共通のエネルギーを感じた(大意)」とインタヴューで言っているとおり、コンセプチュアルでも学究的でもなく、体得したミクスチャーをしっかり音に現出させていることに感心。両者共通の音響的な快楽であるサワリがリズミックに活かされているのが良い。⑧
Nia Archives "Silence Is Loud"
Hijinxx / Island

石田昌隆
ジャマイカをはじめとするカリブ海、英連邦の国から、48年から71年の間にUKに移民してきた人をウィンドラッシュ世代というが、現在はもう移民3世の時代になっている。ニア・アーカイヴスも、祖母がパーティでかけていたレゲエ、ジャングルなどの音楽に影響されたそう。ドラムンベースは生まれたときからある音楽で、そのビートにシンガー・ソングライターらしい曲を乗せてくる。⑧
つやちゃん
大きな目盛りで捉えると無論ジャングルのビートなわけだが、もう少し小さい目盛りで捉えていくと音色やテクスチャが歌を映えさせるものになっていて、“古くて新しい”とはまさに。一方、あくまでヘヴィな質感を貫き通す点は他のリヴァイヴァル勢とは一線を画す。もっと多彩なビートで押し引きする構成を作ることもできそうだが、そういった批評受け(?)に目配せせず走り抜けるさまが最高。⑧
村尾泰郎
ジャイルズ・ピーターソンによると、ジャングルはパンクと同じくらい重要な音楽的発明だったとか。本作を聴くと、ジャングルがひとときの流行ではなく文化として若い世代に受け継がれていることがわかる。ジャマイカ系移民の家に生まれたニア・アーカイヴスはビートを自由に乗りこなしていて、その歌声は生き生きとしていて晴れやか。彼女にとってジャングルは祭囃子なのかもしれない。⑦
久保太郎(本誌編集部)
90年代にリアルタイムで聴いてきたドラムンベースは、DJ/クリエイターによるスタイリッシュなアート・フォームという印象だったが、ここまでヴォーカルを中心とした個の意思があるポップな作品に出会ったことはない気がして、目からウロコが落ちた。とにかくエネルギーに満ちていて聴くたびに踊り出さずにはいられない。とりわけ先鋭的ではないものの、端的に言って好きです。⑨
チカーノ・バットマン『ノートブック・ファンタジー』
Chicano Batman ”Notebook Fantasy”
ATO〔ビッグ・ナッシング〕 ATO0664CDJ

石田昌隆
胸にひらひらのフリルがついたコスチュームのチカーノ・バットマンを、千葉の小さなライヴハウスで観たのはもう11年前のこと。それから大きく成長している。スペイン語で歌う情緒的な曲「Era Primavera」はキラー・チューンだ。チカーノの人たちが気持ちをわしづかみにされている風景が目に浮かぶ。切ないラヴ・ソングのようだが、監獄の島だったアルカトラズ島の話も出てくる。⑨
つやちゃん
これはもう、夢ですね。夢心地にずぶずぶ入って溶けていく、快楽のためのアルバム。先日リリースされたトーキング・ヘッズのカヴァー曲でも彼らのセクシーな“らしさ”が全開だったが、抗しがたいうねりが体の奥を突き動かす本作は、快楽性では過去随一か。特に7曲目は、構築されたグルーヴが後半に形を変えながら、さらなるサイケの渦に誘い込んでいくすばらしい曲。ズブズブズブ……。⑥
村尾泰郎
名前からしていなたいバンドかと思って聴いたら、ラテン色は押し出さず、印象的なのはグルーヴよりも凝った音作り。ファンクやサイケなど70年代風のヴィンテージな味わいを醸し出し、西海岸ロックのメロウさを漂わせながらも今どきのビートで心地よく聞かせる。その辺のバランス感覚はプロデューサーのジョン・コングルトンの采配なのだろうか。ベックあたりとも相性良さそうな音。⑦
久保太郎(本誌編集部)
冒頭のルーズだがグルーヴィなギターのカッティングを聴いて、ああチカーノのバンドだなとニヤけてしまうが、以降もエレクトロニックなファンクあり、ストリングスが盛り上げる曲ありと、音楽的な魅力はテンコ盛りだ。ただ、これもバンドの特徴であるヴォーカルのエフェクトのかけ方が、どの曲も似通った印象を与えるのが痛し痒しか。好きな人にはたまらないものだと思うけど。⑦
ベス・ギボンズ『ライヴス・アウトグロウン』
Beth Gibbons "Lives Outgrown"
ドミノ〔ビート〕 BRC755

石田昌隆
なんと、ポーティスヘッドのヴォーカルだったベス・ギボンズの初ソロ・アルバムである。ブレイクビーツから離れたかったという音作りは、オーガニックな感じのドラムにしたり、ストリングスの入れ方とか緻密に練られていると思う。ただし内省的で、長い年月で蓄積された気持ちが歌い込まれているのであろう歌詞は、ぼくにはやや観念的になりすぎているように思えて入り込めなかった。⑦
つやちゃん
ベス・ギボンズ的な、というか、いわばポーティスヘッド的な音というのはとかく若気の至りのような形で多方面からオマージュされがちで、その気持ちはすごく分かる。だが、本作を聴くとやはりオリジネーターとしての洗練度合いが別格。色々な物が打楽器として使われていて聴いていると非常に楽しいのだが、決してチープにならない。現代的エレガンスの最高峰、と言っていいと思う。⑨
村尾泰郎
ポーティスヘッド結成前、ベス・ギボンズに出会ったジェフ・バーロウは、自分が書く暗い曲を歌ってくれる人がいることに感激したとか。ジェフが抱えていた闇よりも深いところから、ベスがやってきたことが初めてのソロ作となる本作から伝わってくる。日用品を楽器がわりに使ったサウンドは生々しくてプリミティヴ。ベスの声に捉えられて、深い森のような歌の世界に引き込まれていく。⑧
久保太郎(本誌編集部)
静謐な印象で始まる、ポーティスヘッドのヴォーカリストによる初のソロ名義作だが、10年をかけてじっくり作られたという仕上がりは、ここ40年ほどの英国の真摯なポップを総覧しているようでもある。ドラム・サウンドにこだわったというだけあって、後半はかなりドラマティックにトラッドを奏でているような雰囲気もあり、ケイト・ブッシュの85年作『愛のかたち』を思い出したりもした。⑨
GOFISH『GOFISH』
スウィート・ドリーム・プレス SDCD058

石田昌隆
テライショウタのソロ・プロジェクトだけど、演奏は全曲、同じメンバーによるバンド・サウンドになっている。どういうふうにアンサンブルが決まっていくのか判らないが、演奏は、ユニークだけど統一感のある世界観を表現している。特にペダル・スティールが効いている。録音も良い。「けもの」という曲で“ああ、ああ、ああ”と歌っているところがあるが、気持ちの乗せ方が良い感じだ。⑧
つやちゃん
髄所に奇怪な音やクセのある展開が顔を出し、それは参加している演奏メンバー等のラインナップを見ても納得するのだが、でもこれはどうしても“ポップスです”と紹介したくなるような無垢でオープンな空気に満ちている。バンド・アンサンブルなのに、ソロ・プロジェクトらしさが不思議と伝わってくる感じも面白い。一人の音楽家が、すべてを自己開示した開放感がそう思わせるのか。⑧
村尾泰郎
マーティン・デニー風のサウンドから始まり、曲ごとに風景は変わっていくが、どこか非現実的な浮遊感は変わらない。テライショウタの内側から世界を見つめているような奇妙な感覚。立体的な空間のなかで、バンド・サウンドはテライの飾り気のない歌声と一体化。歌と共にアルバムを漂いながら、時には人類が滅んだ遥か未来に音楽を聞いているような途方もない気分にしてくれる。⑨
久保太郎(本誌編集部)
とにかく歌をまっすぐに聴き手に響かせたいという思いが伝わる作品で、音数が少ないながらも的確にヴォーカルを際立たせるバンド・サウンドの美しさも内田直之によるエンジニアリングも実に見事だ。趣味的なグッド・ミュージックに陥る手前でグッとこらえて歌を屹立させつつ、でもポップなクリシェをちょっと許容してもいいかな、というような絶妙な緊張感がほほえましいアルバム。⑧
Tempalay『((ika))』
アンボルデ〔ワーナー〕 WPCL13555

石田昌隆
アルバム・タイトルは“イカ”と読むのだろう。“しきそくぜくう”と読む「(((shiki-soku-ze-kuu)))」に始まり、“くうそくぜしき”と読む「)))kuu-soku-ze-shiki(((」で終わる。どうしてこんなわかりにくい表記にするのだろう。音楽もぼくにはわかりにくいが、もしかして、若い人には表記も音楽もわかりやすいのか?と頭を抱えてしまった。非現実的すぎてつらかった。⑥
つやちゃん
こんなオルタナティヴなバンドが武道館ソールド・アウトなんて、本当にすばらしい時代。19曲とたっぷりなヴォリュームだが、むしろ後半にいくにつれてやりたい放題で笑ってしまった。「時間がない!」の変化球も良いし、「月見うどん」や「今世紀最大の夢」のハズしつつのドリーミーな展開にグッとくる。サイケ感を妖艶で耽美な音色に仕立て上げる能力がずば抜けていて、とても艶やか。⑨
村尾泰郎
キャッチーなメロディーを書けるのに、それをノイズやエディットで解体。その崩し方にこだわりを感じさせる。美しい音も汚れた音も、渾然一体となって高揚感を生み出しているのが現代的。可愛い女性ヴォーカルがフィーチャーされているしダンサブルだし、洗練されたセンスを持っているので、このご時世ならシティ・ポップと言い切ることもできなくもないが、けばけばしい毒気が牙を剥く。⑦
久保太郎(本誌編集部)
試聴用CD-Rをプレイヤーに入れたら収録時間1時間10分超えという表示で90年代のCDみたいだなと思ったが、混沌とした情報量の多いサウンドも90年代的と言えるか。ファルセットを活かした男女ヴォーカルが奏でるメロディとハーモニーの魅力には何度も耳を奪われ、音楽的な素養が相当高い人たちだなと分かるが、全体に貫くニヒリズムの先になにがあるのかまでは、はっきり掴めなかった。⑦
●
以上の「クロス・レヴュー」も掲載されている2024年7月号、好評発売中!
【特集】 アンビエントの時代
【特集】 追悼スティーヴ・アルビニ
折坂悠太/トム・ヨーク/インディアン・ディアスポラ30選 ほか
詳細は下記リンクをご覧ください。
こちらから購入いただけます。
※本記事の無断転載は固くお断りいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
