
【臨床検査技師国家試験】超効率良く合格できる勉強法
〈はじめに〉
第70回臨床検査技師国家試験に約8割の点数で合格することができました(*^◯^*)
私はアニメやゲームが大好きで、そういったものを一切妥協したくなかったので、一日勉強時間を10時間なんて無茶な勉強法はしていません!
そして、基本的に国試前の数ヶ月は学校にもまともに行かず、やることはやってわりと欲望のまま生きてました。
そんな怠慢な私がどうして精神的にも余裕を持って合格できたのか、最低限の労力で合格できる勉強のコツを実体験を含めて記載していきます!
・基本的な用語と略称
[教材]
⚪︎臨床検査技師国家試験解説集Complete+MT
☞「黒本」
⚪︎最新臨床検査学講座(公式の教科書)
☞「赤本」
[出題分野・教科](下の画像参照)
⚪︎アンダーラインが引いてあるもの(3〜8)
☞「主要教科」
⚪︎それ以外(1.2.9.10)
☞「副教科」

と以下略して記載させていただきます。
〈単刀直入!効率が良い勉強の秘訣4選〉
①3年生のうちに、問題の傾向や今後どんな勉強をすれば良いか把握すべし!
4年から始まる復習授業や対策授業で、どこが大事でどこを勉強すれば良いのか事前に知っていることは大きなアドバンテージ!
この時に「あ!これ国試でよく出る問題だ!集中して聞かなきゃ」と思う事ができれば、もう一度集中して勉強しなおすという無駄を省けます。
②4年生の初めは理論で覚えるべし!

4年の最初はこの理論で覚える必要がある「臨床化学」などを勉強し始める事がオススメです!
≪理由は2つ!≫
1.理論で覚えることは長期記憶につながる!
→この時期に暗記で勉強しちゃうとどうせ国試前は忘れてます。
2.理論を覚えることで、わざわざ覚えなくても解けちゃう問題がでてきたり、他の教科の対策にも繋がる!
暗記は一見楽に見えて、自分の首を絞めている場合も多いです。
時と場合で使い分けましょう👍
※ラストの追い込みには暗記が有用だしね
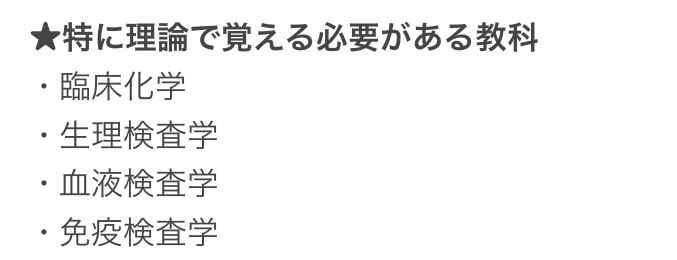
③モチベーションを保つ工夫をすべし!
≪具体的にモチベを保つ工夫≫
1.配点が大きい教科(主要教科)から勉強する。(点数が伸びやすい)
→副教科を本格的にやるのは後!!!
2.勉強に棍を詰めすぎず、メリハリをつける。
3.苦手な教科に取り組まないといけない時、休憩として好きな教科も織り交ぜる。
最初から点数が高ければ、それだけモチベーションになりますし、心に余裕が生まれます。
④模試の前の復習と、模試直しは絶対にやるべし!
模試の前は、自分のまとめノートを一通り読んで、定着させてください!
(まとめただけで満足度してちゃ意味ないのです!)
それに、模試直しをしないと模試をやった意味が本当にないので絶対にやってください!
次の模試に間に合わないときはせめて答えだけでも確認しましょう。
〈実体験!勉強の開始時期と流れ〉
・いつから勉強はじめたの?
私の大学は、臨地実習先と研究室の配属先が4年の最初の模試の成績順で決まるので、3年生の頃に表面だけ黒本を通学時間にたまーに読んだりはしていました。
4年の前半は卒業研究と臨地実習と学会と大学院入試でほとんど暇がなかったので、本格的に始めた時期は4年の10月ぐらいだったと思いますが、ダラダラと始めていたのでこれと言って明確に始めた時期はないです。
・勉強の流れ
①[3年]
心電図検定の勉強や全学年の中でも山場の定期テストがこの時期にあったので、そんなに暇がありませんでしたが、購入した黒本を通学時間に表面だけ読んで、国試問題の傾向や押さえるべきポイントなどを漠然と把握しました。
この頃、同時期に初めての模試がありましたが、たしか85/200点くらいだったような気がします。(その場しのぎで定期テストを受けていたので、2年でやったことほとんど覚えてなかった...)
②[3年:終盤(1月)]
心電図検定3級の試験がありました。
履歴書に何もないと寂しかったり、何か強みがあると就職がしやすいと思うので、資格を取りたい人等は1~3年生のうちにとったほうが良いです!
★学生のうちに取得をオススメする資格については今度まとめたものを掲載予定ですのでお待ちください(^人^)
③[4年:4月〜5月]
「まず始めるべきオススメの教科は、理論で覚える教科とか、臨床化学!」と言っておきながら、等の本人は当時臨床化学が苦手な教科だったので、割と後回しにしていました。(研究室の先生が専門で、勝手に教えてくれるため定着は徐々にしていた。)
この時期は卒研が忙しく国試を勉強した覚えがあんまりないですが、
3年に引き続き、黒本で全体像の把握を中心に勉強をしていたんじゃないかなぁと思います。
余裕があれば、並行して理論で覚える教科のまとめノートなどを作り始めると良いと思います。
④[4年:6月〜7月]
・私の大学はこの時期に臨地実習🧪
・臨地実習の課題である復習レポートは割としっかりやっていて、国試勉強をする暇はありませんでしたが、自然に国試に役立つ知識が定着していました。
実際に経験しないとイメージがつかなくて解けない問題があるので、これはこれで国試対策でした。
余裕がある人はまとめノートの制作を!
⑤[4年:8月〜9月]
・学会、大学院入試の対策、卒研発表など忙しかった。
・まとめノートを並行して作成。
・対策本で過去問と解説を見る
⑥[4年:10月〜11月]
・四年の初めからこのくらいの時期までは模試が月に一回くらいだった気がします。
・提出を求められる場合もあったので、模試直しもやれる範囲でしっかりやりました。
・適宜、まとめノートに新たな知識を追加するの繰り返し。
→これでまとめノートの完成度を上げていきます!
⑦[4年:12月〜1月]
・黒本をしっかりと裏裏回答まで読み込む。
・特に1月は模試が週1ペースに。
・わかる問題が多くなり、模試直しが面倒になってくるので、わからない問題だけ裏回答を作成。
★ようやく副教科に本格的に手をつけ始める。
⑧[4年:2月~国試3日前]
・最終確認(黒本の過去問をもう一周解き直そうとしました→結局時間なくて読み切れなk…)
・大学の図書館で金原出版の問題集を借りました。(ほんの少しだけ使った。)
私の大学で成績がトップだった子は、余裕があったからなのか、この問題集をよく解いていました。
オリジナル問題?もあり、難易度は国試よりも高い問題がちょくちょくあるので、八割や九割を目指す人ならやってもいいかなぁ
⑧[4年:国試2日前~当日]
・自分のまとめノートを一周。→これも結局間に合わないk…
みなさんは、自分のまとめノートの量と相談し、「まとめノートはこれ以降もう二度と見ることはできない」と思ってじっくりと全て読み切れる十分な時間をとってくださいね。
この最後のまとめノート周回は本当に大切。
最後まで覚えられない・不安な表などはスクショして当日にもう一度読み返せるようにまとめておきましょう...!!
〈まとめ〉
【始める教科オススメ優先度】
下の表と並行して、隙間時間に黒本などの過去問で他の教科も触りだけでも良いのでやっていくことがバランスよく得点を伸ばせるコツ!

結局は、好きな教科も織り交ぜながらやりたいやつからやればいいので、縛られすぎないように!
あくまでも参考程度にどうぞ!
〈さいごに〉
いかがだったでしょうか。
自分なりに有料級の情報を詰め込んだつもりです
今回が初めてのブログだったので、もう思いっきり詰め込みました!
今後も時間ある時に投稿していきたいと思っていますので、SNSなどのフォローもぜひ!
オススメの参考書や就職関連についても投稿していこうと思ってます(^^)
最後まで読んでいただきありがとうございました!

第70回臨床検査技師国家試験合格💮
医科大学内の難治性疾患治療に関する研究をしている場に就職が決定し、技術員兼研究員として活動🔬
X(旧Twitter)やInstagram、
SUZURIでもグッズ販売中
※こちらのブログはアフィリエイトリンクを含んでいる場合があります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
