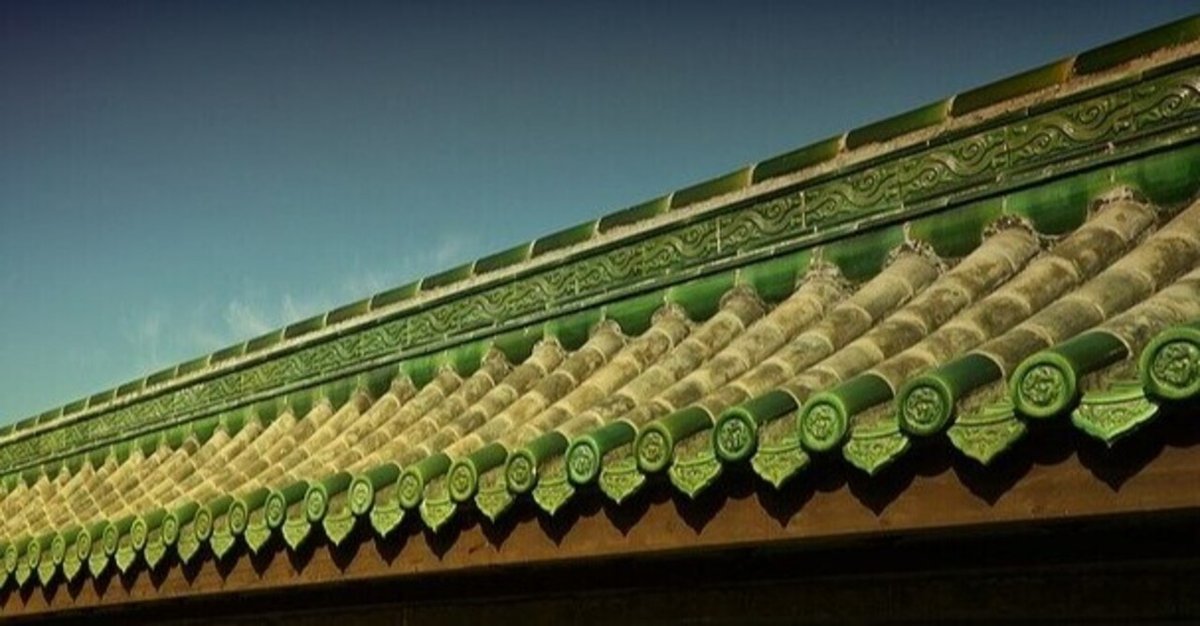
史実からみた三国志の世界を語ってみたよ
この記事は「マイスター・ギルド:夏のアドベントカレンダー2021」12日目の記事です。
はじめまして。マイスター・ギルドの大江です。
note初投稿、そしてアドベントカレンダーなるものに初挑戦です。
どうぞお手柔らかに。
今回note初記事として私の数ある趣味趣向の中で歴史というジャンルでのお話を書いてみたいと思います。
歴史のなかでも特に三国志の世界にのめり込んで小説とか漫画、ゲームなどありとあらゆる三国志を堪能しつくしてきたんですが、それだけでは飽き足らず「正史三国志」という歴史書まで読破してしまうほどのハマりっぷり。
もはや三国志ファンではなく三国志マニアといっても過言ではないでしょう!
(多分ちょっと言い過ぎ)
そんな三国志について少し熱くゆるーく語ってみたいと思います。
ゲーム「三國無双」や漫画「蒼天航路」、北方謙三の小説「三国志」など様々なコンテンツのほとんどが中国の明代に創作された「三国志演義」と呼ばれる小説がもとになっているのをご存知ですか?
(三国志演義は「水滸伝」「西遊記」「金瓶梅」と並ぶ中国4大歴史小説のひとつです)
この三国志演義も正史三国志をはじめ様々な文献とか逸話なんかの史実をもとにして作られてるんですが、より話を面白おかしくするために架空の世界観やキャラ設定、エピソードなんかがいたるところにちりばめられたりしてるんです。
史実を読み解くと「えっ!?そうだったの!?」とそれまで慣れ親しんだ三国志のイメージとのギャップなんかに驚くこともしばしば。
そんな三国志の史実で語られた特に印象深いトピックスを3つほど紹介したいと思います!
(内容は諸説ありです)
乱世の奸雄、曹操の素顔とは!?
曹操といえば三国志演義の主人公劉備の敵(悪役)として誰もが知る人気の高い武将。
後漢末期の群雄割拠の戦乱においてメキメキと頭角を現し最大勢力を築いた曹操はコーエー三国志や三國無双のようなちょいワルおやじな風貌と渋い声で威風堂々としたキャラがとても印象的でメチャカッコいい武将だったりします。
しかしそんな曹操の容姿について「魏氏春秋」や「世説新語」といった文献には、
「姿貌短小(見た目ちっちゃい)」「形陋(みすぼらしい)」
(゚Д゚) ちょっとヒドくない?
正史三国志では劉備や孫権の容姿についてはわりと普通に書かれているのに何故か曹操に対しては全く触れられてないばかりか他の文献ではひどい言われよう。
(あまりにひどくて正史三国志には書けなかったとの噂も・・・)
この時代は「有能=家柄&容姿(特に身長)」だったようで、家が金持ち&高身長イケメンなら多少のバカでもヒョロガリでもモテモテの出世街道まっしぐらなのです。
(ちなみに曹操は家柄もあまり良くなくて曹操自身ちょっとそれを気にしてる)
今も昔も世知辛い世の中ですよねっ!!
だけどそんな容姿や家柄がビミョーでも文武の才はずば抜けて高く、君主としてのカリスマ性に加えて軍略家・政治家としての高い能力のみならず詩人・文学者としてもその名を後世に轟かすほどの才能のかたまりだったようです。
特に文学者としての能力は高く現代の独裁者や経営者にも愛読者が多い「孫子の兵法書」は当時誰も理解できないほど難しかったものを曹操自ら筆を執りわかりやすく書き直したそうで、今の世に出ている「孫子の兵法書」は曹操なくしてありえなかったと言われるほど。
そして何よりも人を見る目はバツグンで優秀な人材を敵味方関係なく貪欲に集めまくってはその能力をいかんなく発揮させて魏の国の礎を築く名采配ぶり。
容姿や家柄に惑わされることなく人の才能を見抜いて適材適所に采配したその能力は意外と曹操自身の容姿と能力に対するコンプレックスからきてるのかもしれませんね。
三国志のクライマックス、赤壁の戦いの舞台裏に迫る!
画像引用元:photolibrary
三国志のイチバンの見せ場といえば映画「レッドクリフ」の題材にもなった「赤壁の戦い」。
(金城武が演じる諸葛孔明はめちゃカッコいい)
天下統一を目指し南下してきた最強の曹操軍vs劉備・孫権連合軍との長江を舞台とした戦いで、呉の軍師周瑜の敵軍の船を鎖で繋ぐ「連環の計」と劉備の軍師孔明の東南の風を使った強力な「火計」のコンボによって大船団で対峙した曹操軍の船を焼き払い撃退した痛快なストーリーなんですよね。
でも実はそのほとんどが創作なんです。
長江で曹操軍vs劉備・孫権連合軍の戦い自体はあったのですが小競り合い程度で実際は曹操軍の疫病が蔓延したことによる撤退なんだそう。
「連環の計」と「火計」で敵の船を焼き払って撃退した話も後の明代の皇帝朱元璋が同じ赤壁の地で行われた「鄱陽湖の戦い」で使った戦術で、この戦いを丸パクリしたと言われているんです。
三国志演義は明代の羅貫中という人物が書いたと言われていますが、強大な敵に対して主人公が仲間と手を取りあってやっつけるというストーリーは当時の話を面白くするための常套手段だったようで、
羅貫中「んー、クライマックスは赤壁の戦いがいいなー」
羅貫中「あれー?でも史実は中身なくて全然面白くない」
羅貫中「あっ、そうだ鄱陽湖の戦いあったじゃんあれパクろ」
といった感じだったんでしょうね。
ちなみに関羽の青龍偃月刀(せいりゅうえんげつとう)や張飛の蛇矛(だぼう)といった武器も三国志の時代にはなく明代あたりから出てきました。
昔話に現代(明代)のエピソードや時代背景をうまく溶け込ませることで当時の三国志演義の話をより大衆に親しみやすくしたんだと思うんです。
一騎当千、ゲーム三國無双を地で行く猛将!
「登竜門」「十人十色」「破竹の勢い」「苦肉の策」
皆さんが一度は聞いたことのあるこれらの四字熟語や故事は三国志がその由来になっています。これ以外にも様々なものがあるんですが
「泣く子も黙る〜」
っていうフレーズをどこかで聞いたことありますよね?
これは「泣く子も黙る張遼」という故事がもとになってるんです。
張遼といえば後漢末期に三国志最強の武将呂布の配下として曹操と戦い、その後呂布を打ち破った曹操に捕らえられて曹操の説得により臣下となって様々な戦いで大活躍した三国志ファンから高い人気を誇っている武将です。
(すごく好きな武将でつい拼音発音のチャンリャオってなぜか言ってしまいます)
そして史実において「合肥の戦い」と呼ばれる呉の孫権が自ら10万の軍勢を引き連れて張遼が守る合肥の城へと攻め入ってきたお話がイチバンのハイライト。
張遼は千人足らずで城を守っていて進軍してきた10万の孫権軍に勝てるわけねーと思いますが、何をトチ狂ったのか城に立て篭もらず100分の1の兵力差なのに少ない兵士と城を飛び出し自ら先陣きって孫権軍に猛アタック。
しかも鬼の強さで攻め入って孫権をもう少しで捕らえられるところまで追い詰めたそうです。
(ちなみに当時は相手の兵力を10倍に盛って報告するという慣習があったそうなのでおそらく孫権軍の兵力が1万だった可能性あり)
たまらず孫権は一目散に逃げていき、張遼は城に引き返そうとしましたが味方の兵士が逃げ遅れて大軍勢に囲まれているところに引き返して敵の囲みを打ち破って救出したとあります。このとき呉の兵士は既に戦意喪失して誰も張遼に近寄れなかったそう。
(正直こんな戦い方はゲームの中だけかと思ってました)
この戦いで呉の武将兵士は「魏に張遼っていうやべーばけもんみたいなやつがいる」ってかなり動揺が走ったことが民衆にも知れ渡ることになります。
そしてそんな呉の民衆の間では「張来々!(チャンライライ:張遼が来るぞ)」が流行り言葉になって泣いてる子供はその言葉を聞くと恐怖のあまり必ず泣き止んだそうです。
まさに三国志のタケモトピアノ!?
(この意味わかるかな?)
ゲーム「真・三國無双」で張遼を使ってプレイすると必ずと言っていいほどこの「合肥の戦い」を思い浮かべながらプレイすることになります。
(でもゲームでいちばん好きなキャラは孫尚香だったりします)
あとがき

三国志は語りだしたらいくら時間があっても足りません。
(ホントは諸葛亮や趙雲のことも書きたかった)
今回書いたお話もかなり端折って書いてしまいました。
三国志に限らずですが興味のあるものは何でもとことんまで追求しちゃうタチなんです。
そして三国志もそれなりに詳しいとはいいつつまだまだ知らないことの方が断然多いんです。
だからこそいつまでも飽きずに興味を持ち続けられるんだと思います。
投稿者:大江
マイスター・ギルドの異端児。
ムーミンとジブリをこよなく愛する生涯フットボーラー。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

