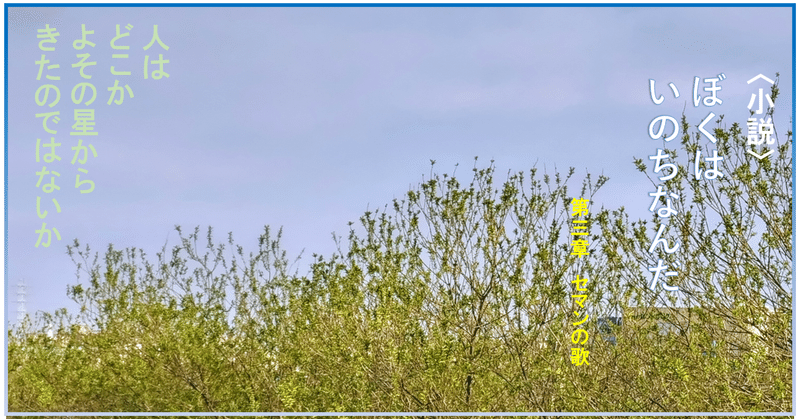
元気な社会(五)
❞元気な社会❞(五)
ルビンが、いのちのセマンと出会い、セマンの翼のうえで夢路の旅にいざなわれて得たものは、物でもなく、欲でもなかった。
それよりはるかに大きく、はるかに澄んだものであった。
きれいな空気をつくる緑であり、その空気や精気をかかえる青い大気であり、人を理解できるマリンブルーの大海であった。
その後ルビンは、寛容で厳格な家庭に育った。
しかし、幼年期をすぎ、中学校時代にさしかかるにつれ、人の物欲が、いやでも目にはいる社会をみてきた。
それは、あらゆるところに現れて、人をねたませ、人を差別し、あげくのはてには、こころなんかよりもカネだと騒ぎを起こす。
子どもたちは、どんなこころで生きていかなくてはいけないのか、きまって物やおカネをもたなくては生きていけないのか、それがわからなくなっていた。
何がいちばん恐いかといえば、何がよくて何が悪いのか、とふんべつするこころを忘れることであった。
救いの手がかりはひとつ。
それは、ともだちの行動である。ともだちのしていることが正しく、そうでないこと、それに反することはまちがいだ、という感覚にヒントがあると考えた。
ルビンの気になることは、こどもたちに元気がなかったことである。
元来の気が薄れていたのである。万物生成の根本となる精気が、活動のみなもととなる気力が、なかったのである。
人の活気の裏側だけが見えている状況であったのだ。
ルビンは、いつも思っていた。
――人もほかの生き物も、意味のあることのできる天性をさずかって生まれている。さずかった天性でまっすぐに、意味のあることをして生きぬいている。大自然を相手にして、それぞれが自然に、つとめをりっぱにはたしている。
人が、かりにほかの星からやってきた生命体であったにせよ、宇宙やこの星の大自然の理法にそって生きればいいのである。いくらさからっても、大自然にまさるはずはない――と。
人は、豊かなこころに飢えると、自然に反発してしまうのだ、と。
人々がほしいのは、元気なこころなんだ・・・、と、ルビンは、いつも思っていたのである。
そのこころをどのように取り戻せばよいかを、いつも考えてきた。
それには、美脳をとり戻せばいいのだ、と。
ルビンがいのちのセマンにそうしてもらったように、子どもたちにも、いのちの翼をあたえなくてはならないと考えてきたのである。
青い空の空気を、青い海の潮風を、子どもたちに、からだいっぱいあびてもらいたいと思ってきたのである。
そして、この島がいい、この島で生活したい、とせがむ子どもたちがおおぜいあらわれてほしかったのである。
つづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
