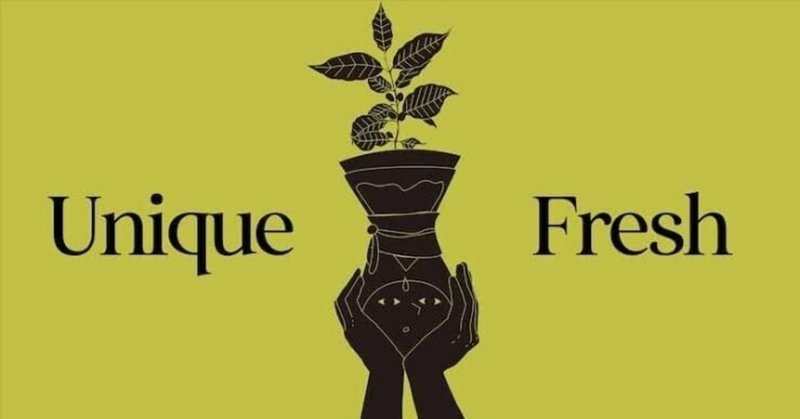
コーヒーの2050年問題
Ep3 コーヒー2050年問題
こんばんわ
RUです。更新まで少し間が空いてしまいました。
年を重ねると、一つのことを継続・習慣化することが難しくなってきますよね。
意識的にでも、何か続けることって素敵な事だと最近つくづく感じます。
今日は「コーヒーの2050年問題」について
コーヒーの2050年問題って何?それって感じですよね。
私も、最初はそう思いました。
なんだか、私達が普段暮らす毎日とは関係がないように感じますが、
「生産者と消費者の間の問題」はコーヒーに限らず存在する問題だと思います。
ここでは、コーヒー市場の視点からにはなりますが、読んでくださっている皆さんと一緒に知ったり、考えるきっかけになればなと思ってシェアします。
簡単にまとめたので読んでみてください。
「2050年にはコーヒーが飲めなくなる?」
世界で消費されているコーヒーの7割を占めるアラビカ種の栽培に適した土地が
気候変動によって2050年には半減すると予測されている
<予想される問題>
・気温上昇や降雨量の変化による収穫量の減少
・コーヒーの品質低下
・コーヒーに携わる人々の収入を減少
そのため、現在の農法や品質を維持したコーヒーを栽培する事が難しくなると言われていて、コーヒー栽培自体を諦めなければいけない状況に追い込まれる生産者が出てくる可能性があるのが現状です。

このままだと・・・?
資金的な体力のある大規模農園やグローバル企業の契約農園でしか、コーヒーを栽培することが難しくなり、現在のスペシャリティコーヒーと呼ばれる多種多様なコーヒーは店頭から消え去ってしまう可能性があります。
国際相場に左右されるコーヒー取引では、大量生産されたコーヒーの供給量が増えれば増えるほど、小規模生産者の収入が減少します。
環境問題の表面化
コロンビアの一部地域では、雨期と乾季の極端化による収量の減少が報告されている。ホンジュラス・エルサルバドル・グアテマラ・ニカラグラでは既に、コーヒー栽培では家計を支えられないことから、アメリカへの密入国を図るケースも増加している。
また、高品質なコーヒーの生産地として知られるケニア・メキシコ、上記の国々も深刻な危機に直面している。
流通の仕方にフォーカスした新たな取り組み
手間暇かけて作られたコーヒーを育てたとしても、国外の市場へアクセスする事ができなかった小規模コーヒー農業は国内の協同組合やエクスポーター(輸出者)に先物価格に基づいた生豆を販売するしかなかった。その為、小規模コーヒー農家が生産コストや生活費を賄えないケースもあり、気候変動のように大きな変化に適応する必要資金を捻出できない状況にありました。
そこで、TYPI CAは価格決定権を生産者に委譲し、ロースターが焙煎豆をカフェや消費者に売るときのように、自分たちで価格を決定できるシステムを導入。
このシステム導入により、生産者は本来あるべき、品質に合った価格での取引が可能になります。
ここで、TYPICAについて少しだけ紹介します。
TYPICAとは、世界中のコーヒー小規模生産者の収益性とロースターの付加価値を高めるための挑戦を目指す企業。
以前までは、コーヒー豆がコンテナ単位(約18t)からの取引が主流だったが、
TYPICAは、麻袋1袋(30kg~60kg)単位でコーヒー生豆のダイレクトルートトレード(直接取引)をすることができるようになります。
規模の大小に関わらず、生産者とロースターにダイレクトトレードできること。サプライチェーンと価格の透明性を確保することをビジョンに掲げている企業です
今回は、少し長くなってしまったのでこれで終了。
次回、第二弾、コーヒー2050年問題!
この記事では、コーヒーの現状と問題について触れたので、
次回は、コーヒーのこれからの取り組みについて触れていきたいと思います。
また、お会いしましょう。
参考

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
