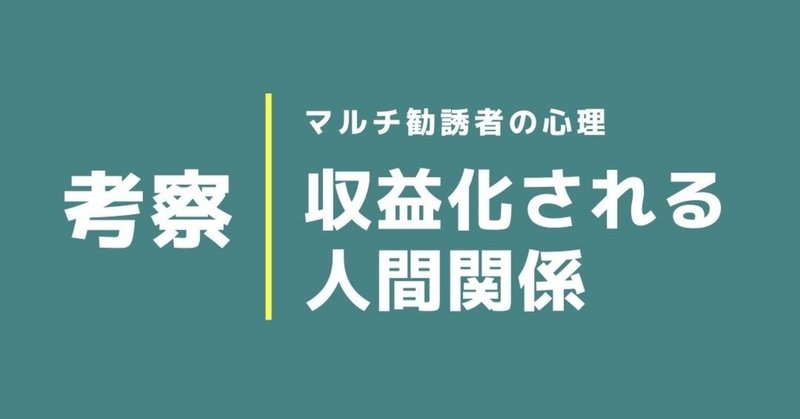
マルチ商法考察: 収益化される人間関係
信頼を利用した勧誘行為が人間関係に与える影響、勧誘者がどういうマインドで勧誘しているか、彼らと接して感じたことについて少し書いてみたいと思います。
マルチ勧誘者が現れる場所
同窓会や合コン、街コン、フットサル大会などに誘われて、蓋を開けてみたらマルチの勧誘だった…という被害はいまだに耳にします。異業種交流会や勉強会に紛れ込んで参加者を勧誘する事例もあるようです。コロナ禍の最中にある現在は違った手法に変わっているのでしょうか。
出会いの場を使って勧誘する手口は、有効だからこそ使い古されているのでしょうけど、だまし討ちです。気心が知れた(と思っていた)友人に会いたかっただけなのに。友達を作りに行っただけなのに。気づいたら何故か勧誘者やその"師匠"、そのまた"師匠"にお金を渡す流れになるわけですから。
取り込まれたら、自分も誰かを勧誘するまでは一方的にお金を吸い上げられる仕組みです。
「本当の友達は勧誘しても離れていかない」?
勧誘者達は口を揃えてこう言います。しかし「勧誘しても離れなかったように見える友人」との友情がどれほど深く続いているかなんて、本当のところは分かりません。
また、友達が居なくても「サークル活動をしていくうちに友達は沢山できる」などと言われます。確かに一時的にはそうなるかもしれません。
そこでできた友達は、自分がマルチサークルの活動を続けられなくなっても、友達でいてくれるでしょうか。
勧誘する側には「勧誘行為によって相手の信頼を傷つける」という意識が全くない点が非常に厄介です。マルチ商法に取り込まれると「友達・恋人・家族を勧誘することは、幸せを広めることなので良いことだ(意訳)」と徹底的に教え込まれるので、罪悪感など湧く余地もありません。
殆どの会員が「良い行い」をしている気持ちになっているような印象を受けました。それはうわべだけで、勧誘対象がお金にしか見えていないケースもあるかもしれませんが。殆どの人が自分も勧誘対象も"成功"できると信じていたようでした。
「人間関係が密な日本だから、ネットワークビジネスは批判されるんだ。〇国ではもっと合理的な考え方をするから、友情に影響がない。日本は遅れている」
こんな主張も実際に耳にしましたが、国柄は関係ないと考えています。英語で「MLM Problem Friendship」などのキーワードで検索するだけでも、勧誘行為に伴う倫理的・モラル面での問題を指摘する記事を数多く目にします。
ところで、勧誘者はマルチサークル内でも決して「マルチ商法」という単語を使いません。「ネットワークビジネス」と呼びます。
以下は同じことを指します。
・マルチ商法
・マルチレベルマーケティング
・MLM
・連鎖販売取引
・ネットワークビジネス
「ねずみ講」は加入者を集めてお金をとる手法は共通してますが「商材に実体がない(あったとしても粗悪品)」などの特徴があります。
また、ねずみ講は違法とされている一方で、マルチ商法は合法です。マルチ会員が勧誘行為を正当化する際に「合法性」を引き合いに出すことも多いようです。
勧誘対象からの質問にはテンプレ回答がある
「本当にいい商品・システムなら、マルチ商法という売り方をしなくても普通に売れるのでは?」と率直に問いたいと思うでしょう。
しかし勧誘者サイドは「これを聞かれたらどう切り替えすべきか」というノウハウも当然、持っています。
例えば、旧友に対する勧誘行為を「プライベートの人間関係をお金に換えてるようなものではないか」と疑問を投げかけた場合、勧誘者は「そういう考え方はマイナス思考だよ。これは”みんな”がハッピーになれる仕組みなんだし、幸せの輪を広げていこうよ」といった趣旨の回答で身をかわします。
特に"師匠"と呼ばれる人には、どんな疑問を投げかけても、本当にスラスラと返事が来ます。勧誘された人が逃げないよう、予め心の中で準備していた理論や思想を展開させ、相手を言いくるめます。
退会を決心した人は、彼らとまともに取り合わない方が良いと思います。
本当に"みんな"はハッピーになれるのか
マルチ勧誘の被害に遭った時に、相談先の消費生活センターの担当の方がこんな例え話を聞かせてくださいました。
ある村に100人の村人が住んでいました。
1人目の村人が「仲間を誘うと、お金が貰える」というビジネスを始めました。誘われた村人は他の村人を誘い、気づけば99人の村人が参加していました。最後の100人目の村人には、誘える相手がいません。お金が貰えません。
当事者である場合は勿論のこと、大切な人がマルチサークルに入会して悩んでいる方も、自治体の消費生活センターに相談してみるのが良いかもしれません。
持っていると成功できない”マイナス思考”の正体
勧誘されたマルチサークルでは、一般的常識という名の”マイナス思考”を持っていると、成功できないようでした。もしかするとサークルによっても違うのかもしれませんが、少なくともこのサークル内では顕著な思想でした。
勧誘された当初、自分の夢や目標などを紙に書くよう勧められたのですが、書くことがなくなると「今は無茶だと思うような夢でも良いから、常識を取り払って思い切り書いてごらん」と"師匠"に指示されました。
気づけば特に欲しくもないものや、それほど望んでないことで紙が埋まってました。
「常識の枠組みにとらわれず、夢は大きく持て」と教えられるのも、勧誘される人が本来持っているはずの冷静な判断力を鈍らせる効果があるのかもしれません。
サークルが主催するセミナーへの参加や、勧誘行為を続けていると「自分の行いは周りの人を悲しませていないか?」という良心の声も、聞こえなくなってしまうのかもしれません。そんな"マイナス思考"なんて持っていたら、成功できないと刷り込まれるのですから。
「成功したい、何もない元の自分には戻りたくない」。そのような思いに囚われ、百万単位で借金をしてもマルチサークルをやめられない人もいます。経済面でも心理面でも、マルチ会員は加害者であると同時に被害者でもあると感じます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
