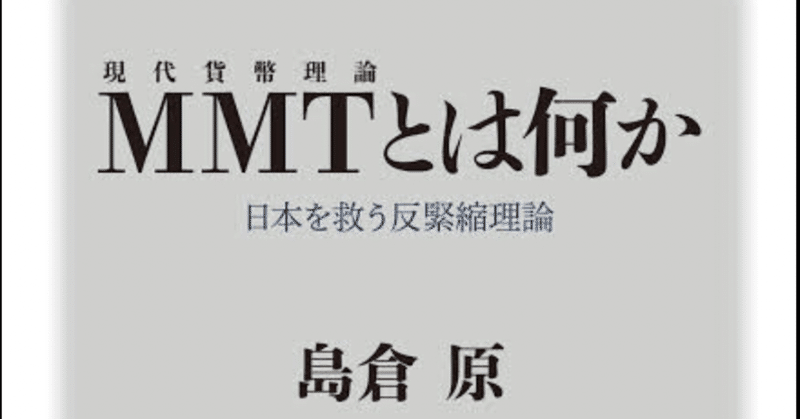
MMTとは何か <日本を救う半緊縮理論> 島倉原著 角川書店 1
新書版の薄さでありながら、MMTの主張を網羅し、かつ客観的データで検証しているとともに、日本のいまの経済状況にどう応用できるかまで踏み込んで解説している。私のように中途半端に経済学をかじった人間にとっても平易であると同時に、信頼性の高いデータを利用しているので納得感もある、お勧めの一冊。いくつかMMTの本を読ませてもらったが、ケルトン教授の「財政赤字の神話」を読んで概略を理解したうえで、この本で確認していくのが一番よく理解できると思う。
内容は読んでいただくとして、一般的なMMTに対する質問にこの本がどう答えているか、Q&A的にまとめてみる。
MMTの骨子は?
=完全雇用と物価の安定を目指す財政提言
=通貨は税金を払うための手段として発達してきた
=自国通貨を発行できる政府において、財政破綻は理論的にあり得ない
=金融緩和(現在の政府・日銀の政策)よりも財政出動(直接政府支出によって 民間の消費意欲を刺激する)の方が効く
= 政府の赤字は民間の黒字
= 政府は無限に通貨を発行できる、ただし過度なインフレにならないよう調整が必要・・つまり財源論は意味のない議論。
= 財政支出において、その支出先が未来につながるものであれば良い。
MMTは無税国家を目指すのか?
= 違う。MMTは貨幣価値を、税金を納めるための手段として定義している。それゆえ無税にしてしまうと、貨幣としての価値が国民に認められなくなるので、無税国家はあり得ない。
税金は何のためにあるのか?
= 納税のために通貨に対する需要を生む。
= 過度なインフレを起こさないための調整弁
= 富の再分配(累進課税所得税、固定資産税、相続税)
= 悪い行いを正す(タバコ税、酒税、環境税、関税)・・関税は国内産業/雇用の急激な衰退を緩和するため
= 税金は国庫を潤すためのものではない!
課すべきではない税は?
= 社会保障税 (企業負担を押し上げ、雇用の抑制につながる)
= 消費税 (購買力を引き下げるので特に不況・デフレ時はだめ。逆進性も高い)
= 法人税 (雇用を海外に移す可能性が高まる。利息が経費になるので借り入れが増える)
MMTは社会主義、共産主義か?
= 違う。財政出動は、あくまで受益者の負担を求める(リタイヤした年金生活者は別)もので、労働意欲と労働機会を達成するための考え方。自由経済や貿易を否定していない。
本当に国家の赤字は民間の黒字なのか?
Aの支出は、Bの収入。そしてその支出と収入を足すとゼロになる。
同じ原理で政府の黒字は、民間の赤字になり、これを足すとゼロになる。
つまり政府は黒字で、さらに民間も黒字ということは原理的にあり得ない。
つまり緊縮財政(政府が黒字を目指す政策)は、民間の赤字につながるということか?
Yes。日本の場合は1990年半ばからずっと緊縮財政モードになっており、それにより民間(企業・個人)の収益は悪化し、デフレ+不況が続いている。
逆に言えば、民間が黒字であり続けるためには、政府は赤字であり続ける必要がある。
国債の役割とは何か?
= 金利が低すぎて過剰投資及びインフレを誘発する場合に国債を発行し、通貨を市中から吸収して金利を上げ、インフレを抑制するための道具。
= 金利が高く、デフレ基調であれば逆に国債を購入し、市中に多くの通貨を流通させ、景気を促進する。
円建ての国債が海外にわたり、それが暴落したり、為替危機をもたらさないのか?
= 海外部門と民間部門で、国債の意味合いは一緒。
= 仮に何らかの要因で海外投資家が日本国債を大量に売り出すとすると、確かに国債価格は下がり、金利は上がり、かつ円安圧力が生まれる。
しかし、上がった金利分は国債を増発することで支払える。かつ金利上昇は、市中の国債を政府日銀が買い上げることで市場の国債を減らし、金利を下げられる。
また円安圧力は、日本は変動相場制採用国家なので、自動的に修正される。つまり円安で輸入は減り、輸出は増える貿易収支は悪化し、その分円への需要は増え、円の対外レートは適正水準に落ちつく。
(その2に続く)
宜しければサポートをお願いいたします。これからも世のため人のため、役に立つ情報発信に努めます。
