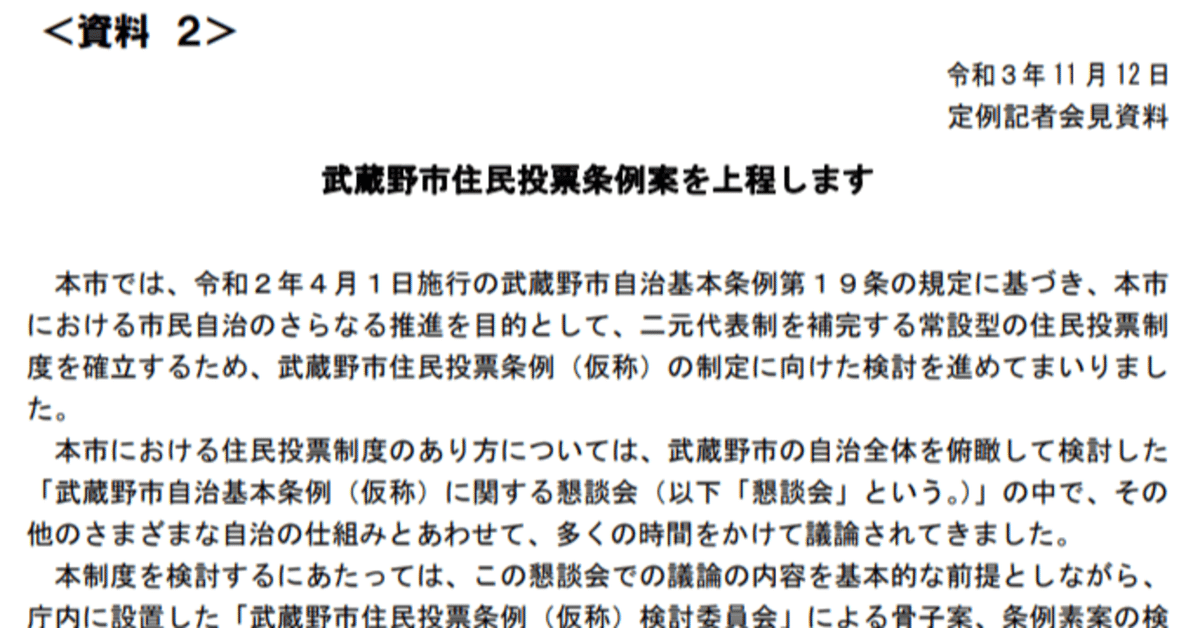
一武蔵野市民の住民投票条例についての見解
現在、武蔵野市においては市長により外国人に投票権を付与する武蔵野市住民投票条例案(以下で、「本条例案」という。)が市議会に提案されているところだが、外国人に投票権を付与する点において民主主義を害する懸念があり、これに反対する。以下に詳細を述べる。
なお、武蔵野市は、本条例案において外国人に投票権を付与することについて、その結論に至った具体的な理由(外国人に住民投票権を付与しない現在、市政において具体的に発生している問題や、当該問題を解消する施策として外国人に住民投票権を付与することの必要性や相当性など)を何らを示すことなく、合理的であると説明するのみである。
市が本条例案において外国人投票権付与を合理的とする具体的な理由は明らかではないが、これまでの市の説明に基づき、その合理性を別途検証したノートについては、下記を参照いただきたい。
1.手続上の問題
本条例は、市長によるその骨子案の提案から素案の提案、さらには本条例案の成案の議会への提案までのプロセスにおいて、市民への周知および意見の聴取が極めて不十分であり、多くの市民の意見を無視して今日に至っている。条例案の作成過程が、そもそも、住民自治に反している面があると考え、この点から、本条例案は一旦撤回した上で、改めて市民の意見を聴取した上で検討する必要があると考えるが、この手続面についての不備については、下記のノートにその一部について触れたが、他にもその詳細について議論されているものもあるため(例えば、長島昭久衆議院議員のnote)、ここではこれ以上触れない。
2.内容上の問題
ここでは、本条例が外国人に投票権を付与している点について、民主主義、住民自治の観点からの問題を指摘したい。
①.選挙権・被選挙権は国民のみが有する
まず、そもそも、現在の憲法及び公職選挙法においては、国政に関する選挙権・被選挙権だけでなく、地方レベルにおける選挙権・被選挙権についても、例外なく国民のみに付与されている。すなわち、仮に外国人が日本に長期にわたり在住し、永住資格などを得ているとしても、上記の選挙権・被選挙権は付与されていない。これは、憲法上、国政、地方政治を問わず、選挙権・被選挙権は国民にのみ付与されており、外国人には付与されていないためである。
②.地方自治法上の住民投票の投票権も国民のみが有する
そして、現在の地方自治体においては、住民が選挙により選んだ首長と議員が住民の代表者として地方自治体の政治決定を行う二元代表制が採用されているが、この間接民主制の他に、住民がそれらの代表者を通さず、住民投票により、首長・議員のリコールや議会の解散請求などの直接請求を行う直接民主制の制度が地方自治法上存在する。この住民投票についても、その投票権者は当該自治体の住民のなかでも国民に限られている。つまり、選挙権を有する者と住民投票の権利を有する者の範囲は同じである。この理由は、上記のとおり、住民投票は、民主制の一つであるという点で選挙と同じであり、地方政治の決定システムの一制度であることに変わりはないため、選挙権と同じく国民にのみ付与されているためである。また、住民投票は、選挙と異なり、住民がその代表を通さず、リコールや議会解散などを直接に請求する権利であることからすれば、民意を地方政治に反映する制度としては選挙よりも直接的であると言うことができ、そのため、その投票権者については国民に限定することはより求められるとも言える。
③.住民投票が参政権とは異なることが外国人住民投票権の理由とはならない
武蔵野市市長は、住民投票は選挙権等の参政権(厳密には選挙権を意味していると思われる。)とは異なると説明している。しかし、そもそも、住民投票は、上記のとおり、直接民主制の一つであり、選挙権等の間接民主制と同様に、政治に参加する制度の一つであり、広い意味では参政権の一種であると言える。しかも、上記のとおり、住民投票は、民意を地方政治に反映する制度としては選挙よりも直接的な制度である。よって、住民投票においても、参政権(選挙権)と同様に、あるいはそれ以上に、その参加者を国民に限定するのが原則であるべきであり、参政権(選挙権)とは異なることが、外国人を参加対象とする合理的理由とはならない。
④.諮問型の住民投票であっても二元代表による政治決定に重要な影響力がある
また、武蔵野市市長は、本条例に基づく住民投票は、上記のリコールなどに関する住民投票と異なり、法的拘束力がない諮問型の制度であることから、外国人に投票権を与えることが合理的であるとも説明している。しかしながら、法的拘束力はないとしても、条例上、市長と議員は住民投票の結果を尊重する義務を負うものとされている。
しかも、本条例の素案の説明では、『法的拘束力を持たない「諮問型」と呼ばれる住民投票制度ではありますが、投票資格者数の4分の1以上(約32,000件)という署名が集められ、議会の議決を要せずに実施された住民投票の結果については、市長と議会は重く受け止めたうえで、最終的に市長と議会が決定するものと考えます。』とされている。さらに本条例の元となっている住民自治基本条例の市が作成した逐条解説では『現行の制度上は、住民投票の結果に法的な拘束力を持たせることはできないため、投票の結果については、市長及び議会は「尊重する」という規定となります。とはいえ、住民投票の結果には実質的な拘束力が生まれるものと考えられる(後略)』と解説されている。住民自治の推進のために、常設型の住民投票制度が制定され、投票資格者の4分の1以上の署名が集められて発議され、投票資格者の2分の1以上(投票率50%以上)の投票により成立した住民投票の結果について、市や議員が実質的に拘束される、あるいは少なくとも重要な影響を受けると考えるのは当然であろう。
さらに、本条例では、住民投票の対象の一つとして、住民が地方自治法上の直接請求により求めた条例の制定・改廃を議会が否決した場合が含まれている。この場合に、当該条例の制定・改廃に関する住民投票が可決された場合、その住民投票は議会の否決の判断そのものを否定する結果となるため、その後当該条例の制定・改廃を可決するよう、議会に対しては政治的な圧力が相当にかかることが予想される。
このように考えれば、法定拘束力がないからという形式論により、住民投票の投票権者に外国人を含めてよいとすることは説得力に欠け、住民投票の結果をそのように軽視する考えは、住民自治の理念にも反する。むしろ、諮問型の住民投票であるとしても、投票資格者の4分の1以上の署名により発議され、その2分の1以上により成立した住民投票の結果は、住民の民意として市及び議員は重く受け止め尊重する義務があり、少なくとも、その政治決定について重要な影響を及ぼすことは避けられないと考えるのが、住民自治基本条例や本条例の素案の解説や、住民自治の趣旨からすれば、自然である。
⑤.外国人住民投票権は、国民の一票の価値を毀損し、二元代表制による民意を歪めることになる
諮問型の住民投票であっても二元代表による政治決定に重要な影響力があるとするならば、本条例に基づく住民投票の投票権についても、リコールなどの住民投票のそれと同じく、国民たる住民に限定するべきと考えるのが自然である。
また、市長や議員を選挙で選ぶ有権者の範囲よりも住民投票の投票権者の範囲を広げ、外国人を含めた場合には、その外国人の数の多寡にかかわらず、投票権者がずれることから、理論的に、外国人を含む住民投票により表される民意は、選挙により表された国民たる住民の民意とは異なるものとならざるを得ないし、国民たる住民一人一人が有するべき一票の価値が毀損されることになる。
そして、上記のとおり住民投票の結果を二元代表は尊重する義務があることからすれば、二元代表の選挙により示された民意が住民投票により示された民意に歪められる結果となりかねない。特に、住民投票の結果が僅差の場合には、外国人の数が全体に占める割合が少なかったとしても、その投票行動が結果を左右するリスクもある。
⑥ 本条例案に基づく住民投票の投票権者についても欠格事由は設けるべきであり、外国人に投票権を付与することから欠格事由を設けないのは本末転倒である
本条例案の骨子案12頁によれば、投票権を有しない者について、「選挙権の欠格事由に該当する者を除外する規定は設けません。これは、憲法改正の国民投票と同様に、本市の住民投票も頻繁に行われるものではないと想定されるため、たまたまその時期に公民権を停止されているという理由だけで、市政の重要事項に対して意見を表明する機会を奪うのは適切ではなく、より多くの住民が投票に参加できることが望ましいと考えられるためです。」と記載されている。
しかしながら、憲法改正の国民投票は憲法制定以来、70年以上の間一度も実施されていないが、武蔵野市の住民投票も今後そのような期間実施されないとする根拠が余りに薄弱である。実際、他の自治体を見れば、憲法改正の国民投票が行われていない期間中にも、住民投票が行われた自治体は数多く存在する。
地方自治法上のリコールや議会解散の住民投票も、本条例案の住民投票と同様に、あるいは法的拘束力があることから、それ以上に、市政の重要事項に関する住民投票と考えることができるはずであるが、これには欠格事由(公職選挙法11条)は定められている。
以上からすれば、本条例案に基づく住民投票においても、欠格事由を定めるべきであり、憲法改正の国民投票と同様に不要とする理屈は不自然、不合理と考える。これは推測であるが、このような建付としたのは、投票権者に外国人を加えたために、武蔵野市が住民投票を実施する際に、外国人について欠格事由と確認することが実務上困難であることためではないかと考える。もしそれが正しいのであれば、欠格事由を定めないのは憲法改正の国民投票と同じく、頻繁に行われるものではないためという武蔵野市の説明自体が、武蔵野市民を欺くものとも言える。
地方自治法上の住民投票と、本条例案に基づく住民投票は、いずれも市政の重要事項に関するものであり、投票権者の範囲について差異を設けるべき合理性がないのであるから、本条例案に基づく住民投票の投票権者についても欠格事由は設けるべきであり、外国人に投票権を付与することを理由に欠格事由を設けないことは、住民投票により住民の意思を適正に反映させるという住民投票の趣旨からして、本末転倒である。
⑦ 市の在住外国人を増やすという政策目的を市民に説明しないことは、市の説明責任違反である
外国人が大量移住することはないとの主張もあるが、大量移住がなくとも、住民投票の対象事項についての賛否が僅差の場合には、少数の外国人の投票行動が結果を左右する、つまり、外国人にキャスティングボートを握られるという状況はあり得る。
さらには、そもそも、仮に現在の外国人の数の割合が僅かであったとしても、今後将来においてもそうであるという保証は一切無く、市や住民が市在住の外国人の数をコントロールすることは不可能である。実際、武蔵野市が行っている将来人口推計では、外国人人口の推計は、「今後の出入国管理制度や社会経済環境による影響が大きいため、流動的な数値として捉える必要がある」と明記している。このように、今後、日本における労働生産人口の減少分を補うことを目的とした労働外国人受入政策については、主に国政レベルで検討されることであるが、将来政府がかかる政策を拡充することとなった場合には、これまでの武蔵野市における在住外国人の増加率よりも高い増加率により在住外国人が増加することも大いに予想される。
さらに言えば、外国人との共生という理念の下、外国人に住民投票権を付与する政策は、合理的に考えれば、外国人が住みやすい市に変えるという政策目的があるはずであり、在住の外国人を増やすことに資する政策であることは間違いない。特に、在留期間や定住という要件を必要としない、異例の、他の自治体とは差別化を図った、外国人への住民投票権の付与は、在住期間が僅か短期の外国人をも増やすことが政策目的であると考えるのが論理的帰結である。
そのような政策目的が、二元代表制による民意を歪めるというデメリットを上回るメリットがある、あるいは、そのような政策目的を達成するためには、外国人への住民投票権の付与が必須であるとは、到底思えないが、それと同時に、外国人への住民投票権の付与により、実際にその政策目的が達成できるかどうかは兎も角として、少なくとも、そのような政策目的があること、それが市民に具体的にどのようなメリットがあり、逆にどのようなデメリットがあり得るのか、そして、そのメリットはデメリットを上回るものであることにつき、市長は市民に説明する責任を負っているはずである。このような説明を一切することなく、現在の外国人の割合が僅かであることを一つの根拠として、外国人住民投票権を認めることの弊害が少ないとの説明は短視眼的な発想であるばかりか、市民を欺瞞するものとさえ感じる。
このような制度を一旦導入した後に改正することは困難である可能性が高いことも考慮すれば、将来を見据えた市の政策としては配慮すべき点の配慮が不十分であると言わざるを得ない。現在の外国人の割合が僅かであることを一つの根拠として、外国人住民投票権を認めることの弊害が少ないとの考えは短視眼的な考えと言わざるを得ず、このような制度を一旦導入した後に改正することは困難である可能性が高いことも考慮すれば、将来を見据えた市の政策としては、上記の国民たる住民一人一人が有するべき一票の価値を毀損し、二元代表制の下での民意を歪めるリスクがある点を含め、配慮すべき点が不十分であると言わざるを得ない。
⑧.外国人住民投票権は、地方自治を害し、地方政治の決定プロセスへの信頼を害する
そもそも、民主主義が支持される理由は、その結論が常に正しいと考えられているわけではなく、その結論如何にかかわらず、国民の間で議論を重ねた上で、多数決により決定することにより、少数者であっても多数意見を受け入れるという決定プロセスを国民が信頼しているためである。現在の地方政治システムにおいては、国民たる有権者の選挙によって市長・議員を選び、原則として当該市長・議員により市政を決定するという決定プロセスが取られているが、ここに、国民以外の外国人にまで投票権者を拡大した住民投票制度を導入した場合、その住民投票の投票権者が国民たる有権者とは異なることから、住民投票で表される民意が選挙により表される民意とはずれるリスクがある。
武蔵野市市長は、住民投票の投票権者を有権者よりも広げ外国人を含むものとすることは、広く民意を問うことにより住民自治の推進に役立つものと説明している。これは一見正しいように思えるものの、上記のとおり、選挙による民意を歪めることとなりかねないことを考えれば、短絡的な考えと言わざるを得ず、住民自治の推進に役立つどころか、むしろ、住民自治を害しかねないものであり、地方自治における政治決定プロセスへの信頼が失われるリスクがあるものと考えるべきである。
⑨.外国人住民投票権の制度目的を達成する他の手段はいくらでもある
確かに、外国人のニーズや意見を聞いた上で、市政に反映することは大切なことである。しかしながら、住民投票の投票資格を外国人に広げることでしか、そのような目的を達成できないとは到底考えられない。
例えば、総務省はHPで、地方公共団体や地域国際化協会、NPO法人等の団体による優良な多文化共生に資する取組をまとめた「多文化共生事例集(令和3年度版)」を公表している。そこでは、コニュニケーション支援、生活支援など、大きく5項目に分類された97の事例が紹介されている。そのうち、外国人住民の社会参画支援という項目で紹介されているのは、下記の5事例であるが、外国人住民と行政機関等の橋渡しの役割を担うキーパーソンやコミュニティリーダーの事例等が紹介されているものの、外国人住民投票権の事例の紹介はない。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000765992.pdf

また、政府の「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」で決定された「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和3年度改訂版)」においても、「地方公共団体における一元的相談窓口の設置」や「外国人支援者のネットワークの構築」などが施策としてあげられているが、ここでも、外国人住民投票権について一切の記載がない。

https://www.moj.go.jp/isa/content/001349617.pdf
このように、国の政策として、あるいは自治体が独自に、外国人受入政策として他の自治体が取り組んでいることは、外国人向け教育や外国人の社会参加が中心であり、住民投票権の付与や外国人による自治体の政治決定プロセスへの参加に関する権利の付与と外国人受入政策とは必ずしも結びついていない。
他方で、住民投票の投票資格を外国人に広げることによる問題は、上記のとおり地方政治の決定プロセスへの信頼性を害するという地方政治の根幹にかかわる問題をはらむことにならざるを得ない。
外国人の意見を聞く手法としては、アンケートやキーパーソン、支援者ネットワーク等適宜の方法があることを考えれば、地方政治の決定プロセスへの信頼性に与える問題を甘受してまで外国人に住民投票権を付与すべきメリットがあるとは到底考えられず、むしろデメリットの方が圧倒的に大きいと感じざるを得ない。したがって、住民投票の投票権者を外国人に付与することは合理的な政策と考えることはできず、かかる外国人に投票権を付与する本条例には反対する。
⑩.外国人住民投票権を付与しないことは、外国人差別ではない
なお、外国人住民投票権を付与しないことについては、外国人地方参政権の問題と同じく、国民と同じく税金を納めている外国人に対する差別だとの主張がある。
しかし、憲法上、表現の自由などの自由権は概ね外国人にも保障されているが、参政権については保障されていないと考えられている。また、外国人は母国で参政権を有する場合が多く、他方、日本に在住する日本人は日本での参政権しか認められないのであるから、外国人に参政権を付与しないことが不平等であると一概に言うことはできない。
諸外国の状況を見れば、北欧等においては地方参政権を一定の外国人に付与しているようであるが、米国、英国、ドイツ、フランス、イタリアなどの欧米主要国は、一部地域やEU市民などの例外を除き、外国人に地方参政権を認めていない。よって、外国人住民投票権を認めていない日本は政治的に遅れた国ということではないし、参政権以外の権利については、広く外国人にも日本人と平等に与えられているものがあるのであるから、参政権を外国人に付与しないことのみを取り上げ、外国人差別であるとの主張は、バランスを欠いた公平性を欠く主張であると言わざるを得ない。
⑪.地方自治体も国と同じく主権(統治権)を行使する主体である
また、外国人地方参政権を立法により付与することに賛成の立場からは、地方は国と異なり、住民サービスの提供が主であるため、外国人がその決定プロセスに参加しても弊害は少ないとの主張がなされることがある。すなわち、国政参政権について外国人に付与することは憲法上禁止されるとの立場に異論を唱える考えはほぼ無いことを前提として、国政と地方政治はその役割が異なるとの主張である。
しかしながら、地方であっても、地方自治体は住民の権利を制限するような条例制定や行政執行を行う主体(すなわち、主権の行使を行う主体である。例えば、地方税の徴収、都市計画の決定は、私権制限を伴う主権の行使であるし、また、罰則を伴う条例制定権の全てが主権の行使である。さらに、新型コロナ対応や環境保全のための私権制限など、私権制限を伴う主権の行使は多数存在する。)であり、その点、国と何ら変わらない。また、地方であっても、例えば、武力攻撃事態が発生した場合は対処措置を執行する責務を有する(武力攻撃事態法5条)など、安全保障にかかわる事務を行う主体でもある。そうであれば、地方は住民サービスを行う主体であり、国と異なるとの考えは説得力に欠ける。
外国人参政権に関する平成7年の最高裁判決が言うとおり、「地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すもの」であり、「国民主権」の原理に基づき、本来国民が有する主権を、国民相互の権利を調整し、秩序を維持し、国民の権利を保護するために、国民が選挙等の民主主義的なプロセスを経て国及び地方に委託することにより主権を行使する主体となっているという点においては、地方も国と何ら変わりがなく、地方であっても、その立法・行政行為は、まさに主権の行使にほかならない。よって、かかる主権の行使が認められるのは、その主権が国民たる住民の民意に基づいているためであることからすれば(国民主権)、地方参政権であっても、国政参政権と同じく、外国人に付与する合理的な理由はない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
