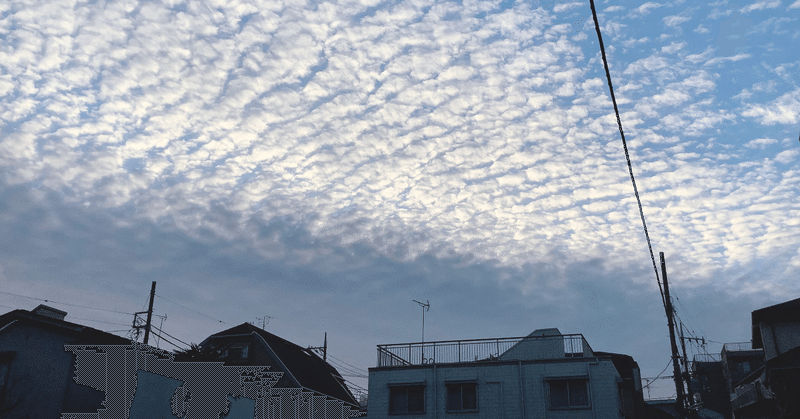
目標設定について(社長の言葉を新卒が解釈編)
お正月からはや3ヶ月が立ちました。
あの時、立てた目標はみなさんどうなっているでしょうか?
弊社では、例年まではあまり「目標」を立てることをしない流れがありましたが、時代の流れをみて「目標」を立て始めました。
最近、noteを始めた社長ですが、その社長が社内向けにこんな記事を書きました。
僕は、この目標設定の話を聞いて目標を立てたのですが、
今まで休暇の時間は部屋でぐーたらしていたのが、
よく外に出るように変わってきました。
ありがたい話だったので、かすかな記憶や先輩等へのヒアリングを頼りに、社外向けに書き換えてみたいと思います。(間違っていたら訂正・補足お願いします)
なぜ目標設定が大切か
前提→適切な目標設定でフローに入ると発達が促進される
くわしい説明はこちらがされているのでしょうか。。
t.ly/j6qLJ
チクセントミハイ博士のフロー理論が元になっているのでは?と思いましたが、合っていますかね。。要は、幸せ感をや自尊感情が満たされながら、
爆発的にスキル的な成長ができるということ。。。
フロー恐るべし。このフローになるための目標設定の仕方を社長が語られます。
フローとは?
⚫フロー、個別の特性、得意な事、役割り
本当に社内向けですね。笑
エッセンスだけまとめてくださってるので、
社内の人には、すぐに思い出すトリガーとして有り難いnoteです。
フローの心理学的な説明はこちら。
フローとは
フローは、特性と得意と役割
を考慮することが大切っぽいです。
けれど、少しわかりにくいですよね。
僕流に言葉を言い換えます。
特性とは
「ついやっていること」
得意とは
「秀でていること」
役割とは
「必要とされていること」
でしょうか。
それぞれ、違いがわかるように具体例を出しますと
twitterはついやってしまう(特性)けど、いいねをもらえるツイートをするのは苦手(得意)。
twitterで共感を呼ぶツイートをつくれる(得意)けど、会社では広報を必要としていない(役割)。
みたいなものですね。
確かに、どれかが欠けすぎていると
「どうして、自分、こんなことやってるんだろ・・・」
となってしまいます。
ワクワクとは?
①ワクワク、認識範囲にも関与する
(実現したい認識範囲のVISION×その中の自分)あるべきに縛られない、本当にワクワクする範囲
あるべきに縛られない、本当にワクワクする範囲
まず、こちらについて。
「認識範囲」とは「自分ごととして捉えている範囲」のことです。
この範囲を考慮することで「本当にワクワクするもの」が決まります。
例えば、僕は、大学の頃、民主主義が健全に回るために、選挙前にイベントをするような"人物"をやっていましたが、本質的に価値を体感していたのではなく、そういうことをしている大人がたまたまかっこよくて、かつ、よく読む評論等で「国がヤバイ」という旨の文章を読み、「全国民が政治に興味を持つのはマスト!」と「あるべき」をつくっていたので、そういうことをしていました。これが「勘違いワクワク」の事例です。
適切なワクワクはその人のステージや環境によって変わるようです。
実際に、社会人になって、僕はまだ国のことを真剣に考えてしまうような「格」ではないことがわかりましたし、社員という「環境」に身をおいた今、政治のことよりも目の前のことに夢中になりつつあります。
そういうものではなくて、本当に自分の身の丈にあった、心から気分が高まる「湧く湧く(ワクワク)」を考えるのが大事だということです。
そこで、僕は、
「『モテる』とか、どうでしょうか?」
と社長に聞くと
ちょうどいい感じの目標だと言ってもらえました。(僕はモテないので)
さて、ここから社長の第二弾のメモ?に移ります。
②変化するものだし、多視点で作れるはず。
(範囲が広がると他力も使えるようになる)
これは、今まさにそうですが、ただの「モテる」ではワクワクしなくなってきたんですね。少しモテてきた感があって、つまらなくなってきました。(笑) 目標の難易度を変える時期なんでしょう。
また、「多視点」というのは、ワクワクは一つではなく、TPOに応じたワクワク像をつくれるということです。
例えば、noteを上手に使いたくて目標設定をする際、
「noteのコンペティションで入賞する!」
等、自分の今の環境にあって、かつ、少し自分には難しいかもと思われるくらいの難易度のワクワク探しをするのが大切です。
ワクワクとフローの関係
目標設定はスキル
→ワクワクとフローは個別に考える。そして繋がりを考えて設定する。
まず、一旦、ワクワクとフローの違いについて書くと
自分や周囲の理想の状態(be)→ワクワク
具体的な極める何か、道(do)→フロー
ですね。これを前提に、「個別に考える」というのはどういうことかと言うと、一旦、それらを別個に、独立して考えてみるということです。
例えば、僕であれば、「モテる」という理想像はワクワクしますが、適切な手段として「人の話をうんうんと聴く」を選ぼうとすると、フローに入れません。僕は、「人に話をする」の方がフローに入れるのです。(笑)
こういう風に「ワクワク実現のために効果的な手段」
を考えようとすると、「フローが起きない」が発生するので、まずは「フロー」に意識を向け、それから「"結果的に"モテる」を探します。
すると、例えば、僕であれば、「絶対楽しんでもらえる話し方を考える」や「筋トレする」等、フローに入れる手段が浮かび上がってきます。
こんなものでしょうか?汗
難しいポイントとその対処
1、フロー見つけられない問題の1つの視点
→嫌いなことは好きなことかもしれない。
フローに入れるものを「嫌いなこと」だと考えて避けていることがあるそうです。これは、リンク先がとてもわかりやすく書いてあります。「こういうことがある」という視点を持つだけで自分で気づきやすくなりますし、また、他人に「フロー探し」を一緒にしてくれないかと頼みやすくなりますね。
2、フローとわくわくを繋げられない
→マクロミクロの柔軟性
例えば、「モテる」に囚われず、「フローになる時なにがあるかなぁ」を考えて、「数字の分析」がフローの候補として出てきた時、どう、「モテる」と「数字の分析」を繋げるかは至難の技です。
そういう時、ワクワクとフローのグッドマッチが大切なので、
「他を探す」か「合うように変える」のどちらかを選ぶことになります。
「他を探す」
「ワクワクは他にはないのか?」
「フローは他にはないのか?」
と相性のいいワクワク✕フローの組み合わせを探す問いを投げてみます。
「合うように変える」
例えば、「1年以内に10人の女性と手をつなぐ。そのために、声をかければ僕のことを気になってくれる可能性のある人は50人に1で、その50人はこういうジャンルで、こういうイベントにいけば、何割いて、だから月何回、こういうイベントにいく必要があって、、、」
と、戦略という調味料を加えることで、「モテる」と「数字の分析」をグットマッチにしていきます。
こうして、目的すらも手段に合うように変える等して、幅を広げて柔軟に考えることで、最適な目標設定を目指そうというのが、こちらの主旨です。
こんなものでしょうか?
もしかしたら、若干ニュアンスの違いがあるかもしれないですが、
自分の血肉化のために書いてみました。
目標設定に悩んでいる方がいたら、参考にしてみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
