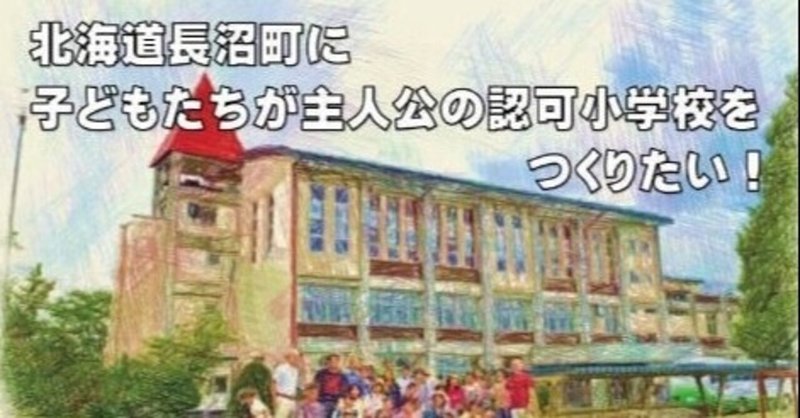
強制なしの教育などない?自由はきれいごと?
前回の記事に、感想などお寄せくださり、ありがとうございました。
NPOまおい学びのさとでは、様々なSNSを通じて発信しています。
さて、前回の記事に続き「自由な教育とは?」
(前回の記事「教育に強制は要らない」は、こちらです)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
■強制なしの教育などない? 自由はきれいごと?
「遊びと勉強は違う」
「きれいごとを言うな」
「自発的と言っても、教師や親がやらせなければ子どもたちが自ら学習をするわけがない」
「子どもの将来のためには、ある程度の強制は必要だ」
という言葉が返ってきそうだが、それは学習が決して楽しいものではなく、ある程度は苦痛や負荷がかからざるを得ない「勉強」だととらえる考え方から来ている。
しかし、それを言う人は、自分が受けてきた既存の学校教育しか知らないから、学習の楽しさや学びの多様な意味に気付いていないだけなのではないか。
人は案外、自分の被教育体験のみに依拠して教育について語り、既存の教育を反復再生しようとするだけの結果に陥りがちである。
ある人が「自分が子どもの頃しつけられ親に強制された勉強や習い事が後で役に立ちありがたかった」という体験を挙げ、子どもの教育には強制が必要であると結論付けていた。
確かに、そうした例はある。
だが、自分の体験だけでは、すべてを語れることはできない。
この方は、作家として社会的に名を知られるようになった、いわば「勝ち組」だから言えることで、学校教育の中で、成績で格付けされ、選別され、落ちこぼれてきた人たちのことをどう考えるのだろうか。
おそらくは自己責任の一言で、自己の出自や生育環境の有利さを勘定に入れず、不遇な生活・教育環境の人たちの努力の不足だけを責めるのだろう。
以前、臨教審でも「できん奴は、できんでいい」と言った発言があった。
教育の階層再生産は当然で、社会格差の固定化は努力の帰結でしかないと考えている人もいる。
多くの政治家・為政者も残念ながら、自分の教育体験や信条で居酒屋談義をくりかえすだけの教育弥縫策・教育改革に終始している。
でも、それは案外無意識的に、市民の政治的関心を削ぎ、体制に従順な扱いやすい国民を生み出そうとする意図・本音が隠れているだけのことかもしれない。
過去の教育政策は体制に従順で、国家の経済繁栄に役立つ人づくりのため、将来の収入や地位を餌に規格の学習内容を習得させ子どもたちを点数で序列化してきた。
それが、共感性をすり減らした拝金主義で指示待ちの若者を生んできた。
教育における強制は、教育本来の目的をすり替え、子どもたちの意欲・自発性を削ぎ、自己肯定感を損ない、人間関係に妬みや猜疑を持ち込むことになる。
我々は、教育の強制による「結果」ばかりを評価し、強制によって損なわれたものを見ようとしてこなかったのではないか。
多くの知識やスキルを身につけた高学歴エリートの能力を「結果」として、競争の中で落ちこぼされてきた層の人たちの能力や生活に目を向けず、さらにエリート層にありがちな損なわれた共感性や「今だけ、自分だけ、金だけ」というような価値観を黙認してきたのではないだろうか。
強制は必要悪ではない。
強制のない教育は有り得るし、強制などなくても喜んで学びに向かうのが子ども本来の姿であり、人間の本性なのだ。
そうは言っても、「現実に目の前にいる子どもたちは、自由にされると遊んでばかりいるか、何をしていいかわからなかったりして、進んで勉強する者などいない。」と特に教育現場の教師たちから反論がありそうだ。
しかし、それもやはり既存の教育しか知らないからだ。
目の前の子どもたちは、家庭や学校でのしつけや強制で、既に意欲が減退し指示待ち姿勢を体得してきた子どもたちも少なくないが、急がなければ自由の中で、やがて意欲や学びの姿勢を恢復するはずである。
待ちの姿勢と子どもたちの活動の中に、学びを見出す目が大切なのだ。
自由にして手出しをせず学びが生まれなかった場合の怖さに耐えられず、強制的な教えに役目・達成感を見出そうとするのが往々にしてありがちな教師の姿だ。
自由な教育、自由な学校は空想ではない。
30年前なら理屈で説くしかなかったが、今現実に和歌山県の自由な認可学校「きのくに子どもの村学園」の30年近い実践があるのだ。
百聞は一見に如かず。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
では、「自由な教育」は、何も強制されない、何をやってもいい、何でも許される教育なのでしょうか?
次の記事で、ご紹介します。
よろしければ、学校設立・運営へのご支援をお願いいたします。
