また会えたから
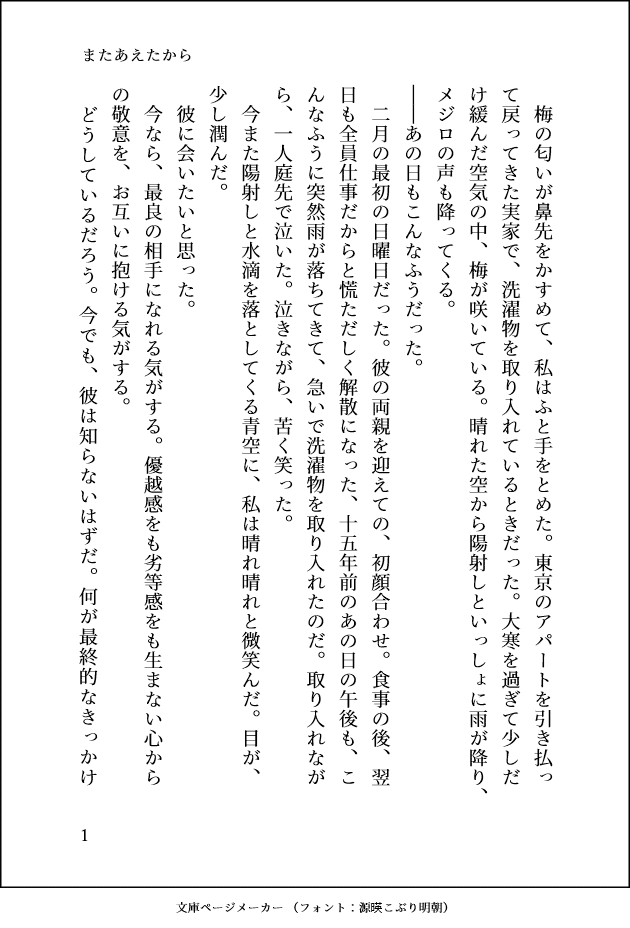

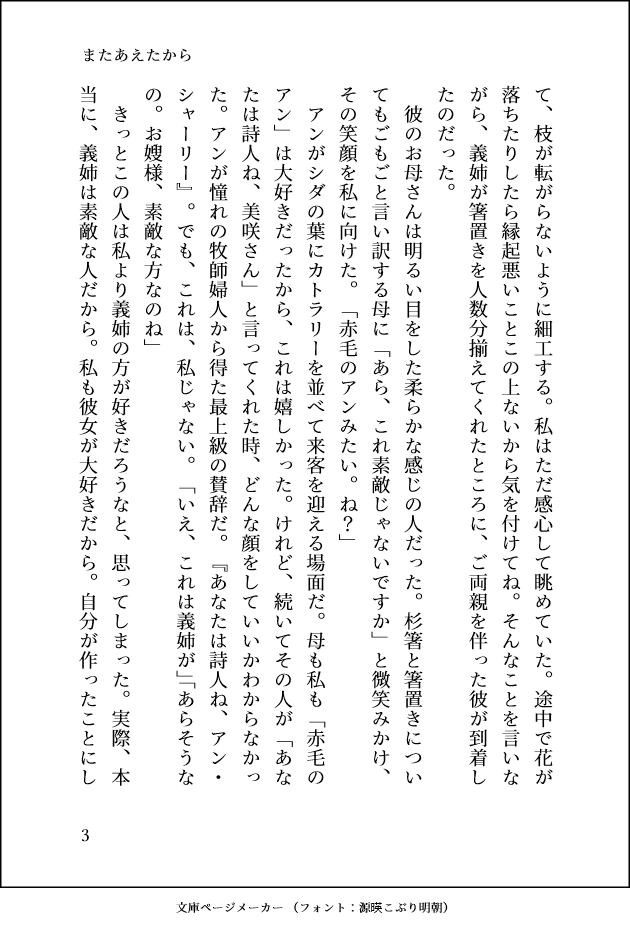

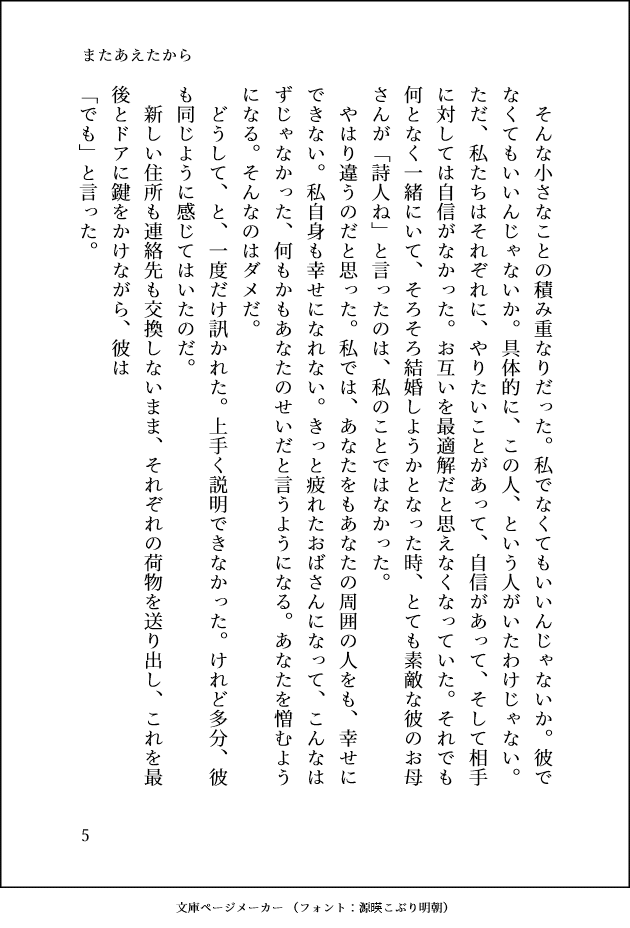




梅の匂いが鼻先をかすめて、私はふと手をとめた。東京のアパートを引き払って戻ってきた実家で、洗濯物を取り入れているときだった。大寒を過ぎて少しだけ緩んだ空気の中、梅が咲いている。晴れた空から陽射しといっしょに雨が降り、メジロの声も降ってくる。
――あの日もこんなふうだった。
二月の最初の日曜日だった。彼の両親を迎えての、初顔合わせ。食事の後、翌日も全員仕事だからと慌ただしく解散になった、十五年前のあの日の午後も、こんなふうに突然雨が落ちてきて、急いで洗濯物を取り入れたのだ。取り入れながら、一人庭先で泣いた。泣きながら、苦く笑った。
今また陽射しと水滴を落としてくる青空に、私は晴れ晴れと微笑んだ。目が、少し潤んだ。
彼に会いたいと思った。
今なら、最良の相手になれる気がする。優越感をも劣等感をも生まない心からの敬意を、お互いに抱ける気がする。
どうしているだろう。今でも、彼は知らないはずだ。何が最終的なきっかけだったか。
――あなたは詩人ね。
そう言った、美しい女性。素敵な人だった。お義母さんと呼びたかった。けれどその一言が、私を諦めさせた。
自慢の手料理をふるまいたくて、家での食事を主張した母。吉野に住む姉が毎年間伐材の杉箸を束で送ってくれるのだと話題にしたいばかりに和紙に包まれた祝箸ではなく裸の杉箸を使うことを主張した母が、箸置きを用意していないことに気づいたのは、もう先方が家に到着しようかという頃だった。私は歩いて五分のところに新居を構えていた長兄のお嫁さんに電話をかけた。
お義姉さん、箸置きって持ってる? え、使ったことない、そんなもん。そう言いながらもすぐに来てくれた義姉は、剪定鋏を持って庭に出ると、伸び放題の梅の枝をたくさん伐ってきた。白い蕾をつけた緑色の木肌を蕾のすぐ横で切って、丁度いい長さのもの以外を惜しげなく捨てながら、6~7センチの、パールのついたネクタイピンのように見えるものを作った。蕾のついていない側を少し削って、枝が転がらないように細工する。私はただ感心して眺めていた。途中で花が落ちたりしたら縁起悪いことこの上ないから気を付けてね。そんなことを言いながら、義姉が箸置きを人数分揃えてくれたところに、ご両親を伴った彼が到着したのだった。
彼のお母さんは明るい目をした柔らかな感じの人だった。杉箸と箸置きについてもごもごと言い訳する母に「あら、これ素敵じゃないですか」と微笑みかけ、その笑顔を私に向けた。「赤毛のアンみたい。ね?」
アンがシダの葉にカトラリーを並べて来客を迎える場面だ。母も私も「赤毛のアン」は大好きだったから、これは嬉しかった。けれど、続いてその人が「あなたは詩人ね、美咲さん」と言ってくれた時、どんな顔をしていいかわからなかった。アンが憧れの牧師婦人から得た最上級の賛辞だ。『あなたは詩人ね、アン・シャーリー』。でも、これは、私じゃない。「いえ、これは義姉が」「あらそうなの。お嫂様、素敵な方なのね」
きっとこの人は私より義姉の方が好きだろうなと、思ってしまった。実際、本当に、義姉は素敵な人だから。私も彼女が大好きだから。自分が作ったことにしとけばよかったのにと義姉は言ってくれたけれど、そういう問題ではなかった。それに、ここで馬鹿正直なのが、なけなしの私の良さだとも思う。
誰も悪くはなかった。みんな、優しい、いい人だった。私は彼が好きで、彼も私を好きだと言ってくれていた。けれど。
ある時彼は酔った友人を介抱していた。居合わせた別の友人が、今度私も酔っぱらうから介抱してねと言った。彼はいつでも、男女の別なく誰にでも、節度を持って優しかった。
ある時彼が言った。結婚を考えるより今は仕事が面白くて、と。私の部屋で一緒に暮らしながら。
ある時彼が言った。YやNの言ってくれた感想が一番嬉しかったな、ああいうのが原動力になるんだよな、と。私も知ってる友人たちの名を挙げて。
しょっちゅう、私たちはお互いに言った。きっとこれは理解してもらえないと思う。
また私たちは言い合った。詳しくないからって別にそれが嫌いなわけじゃないからね?
そんな小さなことの積み重なりだった。私でなくてもいいんじゃないか。彼でなくてもいいんじゃないか。具体的に、この人、という人がいたわけじゃない。ただ、私たちはそれぞれに、やりたいことがあって、自信があって、そして相手に対しては自信がなかった。お互いを最適解だと思えなくなっていた。それでも何となく一緒にいて、そろそろ結婚しようかとなった時、とても素敵な彼のお母さんが「詩人ね」と言ったのは、私のことではなかった。
やはり違うのだと思った。私では、あなたをもあなたの周囲の人をも、幸せにできない。私自身も幸せになれない。きっと疲れたおばさんになって、こんなはずじゃなかった、何もかもあなたのせいだと言うようになる。あなたを憎むようになる。そんなのはダメだ。
どうして、と、一度だけ訊かれた。上手く説明できなかった。けれど多分、彼も同じように感じてはいたのだ。
新しい住所も連絡先も交換しないまま、それぞれの荷物を送り出し、これを最後とドアに鍵をかけながら、彼は
「でも」と言った。
「マシな方だったよな? 俺たち」
私は黙って頷いた。
「また会えるかな」と、彼が言い、
「会えるといいね」と答えた。
水鳥を浮かべた川面と広い河川敷が終わり、線路の立てる音の響きが変わると、両側にはまた刈り株の残る田んぼが広がった。遠景には、葉を落とした雑木の山々。ところどころに混ざる緑、点在する人家。見慣れた、冬枯れの田舎。変わらないなぁ、と思う。
郷里に戻って三か月。久しぶりに電車に乗って、美術展を観に行った帰りだった。あれから十五年。進学の為に家を出た時から言えば二十五年。
もっと早く帰ってくればよかったと思う。でも、無駄ではなかったとも思う。自分が何を望んでいるかはっきりわかったから。十五年たって、私はおばさんになったけれど、元気で機嫌のいいおばさんで、自分のやりたいことをやっている。
そんなことを考えていた時だった。隣の車両との間を隔てるドアが開いた。何がなし違和感を覚えて目を遣る。通勤通学時間以外で満席になることはまずない、田舎の在来線だ。平日の真昼間だから空席も多い。のに?
入って来たのはサラリーマン風の男だった。何気ない態で通路を中ほどまで歩き、丁度私の正面で座席に腰を下ろすとすぐに、腕を組み、頭を垂れて居眠りを始めた。制服の女子高校生の隣だった。
あ、コイツ痴漢だ、と思った。空いた席がいくらでもあるのに、わざわざ若い女の子の隣に座って、寝たふりするやつ。
案の定、男はほどなく隣の少女によりかかった。色白でぽっちゃりした、絵に描いたようなおとなしそうな高校生が、スマホから顔を上げて居心地悪そうに身じろぎする。
何の都合でこんな時間に電車に乗っていたのか知らないが、立ってしまえばいいのにと思う。電車が揺れた瞬間、相手が更に寄りかかろうとするタイミングで、思いっきり外してやればいい。そう思うけれど、彼女にはできないらしい。本当に眠っているだけだと思っているのだろうか。
彼女に声をかけるべきか、それとも……と考えた時、車両の一番端の席に座っていた別な男が立ち上がり、少女の前に移動した。何だコイツ、仲間か? と思う。
「すみません」
その男は高校生に声をかけた。
「すみません、お嬢さん。わけあってどうしてもその席に座りたいんです。大変申し訳ないんですが代わってもらえないでしょうか」
高校生はぱっと立ち上がり、半泣きの目と声で「ありがとうございます!」と言うと、鞄を抱きしめて、痴漢が現れたのと反対側のドアに消えた。見送って、男性がゆったりと腰を下ろす。自分の言葉通りに。
私は笑いそうになった。なんて回りくどい助け方だろう。でも効果的だ。隣の男は、後を追うこともできず、咎められてもいないのに冤罪を主張することもできない。
痴漢は狸寝入りを続け、次の停車駅で忌々しそうに隣を睨みつけて降りて行った。余裕の笑みで受け止めた男性は、ドアが閉まってから「フンッ」と鼻息も荒くふんぞり返って腕組みをする。私は思わず吹き出した。この子供っぽい振る舞いとさっきの大人ぶりのギャップがおかしくて、笑いが止まらなくなる。
「そんなに笑わなくても」
とうとう、男性が小さくつぶやいた。
「ごめんなさい。だって……」
なおも笑いをおさめられずにいると、
「え……」と、小さく息を呑む声が聞こえた。
「美咲?」
呼ばれて顔を上げ、私もまた息を呑む。
私がおばさんなら、彼もそれなりにおじさんだ。でも変わってない。相変わらず、節度を持って誰にでも優しい。
あごめん呼び捨て。えっと守屋さん。いや今何て名前。変わってないよ美咲でいいよ。なんでこんなとこにいるの。いや実は――
話すことがたくさんありすぎて、私たちは電車を乗り過ごしてしまった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
