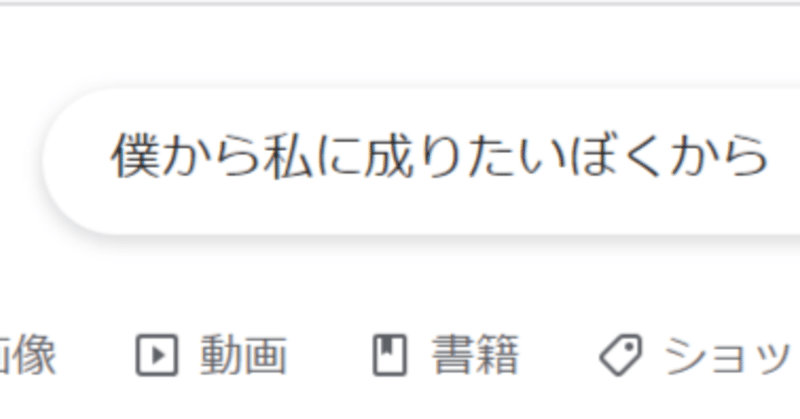
1969年5月の19歳:「赤頭巾ちゃん気をつけて」を読んだ大学一年生が、発表翌月の『中央公論』へ書いて送ったこと
公益性に鑑み、全文を引用します。作者氏名のみ略します。
僕から私に成りたいぼくから
意外や意外!『中央公論』にこれほど卑近な小説(「赤頭巾ちゃん気をつけて」五月号)が掲載されるとは。卑近どころか、同年齢のせいかぼくにとっては膚にピッタリとそれこそネッチャリとへばりつくようで、でもサッパリとした気がするから愉快で、爽快で、新鮮でスカッとしたんだ。
かくいうぼくは、筆者と似たりよったりの環境、道筋を経て名古屋のミニ日比谷高校に在学し、その中でぼくはぼくのクラス仲間のように文学に何かを強く求めるでなし(彼らのように人生に臨もうとすることはあるが)、善悪万事(現実生活に差し障りのない程度に)少しずつかじってきた、現実的、実際的、優等生的(皮肉に)な青年であるようだ。そして東大入試中止を迎えた受験生だったぼくだったんだ。
言うまでもなく現代日本社会(マスコミとか小説界)では、風潮としてこの種の人間はエリートという鼻もちならない奴らだと嫌悪する空気があり(筆者の言う通り)、個性の強い苦悩を背負うた青年なんかは小説の題材にもなるらしい。いうなれば現代のマスコミによって製造されたモデル的青年なのかもしれないのだけれど・・・・。ぼくが読んできた「遅れてきた青年」等の大江健三郎作品では、この小説のように仲間意識を抱くほどの親密感、共感を味わえなかった。
筆者は、自分の性的欲求が人並以上(青年として正常)なのに、恐らく唯一の犯罪者的罪悪感(大ゲサだけど)を抱き、否それさえもすべて自身の生き方を疑いつつも肯定していく自分の事柄の中の象徴的なものにしているのかもしれないが。最後の章で薫クン(筆者)は自己決定をする。彼は率直に嬉しい。それは自分自身の心の地殻を割って溢れる本当に絶対に純粋に自分のthought,feeling だから。そうなんだ。借りものじゃないのを見出し創り出したから。ぼくも嬉しくなりそうさ。
出典 『中央公論』1969年6月号, pp426-427
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
