
あわよくば
案内のとりが見あたらなくなって、雪の雲と、いつまでも南中に居座る真っ白な太陽のせいで、東も西もわからなかった。とりは戻らず、わたくしの口笛は風に消えた。風に流されたか、寒さに打ち死んだか。先導をうしなったわたくしたちは、地図をぐるぐると回しながら、たしからしきほうへ闇雲に足を掻いた。冷気のなかを進みゆくうちに先端からあらゆる感覚が奪われていくようだった。と、おもっているあいだにほとんど奪われた。精霊の空の日には、いたずら好きな精霊が人のたましいを抜きに来る。雪の空の日には、雪の女王の気分次第でひとが消える。音も、匂いも、気配も。閉じた世界のなかに蠢くわたくしのからだが求めているのは、温度であった。
足掻けるだけ足掻いても、温度が戻ってこない。氷の鋭さとも違う、包み込むような、幾重にも巻き付くような深い寒さに脳がゆっくり閉じていく。
― わたくしはルイベを食べに来た。
やわらかくあたたかいものに覆われたわたくしのからだは、繭のように転がっていた。頭頂部から足の先端にかけて包まれ、その中で、わずかに光を感じながら、肩を開き、掌を天に向け、両足を伸ばし、おしまいのときを待つかのようにじっとあった。冷え切って機能をなさぬ四肢をうとましくおもいはじめた頃、胸の真ん中あたりから、魂らしきものの出入りするのがわかった。ような気がした。痺れ、途切れゆく意識が、まどろみにも似て甘やかに感ぜられ、いっそ煙のように消えてしまえたら、とおもう反面、このままひそりと立ち消えてしまうことを、無念におもった。せめて、ルイベを、と願い、にじりよる虚無を懸命に払おうとするが、欲求は次第によわくなり、ときどきあたまをもたげては、ややつよくなり、しかし、冷え行く細胞に留められ、願いそのものが散り散りに、さらによわくなって、確かめるのが面倒になるほど、ともしびとなりかけ、意識というものを考えやることも出来なくなり、これでもうしまいである、と呼吸をさえ放棄しようとしたところに、太い呼び声を聴く。
貴女、しっかり。
しっかり、の、声と共に、首から上を覆っていた布が剥かれ、開かれた。
天井から注ぐ橙色の光がまぶしく、目玉を晒してはおられない。上瞼と下瞼とをきちりと合わせたまま、真上からする声と、光源の据えられているであろうその天井までの距離とをわたくしは測りかねている。
白の世界のあてどなさには、なすすべがなかった。ひとり消えゆくのは心もとなく、見守りのあることにはそれだけでなにかを託せるような、ひとつ、責務から放たれるような安らぎをおぼえた。貴方は、と尋ねようとする舌は痺れたままことばが出ない。隣にはもうひとりいるらしく、それらしき物体の気配を感じるものの、一向に動く様子がない。それは少し前のわたくしと同じく、縮こまった肉のかたまりとして、健気に横たわっている。あたたかな火のにおいがして、パチ、と何かが爆ぜた音がして、つと、爪先が鈍く痛みを取り戻しかけていた。
とりが、呼びに来てくれたんです。
幾重にも巻かれた布の上からそっと啄まれているような刺激に、薄目を開ければ、毛皮を纏った大きな男がわたくしの足を丹念にほぐしているらしかった。くたびれ果ててもなお歩き、疲弊したそれはたいへんによごれているはずであった。腫れたり、爛れたりしているだろうし、痛くもある。しかし、痛みよりも何よりも今はそこにふれられるのが恥ずかしい。
次は、手を。
発せられる低音が肌を滑り、わたくしのうすい腹に響く。
男は何か唱えながら繰り返し掌をかざし、ひらめかす。凍えた唇が押し開かれ、ミルクのような温かいものを流しこまれたわたくしには、此処にあることをうべなわれ、ゆるされたような気持ちが湧いてくる。そのうちに、感覚を無くした四肢の末端にとくとくと血が通い、酸素が行き届き、取り戻され、失われてしまったはずの温度が巡り巡ってくる。ああ、血の流れだ、とひらめきを得たような瞬間に、魂が、ひゅんと戻った。
どうか安心して、もうすこし、休んで。
まろびでることばをそのまま受取り、二度、三度と眠りに落ちた。四度目の眠りから覚めると、ただいまの自分がどのような状態にあるのかを知りたくなる程度には己をとりもどしかけていた。まどろみを振り切れるほどに。からだの真ん中で、血を送るための器官が躍起になって頑張りだしていた。
あたため続けてくれた毛皮の男は、ハルニレの精霊を身につけていた。救済や浄化を生業にしているらしく、端々に祈りのことばを吐いた。七つの時、このまちで一番立派なハルニレが落雷に死んで、その木は、男がうまれる前の、男の父のそのまた父の父が庭に植えたもので、ハルニレが引き受けてくれなければ、自身が召されていたにちがいない、と真剣な顔をした。拠り所をなくした精霊は、完全に男につき、木の精をもつと土地を離れられなくなる。男には土地の記憶が積もりゆくことが決まった。うまれるもの、消え、失せるもの。雪の中に芽吹くもの、凍てつくもの。男は憶えている限りまちの外には出たことはないが、まちの外からくるひととこうして交わってきたから、外へ出たのとほとんど同じだろう、と、わたくしの手をぎうと握った。彼の妹には狐の精霊が、弟には亀がついているらしい。
亀?
そう。幸運のしるしの。
う、と、くぐもった声が静けさを割ると、男がそちらへ移動した。
わたくしは横たわったままゆっくりと右手に顔を傾け、隣にあったのが、どうやらわたくしの連れ合いであり、彼もまた、息を吹き返してしまったものらしいと知った。
(了)




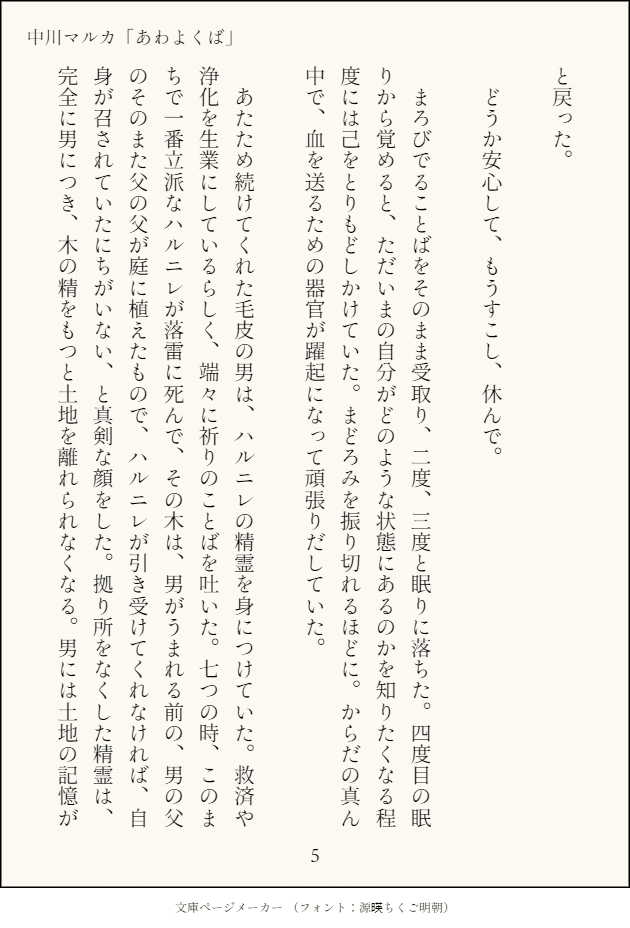
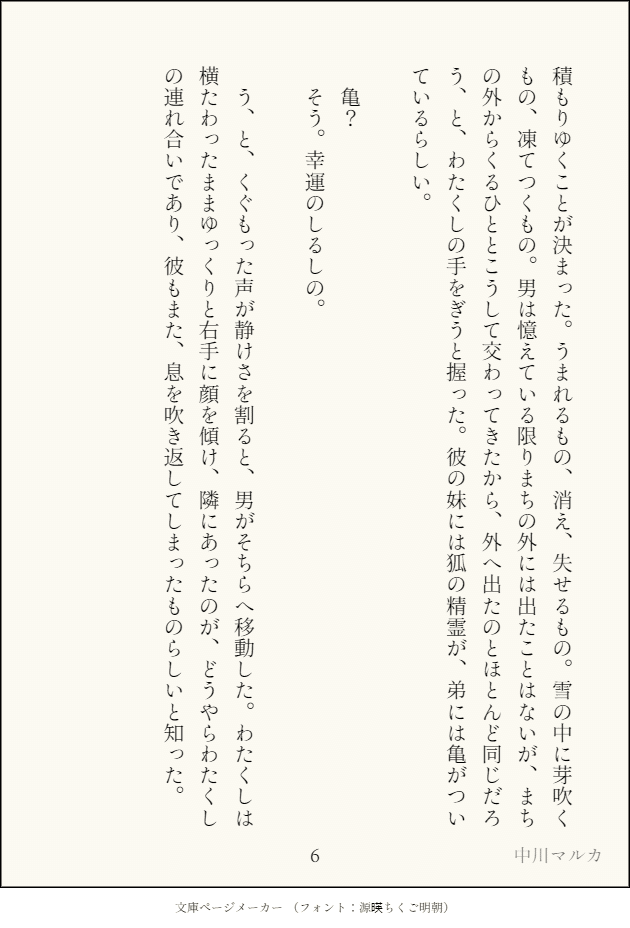
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
