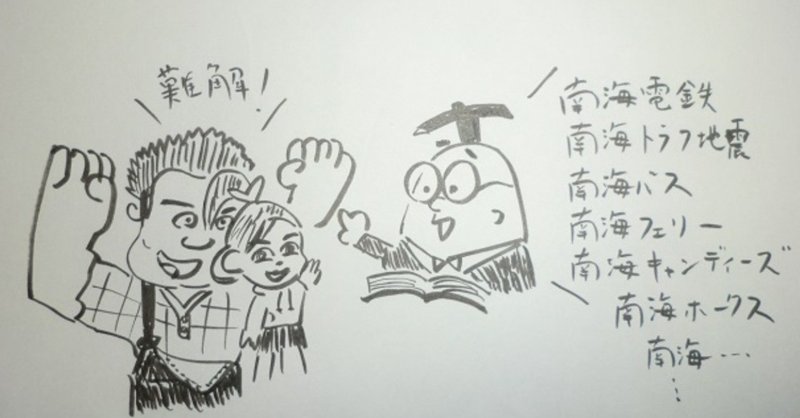
難解な映画レビュー「シュガーラッシュ・オンライン」

あけましておめでとうございます!
今年もラロッカは、なかなか理解されない難解なことをつらつらつぶやいていきますので、よろしくお付き合いお願いいたします。
そして今年最初の難解なブログは、「コメディ」映画の話をします。
去年僕が最後に観た映画はディズニーアニメのコメディ「シュガーラッシュ・オンライン」でした。
僕はこの映画のクライマックスの展開が大好き!
というのも、クライマックス直前に行われたある会話がとってもキレイな伏線になって効いている気がして、それはそれは気持ちいいのです。
しかしこのことを、一緒に観に行った人に勢い込んでしゃべったのですが、そうだっけ?みたいな薄い反応しか返ってきませんでした。
これは、デジャブ!
去年のマンスリーシネマトーク東京(MCTT)の「セラヴィ!」の回の記憶が蘇りました。
「セラヴィ!」は、ある結婚式の一夜のドタバタを描いたフランスのコメディ映画。
このMCTTでの僕の感想は、もちろん絶賛。中でも、髭剃りが伏線になって、後半の思いもよらない展開になるくだりが、本当に素晴らしいと熱を持って語ったところ、他の参加者の方は意外と冷めた反応。伏線ではあるものの、その後の展開のためにとってつけたような、キレイな伏線にはなっていないというものでした。
そうなんですよ。
どうも、僕がキレイだな、とか、気持ちいいなとか思う伏線はあまり市民権を得られないようなのです。
逆に、去年、伏線が大絶賛された映画がありました。
観られた方はピンとくると思いますが、
「セラヴィ!」の伏線が、「風が吹けば、桶屋が儲かる」式だとすれば、その映画は、「桶屋が儲かったのは、風が吹いたから」式の伏線といえるものでした。
要は、「結果」を先に見せて、そうなった「原因」を後から提示するという形。
密室で人が殺されていて(結果)、どうやって殺した(原因)のかを解明するミステリー的な手法です。
このミステリー的手法(「桶屋」式)が、コメディの「伏線」にも効果的なのは、観ている方が、「桶屋」の段階で、これは何かあるぞと思って身構えられるところ。
その後、完全に「桶屋」を意識付けされた状態で「風」が直撃するわけですから、とってつけられた感はなく自然に受け止められ、しかも「風」が意外なものあればあるほど、「なるほど!」「やられた!」という反応も大きくなるわけです。
一方、「風が吹けば、桶屋が儲かる」式(「風」式)の方は、「風」の段階では、観ている方はただ「風」が吹いているだけの通り過ぎる一つの事象でしかありません。
その後「風」に対してそんなに意識付けされてない状態で、急に「桶屋」が儲かって、急に「風」の意味合いが変わるものですから、ストーリーのためのとってつけたような伏線だったなあと感じられる場合が出てきてしまうわけです。
そしてそれは、「風」と「桶屋」の関係が意外であればあるほど、そんなバカな!となってしまうわけで、その匙加減が非常に難しい手法なのだと思うのです。
つまり、「風」式は、「桶屋」式以上に、難しいバランス感覚が必要になるということです。
ところが、「風」式は、一見工夫のない、オーソドックスなコメディに見えてしまうため、成功しても「ああ、面白かった!」で終わってしまい、失敗したらケチョンケチョン。高く評価されることが少ない印象があります。
「セラヴィ!」のMCTも、東京、神戸、名古屋の音源を聞く限り、絶賛は僕一人だけ。
三谷幸喜関連作品も、「桶屋」式の「12人の優しい日本人」以上に評価されているものはない気がします(実は僕自身も「12人」が一番、笑)。
コメディ映画の優劣を無理やりつけるとすれば、
出来のいい「風」式>出来のいい「桶屋」式>出来の悪い「桶屋」式>出来の悪い「風」式
となるべきだと僕は思います。
しかし、現状の評価は、
出来のいい「桶屋」式>出来のいい「風」式≒出来の悪い「桶屋」式>出来の悪い「風」式
となっている気がします。
ここでもう一つ。
伏線が大絶賛されたある映画と、「セラヴィ!」を比べると、明らかに前者には、熱意があふれているという指摘があります。
それは、登場人物のみならず、作り手においても差が歴然であるというのです。
僕は、前者の映画の情熱はもちろん受け止めて、感動しました。
でも、「セラヴィ!」には熱意がないという意見には、どうしても賛同できません。
なぜなら、前述したように、非常に難しい、そして現状の評価では、こんなに割の悪い、報われない、「風」式コメディに手をつけるなんてことは、作り手は相当な情熱を秘めていないとできないと思うのです。
ちょっと、野暮なブログだったかなあ・・・。
いずれにしても、今回取り上げました「シュガーラッシュ・オンライン」は、ディズニーアニメの衣を着た「風」式コメディの傑作であると、僕は思っています!
ぜひ、「伏線」という視点からも、作り手たちの情熱を感じ取ってほしい一作です!
text by ラロッカ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
