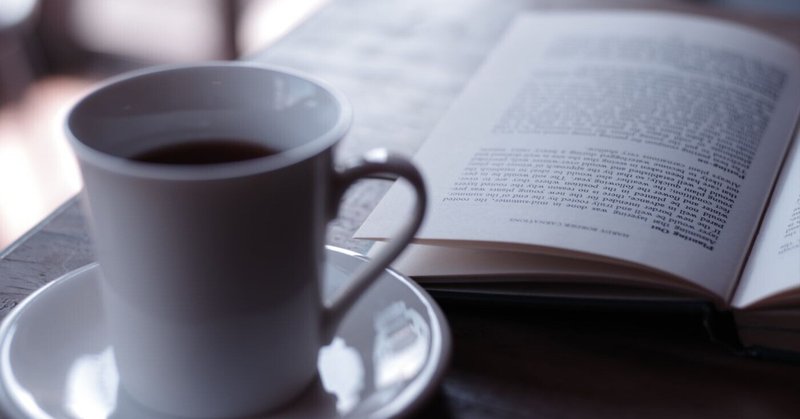
100冊目:新規事業開発マネジメント
1章 なぜ今、新規事業やイノベーションが必要なのか
新規事業やイノベーションを生み続けなければ、どんな企業も生き残れない。どんな事業も衰退する時がくる。特にVUCAやコロナショックによる一層厳しさを増田今後の企業経営では、プロダクト・ライフサイクルが速まり、事業が短命化の一途を辿る。
日本のベンチャー・スタートアップは数や規模感、影響力の観点から、現状日本経済に与える影響は限定的(日本全社の1%未満)。
日本の大企業は全国労働人口の約30%、特筆すべきは保有する経営資源の豊富さ、大企業の内部留保は約460兆円にのぼる。特に天然資源が乏しい日本では、最も重要な経営資源は人材である。そして、日本はまだ終身雇用を前提にした流動性の低い社会であるため、「社会や顧客の大きな課題を解決する事業」への取り組みは、大企業がどう外部を活かして成果を出すかにかかっている。
2章 新規事業開発は、なぜ上手くいかないのか
既存事業と異なり、そもそも対象となる市場や顧客が不明確のケースが大半。情報が皆無に近い状況で検討を進めるため、事業プランや計画の精度が高くなく、不確実性が高くなる。結果、新規事業の成功率はセンミツ(0.3%)であり、「多産多死」を前提に事業を捉える必要がある。
大企業で新規事業開発が上手くいかない3つの理由
①は3章、②は4章、③は5章・6章でこの理由に対する処方箋を述べる。
①ビジョンや開発に対する方針・戦略がない
②良質な多産多死を実現するための組織になっていない
③自社の性質や事業の不確実性に応じた事業開発プロセスを実行していない
3章 いかにしてビジョンを描き、新規事業開発の方針や戦略を策定するか
下記7つのステップを明確にし、経営層がストーリーとして語り続けることが、新規事業開発全体の方針や戦略を共有し、浸透させていく上で重要。
[1]全社ビジョンを明確にし、企業としてどこへ向かうかを示す
[2]ビジョン実現に向け、なぜ新規事業に取り組むかの意義を見出す
[3]既存事業の干渉を受けない投資資源を確保する
[4]どんなテーマや領域で、どんな事業を取り組むかを定義する
[5]いつまでに、どの程度の目標を狙うか目線を合わせる
[6]誰が、どのように行うかのアプローチを検討する
[7]何にいくら投資するか、適切なポートフォリオを組む
[1]ビジョン策定には「有意義性」「貢献性」「具体性/独自性」「実現性」「透明性/公平性:」が論点として挙げられる。
[2]イノベーションの緊急性と実施するための能力は反比例する。既存事業の基盤が揺るぐと緊急性が高まるが、制約が多く能力が十分発揮できない。
[4]マクロな外部環境や産業・業界の環境分析と、自社の保有する経営資源(アセット)の棚卸しなどは不可欠。
[5]目線=事業ドメインや参入する市場×時間軸×規模感
[6]自社の経営資源「クローズドイノベーション」外部との結合経営資源「オープンイノベーション」
4章 良質な新規事業への挑戦を量産できる組織を作る
組織を作る4つのステップ
[1]組織・人材に対する考え方や軸、思想や価値観の醸成
[2]リーダーに適した人材(イノベーター)の発掘・支援
[3]能力・成果を最大化する育成・支援
[4]健全な多産多死を実現する組織文化や仕組みの構築・定着
[1]希少なイノベーター人材と良好な関係を築きマネジメントする「IRM」
[2]志向性・資質を把握し、発掘・配置する
新規事業に興味がなく、成果を重視する人は既存事業が適する
[3]イノベーター・ジャーニー・マップ(IJM)の活用
[4]撤退基準の明確化とノウハウの体系化・標準化
Google20%ルールは制度(ハード)と心理的安定性の文化(ソフト)の
組み合わせ、これによりイノベーティブな活動サイクルが生み出される
5章 不確実性をコントロールする新規事業開発プロセスとマネジメントとは
既存事業は調査・分析重視型アプローチ、新規事業は仮説・検証重視型アプローチを採用する。
新規事業開発におけるフェーズの3C
Concept(事業構想)0→1
Creation(事業創出・事業化)1→10
Complete(成長・拡大〜完成)10→100
新規事業開発における7つの検証項目
A)顧客と課題. Concept
B)提供価値と解決策. Concept
C)製品と市場 Creation
D)事業性・収益性. Creation
E)成長・拡大可能性. Complete
F)持続可能性 Complete
G)戦略との親和性. Complete
新規事業開発における10のプロセス
[1]Insight=深い洞察により課題を発見する→A)
[2]Define=課題仮説の検証を通じて課題を定義する→A)
[3]Ideation=定義した課題を解決するアイデアを検証する→B)
[4]Prototyping=アイデアを試作品にして有効性をテスト→B)
[5]Development=テストを踏まえて製品とビジネスモデルを開発→C)
[6]Launch=製品を世に出して良質な初期顧客を獲得する→C)
[7]Monetize=製品を提供・販売して収益化する→D)
[8]Growth=投資によって事業を成長・拡大する→E)
[9]Exit=持続的に成長可能な構造を作る→F)
[10]Core=中核領域の事業として貢献性を高める→G)
事業構想フェーズのアプローチ分類
・アセットドリブン(価値・解決策×現状志向)
・ビジョンドリブン(価値・解決策×未来志向)
・マーケットドリブン(顧客・課題×現状志向)
・ミッションドリブン(顧客・課題×未来志向)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
