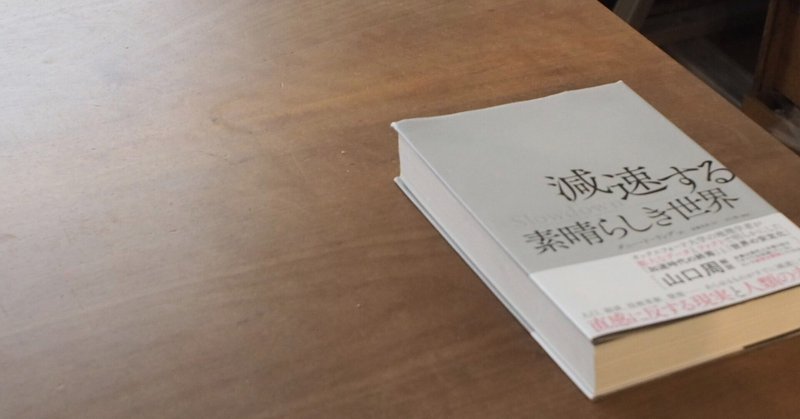
「減速する素晴らしき世界」を読んで
アメリカの地理学者による、データと解説満載の、500ページもある考察本で、私も3ヶ月くらいかけて読みましたが、個人的に、2022年のベストワン書籍でした。その感想や自分の考えている事を書きます。
これだけ長いと読むのが大変だし、そもそも一般的にはこんな厚い本、買おうって気にならないと思うんですよね。私も、寝る前に読むだけじゃ全然進まないから、外出時も持ち歩いていたけれど、重くて不便でした。
それを超えて読む価値があったんですけど、人に勧められるかというと気軽には難しいところです。
私、クリフトンストレングス(企業などが使う強み発掘ツール。具体的に自分の強みがわかる)で「学習欲」が強みにあるので、基本的に勉強するのが好き、むしろ好きを超えて勝手にやってしまう。その背景にあるのは、知らないことを知りたいという衝動です。
昔は、勉強が好きなのにさして賢くなっている様子もない自分のことを否定していて「1円にもならない勉強をするより商売しろ自分」と思っていたんですが、衝動ならばコントロール不可だから、そこからは開き直って読書に埋没する日々になりました。
そんなわけで私は難しい本も読むのですが、ぶっちゃけ 読めていません。
本を読まない人の多くが、読む人のことを「全て理解しながら端から端まできちんと読んでいる」なんて思っていると思うんですが、もちろんそういう人もいると思うけれど、そんなことない人も多いかと。
書いていある内容の9割わからない時もあります。
特に学者さんが書いているような本は日本語なのに難解なことがあって、文体が独特で主語が2つになってたりとか、一文がやたら長くてあっちこっち飛ぶとか、難しい語句のオンパレードで暗号のようだとか、ザラです。
私も昔は「本は全部を理解しながら端から端まで読むもの」と思い込んでいて、そういう読み方ができないのに手に取る私は邪道だと思ってたし、割と長い間それを誰にも言えなかったのですが、ある時、パートナーにカミングアウト。
言葉のプロであるパートナーが「それで正しいんですよ。今の自分に読める範囲で読むのが、本を読むということです。読める本だけ読んでもそこに成長はないですよ。」と教えてくれました。
正直、9割理解できないのもどうなの?と思ってたんですが、それでもなぜか私は読み進められていたんですよね。
おそらく私は、抽象概念の理解は得意みたいで「つまり何を言おうとしているのか」は、たとえ9割読めなくてもだいたいわかるんです。
小さな子どもを見て、言葉はわからないはずなのに、こっちの言っていること絶対わかっているよね、と感じられることがあると思うんですが、良く言えばあんな感じなのかな。
落合陽一の最近のベストセラー(岸田総理も購入したらしいです)「忘れる読書」にも似たような話がありました。
乱読、積ん読、ざっと流して読む、何度も読む、あっちこっち行ったり来たりする。読書はもっと自由でいい、と。
1、減速する素晴らしき世界
著者:ダニードーリング(オックスフォード大学 地理学教授)
発行:2022年7月
価格:2,800円+税
まずタイトルの「減速する素晴らしき世界」を見て、えっこれどっち?って思ったんですよね。
「素晴らしき世界が減速する(残念)」なのか
「減速する世界が素晴らしい(期待)」なのか
答えは後者でした。
今、世界は、出生率も、人口も、奨学金の借入額も、テクノロジーの進化も、乳幼児死亡率も、あらゆる事の、その進み方は緩やかになっているから、もうそういうフェーズだから。そういうもんだから。
そんな低成長の時代、成長しなくちゃいけないという呪縛から解き放たれて、私たちはゆっくりと物を考え、まわりの人を大切にしながら、自分らしく生きていく事をクリエイションできるのではないか、というメッセージの本です。(ただし気温だけは、地球規模で上昇し続けているという例外があります)
その話をするために、あらゆるジャンルにおいて進化のスピードが落ちているということを、数百ページに渡るデータとその解説で示してあります。よくこんな本を作ったもんだ、世の中には凄い人がいることに驚くばかりです。
例えば、私は少し前、1926年(第一次世界大戦後)に作られた、国鉄の、外国人向けガイドマップ、というものを見せてもらったんですが

明治維新からの50年あまりで、国鉄は日本全国、当時占領下にあった台湾や中国の一部を含めて、その土地を埋め尽くすように鉄道を敷いたわけです。たった50年で日本中の端から端まで列車で行けるようになった。当たり前だけど今の日本に当時のスピード感や勢いはもう二度とやってこない。
進化のスピードが遅いというのは基本的にはこういうことを指しています。
他にも公衆衛生の進歩で乳幼児が死ななくなれば、リスク回避のために子どもをそうたくさん産まなくても良くなるので出生率は自然に下がる、とか。
そもそも、なんでも限界というものがあって、出生率が上がり続けたとしても女性1人が50人100人生むなんて事は絶対に起こらないし、土地に限りがあるんだから、鉄道が青天井に増え続けていくなんて事だって起こらないわけで。どこかで必ずスローダウンは起こるし、それはあらゆる分野に連動しているから世界的に、どの分野でもスローダウンするのは当たり前のことなんだよと、著者は伝えています。
著者は、進化のピークはだいたい1968年ごろと言っているので、私たちが生まれ、生きてきた時代は、まさかの、すでに減速している最中だったっていう。そして今もどんどん減速しています。
短期的にみるとその減速具合がわかりにくく、GDPでは確かに成長しているし、人の暮らしは楽になっているし、デジタルでできなかった事ができるようになり、便利なものがたくさん増えているように見えています。でもその一方でここ最近は特に顕著に、素人の我々にもわかりやすく、減速している感じも見えるようになってきた気もする。
私は街歩きが趣味ですが、もうずっと何かこう、歩いていても、新しいビルができるスピードよりも、古いビルがどんどん古くなるスピードの方が速いなってことは感じていたんですよね。
新しく建てられるビルのデザインに新鮮な驚きはあまりなく、それよりも古いビルのその古さに味わいを感じ、自分の知らない時代のデザイン性の高さに発見がいくつもあるとか。
それは、進化より退化のスピードが速いということであり、進化に見られない美しさを、退化の方に見出してしまっている現状があるのだなと。
人間の、デザインする力もスローダウンしているのかもしれない。
いまのレトロブームって、こういうことを皆が潜在的に感じているからなんじゃないかなと思ったりもする。古いものが良いという単純な選択ではなくて、新しく、人を新鮮で前向きな気持ちにさせてくれるものが、実は生まれていないからだと言えるのではないか。
絵本とか、映画とかだって、私たちは名作と呼ばれるものを知っているし、今もあらゆる形で消費されているけれど、これからの未来に名作になっていくだろう作品が生まれるスピードって、過去、名作が生まれてきたスピードよりも遅く感じない?人は、過去と同じだけの熱量で今もクリエイションをしているだろうか?とても疑問です。
ただそれは別に悪いことではなくって、イノベーションを起こすにはある種の飢え(絶対こうしたい!)が必要だし、アートが生まれる背景には事実として格差が存在する。
人が毎日の食事に困らなくなり、病気をしにくくなり、安全に暮らせるようになったら、飢えてないからイノベーションもアートも必要なくなっていくんですね、得れば何かを失う、世の中はそういうもの。
だから、もはやスローダウンは世界のどこにいても免れないんだけど、ここで面白い事実があって
2、世界で一番早く減速している日本
世界のどこよりも早く、進化のスピードを緩めてスローダウンしているのが日本だという事実。本に、はっきりと書かれているし、確かにそうだよねーと思う。
世界で日本だけが給料が上がっていないとか、日本の政治は地に落ちているとか、ネガティブな話が多くて諸外国よりも劣勢にあるように見えるけれど、世界規模で考えてみると、単純にスローダウン先進国なんだとも言える。
日本が世界の中で最も早く超高齢化時代に入ったのも、それを示していると思う。
それは、ある意味でチャンスだと思ってる。
右肩上がりの経済成長を求め続けられる資本主義社会も、独裁的になりやすい共産主義社会も、どちらもうまくいかないことに人は気づき始めて、新しい社会を模索する時代にきていて、
日本が、低成長時代における生き方のモデルを世界に提示することができれば、高度経済成長期のハードウェア産業ではない事で、世界を再びリードする存在になれるかもしれない、そんな可能性が日本には残っていると思う。
もちろん日本が別にリーダーになる必要はないんだけれど、日本がスローダウンの先駆けであるだけでその存在自体が貴重なデータとなり、その上でもしも素晴らしい最適解を見つけられたら、世界が救われることは確かだなと思う。
たとえ失敗しても、少なくとも他の国が失敗しないための役には立つし。
だから私はこの本を読んで、とても明るい気持ちになったんですよね。
日本には、やるべき仕事がある。
3、AI社会
世界はスローダウンしているけれど、目の前の世界はとても速いスピードで進んでいるように思えて、特にAIの進化が目覚ましく感じる。
最近「チャットGPT」というツールで遊んでいるんですが、これは、オープンAIが公開している、会話形式でAIがいろんなことに答えてくれるツールです。日本語対応しています。
自立共生性について書籍を聞いたら、麻原彰晃をオススメされたりもしたんですが・・・ドユコト?(しかも今は販売もしていないはずですが)
適切については「適切」を定義しないと答えが出ないようです。
質問力が大事ですね。

そのほかにも「私の住む地域のシングルマザー支援にはどんなものがあるか?」とか「クリフトンストレングスで私の強みは「戦略性」ですが、具体的に仕事に生かすならどのようなアプローチがありますか?」とか、色々聞いてみたら、それなりに答えてくれました。
チャットGPTは、ユーザーからのフィードバックをもとにどんどんと作り変えていくようですが、今のところは文章形式でプロフェッショナルな事柄に文字列で答えるのが得意なので、つまり、宿題をやるとか、論文を書くとか、プログラムを書くとか、そういうのが得意なわけですね。
(プログラミングはノーコード(コードを記述しない)時代になってきましたね、日本のプログラミング教育とやらはどこへいくのでしょうか)
そして、世の中のこういうツールの多くがオープンソース(無料)
マイクロソフトがWordやExcelにAIを搭載して、文字を打たない、表を自分で作成しなくても良い機能を持たせたりするというニュースもありました。
そのうちGoogleの検索窓に文字を打つことも、なくなるんでしょう。
少し前には「AIに仕事を奪われる」なんて話題で盛り上がっていたけれど、もはやそんなレベルの話ではなくなり、プログラミングもライティングも士業もAIがやるようになるのは時間の問題のみならず、AIという世界の中で私たちは暮らすようになるから
AIとは今から仲良くなっておくのが良いのでは、と思っています。
かつて「パソコンとか苦手だから・・・」と言っていた人も、どれだけ苦手でも今はウェブから申し込みもするし、とあるエキジビジョンはLINE登録必須で、そこからしか申し込みができなかったし、仕事もバイトもアプリで探す時代になりました。(オススメはハローワークですが)
好き嫌いとかではなく、もうそういうもんです、問答無用。
AIも、きっとそんな感じ。
否が応でもAIの世界で生きることになる私たち。
私たちは、AIでできてしまう事は手離して(AIのが確実に速くて正確で、どう転んでも我々は勝てないですからね)自分にしかできないことをする、選択肢がもうそれだけになってきている。ある意味とてもシンプルで、やることが絞られてきていると感じます。
4、スローダウン✖️AI
スローダウンとAIは、とても相性が良い。
無駄に働くことを手離して、もしたくさん音楽を作りたい人なら、AIを活用し、昔だったら1曲に1ヶ月かかっていた音楽を10秒くらいで作成し、1000人の人に1曲ずつプレゼントすることもできる。
小説とか、台本なんかもきっとすぐ書ける。
お金を作る方法とか、物を売る方法とかはどんどん体系化されて、お金持ちになる事も、技術的に解決できるようになってしまった。
そういうことはもう、あまり難しい話ではなくなってきてて。
じゃあ私たちは何をして自己実現していくのだろう。
好きなことをしろと言われても、それは何?
答えは一人一人違うんですが、そこにたどり着くために必要なことは、私が思うのはまずは自己理解。
クリフトンストレングスなどのツールなどでわかる「自分が衝動として無意識にやってしまう強み」のようなものを見つける事。
それって、たぶん、AIに仕事を奪われないポイントのようなもんなんですよね。私は勉強するのが無条件に好きなだけで、AIと競うようなことはしないわけだからそこは自然に住み分けられるって事です。win-winです。
友人に「幹事は得意ではないが、幹事のサポートは得意」という強みを持つ子がいますが、そこまで明確になると行動に迷わなくなって、徐々に生きやすくなるなと思っています。
私は数秘術をやっているんですが、こういう具体的な強みに関しては、数秘術以上にわかる。だからクリフトンストレングスは有料ツールだけど、機会があればおすすめです。
ただ、診断結果だけだと解釈が難しく現実的に応用できない人が多いと思うので、解説してくれる人が必要です。私は独学しました。
あと個人的には
言語を磨く事が大事だと思っています。
日本語もそうだし、できれば外国語も。(私も勉強中)
ひとつには、作業的なことに時間を使わなくて良くなったら、人がやるのはクリエイションとコミュニケーションになってくるから、抽象的なことや感覚的な事を言葉にする力や、それを感じられる感性が、必要不可欠になっていくと思う。
もうひとつ、AIは今の段階ですら「どうしてそういうことが言えると思うのか?」といった比較的深い質問にも答えてくれるから、自分の脳内をどう質問に置き換えれば、良き答えが得られるのか、の、精度が求められるようになる。
音楽を作るにしても、絵を描くにしても、3Dプリンターで出力するにしても、全部言葉で指示できるのだから、逆にそこは言葉しかないのだから、深みのある作品を作ろうと思うと、どんな言葉を使い、どう伝えるかが大事になるのは、容易に想像できる。
その言葉を磨くには、教養が大事で。
教養はいろんな解釈ができるけれども、表面的にキラキラしているとかファッションが素敵とか部屋が綺麗とか、そういうのとは違う、奥の深い人と繋がって、コミュニケーションを取るのが一番良いと思います。
素敵な人と繋がると、自然にそのありようがインストールされる、人間は環境の生き物ですし、私なんかめっちゃ流されやすいので、環境を整えるしかないんですよ。自分に良い影響を与えてくれると思う人としかつきあわないし、くだらないネットニュースを見ると影響されるので見ないし、ツイッターも不要なものを見ないように気をつけています。
自分の意志の力に自信がないからこそ、仕組みで解決です。
ポルカてんちょ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
