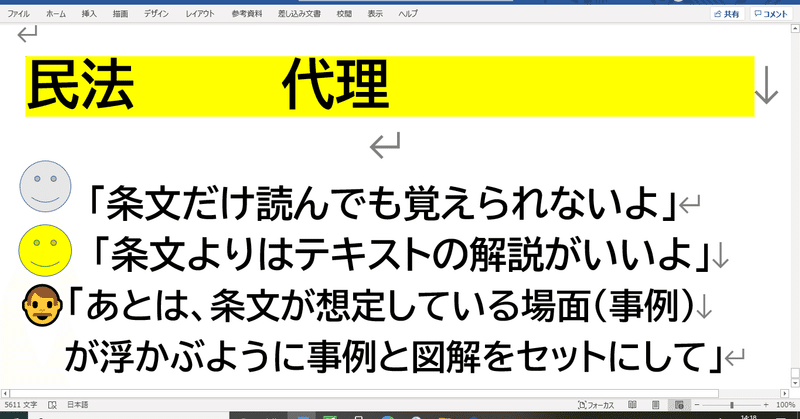
民法思考力養成7 代理
記事前半は、YOUTUBE動画と同内容です。
後半の「イメージ・記憶促進ノート 無権代理行為の相手方が主張できること」は、YOUTUBE動画で収録していない内容となります。
今回は試験に出やすい「代理」です。
では、「代理」の出題傾向から入ります。
代理は、過去10年で6回出題され頻出分野。
(記述式は過去10年で2回出題)
記述式問題の過去10年の出題実績は、
2011年46問 表見代理と使用者責任
2013年45問 無権代理人に対する責任追及関連
です。
代理も事例問題で出題されますので、今回は、
事例分析力と、民法の思考の筋を、順序立てて
分析できる力を試すため、記述式問題にチャレンジしていただきます。
総合問題 事例分析力 と 民法の思考力 を鍛える
👨事例問題の解説の中で民法の思考の筋を覚えよう!
🔵オリジナル記述式問題
AはBにピンクとブルーのダイヤモンド各1ピースの買付けを依頼し、各ダイヤ120万円以内で購入する代理権を授与した。その翌日BはCとの間でピンクダイヤ1ピースを100万円で購入した。その1週間後、BはCとの間でルビー1ピースを100万円で購入した。CがAに合計200万円の代金を請求するために必要となる法律構成を考え、その法律構成の要件のうち、相手方Cがみたしていなければならない要件は何か。解答欄のマス目の最後に印刷されている「場合」の前に入る文章を、民法の規定に照らし、40字程度で記述しなさい。
なお、BはAの代理人と名乗って契約を締結しており、Cは全く代金の支払いは受けておらず、代金債権の消滅時効期間は経過していないものとし、民法上問題なく代金請求ができると考える売買については、法律構成を考えて要件を示す必要はない。
👇 3人以上登場する場合は、事例分析を図解してから
民法の思考をあてはめた方が分析ミスが起きにくい。
👨図解を実演し事例分析 図解を実演。

👨図解の内容面(問題文から拾う情報)のポイント
太字部分が今回工夫したところ。
1 登場人物の立場・肩書を略記、位置固定
(本人=本、代理人=代、相手方=相)
(売主=ウ、買主=カ)
2 登場人物の善意・悪意・過失等の心理状態を略記
し〇囲み。不明な場合は、〇だけ表記して空欄(?)
3 複数の契約や権利の移動につき、時系列を示す
4(返還請求の可否を問う場合)物体の所在を書く
5(権利の帰属を問う場合)権利の帰属が分かるように
6(主張の可否を問う場合)
誰が誰に何を主張できるか矢印で結ぶ
7 権利が移動する場合は、移動の様子も矢印で表記
👨図解の技術面(書き方)のポイント
太字部分が今回工夫したところ。
自分の中で表記の仕方を統一しておき、
何度見ても一瞬にして何を示しているかわかるように
1 権利の移動は、原則、左から右へ(復帰は逆移動)
2 複数の契約がある場合、
時系列を古い順に➀➁➂と番号を振る
3 物体が、土地・建物・動産は区別して表記
ダイヤ=ダ、 ルビー=ル
4 「権利の移動」と、「主張内容(請求権)」は、
違う矢印表記で統一して表記
5 略語を統一しておき、一貫した表記
👨出題意図
CがAに対して合計200万円を請求できる法律構成が何かを考える力を試し、その法律構成を使うために求められる要件を解答することを求めた。
👇事例分析ができたら、民法の思考の筋を確認しよう!
丸暗記ではなく、応用力をつけるため、解答を導く
理由を確認しよう!
👨民法の思考の筋 原則論から入り例外を検討する!
➀Aはブルーとピンクのダイヤモンド各1ピースを購入する代理権をBに授与したところ、Bは、Aの代理人と名乗ってピンクのダイヤをCから購入しているため、代理権の範囲の行為として、代理行為の効果がAに帰属し、Aは買主の地位が帰属し代金支払債務を負うことになるので、この時点で売主Cは、Aに100万円の代金請求できる。
👇
➁その後、代理人Bは、Cからルビーを購入した行為は、代理権の範囲を超えて無権代理行為であるため、代理行為の効果はAに帰属せず、Aに買主の地位も代金債務も帰属しないため、売主Cは、ルビーの100万円の代金請求をAにすることができないのが原則。
👇
➂しかし、例外的に、表見代理が成立すれば、無権代理行為に巻き込まれた相手方Cは、代理権を授与した本人Aに対して、契約上の責任を追及することができ、ルビーの売買代金100万円を請求でき、合計200万円をAに請求できることになる。
👇
➃そこで、表見代理の成立要件3パターンを検討する
A 代理権授与表示(代理権を与えたかのような表示)
要件 【109条】
❶代理権授与表示
❷表示された代理権の範囲内又は範囲外の行為
❸範囲内⇨相手方が善意無過失
範囲外⇨相手方が代理権があると信ずべき正当な理由
B 権限外の行為(代理権は与えているが権限外)
要件【110条】
❶原則何らかの私法上の代理権がある
❷代理人がその代理権の範囲を超えた
❸相手方が代理人の権限があると信ずべき正当な理由
C 代理権消滅後の行為
要件【112条】
❶過去に代理権があった
❷過去の代理権の範囲内又は範囲外の行為
❸範囲内⇨相手方が善意無過失
範囲外⇨相手方が代理権があると信ずべき正当な理由
👇
➄本問では、代理人Bは、ダイヤ購入の代理権を超え、ルビーを購入し、権限外行為のBパターン。相手方が「代理人の権限があると信ずべき正当な理由」があれば表見代理が成立し、本人Aに代金請求ができる。
👇
➅よって、➄の場合、CはAに、200万円の代金請求ができる。
記述式正解例
(代理人Bの権限外の行為につき、Cが契約当時代理人の権限があると信ずべき正当な理由がある)場合
(43字)
正解例は、条文の文言をなるべく使う方針の方がよいので、以下の110条の文言を使っている。
📖民法109条1項(代理権授与表示:表見代理)
「第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
📖109条2項省略
📖民法110条(権限外の行為の表見代理)
「前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。」
なお、「代理人の権限があると信ずべき正当な理由がある」は、ほぼ善意かつ無過失と同じ意味と解釈されている。
さらに、「代理人の権限があると信ずべき正当な理由がある」かどうかを判断する基準時は、「表見代理行為が行われた当時の事情」で判断する(大判大8・11・3:我妻・有泉コンメンタール民法総則・物権・債権)とされているが、字数制限があるので、単に「契約当時」としている。
ここで、オリジナル記述式問題の解説は終わり。
無権代理行為の場合に、相手方が主張できる内容について、さらに網羅的に知識を整理して、記述対策の訓練を積みたい方は、
以下のイメージ・記憶促進ノートをご活用ください。
まずは目次をご覧ください。。
イメージ・記憶促進ノート 無権代理行為の相手方が主張できること
目次
STEP1 受験生のインプットが弱そうなところを確認
👨あえて省略気味の事例問題を読んで民法の思考の筋を覚えよう!
🔵オリジナル事例正誤問題(事例分析図を完成後、民法の思考の筋へ!)👨私の事例分析図を紹介
👨図解の内容面(問題文から拾う情報)のポイント
👨図解の技術面(書き方)のポイント
👨民法の思考の筋
STEP2
👨民法の思考の筋を文章化できるか、記述式問題にチャレンジ!
🔵オリジナル記述式問題(事例分析図を完成後、民法の思考の筋へ!)
Aは、Bに「ロレックスのアンティーク腕時計1本を50万円以内で買い付ける」代理権を授与し、その後、BはコレクターCの所に下見に行き価格交渉をしたが、価格が50万円を超えそうな見込みのため購入せずに出直すことにした。その後、Bは破産手続開始決定を受け、その決定から2週間後に、再度Aの代理人としてCの所に行き、ロレックスのアンティーク腕時計1本を40万円でCから購入した。Cは、Aとの間の契約が無効な状態を確定させるため、どのような要件のもとで、どのような権利を行使できるか。民法の規定に照らし、解答欄に印刷されている「Cは、」に続け、末尾の「ができる」の間に入るように、40字程度で記述しなさい。なお、記述にあたっては「代理権を有しないBがした契約」を「契約」と表記すること。
解答欄イメージ(解答欄のマス目は45字)
Cは、( 40字程度 )ができる。
👨私の事例分析図を参考までに下に掲載する。
👨図解の内容面(問題文から拾う情報)のポイント
👨図解の技術面(書き方)のポイント
👨民法の思考の筋
👨記述式問題正解例
👨出題意図・配点 ~令和2年度本試験の出題意図を参考~
ここからは本文です。
ここから先は
¥ 100
サポートしていただきまことにありがとうございます。頂戴したサポートは、記事の執筆活動の費用にあてさせていただきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
