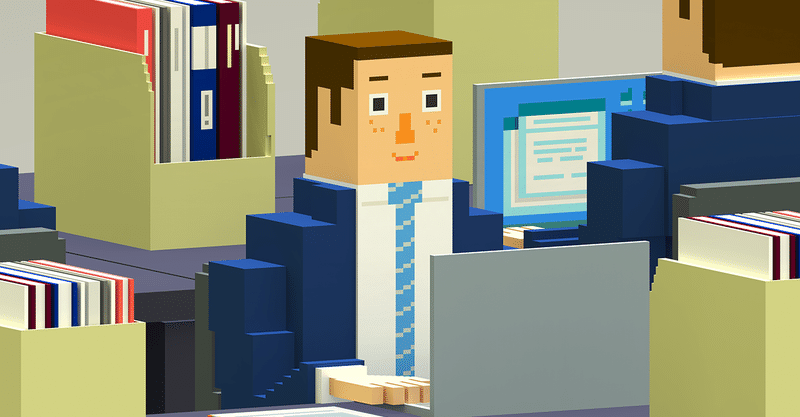
私は昭和の終わり頃に、営業事務として商社で働いていました。そのころの仕事術で昭和と令和との違いを書いています。
昭和60年代の転職事情はどうだったのでしょうか。男女雇用機会均等法が始まったばかりで、結婚後も独身時代と同じ仕事を続ける人は公務員くらいでした。
普通の事務員さんは、結婚後も続けますが、妊娠したら辞める方が多かったです。家庭の育児方針や、保育園の定員もあり、正社員を続けることは大変でした。令和の現在ほど夫の協力は、ありませんでした。
新卒で入社した会社より、好条件の仕事はめったにありませんでした。ヘッドハンティング、外資系、という転職のキーワードは平成に入ってからメジャーになってきました。それと同時に派遣社員という働きかたも平成に入ってからの就業形態だと思います。
男性の場合、ある程度安定した企業に就職した方は、定年まで勤めます。中小企業に勤めていた方は、「脱サラ」されていました。つまり、起業です。
私が働いていた中小企業の商社は、100期末を目前に解散しました。働いていた社員の内、営業マンは起業して、自分の顧客を引き継いでいきました。
「転職」より「脱サラ」を選んだほうがやりがいがあると思ったのでしょう。令和の現在はどうでしょうか。起業は簡単にできますが、顧客を持つのは難しそうです。
女性は、結婚退職して、パートタイムで働く方が多かったですね。一般職、総合職の区分が出始めたのも平成になってからです。一般職は主に事務の女性を指す言葉でした。一般職の仕事は、現在では派遣社員が占めるようになり、希少な存在になりつつあります。
結婚退職で、仕事を辞めた女性は、その後パートタイムで働く方が多くいました。子供やお年寄りの世話で自宅から出かけられない方は、「内職」をしていました。これは現在の「在宅仕事」です。在宅の請け負いライティングの収入は昭和の内職仕事と金額は同じくらいです。これは真実です。
サポートしていただけたら、とっても嬉しいです。昭和の文化をとことん、語ってみたいと思います。昭和のOL仕事についてお知りになりたいことがあれば、コメント下さい。noteでお答えいたします。
